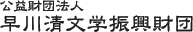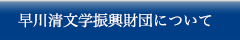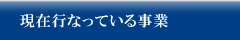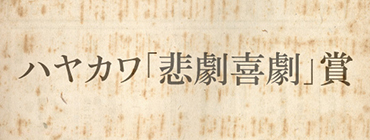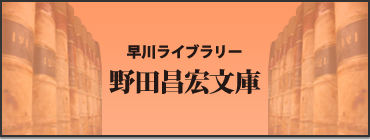第十三回アガサ・クリスティー賞選評
選 評 鴻巣友季子
今回は応募数も多く、受賞に関してはけっこう意見が割れ、選考は長引いた。全体のレベルは高い。読んだ順に選評を。
今葷倍正弥『罪の波及』は、十五年前の殺人事件の真相を洗い直すミステリで、被害者の娘が過去を調べだしたことから物語が動きだす。子どもへの虐待が関係している。事件は被害者と家族のみならず、加害者と家族の人生をも壊すことを描く文章からは、誠実さが伝わってきたが、善悪の掘り下げにもう少し深みがほしかった。また雑誌社の女性と、年上の男性ライターとの関係性の書き方がいささか古臭いのでは(気に入った女性が泥酔したら「お持ち帰り」するはずだ、などの発言)。
小塚原旬の候補作を読むのは三度目。一回目と二回目の飛躍幅がめざましく、今回も相当の伸長を見せた。『機工審査官テオ・アルベールと永久機関の夢』は十八世紀欧州に登場した「永久機関」の審査をめぐる異色ミステリだ。昨年のイエス・キリストの裁判を弁論戦に焦点を当てて描いた作品につづき、歴史ミステリの一分野を独自に開拓するポテンシャルを感じて優秀賞を出した。課題をいうと、昨年同様、プロットがやや起伏に乏しく、シーンを並列した形になっていること。豊富な知識と独自の視点を武器にいっそう腕を磨いてください。こういう作品を世に送りだせて嬉しく思います。
菊田将義『2079』は、アジアの一国を舞台にしたサスペンス・ミステリ。「うそをつくと死ぬ」機器を国民が装着させられている管理国家だ。ディストピアものは寓話的な手法が流行っているが、本作はあくまでリアリズムに則っており、そのため細部の粗さがやや目立った。『一九八四年』など見ればわかるとおり、言語の扱いに作品の風刺性の心髄は出る。一つの文言を真と偽に分けることは話者自身にも困難だが、そうした人間の思考と感情と言語の複雑な関係を単純化しすぎた感がある。トリックとしては、母が「刺殺」という語に嘘の意味を教えるくだりで、なぜ嘘をついたのに母は死なずに済んだのかが説明されていないことが、疑問視された。
江戸川雷兎『限りなく探偵に近い探偵』は、探偵小説の形態をしたメタ・サイコスリラーというべきか。筆運びも構成もキャラ作りも上手い。凝った遊び心も買いたいが、もっとオーソドックスな題材で勝負した作品も読んでみたい。
大賞の葉山博子『時の睡蓮を摘みに』はスケールの大きな歴史ロマンミステリ。一九三九年、主人公は名門女子専門学校の入試に落ち、縁談を蹴る形で父の駐在する仏領インドシナへ旅立つ。男尊女卑の日本では「頭の中を纏足されているみたい」と、猛勉強の末バカロレアを取得しハノイ大学に合格、地理を専攻するという設定からわくわくさせられた。
とてつもなく分厚い知識の土台に支えられ、候補作のなかで神殿のように屹立していた。主人公が外海をいく舟を、ハロン湾からの視点で書いている序盤から引き込まれたが、このピクチャレスクな描写力をもっと振るってください。活躍、期待しています。
選 評 法月綸太郎
『時の睡蓮を摘みに』は第二次世界大戦下の日本軍による仏領インドシナ進駐を背景にした骨太の歴史サスペンスで、クリスティー顔負けの人間観察と、ル・カレやグリーンのような文学的香気に満ちている。植民地における民族間の支配従属関係を見据えた第一部と戦火の中で在外邦人の階級差が露わになる第二部の対比・相乗効果から、物語の焦点がヒロインの選択に絞られていく終盤の展開に静かな興奮を覚えた。候補作中でも別格の出来で、大賞受賞作を選ぶならこれしかないだろう。豊かなディテールと伏線の妙を味わい尽くすには熟読を要するが、「新しい戦前」と言われる今の時代にこそ読まれるべき作品だと思う。
『機工審査官テオ・アルベールと永久機関の夢』は近世ヨーロッパが舞台の時代ミステリ。永久機関をダシにしたコンゲーム小説に、工学系ハウダニットと西洋チャンバラを組み合わせた野心作である。作者は三度目の最終候補だが、毎回意表をつく奇抜な設定が持ち味で、一作ごとにストーリーテリングもこなれてきた。今回は語り口に工夫の跡が見えるが、後半やや書き急いだせいかフィニッシュで息切れした感があり、協議の末に次点の優秀賞作品として世に出すのがふさわしい水準と判断した。今後は手癖に流されず、粘り腰の寄せを心がけてほしい。
以下、選に洩れた作品について簡単に。『罪の波及』は殺人事件の被害者遺族と加害者家族のその後の軌跡をたどる社会派風人情ミステリ。リーダビリティの高さは五篇中一番だったけれど、話の底がすぐに割れてしまうのが難。雑誌記者ヒロインの成長をスキップして、中年男性の願望充足小説に着地するのも筋が違うのではないか。
『限りなく探偵に近い探偵』は技巧的なプロットに完全に騙されたが、犯行の土台となる特殊設定が脆弱すぎて、物語を支えきれていない。特にカルト教団の教義が説明不足で、犯行と動機がトートロジーに陥っているように見える。
『2079』は嘘をつくと即死する国という設定が魅力的で、異邦が舞台の警察小説としても読み応えがある。とはいえ、言語の扱いには疑問が多く、同じ日本語でも社会体制が異なればもっとズレや誤解が生じるはず。そもそも嘘をつけない母親がどうやって虚偽の語意を教えたのか、具体的な説明がないのはミステリとして致命的では。
選 評 清水直樹(ミステリマガジン編集長)
第一回から昨年まで選考委員を務めた北上次郎氏が今年一月に逝去された。氏は新人作家の可能性を第一に考え、発想の新しさ、印象に残るシーンが書けているかといった点を重視されていた。そして、「新人作家はとにかく書き続けることが大事だ」と、受賞者にアドバイスされていたことを記しておきたい。
菊田将義『2079』は、嘘をつくと命を失うという架空の国家で起きた殺人事件を、日本の警察から派遣された警察官が捜査する特殊設定ミステリ。日本人警察官と現地の警官たちとのドラマがよく書けていて読ませる。やや類型的だがキャラも立っていて、映像化向きの作品だと思った。私は最高点を付けたが、他の選考委員が指摘した設定上の問題点には完全に同意する。物語を作る力には将来性を感じるので、ぜひ別の題材で再挑戦して欲しい。
葉山博子『時の睡蓮を摘みに』は、第二次世界大戦前夜の仏領インドシナを舞台に、歴史の流れに翻弄される日本人女性を主人公にした作品。歴史や政治状況の記述は興味深く読めるし、登場人物の行動にも必然性がある。だが、複雑で膨大な歴史的な記述のなかにストーリーが埋没してしまっている印象は否めず、またミステリとしての評価を考えて最高点は付けられなかった。ただ、これだけのボリュームの作品を構想し書き切る力は相当なものだし、大きな将来性を感じる。大賞受賞に全く異論はない。
小塚原旬が最終選考に残るのは三度目。『機工審査官テオ・アルベールと永久機関の夢』は過去の応募作に比べ、物語の構造が練られ読み応えも増している。もともとキャラクターを魅力的に書く力はあり、今回もその長所は際立っていた。一方で、分量と比較してエピソードを盛り込み過ぎな印象があり、個々のパートがやや物足りなく感じた。協議の結果、優秀賞を与えることになった。
今葷倍正弥『罪の波及』は社会派ミステリ。被害者家族だけでなく、加害者家族にも焦点が当てられているところが特徴で現代的だと感じた。逆にいうと新味はその点でとどまっており、特徴的な作品を新人賞に選びたいという点から考えると厳しい評価になった。
江戸川雷兎『限りなく探偵に近い探偵』は、非常に練られた構成で読む者に驚きを与える作品。ただ、プロット・構成に驚きはあるものの、ストーリー・キャラクターに魅力を感じられず、高い評価を与えられなかった。
- <<前の記事:第十三回アガサ・クリスティー賞選考結果
- 第十四回アガサ・クリスティー賞募集要項:次の記事>>