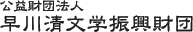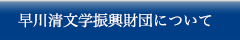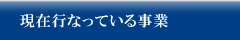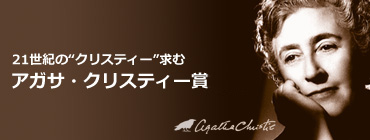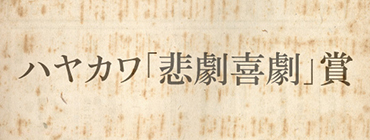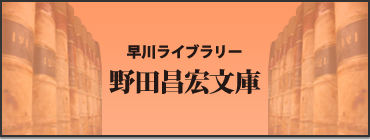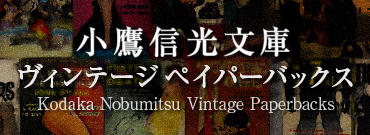第十四回アガサ・クリスティー賞選評
選評 鴻巣友季子
今年もレベルの高い作品が揃いました。大きな傾向として、二作が名画と美術の真贋をめぐる外国を(も)舞台にした作品であり、もう二作が画期的新薬となる物質と人間の生命操作をめぐる作品であったことは、アガサ・クリスティー賞らしいと言えるかもしれません。
根本起男『DIVE 青き闇の温もり』。作者は二〇二一年の本賞でも最終候補になっていますが、人物造形、構成の点で格段の向上が感じられました。
今世紀初頭と現在のタイムラインを行き来しながら、水難事故で一命をとりとめた深海探査船のパイロットに待ち受ける困難と、中国残留孤児の男性とその家族の物語が交錯していく。超ポジティヴ思考の助っ人役(引退した元商社経営者)という役どころは、とぼけた妙味を出しており、高齢化社会における老人キャラの新しい活躍どころの可能性を感じさせました。ただ、これだけの大陰謀と裏切りに巻きこまれたにしては、主人公の感情面が平坦すぎる気はしました。また、テロメアを再生する物質を描くにあたっては、生命倫理のさらなる考察が期待されます。
大賞に決まった睦月準也『マリアを運べ』は疾走する輸送ミステリーで、フォーカスを絞ったシャープな書きぶりが評価されました。MARIAというバイオ医薬とその研究データを、十七歳の無免許の女運び屋が、警察、ヤクザ、カルト教団などの追手を振り切って目的地に運ぶというシンプルな筋書きですが、飽かせず読ませる力量に感心しました。
MARIAは人間の出生に革新をもたらす新薬で、人口減少に朗報とされますが、終盤で急に女性研究者の性被害のトラウマを絡めてきた点には一考を促したいと思います。「DIVE」もですが、パンドラの箱と言われる人間の生老病死の人工操作を書くにあたっては、作中で行き届いた議論、その前に書き手のなかで充分な内省と思索をお願いします。
伊達俊介『「ゲルニカ」一九三七年』。パリを舞台にピカソを探偵役、ピカソを撮影してきた写真家のブラッサイをワトソン役にした設定が秀逸。ただ、各人物の容貌の描写が類型的で、それは性格の造形にも及んでいるように思いました。写真家ならではの目の付け所や描写がほしいところです。
中島礼心『踊るメサイア』。絵画の盗難劇ですが、犯人グループが早くに壊滅させられた後にトーンダウンを感じました。素材はダイナミックですが、小説の書法がダイナミズムに欠けている点が惜しまれました。
選評 杉江松恋
本年から選考に加わりました。よろしくお願いします。
今回の選考は二作のどちらかが本命と考えて臨んだ。
その一つ、『マリアを運べ』は、人と荷物を預かった走り屋がそれを送り届けるというミッション型の冒険小説である。『深夜プラス1』を思わせる設定でおもしろい。
大きな弱点は、運転手を未成年の少女にしたことだ。偽造免許証を持っているが、そんな無茶をさせなくても組織は成人を使えばいいだけの話である。なぜ未成年なのか。作者がそうしたいからだ、としか説明がつかない。ご都合主義だと思ったが、娯楽小説の長所を考慮して加点主義で授賞が決まった。もう一つ、物語の後半でオカルト的言説が展開されるのと、物語にちらつく時代遅れの偏見には閉口させられた。娯楽小説といえども看過できない箇所である。この点の改稿が授賞の条件とお考えいただきたい。
『DIVE 青き闇の温もり』は妻が外国のスリーパー工作員だと判明した男の話である。主人公が自宅に戻れず、妻の動向を隣のマンションから監視するという展開がおもしろい。これは変形のコキュ(寝取られ亭主)小説ではないか。このまま行けば他にない読み味の物語になると期待したのだが、クライマックスが月並みでがっかりした。洋上の活劇なのだが、場面が目に浮かんでこないのである。マンションから出なければよかったのに。スパイの妻のキャラクターもよく余韻が残るので、残念である。
『「ゲルニカ」一九三七年』はパブロ・ピカソを探偵役とする作品で、犯人当てとしては工夫があるのだが、途中のミステリ談義が取って付けた感じでいただけなかった。最大の欠点は「ゲルニカ」をモチーフに使いながら、解釈のおもしろさがないことで、名作の無駄遣いである。本作が美術ミステリと認められるためには、「ゲルニカ」に美術品としての新たな価値を付与するくらいの独創的な視点が必要になる。単にミステリの小道具として消費してしまうには、あまりにももったいない題材ではないか。
『踊るメサイア』には美点が見いだせなかった。作者は、自分の専門については喜々として語るが、それ以外は通り一遍にしか書けない。外国の情景など観光ガイドブックの引き写しのようである。状況が動きではなく会話で説明されるのも退屈だ。他人に読んでもらうための努力を。
選評 法月綸太郎
『「ゲルニカ」一九三七年』は第二次大戦前夜のパリで、ピカソが連続殺人に巻き込まれる歴史本格ミステリ。スマートな設定と正攻法の謎解きに好感を抱くも、小説としての厚みに欠けるのが難。そのせいで犯人が悪目立ちしているし、美術史とのカラミも物足りない。ブラッサイをワトソン役に起用するなら、画家と写真家の「眼」の違いを観察と推理に反映させる工夫をしてほしかった。
ダ・ヴィンチの名画に材を取った『踊るメサイア』は、盛り沢山のディテールにムラがありすぎ、物語が空中分解している。作者目線で書きづらいところ(偽装工作の急所を含む)を全部スキップしたため、読む側が置いてけぼりを食わされた感じ。人物とプロット構成のバランスを練り直した方がよいと思う。
『DIVE 青き闇の温もり』は深海探査艇の操縦士が「隣の密室」に潜伏する変化球設定が絶妙で、水戸黄門的な協力者を始め、ご都合主義を逆手に取った展開がかえって新鮮だった。終盤の超展開はやや飛ばしすぎなところがあるものの、SF的モチーフの危うさを自覚しつつ、物語の外堀を埋める努力を怠らなかった点を評価したい。作者は第11回の『プラチナ・ウイッチ』以来の最終候補入りで、ネタを詰め込みすぎて平板になってしまった前作よりエンタメ小説として格段の進歩を遂げている。総合点ではこれがトップで、選考会に臨むまでは大賞に推すつもりだったのだが……。
大賞受賞作『マリアを運べ』について、事前に付けた評点はけっして高くなかった。カーチェイス小説としての描写が淡泊で、登場人物が何を背負っているか今ひとつ伝わってこないし、バイオ考証の雑さも含め、全体に舌足らずな印象が強かったせいである。ところが選考会で議論を重ねるうちに、弱点と見なした欠落感こそ、この小説を貫く太い芯なのではないかと考えを改めるに至った。一八〇度評価が変わったのは、ドライな風通しのよさ&見切り発車の潔さみたいなスタイルを極めていけば、いずれ『悪党パーカー/人狩り』やJ・P・マンシェットのネオポラールのような境地に行き着くかも、という思いがよぎったからである。疵や粗が多いのも確かだが、そういう無茶振り的な期待と可能性(『DIVE』の作者に不足していたのはこれなのだ)を感じさせる新人として、『マリアを運べ』を大賞に推すことにする。
選評 清水直樹
第十四回目のクリスティー賞は、選考委員が四人に戻り、最終候補に残った四作の選考を行った。
私が最高点を付けたのは、『マリアを運べ』で、とにかくエンタメに徹しているのがいい。ある人とモノをA地点からB地点へ期限内に運ぶというシンプルなストーリーを、スピード感満載で一気に書き上げた印象。主人公の設定が選考会で議論になったが、「一度通った道は記憶している」という特殊能力を持った天才ドライバーなら、無免許の十七歳の少女であってもいい、むしろその方がドライビングの天才であることに説得力があると思う。ハードボイルドを意識したそぎ落とされた文体も、類型的に見えるサブキャラも、読み手をストーリーに集中させることに貢献しているように思え、『TAXi』シリーズや『ミニミニ大作戦』といったコンパクトなカー・アクション映画を観終えたような読後感を与える。エンタメ度では過去の受賞作と比べても屈指で、大賞にふさわしい作品だと思う。
次点は、『DIVE 青き闇の温もり』。最終選考に残ったのは『プラチナ・ウイッチ』に続いて二回目の作者だが、前作よりも読者を意識した作品になっていると感じ、その点は高く評価した。魅力的な導入部から、一気に物語にひきこまれるリーダビリティの高い作品で、今年の候補作の中で小説として最も読ませる力があると感じた。また、中国残留孤児という社会的な問題を絡めて構成しているのも物語に厚みを持たせている。一方で、収まりが良すぎるというか、ウェルメイド過ぎるのが気になり、新人賞の受賞作として積極的に推せなかった。
『「ゲルニカ」一九三七年』は、第二次大戦前夜のパリを舞台にした歴史ミステリ。ピカソが探偵役、写真家のブラッサイがワトソン役というだけでワクワクするが、肝心の、タイトルとなっている大作「ゲルニカ」と、本作で描かれる事件との関連性が最後の付け足しのように思え、もっと深く書いてこそのこの題材ではないかという印象があり、物足りなさが残った。
『踊るメサイア』は、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる絵画「サルバトール・ムンディ」の騒動をモデルにした作品。参考文献に上げられている、この絵画をめぐるドキュメンタリー映画との類似性が気になり、評価できなかった。
- <<前の記事:第十五回アガサ・クリスティー賞募集要項
- 第十四回アガサ・クリスティー賞贈賞式を開催:次の記事>>