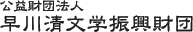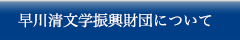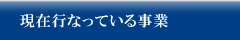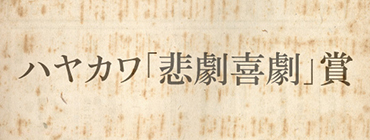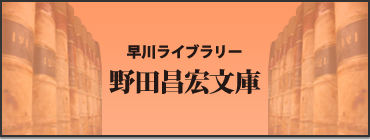第二回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考委員批評文
演劇界は将来有望
鹿島茂(フランス文学)
二〇一四年の演劇界で突出していたのは、蜷川幸雄演出の舞台でしょう。まるで、かつてのプログラム・ピクチャーのように、毎月、エネルギッシュな蜷川幸雄の芝居がどこかの劇場にかかっていました。その迸るようなエネルギーには脱帽せざるをえません。
もちろん、あざとさが感じられる蜷川演出に違和感を覚える人がかなり存在することは承知していますが、私はスペクタクル性というのも演劇の重要な要素だと 認識していますので、蜷川演出を否定しません。個人的にはストレート・プレイを好みますが、けれん味たっぷりのスペクタクル的演出も演劇の一方の極として 全面的に肯定されるべきものと考えています。
とはいえ、蜷川演出も年間に一〇本近くを数えるとあって、出来不出来があったことは確かです。
たとえば、前川知大作の『太陽2068』(Bunkamura)。ご贔屓の前川知大と蜷川幸雄が組んだということで、大いなる期待をもって観ましたが、残念ながら不発でした。なぜなのだろうと考えてみたのですが、主たる原因は劇場にあるようです。
前川知大の劇団「イキウメ」の芝居は青山円形劇場のような無機質的な空間にこそよく似合います。パラレル・ワールド的、近未来SF的な状況設定が青山円形 劇場のようなフラットで何の装置もない舞台に乗ると、観客は目の前に存在しないものを逆によく見ることができるようになるのです。不可視が可視的になるた めです。これが「イキウメ」の芝居の醍醐味なのですが、蜷川幸雄の東京における主たる舞台であるシアターコクーンの舞台装置では、この「不可視が可視的」 になる瞬間に立ち会うことはついにできませんでした。
もう一つの原因はセリフにあります。「イキウメ」の芝居は、一見、平凡に思えるセリフが、 前川劇をよく理解した劇団員同士の絶妙な掛け合いによって次第に興奮の度合を高めていき、最後は次元が違うアナザー・ワールドが現れるところに面白さがあ るのですが、『太陽2068』では、役者相互の呼吸があっておらず、各人が順番にセリフを吐くというレベルにとどまりました。シアターコクーンの音響効果 が悪くて、セリフが聞き取りにくいということもあったかもしれません。通常の蜷川演出では、セリフが聞きとれなくても別にかまわないのですが、この作品に 限ってはうまくいっていないという印象を受けました。
これと逆なのが、古川日出男作『冬眠する熊に添い寝してごらん』で、劇場は同じシアターコ クーン。しかも、セリフは『太陽2068』よりもさらに聞き取りにくく、ほとんど、何を言っているのかわからなかったというのが正直な感想です。ところ が、つまらなかったかというと、そうではなく、なかなか面白かったといえます。芝居というものは、セリフが理解できなくとも、芝居である限りにおいて理解 可能だという芝居のパラドックスを象徴しているような作品でした。
そして、これにより、蜷川演出が海外でも好評である理由がよくわかりました。そう、話されている言葉が外国語であっても、蜷川演出なら、理解可能なのです。これこそが、蜷川幸雄演出の真骨頂ではないでしょうか?
では、蜷川演出はストレート・プレーは向いていないのかというと、そんなことはない。と見事に主張したのが、クリストファー・ハンプトン『皆既食』 (Bunkamura)です。これもシアターコクーンでしたが、このときは巧みな俳優揃いだったためかセリフもすべて聞き取れました。しかし、この作品で 素晴らしかったのは、ランボー役の岡田将生。日本人にランボーは演じられるかという懸念を一瞬に吹っ飛ばしてくれた快演でした。この芝居は、一にも二にも ランボー役の俳優にかかっていて、ミス・キャストだったら、他が完璧でもすべてダメというように書かれています。その点、岡田将生が出現するまで待ち続け た蜷川幸雄の目は確かでした。
では、岡田将生ランボーで何がよかったかというと、「個対絶対の一元的基軸」という橋川文三の言葉を連想させるよ うな「詩的テロリストの倦怠と憂愁」が肉体から滲みだしているように感じたからです。これは得難い資質です。ただ、ランボーの詩というのが青春という特権 的な期間に「限定」された詩であるように、ランボーを演じられるという能力も期間限定のそれですので、岡田将生は今後、自分というものを正しく分析して進 むべき道を考えなければならないでしょう。次回作が楽しみな大型俳優の誕生です。
また、ヴェルレーヌ役の生瀬勝久も好演でした。実際のヴェルレーヌはもっと幼児性丸出しのダメ人間なのですが、ランボーに比べればはるかに人間臭いことは確かで、生瀬勝久はその人間臭さを巧みに演じていました。
いずれにしろ、蜷川演出の多様性に驚いた一年でした。
前川知大と「イキウメ」のことが先に出ましたが、前川知大作『関数ドミノ』は完成度からいえば、今年のベスト・ワンと言ってもいいかもしれません。二〇〇 五年が初演、二〇〇九年が再演ですから、三演ですが、錬成度では劇団「イキウメ」の最高作となっています。とにかく無駄なセリフはゼロで、すべてが数式の ように組み合わされてラストに向かっています。よく数学で最も合理的な解法のことを「エレガント」と形容しますが、私は『関数ドミノ』にこうした意味での エレガンスを感じました。
ただ、前回の選考会からの議論で、候補作は、再演、三演でもかまわないが、十年、二十年というタイム・スパンがあったほうがいいということになっていましたので、残念ながら、候補作を二つに絞る段階で、『関数ドミノ』は外れる結果になりました。
これに対して、劇団「イキウメ」の『新しい祝日』は前川知大の新作ということで大いに期待しましたが、いまひとつ乗ることができませんでした。
なぜなのでしょう?
一つは、アナザー・ワールドに入り込み、半信半疑ながら徐々にアナザー・ワールドの現実を信じていくときの主人公の意識の分裂が観客席にまで伝わってこな かったからではないかと思います。不思議な夢を見たと話している人の話に入っていけないときのもどかしさが最後まで消えませんでした。初演ゆえの練り上げ 不足もあるでしょうが、アナザー・ワールドものの不気味さと居心地の悪さがもっと感じられるようにすべきだったのではないでしょうか?
永井愛作・演出『鴎外の怪談』は、じつを言うとあまり期待を持っていなかったのですが、最初の場面から「もしかして、これはいけるかも」という思いに変わり、最後はスタンディング・オベイションで終わりました。
どこが優れているのかといえば、それは、主人公のはずの鴎外をあえて一種の「虚」として扱ったことです。この意味で、鴎外を演じた金田明夫は損な役回りでしたが、そこをうまく抑えて巧みに演じています。
ではなぜ、鴎外を「虚」とする必要があったのでしょうか? 妻、母、弟子(永井荷風)、若い友人(平出修)、軍医の友人(賀古鶴所)などが鴎外に対して抱 いている愛情のベクトルが異なっていることをうまく使って、それぞれの愛情のベクトルが最後にすべて鴎外という一点に集まるように演出したからだと思いま す。
これは、俳優が入れ替わり立ち替わり一つの同じ舞台に出てくるという演劇の本質に根差した演出であり、他のジャンル、たとえば映画でも、また小説でも不可能なことです。この複数の愛情ベクトルの集積のために鴎外は「虚」でなければならなかったのです。
もう一つ、舞台にはついぞ登場しないにもかかわらず、劇の「虚」の中心となっているのが山縣有朋です。作品の解釈に従えば、大逆事件は山縣有朋が明治国家 を守るために行ったフレーム・アップであり、鴎外はそれがフレーム・アップであることを知っていたために大いに悩んだということになっています。その悩み がドラマツルギーを生む構造になっているのです。
したがって、作品においては、鴎外を明治国家の枠組みの中に止まるよう説得する論理が強力であ ればあるほど、ドラマツルギーは強くなるように出来ていますが、この重要な役割を担っているのが友人の元軍医・賀古鶴所で、この人物がうまく造形できてい るかが、作品のポイントとなります。この難役を若松武史は素晴らしい演技で演じきり、作品に奥行きを与えるのに成功しています。もし、賀古鶴所が欠けてい たら、作品は明治という時代を射程に入れることに成功しなかったかもしれません。
同じく、家庭における明治帝国の論理を象徴しているのが鴎外の母で、これまた大方斐紗子が圧倒的な演技で、最大のクライマックスである「薙刀による外出阻止」の場面を演じ、明治の母の強靭な論理を体現してみせました。
この二人に比べて、個としての鴎外を支えるはずの永井荷風と平出修はいささか弱体ですが、その軽さを補うかたちになっているのが妻・しげのウルトラ個人主 義(ワガママ)です。鴎外はおそらく、自分の公的な側面は国家に捧げたのだから、せめてプライヴェートな側面では、美人で自我の強い女性を妻に持ちたい と、我を通したのですが、水崎綾女は、そのワガママぶりの演技によって、人間・鴎外の一番弱い点(美人好き)をうまく衝き、ドラマツルギーのバランスを 保っています。
とにかく、観ているうちに舞台にどんどん引き込まれていくという希有な体験をすることができた舞台でした。
四人の選考委員が推すという、満票に近いかたちでの受賞もしごく順当と思えるほどの出来栄えでした。
さて、ここの作品の講評は以上にして、今後の演劇界の展望に移りたいと思います。
ズバリ、直感を申し上げると、演劇界は将来有望です。なぜなら、人間の活動がバーチャルになればなるほど、人間は生身の存在との出会いを欲するからです。
その意味で、生身の俳優が舞台にいるということが重要な演劇は時代の要請に答えています。
しかし、その割には、日本の演劇界は層が薄いという印象を否むことができません。こちらがトロール網的に観劇をしていないからなのかもしれませんが、その俳優が出ているだけで観にいきたいと思うような俳優は数えるほどしかいませんし、演出家もまたしかりです。
演劇界は裾野を広げるための地道な努力、たとえば、コミケに似たような、演劇マーケットの開催のようなものが必要なのではないでしょうか?
「鴎外の怪談」三つのポイント
小藤田千栄子(映画・演劇評論)
森鴎外は、言うまでもなく明治の文豪。これだけではなく、日本屈指のインテリでもある。この人の家庭を背景に、ホーム・ドラマの外枠を持ちながら、『舞 姫』がらみの西洋の女性との関わり、さらには大逆事件(一九一〇年)裁判に関する森鴎外の、実に危うい立場などを描いている。この三つが「鴎外の怪談」の ポイントである。
まずはホーム・ドラマの面白さ
公演パンフレットの裏表紙に、森鴎外の家=観潮楼の平面図が載ってい る。開演前に、まずはこの平面図を見て、さすが森鴎外の家って広いなあと、見入ってしまった。もちろん有名な観潮楼だし、来客も多いだろうから、これくら いの広さは、必要なのかも知れないが、それにしても広いし、部屋数も多い。六畳とか四畳半の部屋が、十くらいはある。
別枠で、二階の平面図があり、洋間十二畳、女中部屋八畳、物置六畳とある。そして芝居が始まってみると、主舞台は、二階の洋間十二畳であることが分かった。ここに森鴎外の家族が出入りし、さらには若き日の永井荷風などが姿を見せる。
まず登場するのは、森鴎外の再婚の妻しげ(水崎綾女)。洋書でいっぱいの鴎外の本棚を見ながら、かなり辛口の感想など。この導入部で、人柄の一部が分か る。すでに娘が二人いるが、いま妊娠中で、まずはこの人の食欲描写で笑いを呼ぶ。新入りの女中さんを使って、お鍋に入ったご飯を運ばせているのだ。
そこに登場するのが、鴎外の母・峰(大方斐紗子)。すべて承知の姑ぶりが、さらに笑わせてくれる。大方(斐紗子)さんだと、ああ、そうかやっぱりと、すぐに納得し、いかにもありそうな現実感が漂って、これはもう配役の勝利だった。
同時に、鴎外の嫁・しげを演じる水崎綾女も、とても良かった。知らない女優さんだったが、キャスト紹介によれば、ホリプロ所属で、映像の仕事が多かったらしい。いかにも現代の女の子みたいな作り方が、うまいと思った。
鴎外が、復活の第一作で『半日』を書けば、こっそりと自作の小説『一日』を書いてしまう面白さ。史実かどうかは、私は分からないのだが、『半日』に対し て、すぐさま『一日』だなんて、もう笑うしかないだろう。森鴎外の再婚の妻は、こういう人だったという作者の描き方が、笑わせてくれるのだ。
観潮楼の二階洋間に現われる来客は三人。まず平出修(内田朝陽)は、雑誌『スバル』の発行人。鴎外の作品を掲載するだけではなく、大逆事件の弁護人のひとりでもある。
そして永井荷風(佐藤祐基)は、『三田文学』の編集長として登場する。すでに花柳界の人気者だったような描写もある。
そしてもうひとりが、賀古鶴所(若松武史)。森鴎外の親友で、当時五十五歳。この時代=鴎外=四十八歳なので、やや年上の友人である。耳鼻科医とのことだが、この芝居では、山縣有朋と親しいとか、鴎外周辺の政治的な側面を背負って登場する。
もうひとり新入りの女中さんスエ(髙柳絢子)がいる。この人は、オリジナルのキャラクターだそうだが、出身=和歌山に設定したところが鋭い。大逆事件といえば和歌山だし、しかも事件の、被告のひとりと知りあいだったという設定が、ドラマ性を高めている。
そして主人公=森林太郎(鴎外)は、もちろん作家であり、当時、陸軍軍医総監、陸軍省医務局長。つまり官界の大物でもあるのだ。鴎外は、まずは仕事帰りの軍服で登場するのだが、かなり来客の多い家であることが分かる。そして同時に、当時の検閲の問題なども語られる。
こういう人の家庭描写が中心であり、セリフで、幼少の二人の娘のことが語られると、見ている私たちは、ああ、森茉莉と、小堀杏奴のことだなと思い当たり、当時、何歳だったのかしらなどと、関係ないことにまで、頭がまわってしまうのだった。
当時(一九一〇年=明治四十三年)にしては珍しいなあと思ったのは、森鴎外家が、クリスマスを祝うことだった。クリスマス・ツリーがあり、その飾り付けの シーンもあるのだ。やっぱり森鴎外は、ドイツ留学していたので、西洋の風習を早くも取り入れていたのか、などと教えられたりもした。
鴎外夫人と、鴎外・母との間に、いささかの距離があったとしても、一応、家族はまとまっている。そんな中にあって、鴎外ひとりが、やや腰が引けているという感じあり。いや、ホーム・ドラマというのは、本来、こういうものなのかも知れない。
『舞姫』=西洋女性との関わり
二つ目のポイントは、森鴎外と『舞姫』のヒロイン=エリスとの関わりである。『舞姫』は、映画でも見たことがある。篠田正浩監督『舞姫』(一九八九年作品 /西ドイツとの合作/主演=郷ひろみ)。当時の面影が残っているとのことで、東ドイツ・ロケでの撮影だったが、古典的な都市の映像が、なかなかに見事で、 かなり堪能できる作品だった。もちろん内容は、軍医として留学中の森鴎外が、踊り子エリスと恋に落ちる。だが、ドイツに来た友人に説得されて、恋よりも国 家を選んでしまう話である。いわば悲恋物語なのだが、別に捨てなくてもいいのにと、私など思ってしまったのは確かである。
西洋人が、日本女性を捨てると、よく人種差別などと言われるが、日本人が、西洋の女性を捨てると、人種差別にはならないのだなあ、などとも思ったものである。
『舞 姫』は、宝塚歌劇でもミュージカルになっている。二〇〇八年三月=日本青年館。脚色・演出=植田景子。物語は、ほとんど、いじってはいない。陸軍のエリー ト官僚(愛音羽麗)が、ドイツに留学し、エリス(野々すみ花)と恋に落ちる。だがベルリンに来た大学同期の友人に説得されて、結局は、国家を選んでしまう 話である。
宝塚なので、男役スターに気を使った作り方ではあったが、主人公の屈折した思いなどが、大コーラスを交えて歌われると、なかなかの迫力であった。その大コーラスは、国家のエリートの、宿命のようなものさえ感じさせてしまったのだった。作曲=甲斐正人。
映画の場合も、ミュージカルの場合も、私は、森鴎外って、かなりヒドイなあという感想を持った。その思いが出ているのが「鴎外の怪談」にもあった。鴎外の母・峰が、ふと思い出したように、往時を回想して語るシーンである。
「二十年も前のことだが、留学から帰ったあの子を、ドイツ娘が追いかけてきたとき……」
「一族総がかりで二人を別れさせ、林太郎には、すぐ赤松男爵の御令嬢をめとらせた。でも、一年足らずで離婚だよ。於菟が生まれたとたん、長男ができたからもういいだろうとばかりに林太郎は家を出て……」(本誌=二〇一四年十一月号/以下、セリフの引用は同誌より)。
はっきり言って、森鴎外はエリスを裏切ったのだ。この裏切りが、いま現在の森鴎外をも捉えているのが、とてもよく分かるシーンがあった。妻しげが、家族で 食事に出かけましょうというシーンである。娘二人と、鴎外と、一家四人で出かけることになっていた。ところが鴎外に用事が出来て、行けなくなってしまっ た。すると妻しげは「あんなに前から約束したじゃないですか」と糾弾し、ついに〈裏切り者〉と叫んでしまうのである。
この一言が、鴎外には効いた。「裏切り者」のひと言が、鴎外には、ドイツ語で聞こえてしまうのだ。その言葉に捉えられて、ほとんど動けない鴎外。そうなのか。森鴎外自身も、そんなに気にしていたのかという思いが、客席に伝わる。ここで暗転になるうまさに感嘆した。
大逆事件/軍医としての森鴎外
大逆事件との関わりは、ひとつには、親友の耳鼻科医=賀古鶴所との付き合いから生まれている。この人は、山縣有朋の側近のようで、さらに森鴎外と山縣有朋 を近づけようとする。だが森鴎外は、いささか腰が引けていて、実は「軍医になどなりたくなかった。研究室で、顕微鏡を覗いていたかった。町医者として父の ように生きてもよかった。あのとき、母上とお前が軍医になれと勧めなかったら……」と、つぶやいてしまうのだ。
すると賀古鶴所は「森家の長男と して、ほかに選ぶ道があったか? 軍医にならずにドイツに留学できたと思うか?」と、たたみかけてくるのだ。さらに賀古鶴所は、こうも言う。「軍医になっ たら、お前は出世を望んだじゃないか。どうしても陸軍軍医の最高の地位につきたいと、俺に相談を持ちかけてきた。それには山縣公のお引き立てに与かるしか ないと、二人して計画を進めたんだ。それを忘れてもらっちゃ困る」
そうだったのか。森鴎外って、こういう考え、あるいは行動もしていたのかと、私など、教えられることが多かった。やっぱり、ただの文豪ではないのだ。そしてこの作品は、森鴎外の、こういう面に斬りこんだところが、さらに面白い。
同時に、賀古鶴所は〈キング・メーカー〉でもあり、森鴎外を、さらなる高みに押しあげようとさえする。「お前を男爵にしたかった。貴族院議員になる姿を見 たかった」とさえ言い放つのである。これにはなんと森鴎外、ほんの少しだが、反応してしまうところが、鋭い。鴎外は「男爵……貴族院議員……」と、つぶや いてしまうのである。ああ、やっぱり、男って……の感じあり。森鴎外にして、そうだったのか、と。
そして、もうひとつは、新入りの女中さん=ス エを,和歌山出身に設定したことだ。このオリジナル・キャラクターは、戯曲自体の、とても鋭い一面となっている。芝居の前半で、賀古鶴所が「生まれは紀州 のどこ?」と問うたとき、「新宮です」と答え、私たちをハッとさせる。「このたびの陰謀事件の、ドクトル大石の拠点じゃないか。ドクトル大石を知ってるだ ろう?」と問われて「いえ……」と答えるので、私たちは、ひとまずホッとする。
さらにクリスマスのシーンで、スエがシチウを作るシーンがある。 「西洋料理が出来るのか!」と驚く鴎外。やがてスエは、ドクトル大石がやっていた太平洋食堂なるところで、西洋料理の講習会に出たことなどを話していくの である。そしてドクトル大石には、とても世話になったこと。新宮では、貧乏な人も、みんなドクトル大石に診てもらったことなどを語り、さらに大逆事件で捕 まっているドクトルを助けて下さいとも言うのである。スエは、森鴎外が、裁判と関わっていることを察しているのだ。
そして戯曲として素晴らしいのは、このスエの訴えのあと、鴎外には、かつての、迫害されたキリシタンの祈る声が聞こえてくることだ。鴎外の慚愧の思い。それでいながら、大逆事件には、関わっているようで、実のところは、何も出来ていないことを漂わせてしまう見事さ。
多くのことを詰め込みながら、文豪=鴎外の真実のようなもの。これを漂わせているのが『鴎外の怪談』の、いちばん優れているところだと思っている。
キャラクターとして花を添えているのは、『スバル』編集・発行人の平出修で、大逆事件の弁護士のひとりを兼ねている。そして、もうひとりは、言うまでもな く永井荷風である。永井荷風って、わりと晩年の写真を見ることが多く、最初から〈ジイサン〉というイメージが強いが、もちろん若いときもあったわけで、そ れを二枚目の佐藤祐基が演じている。ゆえに、これなら永井荷風もモテたに違いないなどとも思ってしまうのだった。
女優さん三人の達者さに対して、男優さん四人の、それぞれの個性の作り方が出色であったことも、この作品の魅力を高めていた。
森鴎外=金田明夫は、タイトル・ロールの主役でありながら、周囲に翻弄されてしまうところが、この芝居のポイントでもあり、ああ、そうだったのか、森鴎外って、そういう人だったのかと、教えられもしたのだった。
個性いちばんは、やはり賀古鶴所=若松武史だった。どんな芝居でも、この人が出てくると、ただでは引っ込まないという印象を、私は持っているのだが、今回も、ちょっと不可解な、だが裏では相当な実力者であることを、さりげに示してしまうところが見事だった。
若い男優二人=平出修(内田朝陽)と、永井荷風(佐藤祐基)は、この芝居に、爽やかな風を吹かせたところが見事だった。前者は編集者でありながら弁護士、 後者は編集者でありながら作家という二面性を持ち、それぞれ優れた人たちでありながらも、わりと普通感覚を持っているのが、この芝居に普遍性を持たせたと 思う。
ところでタイトルの『鴎外の怪談』の〈怪談〉とは何のことだろうか。私は、鴎外の二面性、あるいは多面性と解釈し、それは結局〈不思議さ〉に通じているように思っている。
『酒と涙とジキルとハイド』
今年の「悲劇喜劇賞」は『鴎外の怪談』に決まったが、「悲劇」と「喜劇」に分けたら、これはどちらなのだろうか。私は「悲喜劇」のような気がするのだが、 全くもって完全喜劇なのが『酒と涙とジキルとハイド』であった。作・演出=三谷幸喜。私は、次点という感じで『酒と涙とジキルとハイド』を推した。
これは、ひと言でいえば、いくら薬を飲んでも、ハイド氏になれないジキル博士の話である。こんなことって、あり? の世界なのだが、なんと〈あり〉なのであった。
薬を飲んだら、次はハイド氏になる。これが『ジキル博士とハイド氏』のお約束である。映画にも、芝居にも、何度も登場しているが、いつだって、ジキル博士は、薬を飲んだらハイド氏になるのだ。
無声映画版を見たことがあるが、まだ映画技術が発達していない時代だったので、なんと俳優の演技だけで、ジキル博士はハイド氏になってしまうのだった。ジョン・バリモアって、やっぱり名優でしたよ。
最近のミュージカルでは『ジキル&ハイド』(東宝)がある。初演は鹿賀丈史、再演は石丸幹二で、ともに元四季の二枚目テノールが演じたが、これなんか一曲歌っているうちに、ジキル博士は、ハイド氏になってしまいましたからね。
ところが三谷幸喜版のジキル博士は、いくら薬を飲んでもハイド氏にならないのだ。仕方なく、ハイド氏役として、シェイクスピア俳優を雇うという展開だった が、こんなことを思いついたのは、おそらく世界でも三谷幸喜くらいのものであろう。ニール・サイモンも、アラン・エイクボーンも思いつかないことであろ う。やっぱり三谷幸喜は、スゴイなあと思わせる芝居だった。
劇の言葉を磨く
今村忠純(日本近代文学)
『新・明暗』(二〇〇二)に始まり、『書く女』(二〇〇六)につづいて、二〇一四年に二兎社が上演したのは『鴎外の怪談』でした。
夏目漱石の未完小説『明暗』のそのつづきまでを追いながら、これをあらためて劇空間に仕立て直し評判になった、再演も果たしました。それが『新・明暗』でした。『書く女』は、樋口一葉と周囲の人々の生き生きとした交流、とくにもの書く女性へのオマージュとして永く記憶される劇でした。
山本郁子のお延に寺島しのぶの樋口一葉の好演も逸することができなかった。
漱石と一葉と鴎外、といっても劇の形式は題名から見当がつくのですがともにことなります。しかし劇は、どれも日本近代を代表する三人の作家(作品)に対する入念な調査・研究が前提になっていました。
『鴎外の怪談』は、小説家森鴎外のはじめての口語体小説「半日」による復活、つづく「ヰタ・セクスアリス」「沈黙の塔」「食堂」などの小説、また評論「ファスチェス」に永井愛さんは、くまなく目をとおしています。とくに鴎外小説の言葉を次々と劇の言葉に生かし磨きあげていく、これにはほんとうに感心しました。
その結果どのようなことが起こってくるか。小説家森鴎外の復活、第二の出発がどのようにおこなわれたのか、これを劇のかたち、つまり登場人物のせりふをかりて論じてみせてくれた、といってもいい。たとえば「沈黙の塔」の結末をわざと口ごもらせて女中のスエに読ませたり、「沈黙の塔」はもとより、「食堂」について峰やしげが賀古、とくに荷風に問いかけ、これらの作品をめぐっての対話から鴎外の思想を観客に熱意をもって伝えていこうとするプロットにすっかり感心してしまったのです。
「沈黙の塔」「食堂」のこの二つの作品をあげれば、明敏な読者はただちに『鴎外の怪談』には、大逆事件の影が落ちているのではないかと見当をつけられるかもしれません。たしかにそのとおりなのですが、そこにはやはり永井愛一流のアイロニイ、というよりも公人と私人とのあいだで激しく動揺する、しかし愛すべき鴎外像がつくられているのです。
そこであらためて『鴎外の怪談』のプロットを検討しなおしてみたいと思います。
『鴎外の怪談』は、一幕五場の劇です。一九一〇(明治四十三)年十月下旬に幕が揚がり、そのあくる年一九一一(明治四十四)年二月下旬に幕が降ります。
森鴎外の居宅観潮楼二階が舞台になっており、演劇内時間は、一場ごとに一カ月が、つまり五カ月が経過していきます。上演時間は、ほぼ二時間半でした。
「好イ年ヲシテ少々美術品ラシキ妻ヲ相迎ヘ」と四十になった鴎外が、いささか照れくさそうに、しかしほんとうに心からうれしそうに、年上で終生の盟友であった賀古鶴所に報告した手紙がのこされていました。大審院判事荒木博臣の二十二の長女しげと再婚した鴎外は、わずか三カ月足らずの小倉でのまちがいなく至福であった新婚生活を送り、帰京します。一九〇二(明治三十五)年三月、この二人を観潮楼に待ちうけていたのが母峰でした。
つまりこの劇の幕が揚がるのは、それから八年目の一九一〇年ということなのです。鴎外はしげとのあいだに長女茉莉、二女に杏奴をもうけているし、鴎外その人はといえば、一九〇七(明治四十)年に陸軍軍医総監となり、陸軍省軍医局長に就任していました。
さらにこの劇に深くかかわり、いちばんに知っておきたいことはやはり山縣有朋の輪廓ではないでしょうか。山縣有朋と森鴎外との関係についてならば、賀古鶴所や峰、と鴎外の劇中の言葉(対話)によって十分すぎるほど十分に理解することができると思われます。
一九〇九(明治四十二)年十一月十八日付の東京朝日新聞を引用しておきます。「山縣枢相となる」がそれです。
枢相親任式 十七日午前十一時、宮中に於て親任式を行はせられ、桂首相参列の上山縣公、牧野伸顕男を御召の上、左の辞令を御配授あらせられたり。
枢密顧問官元帥陸軍大将正二位大勲位功一級公爵 山縣有朋
山縣有朋の上奏で西園寺公望の後継首班に指名されたのが桂太郎。第二次桂内閣は、無政府主義・社会主義の取締りを一層強化していくことになります。
山縣有朋は、はやくには徴兵令の制定のみならず、また教育勅語の渙発の国民教化(第一次山縣内閣)などもふくめ、帝国陸軍の軍制の理念を確立し、やがて陸軍(省)の最長老、元老として官政界はもとより、貴族院、枢密院、そして宮中に対して目を光らせ絶大な権勢をふるうことになった代表的な藩閥政治家として知られています。山縣有朋の構想した国家と軍部の青写真に、鴎外の陸軍軍医総監というポストも担保されていたのです。ひいては今日の、現代国家防衛をかたちづくる大本の思想が、山縣有朋の思想に見通せるといってもけっして過言ではありません。
さてこの劇は、しげのいま書いている口語体小説の言葉を、しげ自身が口に出しているところから始まります。
劇中の峰の言葉をかりれば「林太郎の真似をして小説を書き出した」という、そのしげのいま書いているのは「一日」という小説です。もっといえば、この「一日」は鴎外のはじめての口語体小説「半日」のむこうをはってつけられていた題名でしたからほんとうにおかしくて笑ってしまいました。峰としげ、つまり姑と嫁の対立は「半日」に知られているとおりですし、さらに鴎外には前妻とのあいだにもうけた於菟がいました。この劇に於菟は姿を現しませんが、於菟にも心をくばり、しげと峰を気遣う鴎外にまで永井愛の目がとどいているのです。
この劇が見事だったのは、さらに大成功をおさめたのは、このしげの(独語といっていい)言葉から始まっていたことにあります。
そして「一日」というしげの小説が、書かれざる小説になってしまったというそのてんまつこそがこの劇の結構になっていたのにほかなりません。
しげの書かれざる小説「一日」が、鴎外の人生の後半生を決めたことになる、結果としては、これが永井愛の着想でした。しげのせりふをかりれば「富子の夫が山縣公のもとへ行かなかった」、だから「一日」は焼き捨てられたのでした。
長くなりますが、やはりこのしげのいちばんはじめのせりふ(独語)、「一日」の草稿を引用します。ト書は省略します。
富子の夫は、先生だの博士だのとの世の尊敬を集めているが、その実、金とは縁が薄い。それなのに、ほとんど病気ででもあるかのように、西洋の書物を買い入れる。そして、「芸者に注ぎ込むよりマシだろう」などと澄ましている。富子も仕方なく、「そうですね」なんぞと言っている。
ところが最近ある方面の人たちが、「西洋の書物は危険だ」と言い出した。ついには、ある新聞が「危険なる洋書」という連載まで始めた。これによれば、夫が半生をかけて集めた洋書のほとんどは、危険なる思想に毒されているらしい。
イプセンは健全なる家庭生活を破壊する。モーパッサンは人々を色欲に狂わせる。ゾラは人間の醜さのみを描き、ニイチェは道徳を否定し、ベルレーヌは堕落してもよいのだと囁く。そこに吹き込むのは、「政府は転覆せよ」と煽るロシアの風だ。ことにトルストイ、ツルゲーネフ、ゴーリキーなぞは、社会主義、共産主義、無政府主義などの恐ろしき革命思想を、さもよいもののように宣伝する、文芸の皮をかぶった狼なのだとか。
富子はこの連載を愛読した。そして、危険だと言われれば言われるほど、読みたくてたまらなくなった。ついにイプセンに手を出した。今では、「妻である前に、まず人間でありたい」なんぞと思うようになっている。ああ、恐ろしや、恐ろしや……
鴎外が「半日」に書いていたように「此家に来たのは、あなたの妻になりに来たので、あの人の子になりに来たのではない」としげは鴎外にいいはなっていたのにちがいありません。
もししげの書いた小説集(『あだ花』)を読み、「半日」を読んでいる観客(読者)ならば、なるほどしげは、このような小説(「一日」)を書いていたであろうと膝をうち、合点します。いや「半日」の読者であるだけで、永井愛のしげ像にも十分納得がいくと思います。そしてもちろん峰像についても。
しげは、鴎外の月給がそのまま峰の手にわたるのも、がまんならなかったばかりではなく、峰との同席をいやがり食事も別間でとっていたのです。女中のスエにこっそり食事を運ばせるというのも、そういうしげのふるまいのあらわれとして理解できます。
第一場で平出修と賀古鶴所のこの二人が観潮楼に姿を現わします。平出修は大逆事件の弁護団の一人に選任されましたから、くわしくこれの内容を知るところとなっています。
これの善後策を鴎外に仰ぐとともに以後は平出修の口をとおして、逐一秘密裁判の推移を知ることになります。私たちも劇場の観客席からこれを見守りつづけます。
いっぽうのもう一人が森鴎外にもたらすのは、椿山荘で秘密裡のうちに開催される元老・山縣有朋をかこんでの懇談会・永?会の日程でした。いうまでもなくそのもう一人とは賀古鶴所のことです。ここで協議されることが、大逆事件問題終息にむけての工作であることを、また私たちも知らされるのです。
こうしてこの劇の第一場が、一九一〇(明治四十三)年十月下旬に始まるのにも、以後の劇展開を周到にみきわめた上でのことであるということを理解しなければなりません。
(永井愛)の劇の骨組を読みながら劇は批評されるべきであって、思ったこと感じたことを外野席で得手勝手にはやすのは、劇評でもなにものでもありません。
さて第二場では、永井荷風が姿を見せます。森鴎外の推薦で、慶應義塾の先生におさまった荷風を通じて、荷風その人のことはもとより「三田文学」や「早稲田文学」、また一九〇九(明治四十二)年に旗揚げした小山内薫の自由劇場のことが話題になるなど、文学・演劇の同時代の語られているのが第二場です。もとよりそれにとどまらない。文学・演劇の同時代を語るということは文学者、演劇人としての鴎外の顔がおのずとそこに見えてくることを意味します。さらに大事なことは、同時代の文学者たちの、いわば大逆事件認識についての問題も明らかにしている、判決以後の文学者の動向も伝えているのです。
第三場は、十二月二十四日の夕方、つまりクリスマス・イヴ、大きな樅ノ木を運んで来たのは永井荷風、日本では禁止されてきたキリシタンのお祭りが、いつの間にか日本の暦になっているというのです。新しい思想が古い思想を更新するという鴎外の論理をこのキリシタンのお祭りに重ねあわせるようにして危険思想といわれている無政府主義の思想のありかたを説いてみせてくれるのが、この第三場なのです。鴎外には津和野の乙女峠でのキリシタン弾圧の記憶がよみがえっています。
第四場は一九一一(明治四十四)年一月十八日夜、大逆事件の判決のくだされたその日の夜、荷風にこの裁判のカラクリを説く役まわりを演じさせ、鴎外を山縣有朋のもとに出かける決意をうながします。荷風、そして賀古と鴎外とのあいだにかわされる必死の言葉にこそ、劇の言葉の論理に命をけずる永井愛の本領が発揮されていたことは、あらためてことわるまでもありません。
しかもこの一部始終を丸窓の障子のむこうで聞き耳をたてていたしげが、とつぜん出現するとは、一体だれが想像していたでしょうか。さらに薙刀をふりかざし、白装束の峰までがここに現れるとは。そればかりではありませんでした。峰は、懐剣をとりだし、自分の命にかえても、これから山縣有朋のもとにむかおうとしている鴎外の前にたちふさがるのですから。
しかし「歴史」を書きかえることはできません。すこぶる上機嫌に声をはずませ鴎外を送り出そうとしていたしげもいたし、そのような鴎外を立ちどまらせた峰もいた、つまりそのようにそれぞれの人知れず思い屈した気持を伝えることこそ劇のちからであること、そのことを教えられる、そこにかくれた詩と真実があるのです。
第五場は、一九一一(明治四十四)年二月下旬、しげに待望の男子が誕生します。類が生まれました。不律を生後間もなく亡くしていますからしげにとっては二番目の男子の出生なのですが、そのことが森家にどれほどのしあわせをもたらしたかということをこのエピローグは語りかけています。
二十年前にベルリンで買ったボタンが身になじんでいた、そのボタンの一つをどこかでなくしてしまった、そのなくしてしまったボタンと重ねあわせるようにうたっていたのが「こがね髪ゆらぎし少女/はや老いにけん/死にもやしけん」というよく知られた「うた日記」の「扣鈕」でした。「少女」に、「舞姫」のエリスとの記憶を結びつけ、いってしまえば「半日」のお嬢さん育ちの奥さんとの関係に結着をつけようと試みる、そこに『鴎外の怪談』が成立していたのかもしれません。
またいわずもがなのことなのですが、エリスと太田豊太郎、豊太郎と天方伯、豊太郎と親友相沢謙吉の関係(「舞姫」)も「歴史」は、大多数の読者の知らぬところとなっています。しかし、太田豊太郎とその母の関係(「舞姫」)と、文学博士高山峻蔵と母君の関係(「半日」)からきれいに割り出された鴎外と峰とであってみれば、かたぐるしい「歴史」(事実)にしばられることのない、たのしい批評でありたいと私は切に思っています。鴎外は「歴史其儘」と「歴史離れ」の、その是非をはたして問題にしていたか、けっして問題にしてはいなかったとおもいます。くもった眼鏡をはずし、「歴史」とは何かを問うところから始めなければならない、そのように『鴎外の怪談』を観ながら考えました。
大方斐紗子の峰はもとより、金田明夫の森鴎外、若松武史の賀古鶴所の、それぞれの役どころの急所をおさえた、緩急自在な演技に舌をまきました。水崎綾女のしげには、身を投げ出すような放胆さがあり、内田朝陽の平出修には、書生っぽの弁護士の真直さがあり、佐藤祐基の永井荷風には、いいかげんな、しかしおやと思わせるような芯の強さが見つかりました。「聞こえてまへん。聞こえてもわかってまへん」といっていた髙柳絢子のスエが、ドクトル大石から教えてもらったシチウをつくり、鴎外にドクトル大石の命ごいをする言葉が忘れがたいものになりました。劇とはスエのような進行係が生きてたちまち劇の筋道が見えてきます。スエは森家のすべてを知っています。
「菜が居合い」が鮮やかに斬った鴎外と時代の心
高橋豊(演劇評論)
「永井愛」とはどんな劇作家・演出家か。登場人物や時代・社会への「長い愛」を持つ人と捕らえるのが、一般的だろうが、「菜が居合い」と読めないか。
瞬間に相手をきる「居合い」の武器が、剣ではなくゴボウや大根、ニンジンなど、ごく日常の食卓の菜っ葉であることに驚きがある。その覚悟を持って、時代を 社会を、きっちり鮮やかに見直していく。日々の暮らし、生活へ深い目を注いでいるからこそ、永井の作品は私たちの心を打つ。
長く永井の舞台を観続けた者の一人として、まず彼女の軌跡を簡略にたどりたい。
一九八一年に結成された二兎社は、永井ら兎年生まれの女優二人の劇団で、互いに創作を行って出演、早替わりが面白い「カズオ」など、話題を呼んだけれど、九一年に永井が単独で主宰するようになってファンとしては正直、先行きがどうなるか心配だった。
九四年、「時の物置」を皮切りとする「戦後生活史劇三部作」が二兎社と永井に対する注目度を飛躍的に高める。
第一作は、テレビなど家庭に物質文明が流れ込んだ昭和三十年代を、次作「パパのデモクラシー」は敗戦直後の都市生活者の生態を描き、最終作「僕の東京日 記」が七〇年安保闘争の挫折から個に分裂していく人たちの生活を活写した。時代の転換期に立つ人々を丹念に造形し、生活感のある群像劇となっていた。
九七年、永井は二兎社以外の劇団のため新作を書く。
青年座へは祖母をモデルにした明治時代の女子師範学校が舞台の「見よ、飛行機の高く飛べるを」である。秀作。若い女優がたくさん出て、大いに華やいだ。
テアトル・エコーには、「ら抜きの殺意」を書き下ろした。こちらは現代も現代。いい大人まで「ら抜き言葉」を使ってしまう現実を見据えながら、永井は「男 言葉」と「女言葉」を区分けしようとする日本語特有の現象に切り込んでみせた。本作で永井は第一回の鶴屋南北戯曲賞を受賞したのだけれど、表彰式で当時、 日本劇作家協会会長だった井上ひさしの辛口の挨拶が、今も忘れられない。井上は「永井さんが受賞後にどんな作品を発表するかが決め手で、ずっと問われる。 その成否によって、南北賞の価値も評価されるだろう」。
同賞の選考委員は、東京演劇記者会所属の現役の新聞記者たちが務め、私もその一員だった けれど、井上の迫力ある一言に度肝を抜かれた。実は井上の新作も候補作の一つに挙がっていたのだが、永井作品の評価の方がずっと高かった。今になれば、井 上の〝直言〟がよく分かる。笑いを交えながら社会の真実を突く「ポスト井上ひさし」を永井に託すため、敢えて厳しい注文を井上は付けたのだろう。
もう少し、永井のこれまでの軌跡をたどる。
男女間の「本音」と「建て前」にさらにメスを入れた作品が、二〇〇〇年初演の二兎社「萩家の三姉妹」である。舞台は現在の日本だけれど、チェーホフの「三 人姉妹」を根底にしながら、長女はフェミニズムの研究家の大学助教授で、次女は専業主婦だが、不倫に走り、三女は未だに自立できない。日本の「男社会」の 欺瞞性を、笑いと共に徹底的に暴き出している。
翌〇一年に初演の「こんにちは、母さん」が、永井の家庭劇の傑作だと思う。七十歳を過ぎた母親の 老いらくの恋が中心のようだが、実は中年の息子の心模様に焦点を当てる。彼は会社でリストラ担当を命ぜられ、家庭は離婚寸前で、ストレスはたまるばかり。 二年ぶりに母親が一人で住む実家に戻ったけれど、会話が続かない。母と子が心を開き、真にもう一度、新たに出会えるまでを丁寧に描き出している。
永井は政治的な社会問題からも決して逃げない。
代表が〇五年初演の「歌わせたい男たち」だ。ある高校の卒業式で「君が代」を歌わせたい校長と、それに反対する教師とのドラマが中軸である。単なる論争劇 でなく、校長がピアノ演奏のために売れないシャンソン歌手を音楽担当して雇ったり、反対側の教師にもさまざまな屈折があるなど、しっかり笑いを盛り込んで いるのが、永井らしい。今の教育現場における「国旗」「国歌」の問題に真正面から取り組んだ舞台だった。
一〇年には、新作「かたりの椅子」を発表、アートの世界でも免れない日本の「官僚主義」を喜劇として提示してみせた。公立劇場の運営をめぐり、永井が体験した不条理のおかしさを反映させた作品だった。
硬派のイメージが強くなった永井だが、〇四年に女優三人のグループる・ばるに書き下ろした「片づけたい女たち」のようなリラックスして楽しめる舞台もあ る。片づけることが苦手で、モノが散乱し、埋め尽くした部屋で、中年期末の女性三人が「まだやり直せる」「まだ勝負は終わっていない」と言い合う切なさ、 おかしさ。
以上、劇作家・永井の作品は、やわらかなユーモアに包まれたウェルメードの劇でありながら、きっちり現代日本社会の問題の「本質」をあぶりだしてみせる。
さて、今回の二兎社の二年ぶりの新作「鴎外の怪談」(永井作・演出)である。斬新な喜劇が基調で、客席からは笑いがよく起きた。
森鴎外(林太郎)は、明治・大正期を代表する文豪として精力的な文学活動を展開した一方、陸軍軍医総監・陸軍省医務局長と軍医としての最高ポストに上りつめた。
あの時代には珍しく、フェミニズムに理解を示し、子供たちにも優しかった。文学者と軍職者と「二つの頭脳」を持つ鴎外が、最も危ういバランスを生きた時期に、永井は焦点を当てた。
一九一〇(明治四十三)年、社会主義者の幸徳秋水らが明治天皇の暗殺を企てたとする「大逆事件」が報じられたころの、鴎外の住居「観潮楼」が舞台だ。下手に階段がある二階の設定なのだけれど、〝鴎外の階段〟と思えるほど、さまざまな人がこの部屋に出入りする。
まさしくサロン。右の超保守派から左の革新・進歩派まで多様な人の訪れを鴎外は決して断らない。ドイツ留学を経た彼による、当時の日本としては、大変リベラルな環境が生まれたのだけれど、生来の人間嫌いが時に出てきたりもする。
「鴎外の怪談」は、冒頭、鴎外(金田明夫)宅の主導権をめぐって、後妻・しげ(水崎綾女)と母・峰(大方斐紗子)の壮絶な言葉によるバトルで始まる。鴎外は妻に対しては「良い夫」、母に対しては「良い息子」としてふるまい、危ういバランスを取っていた。
「大 逆事件」で逮捕された被告人の弁護人を引き受けた文学者・平出修(内田朝陽)は『スバル』の編集・発行人だけれど、ヨーロッパの社会主義・無政府主義に造 詣の深かった鴎外からレクチャーを受けにやってくる。鴎外を慕う作家・永井荷風(佐藤祐基)も、この事件に関心は深い。
観潮楼には、平出らとは 全く立場の違う人物が頻繁に訪れた。鴎外の親友で、同じく帝国陸軍の医局に所属する賀古鶴所(若松武史)らだ。鴎外も賀古も、時の大権力者・山縣有朋の私 的諮問機関「永錫会」のメンバーであり、社会主義者の徹底的な取り締まりを目的とした極秘の話し合いを行っていた。
登場人物七人のうち、実在し なかったのは、お手伝いのスエ(髙柳絢子)だけである。和歌山県出身の彼女は、「大逆事件」で処刑される医師・大石誠之助が営んでいた太平洋食堂で西洋料 理を習い、シチュー料理など習得していた。鴎外の〝サロン〟の第三者、私たちに最も近い庶民の「観察者」と言えるかもしれない。作者の永井は絶妙なタイミ ングでスエを登場させ、「二つの頭脳」を持つ鴎外の右往左往の目撃者となる。
本作の魅力の一つは、鴎外や賀古、平出や荷風とのやり取りで「大逆事件」の実相が伝わってくることだろう。
親友同士だが、鴎外は賀古へ「この秘密裁判の言い分が通用するのは日本国内だけだ。すでに欧米各国は疑いの目を向けている」と批判する。賀古は「国家には 秘密にしなければならないことがある。わが国及びわが国民の安全の確保のために、保護しなければならない秘密はどうしたって出てくる」と切り返す。
特定秘密保護法を含め、現在の政治状況の問題をリアルに考えさせるのだ。反対勢力を「圧殺」することを国はためらいもしない。
本作の魅力の二点目は、妻しげと母の峰が実に生き生きと描かれていることである。特に後妻のしげは悪妻の評があったけれど、フェミニズムに理解を示す夫・ 鴎外との良好な夫婦関係がよく分かる。夫を子供たちと一緒に「パッパ」と呼び、新聞が「危険なる洋書」などで夫の愛する欧米書を追放する動きを嘆く。鴎外 が書いた「半日」に対抗して「一日」を執筆したいと思っている。
鴎外のデビュー作「舞姫」での、ドイツ人女性エリスへの思い出もちゃんと登場する。「恋人を捨てる罪の意識を、日本で初めてちゃんと描いたのは鴎外だったのではないか」と、しげは夫へきっちり言うのである。夫の思いに対する再評価とも言えるかもしれない。
二兎社は、作・演出の永井単独の劇団だから、キャストは公演のたびに変わる。今回は全員が二兎社へ初参加である。それにしても見事なアンサンブル。
ベテランの金田、若松の演技の確かさに目が行ってしまうのだけれど、とりわけ、母・峰役の大方には大きな拍手を送りたい。頑固な姑のようでありながら、鴎 外への理解を示しつつ、終盤、「大逆事件」で山縣公へ〝直訴”に行こうとする息子を、白装束に鉢巻、薙刀姿でおし留めるのだ。実際にはありえなかったこと だけれど、舞台として観る限り、とてもおかしい。
「鴎外の怪談」は、なぜか今年度、他の演劇賞と全く無縁だった。
永井はかつて「打率十割」と言われるほど、毎年、さまざまな演劇賞に輝いていた。その結果、彼女への授賞レベルが高くなってしまったことが一因かもしれない。
もう一つ、「評伝劇」の宿命だろうが、鴎外、荷風ら高名な作家を取り上げると、外野席がやたらとうるさい。
「こんなことはありえない」など、いろいろ注文が出てくるけれど、永井の創造の世界だから、現実と違ってもいいではないか。さらに言えば、明治末期の話とみせて、永井は今の平成日本を描いているのではないか。
永井の心の中には現状に対する「危機感」がある。このままの日本では、どこへ行ってしまうのか。「大逆事件」前後の明治は、決して他人事ではない。
わきの話かもしれないが、本作が二兎社と公立劇場の共同制作だったことも記しておきたい。画期的なことで、公立劇場を中心に全国公演が行われたのだ。
永井愛のここ数年の久しぶりのスマッシュヒット。ハヤカワ「悲劇喜劇」賞の受賞作として何一つ文句はない。
* *
悲劇喜劇賞の候補として、私は「鴎外の怪談」と共に、「冬眠する熊に添い寝してごらん」(Bunkamura)を挙げた。実はこちらが第一候補のつもりだったから、紙面で少しばかり語りたい。
「冬眠する熊に添い寝してごらん」は、年初め、東京・シアターコクーンで上演された。四十代若手の小説家・古川日出男の書き下ろし戯曲を、もう八十に手が届きそうな蜷川幸雄が演出した。戯曲が文芸雑誌『新潮』に掲載されたことも珍しかった。
台本を一読、時空を奔放に行き来するなど、奔放な想像力に驚かされて、「これは作者から蜷川への挑戦状だ」と思ってしまった。詳細なト書きがあるのだけれ ど、どうやって舞台化するのか、ごく普通の演出家なら頭を抱えるはずだ。例えば〈ふいに舞台上に出現する「場面」。七人の老婆たちと仏壇=大仏壇をステー ジにとどめ置きながら、大胆に横切る一頭の犬〉〈これは民話にいう人と犬の結婚なのか〉〈吹雪、七人の老婆たちが「般若心経」を唱和する〉などの詳細なト 書きの後に、不意に現在の回転寿司の店内が指示されるのだ。
主軸となるのは、伝説の熊猟師を先祖に持つ兄弟の話である。兄(井上芳雄)はライフル競技でオリンピック競技に選ばれた名手だが、商社員の弟(上田竜也)の恋人の女詩人(鈴木杏)と激しい恋に落ちる。
その場所が北陸の回転寿司店なのである。コクーンの舞台から客席の通路を一周して巨大なコンベヤーが登場して、観客をアッと言わせた。劇作家のト書きはきちんと守るという蜷川の覚悟が伝わってくるようだった。
芝居の縦軸は、伝説の熊猟師と熊、そして犬をめぐるサーガ(年代記的な物語)だ。人は熊を「山の神」とあがめつつ、射殺し、「熊の肝」を求める。
明治時代に隆盛を迎えた新潟県の石油村にも触れられる。大正期に入ると衰退を始め、日本は新たなエネルギーを求めて、ロシア革命後のシベリアへ無謀な出兵を試みて、多数の死傷者を出した。
かつて製油所の本社があった新潟県柏崎市は、一九六〇年代、原子力発電所の誘致を決めた──。
ともかくスケールの大きな物語だ。巨大な大仏像が反転して、犬の顔の「犬仏像」となるなどの仕掛けを含め、古川の蜷川に対する挑戦=遊びが楽しい。
古川は福島県生まれ。「3・11」の東日本大震災の後、清水邦夫作・蜷川演出の「血の婚礼」(Bunkamura)を観劇。この際、蜷川に「ホンを書きませんか」と誘われたという。
もともと古川は、清水の作品に強い影響を受けていて、蜷川に戯曲を書くことを約束した。
今回の舞台設定は、新潟県出身の清水に敬意を表してのものだろう。タイトルも、清水の例えば「ぼくらが非情の大河をくだる時」など長い表題を意識している のだろう。清水・蜷川のコンビ(現代人劇場・櫻社)が疾駆した六〇年代末から七〇年代の小劇場運動(当時アングラと言われた)演劇へ捧げた古川のオマー ジュといえるかもしれない。
美術の中越司、演出補の井上尊晶らスタッフの協力をもとに、蜷川が演出力をフル回転させた。古川のト書きの難題を解決していくたびに、蜷川はひそかな喜びを感じたのではないか。
蜷川は一四年、再演を含めて十本を越える作品を演出した。なんというエネルギー。その源は年初の「冬眠する熊に添い寝してごらん」との格闘にあったと思うのだ。
第二回ハヤカワ『悲劇喜劇』賞選評
辻原登(作家)
ハヤカワ『悲劇喜劇』賞の選考に今回の第二回から加わることになったが、なぜ私にお鉢が回ってきたのか分からない。分からないままにあれこれ想像するに、 やはりこの賞の仕掛人のお一人、矢野誠一さんの存在がクローズアップされる。矢野さんが委員に私を推薦されたとすると、二つの機縁が考えられる。
私が以前、『圓朝芝居噺 夫婦幽霊』という小説を書いた時、落語という話芸の中にある強烈な演劇性と小説性という視点から、矢野さんがあたたかなエールを送って下さったことがあった。
また、矢野さんと私がかつて神田駿河台にあった文化学院の先輩と後輩であること。
この二つの機縁が揃えば、それで説明がつくかと言うともちろんそんなことはない。
矢野さんは、第一回の賞の発表号(『悲劇喜劇』二〇一四年五月号)の巻頭に、早川浩氏の「創業者の想い」という文と共に、「新しい賞の意義」という文章を 書いておられる。そこで矢野さんが強調されているのは「演劇批評」の復権、あるいは確立ということだ。つまり「賞」そのものが、あるいは選考がそのまま批 評性を持つということ。早川浩氏の「創業者の想い」と矢野さんの文を併せ読むと、お二人の演劇への並々ならぬ愛情と情熱がうかがえる。
「批評」が 機能するには、外部からの視点が必要だ。それで、『圓朝芝居噺』を書いた私に選考委員に加われということなのか、というふうに考えたのだが、小説の世界で も演劇同様、いやそれ以上に「批評」は衰退しているのである。その嘆きを、小説家たる私に演劇にも投げかけてみよ、との仰せなのかもしれないと勝手な想像 をふくらませた。畏れ多いことではあるが、先に選考委員に就いている鹿島茂氏の次のようなコメントに出会って、及ばずながらとお引受けすることにした。
私は自分の体験したことのないことを依頼された場合には例外なくこれを引き受けるのを原則にしていますので、ハヤカワ「悲劇喜劇」賞の選考委員も、(少し 考えてからですが)引き受けることにしました。これまで、観劇を習慣とすることもなかったし、いわんや劇評というものもほとんど書いたことはなかったの で、いさぎよく原則に従ったというわけです。(『悲劇喜劇』二〇一四年五月号)
私が昨年、観る機会を得た舞台は以下の通りである。
「アルトナの幽閉者」(二月 新国立劇場小劇場)
「マニラ瑞穂記」(四月 新国立劇場小劇場)
「わたしを離さないで」(五月 ホリプロ、彩の国さいたま芸術劇場大ホール)
「永遠の一瞬」(七月 新国立劇場小劇場)
「兄おとうと」(八月 こまつ座、紀伊國屋サザンシアター)
「炎 アンサンディ」(十月 世田谷パブリックシアター、シアタートラム)
「鴎外の怪談」(十月 二兎社、東京芸術劇場シアターウエスト)
「皆既食」(十一月 Bunkamura、シアターコクーン)
「鼬」(十二月 シス・カンパニー、世田谷パブリックシアター)
番外「War Horse~戦火の馬~」(八月 シアターオーブ)
いかにも少ない。だがこれが精一杯だった。そして、ある劇場では讃嘆、ある劇場では失望を味わった。
見ごたえのあったのは二つの舞台、「マニラ瑞穂記」(新国立劇場)と「鼬」(シス・カンパニー)である。
新作ものと翻訳劇には余り興が乗らなかった。俳優の演技や演出、衣裳・音響ではなく、戯曲そのものに張りがない。演出家や俳優は何とか舞台で、ドラマに張 りを与えよう、生みだそうとしているのだが……。──張り、だって? それって一体批評? という声も聞こえてくるが──。
その典型は「アルトナの幽閉者」だった。サルトルの作劇術には何ら見るべきところはない。人間造形も浅い。そんなことはないという人もいるだろうが、彼の紋切型の人間観(実存主義)にこちらは少し食傷気味なのだ。
人間が運命に翻弄される、といえば劇的と思えるかもしれないが、それは本当は神々だけが成しうることで、一介の人間、それがたとえ劇作家であろうと許され ることではない。人間の運命を弄ぶ悪しき作者になるかならないか、「炎 アンサンディ」の作者はきわめて無邪気にその道を選んだようだ。「ギリシャ悲劇」 においても「古事記」の世界にしても、人間は本当に神々、神の声(神託)を聞いている。物理的に聞こえていたのである。
神々の声を失なった私たちが、神々になり変わって、人間の運命を描くにはどうすればよいのか。
「鴎 外の怪談」「マニラ瑞穂記」「鼬」は、作者に人間の運命を弄ぼうという考えは微塵もない。シェイクスピアにもチェホフにもカミュにもない。人間の理解の手 の届かない世界を魂の奥底にひそめながら、運命を弄ぼうとする誘惑に打ち克った者だけが、本物の劇的空間を実現することができるのだ。
「マニラ瑞穂記」と「鼬」はまさにその好例だ。「マニラ瑞穂記」では舞台をぐるりと客席が取り囲む。男たち女たちが渦を巻くように動きはじめ、いつしか観客をもその渦巻きの中に吸い込んでゆく。
「鼬」 では、舞台を上下左右一杯に大きなだるま屋の内部が占める。まるで鯨の腹の中のようだ。仄暗い闇が水のようにみちている。人物が出入りするごとに開けられ る戸口からわずかな外の光が差し込む。その光が、私には四月に観た「マニラ瑞穂記」の南方から差す光のように思えた。事実、萬三郎は南方から帰って来る。
「鼬」の幕間でのこと。すぐうしろの中年女性三人が、美女が一生懸命悪女を演じようとしてるわね、とクスクス笑いながら言い交わしていたが、それでいいじゃないか、それこそ芝居だし、鈴木京香はみごと「おとり」を演じ切った。
受賞は「鴎外の怪談」に決まった。私は受賞に賛成したが、私にとって神様である鴎外や荷風が、生身の人間の姿となって動き回るのを見るのは、正直言って少し辛いものがあった。
※一部日本語環境で表記できないため、「鴎」を新字で表記しています。
- <<前の記事:第二回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考結果
- 第二回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞贈賞式を開催:次の記事>>