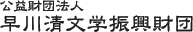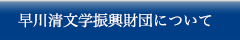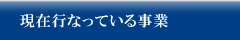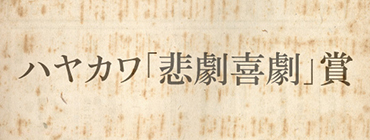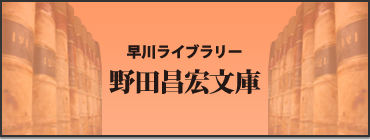第七回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考委員批評文
わたしたちの無意識を規定する家族の形
鹿島茂 (フランス文学者)
十年ほど前から、日本の演劇界は、観客動員を当てこんだ大手芸能プロ人気タレント起用の大劇場主義か、さもなければ、翻訳劇を中心にした小劇場のストレート・プレイかに二極分解してきましたが、観客もまた同じように二極分解したらしく、前者の客席には専業主婦、後者のそれにはインテリの年金生活者が目立ちました。そのいずれもが「日中はヒマ」ということで、演劇界では平日のマチネ興業が常態化しています。
これはあまり好ましい兆候ではありません。観客の老齢化が進めば、マチネにも来なくなるはずだからです。演劇界はさしあたりの観客増ではなく、将来を見越した観客増の対策を講じなければなりません。しかし、実際は、なにか一つ当たると、それと類似した企画ばかりが立てられているように思われます。
それかあらぬか、数年来、作・演出で頭角をあらわしてきた女性の若手が総じて伸び悩んでいるように見受けられます。期待して新作に足を運んでも裏切られることが少なくありませんでした。
なぜなのだろうと考えて、いろいろと仮説を立てたあげくに出した結論は、特殊性から普遍性へと突き抜ける可能性を秘めたテーマが「家族」しか見つからないからというものです。たしかに、自分の家族をテーマにすれば、だれでも一つは傑作を書くことができます。しかし、二つ、三つと傑作を作り出してゆくことはできません。
では、家族以外に特殊性から普遍性に抜けることができるテーマはないのでしょうか?
この問題に直面したとき、現代の劇作家が選ぶのは、第二の家族、つまり疑似家族としての学校の友達、とりわけクラスメートとの関係のようです。そのせいか、小劇場のストレート・プレイ系には舞台が学校となったものが少なくありません。
しかし、家族とは異なり友人関係というテーマでは、「だれでも一つは傑作を」というわけにはいかないのです。なぜなら、友人関係には普遍性が入ってきてしまうため、特殊性から普遍性へ突き抜ける回路を確保することが困難だからです。友人関係をテーマとすることが思いのほか難しいのはそのためです。
この意味において、これは凄いと震撼せざるをえなかったのが、オフィスコットーネ『さなぎの教室』(下北沢・駅前 劇場、作・演出・出演=松本哲也)です。
この作品は久留米市で起きた看護師養成学校のOGたちによる連続保険金殺人を扱 ったもので、故・大竹野正典さんの『夜、ナク、鳥』へのオマージュというかたちを取ったリメイクなのですが、作・演出 ・出演の松本哲也による新解釈により、まったく別の作品に生まれ変わったといえます。
新解釈というのは、性関係(対幻想)を伴う家族だけが家族ではなく、 学校の同級生のような同質・同性集団においても対幻想を核とした疑似家族が形成されうるのであり、その疑似家族の紐帯は実際の家族よりも強いかもしれないということです。
私がこのドマラを観ていて連想していたのは『古事記』のサホ姫の神話でした。
サホ姫の話というのは、天皇(垂仁)の后となったサホ姫 に、その同母兄であるサホ彦が「おまえは夫とこの兄のどちらを愛しているか」と問いかけ、サホ姫が「兄です」と答えると、「ならば、おまえとわたしとで天下を統治しよう」と誘って小刀を渡し、それで夫を殺すように命ずるが、サホ姫はどうしても夫を殺すことができず、最後に夫にすべてを打ち明けてから、産み落としたばかりの子を夫に渡したあと、兄が立てこもる稲城に入って兄に殉じて死ぬというストーリーです。
この物語を『共同幻想論』で分析した吉本隆明は、サホ姫とサホ彦の強い関係は、日本土着の妻問い婚的な母系家族の遺制を残した原始的氏族共同体の対幻想であるのに対し、夫とサホ姫の関係は新しく生まれた大和朝廷的の父系の部族的共同幻想であると指摘したうえで、「サホ姫は氏族的な《対 幻想》の共同性が、部族的な《共同幻想》にとって代られる過渡期に、その断層にはさまれていわば《倫理》的に死ぬのである」と述べています。
このサホ姫の神話をベースにして『さなぎの教室』を観ていると、いろいろなことがわかってきます。まず、保険金殺人の共犯者となった看護師要請学校のクラスメートの四人組の関係ですが、これは単なる女友達の関係というよりも母系家族における兄弟姉妹的な対幻想の関係にあるといえます。つまり、兄に当たるのが松本哲也が怪演した悪い看護師で妹に当たるのが三人の看護師です。その関係はレズビアン的な対幻想でありながら、同時に兄妹の関係、つまりサホ彦とサホ姫の関係に近似しているのです。そのため、サホ姫たちのうち二人は、「兄」であるサホ彦(松本哲也)から「兄」と夫との二者択一を迫られると、容易に「兄」を選ぶことに同意してしまうのです。
当初の予定では、松本哲也が演じた悪い看護師は女優が演じることになっていたそうですが、都合で出演できず、作・演出の松本哲也が自ら役を引き受けたと伝え聞いています。この偶然が、「兄」であると同時に「夫」でもあるというサホ彦的な存在に異様な存在感を与えることになったようです。
ドラマのサホ姫たちは『古事記』とは異なり、夫を殺すことに成功し、保険金を手に入れますが、しかし、その愛(対幻想)の対象が「兄」であったという点では『古事記』の神話となんら変わっていませんし、まさにドラマの本質はそこにあるのです。つまり、外婚的な「夫」よりも、内婚的な「兄」を選ばざるを得ないという、吉本隆明的にいえば「氏族的な《対幻想》の共同性」と「部族的な《共同幻想》」の断層にはさまれて「いわば《倫理》的に死ぬ」というかたちを取らざるをえない母系家族特有の選択がドラマの伏流になっているのです。
ところで、これをエマニュエル・トッドの家族人類学的な分布という観点から眺めると、興味深い事実が浮かび上がってきます。保険金殺人事件の舞台となった久留米市、および作者の松本哲也の出身地である宮崎は、家族類型的にいうと、九州に多い一時的母方同居(ないしは母系屈折のある双処同居)を伴う核家族のタイプ、つまり、太古の昔から戦前まで妻問い婚型の婚姻が一般的だった母系家族の系譜に属すると考えられます。
分かりやすい例を持ち出すなら、波平一家に一時的に同居していることになっているサザエさん一家です。佐賀市出身の長谷川町子さんが描く磯野家においては、マスオさんとサザエさんの夫婦関係よりも、サザエさんとカツオの姉弟関係が前面に出てくることが多いということです。邪馬台国の卑弥呼と弟、サホ姫とサホ彦という、昔から兄弟姉妹の関係があまり変化せずに保存されているのです。アルカイックなこの家族類型の共同幻想は意外に強く九州に残存しており、そのおかげで多くの芸能人や個性的な財界人を輩出する原因になっているように思います。
そうした母系的家族類型の兄妹の対幻想が、より次元の高い共同体である学校に投影されたのが、『さなぎの教室』の看護師養成学校の疑似家族にほかなりません。看護師養成学校という疑似家族から出たはずのサホ姫たちは、明治以来日本の主流となった父方居住の直系家族への誘導があってもなお、最終的には、夫よりもサホ彦であるところの「兄」の方を選ぶことになるのです。
このようにして、ドラマを家族人類学的な観点を導入して眺めてみると、日本という辺境の国の、それも九州の周縁部の家族的ドラマという「特殊性」が逆におおいなる「普遍性」を持って迫ってくることになるのですが、では、この視点から、受賞作のテーナ・シュティヴィチッチ作『スリーウ インターズ』(文学座アトリエの会、常田景子訳、松本祐子演出)を眺めてみるとどうなるのでしょうか? まず、舞台となったクロアチアのサグレブから行きますと、仏独がヨーロッパの中心と仮定した場合、どうしてもヨーロッパの南東の辺境ということになります。また旧ユ ーゴスラヴィア社会主義連邦共和国(以下、ユーゴ連邦)のスケールで眺めると、クロアチアは北西の辺境です。つまり地理的には、二重の辺境性ゆえの特殊性という宿命を負っていることになります。
しかしながら、劇作家が自己表現しようとするとき、こうした辺境性・特殊性を特権的に意識化することはありません。事実、『スリーウインターズ』は第二次大戦末一九四五年のチトーの対独蜂起、一九九〇年のユーゴスラヴィア解体、そして劇作の現時点という三つの冬を縦軸に串刺しにして舞台をつくっていますが、これらの日時はたんにクロアチアだけの問題ではなく、世界史そのものの問題でもあるわけですし、また作者のテーナ・シュティヴィチッチもそのような世界同時性、つまり普遍性を目指しています。
ところで、劇作家が特殊性において普遍性を志向すると決意した場合、容易に意識に浮上してくる普遍性のテーマとして家族の問題であるはずです。家族を持たない人はかなり例外的だからです。そこで、劇作家は自分の家族をテーマにし た作品を書こうと決意するのですが、しかし、ここで、ふたたび普遍性と特殊性の逆転が起こります。家族は普遍的ですが、普遍性からは作品は作れないという公理があるからです。
そこで、劇作家は次に自分の家族の特殊性を掘り下げていく作業に入ることになります。テーナ・シュティヴィチッチもこの選択肢を選んだにちがいありません。おそらく、彼女は自分の家族の歩んだ歴史がかなり特殊だという思い込みがあったのでしょう。
たしかに、劇化されたシュティヴィチッチ一族のドラマはかなり特別なもののように思われます。なかなか、日本では、こうしたドラマは生まれにくいものです。ところが、これに別の角度から光を当てると、特殊は特殊ではなくなり、また普遍は普遍ではなくなってしまうのです。
光というのはこの場合もまたエマニュエル・トッドの家族 人類学です。
トッドの『家族システムの起源』によると、クロアチアが一九九一年まで属していたバルカン半島の旧ユーゴスロヴァキアの大半を占める南スラブ人地域(クロアチアとスロヴェニアを除く旧ユーゴ、とくにセルビア)は、ロシアや中国と同じ父方居住共同体家族という家族類型に属します。これはドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を思い浮かべるとわかりやすいでしょう。強い権力を持つ父親の下に結婚した複数の息子たちの家族が同居するという大家族で、父親の強い権威と兄弟間の平等が特徴的です。日本にはこの家族類 型はありません。
こうしたロシア・中国・ユーゴの類型と似ているようで違うのが、スロヴェニア以北のオーストリア、チェコ、スロヴァキア、ドイツに多い父方居住の直系家族で、これは父親の強い権威のもと、長男とその家族が一つ家に住むタイプで、北東日本もこれに属します。では、ザグレブがあるクロアチア中部の家族類型はどうなのでしょう? トッド分類では、一時的双処同居を伴う核家族ということになります。これはヨーロッパではポーランドやベルギーのワロン語地域、それにアイスランドにしか見られない珍しい家族類型ですが、アジアの最辺境である日本の西南日本には潜在的なかたちで広く分布しています。具体的にいうと、男の子でも女の子でも、結婚した後、一時的に親と同居し、子供が少し大きくなると独立・別居するというタイプで、『サザエさん』の磯野家も、もしカツオの結婚と同時にサザエさん一家が波平一家のもとを離れて独立するならこのタイプになるでしょう。さて、こうしたヨーロッパの家族人類学地図に置いてみると、クロアチアの一時的双処同居を伴う核家族というのはどう説明できるでしょうか?
それは、野球のテキサスリーガーズ・ヒットのようなものだということができます。すなわち、南スラブ人地域から西に伝播してきた父方居住共同体家族も、またドイツ・オーストリアから南下してきた父方居住直系家族も、クロアチア中部という土地が地理的に同じように遠い辺境であるために、強い影響力を及ぼすことができなかったということです。その結果、クロアチアには非常に古い起源的な家族類型である一時的双処同居核家族のままにとどまったということです。
しかし、テキサスリーガーズ・ヒット的な家族類型地域であっても、セルビア的な父方居住共同体家族とドイツ的な父方居住直系家族はいろいろな部分に影響を及ぼしています。
その典型が家の住居形態です。『スリーウインターズ』では、第二次大戦までナチスの協力者だったブルジョワが住んでいた大邸宅に、戦後の混乱期に何家族かが住みつくようになります。ただし、大邸宅ではあっても台所や浴室、トイレなどは一カ所しかないはずですから、それぞれの家族はシェアハウスのようなかたちで共同 生活を営んでいたはずです。日本でも、戦後の住宅難時代にはこうした住み方があったはずですが、さすがにいまではありません。しかし、『スリーウインターズ』ではユーゴ崩壊 どころか、劇の現時点まで、こうした住み方が続いていたようです。これこそは、クロアチアがユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国の一員であり、住宅形態的には、複数の息子の家族が共同で住むという父方居住共同体家族の影響を受けていたことの証拠です。
しかし、主人公一家の家族類型はクロアチア特有の一時的 双処同居核家族のようです。というのも、ユーゴ解体以前から、子供たちは独立すると同時に家を出ていったと想像されるため、原則的には核家族の範疇に入るからです。
この関係はユーゴ連邦とクロアチアの関係にアナロジーさせることができます。
大邸宅がユーゴ連邦だとすると、主人公一家はクロアチアです。家族類型的には、父方居住共同体家族の中に一時的双処同居核家族が居心地悪く包含されているかたちです。
ところで、『スリーウインターズ』には、前面には出てきませんが、ドイツ・オーストリア的な直系家族が伏線として入りこんでいます。というのも、第二次大戦中、クロアチアは強力なファシスト党であるウスタシャがナチの支援を受けて政権を握って恐怖政治を敷いた枢軸国であり、戦後もしぶとく生き残ったウスタシャ残党がユーゴ的な共同体家族的共同幻想と対立し、ユーゴ連邦の崩壊を導いたとわれているからです。つまり、ナチズムを生んだドイツ・オーストリア的 なタテ型の直系家族的共同幻想もまたクロアチアのある部分を支配しているのです。『スリーウインターズ』においても、こうした直系家族的要因と共同体家族的要因の衝突が「三回の冬」を導いたことが示唆されています。
最後に、候補作として議論された作品の中で私が観たものについて簡単に言及しておきますと、前川知大脚本・演出『終わりのない』(世田谷バブリックシアター+エッチビイ、ホメロス原作、野村萬歳監修)は近年の前川作品の中ではもっとも纏まった破綻のない戯曲になっていましたが、以前の「イキウメ」の舞台のような緊迫感を感じることはできませんでした。前川知大自身がいまおおきな転換点に差しかかっているのではないと思われます。
ニック・ペイン作・眞鍋卓嗣演出『インコグニート』(俳優座、田中壮太郎訳)は今年最も野心的かつアヴァンキャルドな作品でしたが、選考会でも述べたように、景や場の切り替えや転換の必然性を保証する要素が確認できなかったために、いま一つ強く推すことはできませんでした。
二〇一九年を簡単に総括するならば、この年もまた、わたしたちの無意識を規定する家族が問い直された一年であったということができるのではないでしょうか?
明日への希望を灯す
杉山弘 (演劇ジャーナリスト)
ハヤカワ「悲劇喜劇」賞は、劇評意欲を最も奮い立たせる優秀な演劇作品を顕彰する。華麗で優美な舞台、思わずもらい泣きしてしまう人情話、破天荒な冒険譚、現代的なテーマに鋭く切り込んだ社会派劇、時代のうねりの中で翻弄される人間ドラマ、運命に抗う人物を克明に追った感動作など、多種多様な芝居が日々上演されている。その中にあって、個人的には、新しい視点や切り口で演劇が本来持っている力を感じさせてくれる作品、言葉を変えれば、想像力を刺激し、新しい発見があり、明日への希望を灯してくれる作品に強い関心があり、これを軸に候補作を絞り込んだ。
二〇一九年を振り返ると、翻訳劇の上演で優れた舞台が多かった。東京芸術劇場/兵庫県立芸術文化センター『Le Pe re 父』、世田谷パブリックシアター×パソナグループ『 CHI MERICA チャイメリカ』、 unrato(アン・ラト)『LU LU』、劇団青年座『SWEAT』、ホリプロ『ドライビング・ミス・デイジー』、パルコ『人形の家 PART2』、シス・カンパニー『死と乙女』、風姿花伝『終夜』、名取事務所『屠殺人ブッチャー』、新国立劇場『あの出来事』、KAAT・KUNIO共同製作『グリークス』、劇団昴ザ・サード・ステージ『8月のオーセージ』などが、舞台成果とともに演劇の多様性を感じさせてくれた。その中にあって、文学座アトリエの会九月公演『スリーウインターズ』は、骨太の戯曲、劇団公演の強み、上演への熱意の三点で抜きんでた演劇の力を示してくれた。
(一)骨太の戯曲
クロアチア・ザグレブ生まれの劇作家テーナ・シュティヴィチッチが二〇一四年に発表した戯曲(翻訳=常田景子)で、四世代にわたるコス一家の物語を、第二次世界大戦が終結した一九四五年、ユーゴスラビア分断が決まった一九九〇年、クロアチアがEU加盟条約に署名した二〇一一年と、三度の冬のシーンを交錯させながら全十四場で綴っている。一九七七年生まれのシュティヴィチッチは、「七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家」からなる理想の国家建設を目指したユーゴスラビア時代に育ち、独裁政権の腐敗やベルリンの壁崩壊に象徴される東西冷戦の終わりでユーゴスラビアが分断され、ナショナリズムの急激な高まりによる内戦の激化した時代に思春期を送っている。目を覆いたくなるような殺人や暴行を見聞きしたことも想像に難くない。このような混乱を招いたのはなぜなのか、という疑問を出発点に、作者は、母、祖母、曾祖母たちの世代が時代とどう向き合い、どのように生きてきたのかに思いを馳せ、女性を軸にした視点から「時代と人 間」を見つめ直している。
オーストリア=ハンガリー帝国下の貴族階級に支配された曾祖母のモニカは、本を読むことや学校に通うことが女には許されない環境の中、メイドとして貴族に仕えながら苦労して子育てをした。ナチスと闘った祖母のロ ーズは、パルチザンに加わっての勇姿とともに理想の国家建設の夢を追いかける。その娘であるマーシャとドゥーニャは理想と現実の狭間に苦しみながら懸命に生きてきたものの、ユーゴスラビア分断に怒り、失望し、後悔する一方で、ある種の空しさに包まれている。そして、独立国家としての新しい道を模索することを迫られたマーシャの娘アリサとルツィアは作者の世代に重なる。イギリスで教鞭をとり、キャリアウーマンとして自立しているアリサ、生き残るために手段を選ばないルツィア。全編を貫いているのは愛する家族を守り、より良い暮らしや社会の実現のため誠実に生きてきた女性たちの姿。悩みながらたくましく生きてきた姿を映し出し、メッセージ色を前面に押し出さない静かな会話から熱い想いを溢れ出させる。構成力確かな骨太の筆致で、クロアチアの悲劇と希望を遠い異国の日本の観客に手渡してくれた。
(二)劇団公演の強み
有志が集まっての劇団という存在は、時として組織の論理を優先させてしまい、所属する俳優やスタッフの自由を奪い、束縛する側面がない訳ではない。少し厄介な存在でもあるが、同じ空間で芝居を練り上げる中で互いの間合いを知り尽くした劇団員による芝居は、長年積み重ねてきた阿吽の呼吸が芝居のアンサンブルを醸し出すことがある。その点で今回の上演は、劇団という存在が大きくプラスに働いた。ベテランから若手までがそろう劇団だけに四世代にわたる配役にも無理がなく、各世代の主役級がこの芝居に集結した。さらにアトリエという小さな空間での競演となり、芝居の緊密度が一層増した。
没落した貴婦人のカロリーナ役に気品を添えた寺田路恵、正しいことをしようとして家族を傷つけてしまい、「呼吸が出来なくなるほど」苦しむヴラドとマーシャの夫婦を演じた石田圭祐、倉野章子のベテラン陣。時代の目撃者として静かな怒りを劇場に解き放つドゥーニャ役の山本郁子や、敗軍の兵士の悲哀を淡々と語るアレクサンダー役の上川路啓志の中堅世代、そして、闘う女性ローズ役の永宝千晶、新しい時代の到来に戸惑うアリサと希望や不安の入り混じった感情を爆発させるルツィアを演じた前東美菜子と増岡裕子の若手と、文学座の俳優の層の厚さと力量を実感することが出来た。同時に、彼らを見続け、その個性を知った上でプロの仕事に徹した美術(石井強司)、照明(賀澤礼子)、舞台監督(加瀬幸恵)などのスタッフワークが芝居を支えた。劇団ならではの強みがこの芝居に注ぎ込まれ、総合芸術としての演劇の力を感じさせる仕上がりでもあった。
(三)上演への熱意
公演実現までの経過もドラマティックだった。発案者で演出の松本祐子は、公演企画を提案したものの、「時代を表現する美術や衣装に経費が掛かり過ぎる」「クロアチアの歴史が日本の観客には分かりにくい」などの理由から本公演とアトリエ公演を二度、見送られている。しかし、松本はそれでも諦めず、家族、とりわけ女性たちを軸にした物語に絞り込み、馬蹄形に客席が取り囲む演技スペースに、テーブルと数脚の椅子、二つのベッド、食器戸棚を置いただけのシンプルな作りに発想を変えた。観客の想像力に委ねることが許されるアトリエという小空間を逆手に取り、ある種「開き直り」にも近い大胆さで企画を再々提出し、ようやく公演実現をつかみ取った。さらに松本はザグレブへ出向いて物語の舞台を肌で感じ、よく知らなかった国のドラマに戸惑いを隠さない俳優たちと劇団内でクロアチアについての勉強会を開き、公演中に作者を招いてトークショーに出演するなど、芝居への理解を深めるための努力も惜しまなかった。俳優たちの演技も稽古中に様々なアイデアが出されたばかりでなく、公演中も日々深化し、ドラマに膨らみが生まれていったという。精神論に聞こえてしまいそうだが、やはり上演にかける熱意こそが、芝居の原動力であり、推進力であることを改めて思い知る機会ともなった。
推薦理由は三点だったが、中でも、上演への熱意を高く評価したい。クロアチアという遠い国から届いた戯曲には、痛みを伴った生々しい肉声があり、その苦しみに耐えながら希望を願って生きる人間の姿が克明に描かれている。人への関心が強い演劇人ならば、誰もが上演を望む作品だったと思う。その反面、実現させるには大きな壁が何層にもわたって立ちはだかる作品でもあった。そこを突破出来た要因として劇団という幸運があり、アトリエ という使い勝手のいい空間があったことは間違いない。しかし、しかし、である。松本の粘り腰と実行力の源泉は「私が感動した作品を舞台で見て欲しい」という情熱に尽きるのではないだろうか。これがなければ日本の観客が『スリーウインターズ』と出合うことは叶わなかったと言っても過言ではない。選考会でも委員三人の推薦があり、最後は全員一致で授賞が決まった。国や環境が異なっても、生きることに苦しみ悩む人へエネルギーを与える舞台になったこと、そして「演劇の力」を存分に示した舞台の受賞を喜びたい。最後にお願い事がひとつ。アトリエでの十六ステージだったことから見逃した方も少なくないと思う。是非、再演を果たして欲しい。
受賞作に次いで推したのがDULL-COLORED POPの『福島三部作』だった。福島・石川町生まれの谷賢一が作・演出し、福島原発事故に正面から向き合った。二〇一八年に発表した第一部「1961年:夜に昇る太陽」に加え、新作となる第二部「1986年:メビウスの輪」、第三部「2011年:語られたがる言葉たち」の三作を休憩時間含め八時間で通し上演した。福島原発事故を語るに際して、その起点となった一九六一年、チェルノブイリ事故に揺れた一九八六年、そして東日本大震災の起きた二〇一一年と、二十五年刻みで物語を描き、半世紀にわたる大河ドラマとして三部作を書き上げた着眼が優れている。さらに、現在も避難生活を強いられている双葉町に暮らしていた農家の穂積家に視点を定め、第一部は長男で原子力研究所の学者となった孝、第二部は次男で双葉町長となった忠、第三部は三男で地元テレビ局の報道局長となった真をそれぞれ主人公に据えた点も秀逸だった。
第一部では双葉町議会が原子力発電所の誘致を議決し、建設候補地の大地主でもある穂積家には町長や東電社員らが訪れ、原子力発電の明るい未来を語って用地買収に応じるよう説得する場面が軸となる。東京五輪を前に、所得倍増計画の恩恵にもあずかれないまま貧しさから抜け出せなかった双葉町にあって、原子力発電に夢を描き、その平和利用に未来を託した思いを物理学者の卵の目を通じて浮かび上がらせる。人形劇にミュージカル仕立て、つかこうへい風のせりふ回しなど手法に工夫を凝らし、祭りのような賑やかさとその後に訪れる寂しさを対照的に描き分けた。続く第二部はウクライナ(事故当時はソビエト連邦)でチェルノブイリ原発事故が起きた際に、対応に追われる双葉町長の姿をクローズアップ した。前年に原発反対派から転向して町長となった忠は、違和感を覚えながら基幹産業として原発を推進し始めていた。 その矢先に事故の報を受け、立ち戻るのではなく、信じてもいない原発について「安全です」と記者 会見で断言してしまう憐れな男を丹念に追いかけた。中でも忠が原発反対の旗をおろして町長選に立候補するまでの討論劇に見応えがあり、ソーントン・ワイルダーの『わが町』を模して、愛犬に人間の営みを俯瞰させ「死者のささやくような声が聴こえますか」と語りかける見立ても効果的だった。第三部ではテレビ局を舞台に報道番組 で指揮をとる真の苦悩が描かれる。「福島県は全滅です」とネットで発信した女子高校生、避難所で放射線被ばくに怯える元教師夫妻、育てていた牛をすべて失った酪農家に加え、原発が建設されて潤った町と事故で避難を余儀なくされただけの町の住民同士のいがみ合いも登場させ、ドキュメンタリー調に被災者の声をすくい上げた。報道の使命と現実とが乖離したために真がある決断をする場面を通じて、警鐘を鳴らす。
故郷の大惨事を数年かけて取材して戯曲を練り上げ、八時間の通し上演が平板にならないよう演出に変化をつけるなど、力作と呼ぶにふさわしい三部作に仕上げた。三作を通して登場する、まばゆいばかりの強烈な光を発する美術(土岐研一)の存在も威圧的で不気味。東日本大震災から九年。復興への道はまだまだ険しい。「第四部」「第五部」と書き続けていって欲しいとエールを送りたい。
選考会で候補作として討論された舞台についても手短に触れておきたい。オフィス・コットーネの『さなぎの教室』は、劇作家・大竹野正典の没後十年を記念した企画。四人の女性看護師による福岡・久留米の保険金連続殺人事件をモチーフにした大竹野の戯曲『夜、ナク、鳥』へのオマージュとして、松本哲也が舞台を宮崎に移して作・演出した新作だ。一人の看護師が夫を殺害する日を起点にして、四人の過去と未来を行き来し、特に中心的人物だったヨシダが看護学校時代から徐々にその怪物性を剥き出しにし、同僚の三人を巻き込み、洗脳し、支配していく過程に主眼を置いて筆を進めている。生命を預かる看護師がなぜ親族の生命を奪っての保険金殺人に手を染めたのか。その経緯を追うことで動機を手繰り寄せようとした。また、公演直前にヨシダ役の女優が降板したため松本が代演し、「瓢箪から駒」の怪演をみせた。選考会でもこの演技を巡って意見が闘わされた。
劇団俳優座『インコグニート』は英国の劇作家ニック・ペインによる脳と記憶とアイデンティティにまつわる物語(翻訳=田中壮太郎、演出=眞鍋卓嗣)。アインシュタインを検死解剖し、その脳を持ち出した病理学者トーマス・ハーヴェイ、てんかん治療のため脳外科手術を受けた患者のヘンリー ・メゾン、そして臨床神経心理学者のマーサ・マーフィーの三人のエピソードを、記憶のプロセス(記銘、保持、想起)に従ってドラマを再構築している。初めて知るエピソードが断片的に進行することに加え、外国人名の二十一役を四人の俳優で演じ分けているため、シーンごとの関係性を整理するだけで手いっぱい。観客への挑戦状のような異色作ではあるが、事前の勉強不足もあって芝居を楽しむまでには至らなか った。
世田谷パブリックシアター+エッチビイ『終わりのない』は、前川知大が作・演出した新作。ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』を原典に、日常と宇宙をつなげる意識の旅が描 かれる。「自分はなぜここにいるのか」「自分は何者なのか」と人生の目的を失った青年の心の放浪を、時空を超えた未来人との遭遇から見つめた作品。背景には地球温暖化での異常気象による未来の地球の姿があり、量子論の多世界解釈を説き明かしながら、地球を離れた人類との意識の交感で「自分探し」をしたところに前川の新境地が示されていた。
文学座ならではの心技一体
辻原登 (作家)
文学座アトリエ公演に通い詰めた時期があった。文学座だけでなく、アトリエっぽい舞台空間には今でも魅力を感じる。二〇一五年四月のさいたまネクスト・シアター、ゴール ド・シアターによる『リチャード二世』(第三回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞)は彩の国さいたま芸術劇場大ホールのインサイド・シアターを使った舞台だった。蜷川幸雄最晩年の演出でもあった。圧巻の舞台だった。
アトリエやドリル・ホール、インサイドシアターに惹かれるのはなぜか、と自問しても納得のいく理由・答を見出せなかったのだが、最近、たまたま『図録・人体の不思議』 (「人体の不思議展」図録、二〇〇五年 インサイト)を繙いていて──実に生々しい「プラストミック」による人体標本──、その中の頭蓋標本をながめているうちに、アトリエやインサイドシアターの空間を連想してしまった。これらの空間は、人間の頭蓋、脳内空間なんだ、と。それも僕自身の頭蓋・脳内空間……。僕は、僕自身の頭蓋の中に入り込んで、脳内を内向きに覗き込んでいる。そのような感覚がアトリエの舞台から生まれる。
『スリーウインターズ』は、文句なしの授賞だった。授賞理由については、選考会記録の、僕を含む選考委員の言で尽くされていると思うので贅言を重ねる必要はないが、先に述べた〝アトリエ公演〟が極めて有効に作用したと思う。『スリーウインターズ』は、クロアチアのザグレブに住むコス家、 四代にわたる女性を中心とする家族の物語だからだ。〝家族〟とは人生における〝アトリエ〟〝バックステージ〟ではないか。 『スリーウインターズ』の舞台と客席図(文学座公演資料)を借りて、先の僕の頭蓋・脳内空間の考えを当て嵌めると次のようになる。
チェーホフの舞台の真実味について、以前もこの欄で触れたことがあるが、『かもめ』でも『桜の園』でも最初は訳が分からない。人物たちの位置がおいおい分かって来て、やがて惹き付けられる。誰がどういう位置で、どういう顔付きで座っているのか。僕たちの頭の中でくっきりと定まって、人物たちの焦点が結ばれ、ドラマは滑らかに、かつ劇的に動き始める。その動き、ムーヴメントから生じる時間感覚こそ、観客がチェーホフから受け取る真実味であり、人生の意味( sens )なのだろう。『スリーウインターズ』。このクロアチアの女性作家テーナ・シュティヴィチッチの戯曲(全十四場)は、チェーホフ劇より、歴史的背景も登場人物も多様で、複雑に入り組んでいるが、作劇術は同一、かつチェーホフ劇に劣らぬ真実味を醸し出すことに成功している。
僕はあらかじめ用意された「コス家一覧とその他の登場人物表」(十三名!)に一切目を通さず観劇に臨んだのだが、二〇一一年、十一月の日付を打った第二場の半ばあたりから、この舞台の成功を確信した。つまり、真実味 000 を嗅ぎ取ることが出来た。
極端に言えば、もうここからは目を閉じて耳を傾けていればいいのである。俳優の所作、息遣い、動きが手に取るように感じられる。無論、舞台は視覚的要素によって成り立っているのだが、優れた舞台は視覚を取り去っても充分鑑賞できる。以前、『桜の園』を朗読で聞いたことがあるが、その魅力は損なわれることはなかった。
確かに、演劇では台詞の荷う役割は圧倒的に大きい。台詞が豊かであればあるほど真実味が増すというものだろう。映画の台詞を、サウンド・トラックで聞いただけでは何が何だか訳が分からないかもしれない。ストーリィーを追うことも出来ないだろう。
小説のカギカッコ、あるいはそれに類する記号で括った台詞は、便宜上のことで、大体、人間は決してあんなふうには話さない。地の文の中に突然声が割り込んで来る。このこと自体が不自然なことなのである。私は、小説上の会話は一種の描写だと考えている。戯曲の台詞を参考にすることもあるが。『スリーウインターズ』の、とりわけラストの十四場で、モニカ・ズィーマがセバスチャン・ア ムルーシュを回想する独白シーンは、演じる南一恵とモニカが一体となって、哀切さは胸底にまで届く。僕は途中で幾度か目を閉じて聞き入った。一度も登場したことのないセバスチャンが、僕の頭蓋の中に確実に存在した。
多くの登場人物の中で、アリサ・コスにも注目したい。アリサは家族劇に欠かせない、言わば〝放蕩息子(娘)の帰還〟の役割を持って登場し、かつての恋人──ユーゴスラヴィアの内戦に参加し、血みどろの殺戮を経験した──マルコ・ホルヴァットから、「軽蔑は、とても弱い武器だよ」という言葉を引き出す、あるいは突き付けられる。これはこの舞台と我々の人生を要約する言葉 es-sence だな、とアトリエの片隅の席にいて痛切に感じたことを覚えている。
ラストシーンは見事だった。一九四五年十一月、先に触れ たモニカ・ズィーマの長い独白の合間に、二〇一一年十一 月、ルツィア・コスの結婚式の楽隊が奏でる音楽が庭から聞こえて来て、アリサが再び旅立ちの荷物をまとめる。
モニカの独白が続いている。一九四五年、一九九〇年、二〇一一年の三つの冬が一つになって、雪が降り、死者と生者が会して踊る。一族再会の輪の中からアリサは抜け、スーツケースを持って、去って行く。
文学座アトリエ公演ならではの、そして文学座ならではの 心技一体、充実した舞台だった。
†
『さなぎの教室』の公演は、下北沢の「駅前劇場」だったが、下北沢に疎い僕はなかなか劇場に辿り着けず、開演ぎりぎりに滑り込んだ。着いてみれば、京王中央口の目の前の「GUSTO」のあるビルの3Fで、一目瞭然、どうして迷ったのか不思議で、ポーの「盗まれた手紙」のような経験だった。
やはり僕好みの頭蓋めいた空間で、舞台下手に設えられた大きな編み籠状のもの(これも頭蓋……)の中に四人の女が腰掛けて待機していて、出入りする。まさに孵化して変態を待つ踊を思わせる装置で、女たちを熟させ、変貌させ、悪を醸成していると見えた。
女性看護師ヨシダ役の松本哲也の怪演ぶりは特筆ものだが、他の女看護師三人、殺されるそれぞれ四人の夫役を演じた俳優たちの力演がなければ、松本の演技も空回りに終わったかもしれない。
公演のチラシには次のような断りが印刷されていた。「※出演を予定しておりました森谷ふみさんが、諸般の事情により降板することになりました。代わりまして、作・演出の松本哲也さんが出演いたします」
僕はこのことが今も気になっている。諸般の事情の詮索はさておいて、何しろ実際の久留米市の女性看護師四人による保険金連続殺人事件をそっくりモチーフにした舞台だ。主犯・主役、悪の代表たるヨシダを演じたのが森谷ふみという女優でなく、急遽松本哲也というややマッチョぽくもない男優が代役に立ったことは、『さなぎの教室』を一段高い水準へと引き上げる要因となったのは間違いない。
ラストで、女たちが殺害したイシイの夫ゴウの頭を、ヨシダが思いっきり蹴り上げる。さらにヨシダは、同じことをゴウの妻であるイシイにもやれとそそのかす。動き出すイシイ……。
舞台は暗転して、時間を遡り、彼女たちがまだ汚れなき存在で、病院実習を無事終えたばかりの場面。ヨシダは、自分が担当した患者に、「あんたは宮崎のナイチンゲールやねーって」と言われたと誇らしげに宣言するところで暗転、幕となる。
女ヨシダの極悪を、男の松本が演じることで異化効果がもたらされ、惨劇が暗黒笑劇へと止揚され、最後の台詞「宮崎のナイチンゲール」が、苦く乾いたカタルシスをもたらした。
アトリエの小宇宙から大きな波紋
濱田元子 (毎日新聞論説委員 学芸部編集委員)
〈何事にも潮時というものがある〉というブルータスの台詞ではないが、二〇一九年はまさに、好機を逃さずつかみ、満潮に乗った文学座の演出家、松本祐子の活躍が際立つ年だったのではないか。文学座での二作品のほか、外部公演や再演を含め計六作品の演出を手掛けた。なかでも文学座アトリエの会の『スリーウインターズ』には心震えた。
今回、初めての選考会におそるおそる参加させていただいたが、この作品を迷うことなくイチオシに選んだ。
もちろん舞台は演出家一人の力では成立しない。テーナ・シュティヴィチッチによるクロアチアの歴史という、素材的にも難易度の高い作品が観客の心をつかんだのは、「役を生きる」文学座の俳優の演技力の高さ、何よりも長い歴史を持つ劇団のチームワークがあってのことだ。
アトリエという小宇宙での冒険的な試みではあったが、インパクトは強く、生じた波紋はおそらく想像以上に広がった に違いない。
* * *
「もう一度見たい」。終演後、しばし余韻に浸りながら、そんな思いにとらわれた。毎日のように劇場に通う生活を続けていても、そう思える舞台に出合うことは、残念ながらそうそうあるわけではない。三時間超の芝居を見るには、決して座り心地抜群とは言えない(失礼!)アトリエの椅子も、少しも気にならなかった。というより、むしろ信濃町にいることを忘れてしまうほどだった。
理由はいろいろある。まず圧倒されたのが、次々と体制や属性が目まぐるしく変わるクロアチアの複雑な歴史と、ザグレブのコス家の四世代にわたる女性たちの家族の節目をより合わせて、壮大な叙事詩に仕立てた構成の巧みさである。
しかも時系列ではなく、時代をシャッフルして展開されるのだから、一筋縄ではいかない。人物造形はくっきりしているが、すべてを一回で咀嚼するには情報量が膨大だ。
タイトルが示す通り物語は、チトーのパルチザンが勝利した第二次大戦後の一九四五年、旧ユーゴスラビア社会主義連邦共和国崩壊前夜の一九九〇年、そしてクロアチアの欧州連合(EU)加盟直前の二〇一一年と、クロアチアの「三度の冬」を軸に描かれる。
チトーのパルチザンに参加した二十七歳のローズ(=第二世代、永宝千晶)は、ナチの協力者だった貴族階級の家を与えられたが、その家はかつて母モニカ(=第一世代、南一恵)が使用人として働いていた家だった。
ユーゴの分裂が決定的になるのは、ローズの葬儀の夜のこと。ローズの娘マーシャ(=第三世代、倉野章子)と夫ヴラド(石田圭祐)の娘であるルツィア(=第四世代、増岡裕子)が怪しげな男性ダミアンと結婚する前夜、ロンドン帰りのルツィアの姉アリサ(=同、前東美菜子)が〝爆弾〟を落とす。
全十四場のうち十三場がコス家で展開されるというのが、この芝居を象徴する。「家」が主要なファクターであり、「家・家族と個人」のアナロジーとして「国家と民族」を描くのが作家のたくらみだからだ。すなわち結婚や離婚、死別といった非常に個人的な出来事が、いちいちクロアチアの体制変化の歴史と重なり合い、多義をはらむ。
たとえばヴラドが娘の結婚を前に語る、〈結婚とは何か?〉で始まる台詞もそうだ。〈他人と絆を結んで、人生の重荷を、そしてまた喜びや幸せを分かち合うということだ〉という言葉は、ユーゴスラビアの理想と民族紛争へと至った悲惨な末路、これから「結婚」する国家統合体であるEU(欧州連合)の理想と現実を考え合わせると、これほど辛辣な皮肉もないだろう。EUを揺るがしたギリシャ財政危機やブレグジット(英離脱)も脳裏をかすめる。
マーシャの妹ドゥーニャ(山本郁子)の結婚がDV夫カール(斎藤志郎)のせいで破綻する。熾烈な内戦で、女性への性暴力が一つの武器として使われ、「エスニッククレンジング(民族浄化)」という言葉と共に国際社会に大きな衝撃を与えたことと考え合わせると象徴的だ。
戦争自体を描いたり、告発したりせずとも、作者の深い歴史認識が、家族のありようの中に落とし 込まれていることにうならされる。
もちろん、クロアチアの歴史を知っていれば、芝居をより深く味わえるだろう。しかし、たとえ複雑な歴史を知らなくても、体制変化による価値観の転換に翻弄されながらも苦境に耐え、よりよい豊かな人生を生きたいと願う女性たちの 息遣いはリアルに迫ってくる。
クロアチアから遠い日本で上演するに当たり、松本をはじめスタッフ、キャストらが一番心を砕いたところも、そこであろう。家族のドラマとしても十分に醍醐味が伝わったのは 大きな成果だ。
現代社会に通じるものも強く感じられた。一時期は三家族が分割して居住していた家を、ルツィアの婚約者が買い取り、ほかの住人を追い出すのは、今まさに世界で起きている自国第一主義、移民排斥の動きにダブる。
公演期間中に来日し、松本とのトークも行ったシュティヴィチッチが「クロアチアは今、ナショナリスティックな風潮がある。歴史の進化は前に進むばかりなく時として溝みたいなところに落ちる瞬間があって、今まさに私たちはその溝の中にいるような気がしている」(「文学座通信」より)と語 っているのは興味深い。
* * *
今年七十年を迎えるアトリエという空間の力も無視できない。松本はアトリエのブラックボックスの空間をあえて飾らず、ベッドやダイニングテーブルといった最小限の家財を置いただけだった。作者が注記しているような写真の映写も使わない。空間を信頼しすべてを、潔く観客の想像力にゆだねた。実際それだけで、どこにでも、いつの時代にもなったのである。
美術でいえば、アリ塚のようにも見える鍵の山も効果的だった。第一場で、チトーのパルチザン兵士として戦ったローズが鍵の山から、自分が生まれたザグレブの家を選ぶ。社会主義になり家は所有者から取り上げられ、すべて国有化され た。コス家の物語は、その鍵の数(もちろんそれ以上)の家とその家族たちの物語のほんの一角にすぎないという暗示ともとれる。
今年の米アカデミー賞は、女性の監督賞候補が一人もいなかったということが話題の一つになったが、本作は女性作家による、女性たちの物語を、女性が演出したことにも意義を感じる。作者も言うように、四世代の女性を描くことで、学ぶことにより自らの人生をつかみ取り、選択していこうという女性の自我の目覚めの物語にもなっているからだ。
モニカは貴族の屋敷で使用人として働き、字も読めなかった。その娘のローズはチトーのパルチザン兵士として戦う。〈家族のためにずっと食事を作ってきた〉と言うマーシャは、自分のこれまでの人生への後悔を口にし、思いを娘に託してきたという。一方、第四世代のアリサになるとロンドンの大学院で学び、恋愛も奔放だ。
アリサの「男の言葉? 男の言葉に意味があったことなんかある?」というセリフも痛烈だ。戦争を起こし、国を混乱に陥れる。ギリシャ劇の昔から、男の政治の犠牲になってきた女性の恨み節が、ここでも繰り返される。世界の仕組みは少しも変わっていないのだ。
そんな四世代、それぞれの女性たちの生き様を、普遍的な「私たち」の物語として身近に引き寄せた女優陣の演技が圧倒的だった。層の厚い劇団ならではの強みでもあろう。
南のモニカに使用人として自分を抑えてきた女性の悲しみがあり、倉野のマーシャは家族への愛と自己実現の間での思いの揺れを見せた。現実的な増岡のルツィアと、理想家肌でややとんがった前東のアリサが対照的な姉妹となり、対決シーンもヒリヒリとして見応え。パルチザン兵士だった永宝のローズに、苦しい戦争を生き抜いた胆力がにじみでた。
世界で富が偏在し、格差が広がり、資本主義のほころびが見えてきたところで、観客それぞれが「いま」を考えさせられたのではないか。ニューヨークの本屋で偶然この戯曲と出合ってほれ込み、粘り強さで企画を通した松本のバックストーリーも、作品に相通じるものを感じる。
文学座創設者の一人、岩田豊雄は「アトリエ憲章」の中で、アトリエの性質に言及し、「文学座の練達者をも含む冒険的な試演の機関」とつづる。『スリーウインターズ』も、実験ができるアトリエという空間だからこそ産まれた作品だったともいえるだろう(難産だったのではないかと推察されるが)。再演を望む声もあると聞く。作品がさらに育っていくのを楽しみにしたい。
* * *
『スリーウインターズ』と最後まで競り合ったオフィスコットーネプロデュースの『さなぎの教室』も面白く観た。こちらは創作劇であり、趣もまったく異なる。実際に起きた福岡県久留米市の看護師四人による保険金目当ての連続殺人事件を題材にしたクライムサスペンス風の人間ドラマである。作・演出、そして主犯格のヨシダを演じた松本哲也は、主宰する「小松台東」でも注目を集めている。会社など小さなコミュニティーにおける日常を舞台に、心の機微をさりげなく潜ませるセリフ劇に妙味がある。
大竹野正典作『夜、ナク、鳥』へのオマージュという企画に、松本なりのアプローチで挑み、事件のまた別の側面に迫真した。『夜、ナク、鳥』が治験患者との対比の中で、「生きること・死ぬこと」を問いかけたのに対し、松本は四人の看護学校時代と往還することで、いつ落ちるともしれぬ人間の心の陥穽をあぶり出す。この作品も時系列ではなく、結果から原因をたどっていくスリリングな見せ方が濃密な空間で奏功した。〝本歌〟の関西弁同様、宮崎弁という方言がもつ独特の人間くささが作品にリアルな息を吹き込んだ。松本のデフォルメを効かせたヨシダの怪物ぶりも強い印象を残した。
関西を中心に活躍した大竹野の作品にほれ込み、東京で猛プッシュしてきたオフィスコットーネの綿貫凜プロデューサーの企画力、情熱が伝わる公演でもあった。
個人的には『スリーウインターズ』の次に、俳優座の『インコグニート』(ニック・ペイン作)を推した。プロデュース公演全盛の時代、文学座と同じく歴史 ある劇団が新しい境地を開いた、意義ある公演だった。
相対性理論を提唱した物理学者アインシュタインの脳を研究のために盗み出した医師のトーマス・ ハーヴェイ、脳機能と記憶の研究に重要な役割を果たした健忘症患者のヘンリー・モレゾンという実在の人物がモチーフだ。トーマス(志村史人)とヘンリー(野々山貴之)、そして現代英国の臨床神経心理学者のマーサ(安藤みどり)、ヘンリーの恋人マーガレット(保亜美)を軸に、「自分とは誰か」を問う物語だ。 『スリーウインターズ』と同じく時系列も場所もシャッフルされるという、実にトリッキーな作品だ。しかも、四人の俳優が二十一の役を素早くギアチェンジしながら演じる。俳優が振り返っただけで別の人物、別の時代や場所に飛んでいる。上下で人物を演じ分ける落語のようでもある。俳優の力量が試されると同時に、演劇だからこそ味わえる面白さが凝縮される。
アインシュタインの脳が約二百四十ピースに分割されたように、断片的に提示されていく場面や情報への戸惑いが続く。ところが、脳のニューロン(神経細胞)がシナプスを通じて互いに情報を伝達し合うように、それらが次第に有機的につながり、一つの大きな物語が見えてくる。最後のピースがぴたりとはまるラスト、舞台の中で語られる脳の働きの神秘を観客自身が実感するという仕掛けにもゾクッとさせられた。
台詞では脳科学の用語も多く飛び交うが、描かれているのは人間がいかに不可思議でいとおしい存在であるかということだ。脳内を思わせるようなフューチャーリスティックな装置(杉山至美術)も俳優座の稽古場にいることを忘れさせた。一場面も見落とせない緊張感もありながら、演出の眞鍋卓嗣がドラマを丁寧に掘り下げ、人間への慈しみを感じさせた。劇団ならではのアンサンブルのよさも光った。長年の俳優座ファンには斬新すぎたかもしれないが、次代を見据えての果敢な冒険を続けてほしい。
選考の対象となった作品についてもう一つ。「福島三部作」には、作家の谷賢一の気骨が強く感じられた。福島県出身でもある谷が、原発の誘致から東日本大震災の原発事故にいたるまでを、綿密な取材を通して生々しいドラマに仕立てた。
問われているのはフクシマだけではない。日本の政策決定過程のゆがみ、中央と地方の格差など普遍的な問題を内包する強度ある作品だ。再演を望みたい。
劇団という集団の力と技に着目して推したのは、期せずして二つとも翻訳劇となった。二〇一九年の現代演劇界を概観すると、『 Le Pere 父』『CHIMERICA チャイメリカ』 『SWEAT』など時代を映す質の高い翻訳劇が多く紹介されたのが収穫だった。もちろん創作劇も、野田秀樹の『『Q』:A Night At The Kabuki』、松尾スズキの『命、ギガ長ス』、赤堀雅秋の『美しく青く』『神の子』、蓬莱竜太の『ビューティフルワールド』、シライケイタの『獅子の見た夢』(堀川惠子原作)などが強い印象を残したが、残念ながら特に若い書き手に少々物足りなさを感じた。今後に期待したい。
今年はNHKの常時同時配信、そして5Gという高速・大 容量の通信サービスも始まる。てのひらのスマホで、たいがいのことは楽しめる世の中になった。だからこそ、遠く離れた国の出来事であっても、俳優の生の肉体と声を通し、人の痛みや悲しみ、喜びを肌で感じることのできる演劇は、よりかけがえのないメディアになるはずだ。
- <<前の記事:第七回「ハヤカワ悲劇喜劇」賞選考結果
- 第八回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞の選考について:次の記事>>