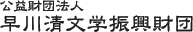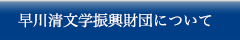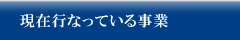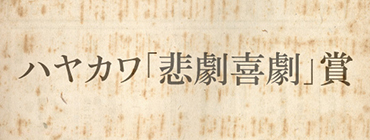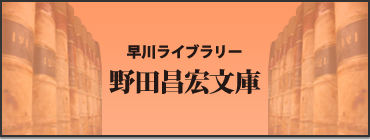第三回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考委員批評文
『リチャード二世』
──ネクスト・シアターとゴールド・シアターの豪華な共演
小藤田千栄子(映画・演劇評論)
二〇一五年=蜷川幸雄演出の舞台は六本あった。『ハムレット』『リチャード二世』『海辺のカフカ』『青い種子は太陽のなかにある』『NINAGAWA・マクベス』『ヴェローナの二紳士』である。この六本のなかには、再演の舞台もあるし、それ以上に複数回にわたっての上演作品もある。特徴は、いつも新しい演出を見せてくれることである。そのたびに、ああ、こういう作り方もあったのかと、教えられること多々の舞台ばかりである。
いきなり圧巻のタンゴ■
なかでも飛びきりは『リチャード二世』であった。チラシやパンフレットを見ると〈さいたまネクスト・シアター第六回公演〉と記されている。だからこれは若手中心のネクスト・シアターの公演なのだが、ゴールド・シアターの方たちが、力強く共演していて、この共演ぶりが、作品自体の魅力を、さらに大きくしていたのが特徴であった。
急いで追加すると、二月末に再演版を見せて頂いたら、チラシにもパンフレットにも〈さいたまネクスト・シアター×さいたまゴールド・シアター〉となっていた。つまり二つの劇団の共演と、はっきりと示されていたのである。この変更は、ゴールド・シアターの頑張りの、ひとつの証明であったとも言えると思う。
ところで、文庫本『リチャード二世』(松岡和子訳/筑摩書房)の巻末には、上演年表が掲載されているが、上演の少なさに、あらためて驚く。私など来日公演を、いちど見たことがあるくらいである。ゆえに、ほとんど初めて見た『リチャード二世』なのだが、なんとオープニングから圧倒されてしまった。
上演されたのは、彩の国さいたま芸術劇場のインサイド・シアター。三方に客席が作られ、残る一方向が、普通の劇場でいうホリゾントになる。そして、このホリゾントの奥から、主として俳優たちは登場する。
まずは〈ウィンザー城の玉座の間〉から始まるのだが、平土間舞台の奥から、いきなり多数の人物が、なんと車椅子で登場したのには驚いた。「これはいったい何?」と、見ているだけでアセってしまったほどだが、よく見ると車椅子に乗っているのは、ゴールド・シアターの方たちのようだ。演劇の舞台に、こんなにたくさんの車椅子が登場したのは初めてのことと思えるが、さらによく見ると、その車椅子を押している人たちもいる。
その押している人たちは、比較的若いので、ネクスト・シアターの方たちかしら、などと思いながら見ていた。するとどうだろう、車椅子の人たちは、みんな立ち上がって、押していた人たちとカップルになり、タンゴを踊り始めたのだ。振付=佐野あい。
この一瞬の驚きよ! 車椅子での登場も驚きであったが、瞬時にしてのタンゴには、さらなる驚きがあった。
「これってナニ?」──こんな舞台は見たことがない。こんなシェイクスピアは見たことがない。最初のうちは、あっ気にとられ、「これってナニ?」状態で見とれていた。しかも全員が礼服なのだ。男は、黒紋付に袴姿。女性は黒留袖というのか。ようするに第一礼装である。イギリス宮廷の話なので、礼服という設定か、などと思いながら見ていた。
たしか蜷川さんは、「芝居は最初の三分間が勝負」みたいなことを言っていたのを思い出す。どの作品かは忘れたが、インタビューに答えて、そのような発言をされていたのが、強く印象に残っている。このインタビューを読んでから、蜷川さんの芝居の、その始まりには、いつも注目していた。
常に工夫がこらされていて、ハナから見入ってしまうのが特徴だが、こんどの『リチャード二世』には、ホントに驚いた。みなさん、ダンサーではないので、踊りが上手とは言えないが、なんだかとても魅力的だったのである。タンゴという音楽自体の魅力、加えて和装にての動き、そして俳優たちの踊りという三つの要素に支えられて、この『リチャード二世』は、オープニングから私たちの心を捉えてしまった。
多分、何年の後にも『リチャード二世』が語られるときは、「あのタンゴが……」と、みんながクチにするであろう。それほどまでに魅力的であり、圧倒的なタンゴでもあったのだ。いったい、あの人たちは、どんなふうに、そしてどれくらい、タンゴのレッスンをつんだのであろう。
セクシーなボーイズ・ドラマ■
物語は、十四世紀末の、イギリス宮廷における王位交代劇である。イングランド王リチャード二世は、まずは従弟のヘンリー・ボリングブルックを追放する。この後、リチャード二世の後見人でもあるボリングブルックの父=ジョン・オヴ・ゴーントが没すると、全財産を没収してしまうのだ。リチャード二世自身の、アイルランド討伐のための軍資金にしたのだ。追放先で、この一件を知ったボリングブルックは、大軍を率いて、リチャード二世を追い詰めていく。そしてリチャード二世の退位へとつながっていくのである。
はっきり言って、これは王位交代の政治劇だと思うが、蜷川版の『リチャード二世』は、なんと言っても若い男優たちの魅力、さらに言えば、セクシーなボーイズ・ドラマの魅力にあふれていた。
リチャード二世を演じたのは内田健司。パンフレットに掲載の資料によれば、二〇一一年よりネクスト・シアター所属だそうで、初舞台は『血の婚礼』とある。だが私が最初にビックリしたのは『カリギュラ』のときだった。これは正確には「2014年・蒼白の少年少女たちによる『カリギュラ』」と書くらしいのだが、カリギュラって、こういう少年だったのかと、見入ってしまったのだった。
いや、少年というのは、ちょっとヘンかも知れないのだが、内田健司は、いつだって少年のイメージであり、繊細で大胆。服など、着ていても着ていなくても、そんなことは、どっちでもいいという感じの俳優であった。これは多分、俳優の個性ということになると思うが、『リチャード二世』のときも同様であった。
この人は、すぐにあっさりと上半身裸になるシーンが、いくつもあったが、それが実にサラリとしていて、清潔感にあふれ、なんと細身な! と見とれてしまうのであった。しかもこの姿で、いきなりのタンゴである。もう見とれるしかないであろう。
ボリングブルックは竪山隼太。パンフレット掲載の資料によれば、劇団四季にいたことがあるようで、『ライオンキング』には、ちょっとビックリ。いったいどの役を演じていたのだろう。蜷川作品では『ガラスの仮面~二人のヘレン~』(二〇一〇年)『ボクの四谷怪談』(二〇一二年)などに出ていたらしいのだが、私はこの『リチャード二世』で知った。
この二人が最初のほうで、いきなり和装を脱ぐと、なんと黒燕尾姿になるシーンがあった。この早替わりも驚きだったが、男二人の黒燕尾が、タンゴを踊り始めたのだ。こんなこと、シェイクスピアの戯曲には、どこにも書いてない。でも、舞台では、いきなりのタンゴで、これがまたなんともステキなのだ。この二人って、どういう関係? とも思うほどのステキなタンゴだった。
ボリングブルックとは、いちどは追放されるのだが、戻って王位につき、のちにヘンリー四世となる人である。ロイヤルの、はっきり言ってエライ人のはずなのだが、こちらもまたセクシーな作りで、そうなのか、『リチャード二世』とは、若い男二人のボーイズ・ドラマであったのかと、思わぬところで教えられてしまったのであった。
しかもこの二人は、特にリチャード二世のほうは、よく脱ぐのだ。実にあっさりと上着を脱いで、上半身裸になる。細身の王様で、身体つき自体が繊細さを表現しているようでもあった。そしてこの芝居は、リチャード二世とボリングブルックが対面するとき、最も魅力を発揮する。
そうなのか、『リチャード二世』とは、ボーイズ・ドラマなのだと確信したりもしたのだが、それも、かなりセクシーなボーイズ・ドラマと思えたのであった。
このような美少年二人にからむゴールド・シアターの俳優たちがまた健闘であった。特に、ボリングブルックの父親=ジョン・オヴ・ゴーント役の葛西弘には感心した。さらに『リチャード二世』には、いくつものゴールド・シアター向きの役柄があるが、みなさん見事なセリフ術で、こちらは懸命に聞いてしまうのだった。
原作の文庫本を読むと、セリフの長さには、かなりビックリ。私など途中で、ひと休みの感じだったが、みなさん、この長いセリフをこなしていたのにも感心した。
インサイド・シアターの舞台の使い方にも工夫がこらされていた。ホリゾントの奥は、こちらが思っている以上に深く(もしかしたら、本舞台以上に広いのでないだろうか)、その奥からの登場が、ドラマ自体に深みを与えているのだった。
魅惑のタンゴは、オープニングだけではなく、エンディングにも登場して、『リチャード二世』の総仕上げとした。再演のパンフレットには、四月の海外公演(ルーマニア国立クライオーヴァ劇場)も発表されていたが、海外の方々が、この日本味の『リチャード二世』を、どんなふうに見るのかと、それもまた楽しみになってきたのであった。
宝塚新世紀に名作の誕生■
『リチャード二世』についで、もうひとつ強力に推薦したかったのは、宝塚雪組のオリジナル・ミュージカル『星逢一夜』である。脚本・演出=上田久美子の大劇場デビュー作だ。宝塚歌劇団には、『ベルサイユのばら』で有名な植田紳爾以下、二十五名の演出家がいるが(『宝塚歌劇100年史』より)、上田久美子は、いちばん若いほうから二番目になる。
宝塚は、二〇一四年の百周年の賑わいを経て、昨年=二〇一五年は百一周年、つまり新世紀の始まりと位置づけ、いくつもの秀作を発表した。私見では、雪組の『ルパン三世―王妃の首飾りを追え!―』、宙組のロンドン・ミュージカル『TOP HAT』、月組のフランス・ミュージカル『1789―バスティーユの恋人たち─』、そして雪組のオリジナル『星逢一夜』などが秀作であったと思えるが、なかでも宝塚オリジナルで健闘の『星逢一夜』を推薦したい。
『星逢一夜』の前に、上田久美子は、宝塚バウホールほかでの小劇場ミュージカルで、二本の作品を発表している。まずは月組の『月雲の皇子―衣通姫伝説より―』(二〇一三年)で、これは古事記に取材した兄弟皇子の物語。バウホールのみでの公演でスタートしたのだが、あまりの好評に、急遽、東京公演が決まったというデビュー作である。
ついでの作品は宙組『翼ある人びと―ブラームスとクララ・シューマン─』(二〇一四年)で、タイトルどおり、あのブラームスとクララ・シューマンの、淡い恋物語である。この素材は、アメリカ映画『愛の調べ』(一九四七年)で有名だが、音楽が華麗で、有名曲がいっぱい。基本はラブ・ストーリーなのだが、節度ある関係が、宝塚ロマンによく似合って、幸せな観劇となった。
そして登場したのが『星逢一夜』である。星逢(七夕)の夜に出会った、九州の小藩・三日月藩の子供たちの話である。子供時代の描写が、まず引きつける。
村の子供たちは、みんな集まって夜空の星を見ている。リーダーは、藩主の息子・天野晴興だ。夜空の星をみることで、子供たちの心は、ひとつになっていた。雪組のスターの方々(早霧せいな、咲妃みゆ、望海風斗ほか)が、全員、子供時代も演じ、肩上げをした着物の着こなしが、なんだかとても可愛い。
やがて藩主の息子は江戸詰めとなり、八代将軍・吉宗に引き立てられる。その理由が、まずは宝塚らしいので感心した。つまり名家の息子でもなく、さらには剣術の名手でもなく、「彼は星をみる」と言うのだ。星をみるとは、多分、天候をみるということなのだと思うが、これがいかにも女性劇団らしいロマンに繋がっているのである。
やがて三日月藩では、一揆が起きる。詳しくは語られないが、多分、吉宗時代の政治の問題、つまり厳しい年貢の取り立てが理由と思えるが、その一揆を収める役目を、主人公が負わされるのである。しかも一揆のリーダーは、かつて一緒に星を見ていた親友である。
宝塚の舞台に、農民一揆が出てきたのは初めてだと思うが、かつての親友同士の対決がドラマの山場を作り、さらにうまいと思ったのは、このドラマの決着のつけ方であった。
もちろん、主演カップルの、せつないラブ・ストーリーもあるが、なんと終幕でドラマは、物語のスタートに戻り、みんな子供時代に戻っての幻想を見せてしまうのである。全体的にロマンチック色に染めあげて、宝塚の最良の面を見せたオリジナル・ミュージカルであった。
宝塚の演出家は、ほとんどが脚本家を兼ねているが、次回作が、さらに期待されている新進である。
傑作との遭遇・未遭遇
鹿島茂(フランス文学)
まず、二〇一五年は大学からサバティカル休暇をもらい、フランスに滞在する期間が長かったため、例年より日本で芝居を見る機会が少なかったことをお詫びしなければなりません。そのため、重要な作品を見逃していた可能性があり、『悲劇喜劇』賞審査員の資格に問題ありといえるでしょう。
しかし、そうした観劇機会の少なさにもかかわらず、全般的な印象を述べさせてもらえば、やはり今年は豊作な年ではなかったな、という感想を抱かざるを得ません。
原因の一つは、ここ十年ほど演劇シーンを賑わしてきたスター劇作家に中だるみ感が出て、いまひとつ優れた作品に巡り会えなかったことにあります。
一例を挙げると、岩松了作・演出、Bunkamura『青い瞳』(シアターコクーン)。自衛隊の海外派遣が現実となっている時代ですので、帰還兵の日常復帰というテーマはとてもアクチュアルなものなのですが、作者の心の中で結晶する何かが欠けていたのか、焦点が結ばれないままに終わったという感がありました。
これに比べると、蜷川幸雄演出の公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団『リチャード二世』(彩の国さいたま芸術劇場インサイド・シアター)は持ち前の鬼面人を驚かす演出が「決まった」ばかりか、言いたいことがはっきりと観客席にまで伝わってきました。それは、限界ある人間の生の中で、たとえ漸近線的にであろうと永遠なるものにどこまで近づけるのかという、芸術家ならだれしも思い描くであろう夢です。それを蜷川幸雄がこの作品に託しているということがはっきり伝わってきました。さいたまネクスト・シアターとさいたまゴールド・シアターを直前になってドッキングした効果が見事に現れている舞台でした。自身、車椅子で演出を手掛けている蜷川幸雄が、ゴールド・シアターの俳優たちを車椅子に乗せて舞台を縦横に駆け巡らせるというスペクタクルが冴えに冴えていました。
演出の面では、前半を抑え気味にしておいた効果が後半になって大きく出て大団円を迎えるというセーヴ演出が成功していて、『リチャード二世』という、上演回数が少なく、ある意味、とても地味な芝居を傑作に仕立てています。演出次第で、戯曲の中に眠っていた芸術性が目覚めるという奇跡を目の当たりにした思いです。私自身は、若手の劇作家の作品を推すという方針を取ったので、候補作に挙げてはいませんが、『悲劇喜劇』賞にまことにふさわしい作品であると思います。
では、次に、私が推した作品の選評に移りたいと思います。
一つは、前川知大作・演出、劇団イキウメ『聖地X』(シアタートラム)を推しました。これは、二〇一〇年初演で数々の賞を受賞した『プランクトンの踊り場』の再演なのですが、しかし、前川知大は自己模倣を避けるため、作品をいったん解体して再度組み立てるという方法を取り、自作の中からもう一つ潜在的に存在していた自作を取り出すという試みに挑戦しています。
『聖地X』のテーマはドッペルゲンガーですが、これこそ今日的な問題だと思います。そう感じるのは、アルツハイマー症の人が多くなり、彼らが日々ドッペルゲンガーの世界を生きていることがあるかもしれませんが、より切実なのは、若い人たちの間にドッペルゲンガー的不安が広がっていることです。アイデンティティ・クライシスという言葉がありますが、現実はすでにそれを通り越していて、自己分裂のつくり出すドッペルゲンガー的状況がいたるところで発生しているのです。
演技陣も、浜田信也、安井順平、伊勢佳世、盛隆二、岩本幸子、森下創、大窪人衛といった「イキウメ」のレギュラーメンバーが勢揃いで、よく練り込まれたセリフのやり取りが緊張感を持続させています。
新作を重視するという本賞の方針に敢えて逆らって本作を推したのは、再演とはいえ、まったく別作に近い印象を与える演出の冴えを高く買ったからにほかなりません。演劇的カタルシスからいったら、間違いなく、本年度ベスト・ワンの舞台でしょう。
芸術に対し、前川知大作・演出、カタルシツ『語る室』(東京劇場シアターイースト)はそのタイトル通り、幾重にも入れ子構造になった時間をエッシャー絵画のように扱った意欲的作品ですが、なんというか、本来なら一気にフォーカスしていくべき時間の「焦点」のようなものが現れてこないという思いを強くしました。どこがいけなかったかというと、われわれの日常の中に潜む闇のようなものがいっこうに現出してこないからでしょう。成功した前川作品には例外なくこれがあり、思わず肌に粟を生じるような感覚を抱くものですが、『語る室』はエッシャー的な自己言及性にこだわるあまり、この点を逸していて、残念ながら完成度は『聖地X』に及びませんでした。
『悲劇喜劇』賞の候補作としてもう一つ推したのは、古川健作・日澤雄介演出、劇団チョコレートケーキwithパンダ・ラ・コンチャンの『ライン(国境)の向こう』(東京芸術劇場シアターウエスト)です。矢作俊彦の『あ・じゃ・ぱん』という小説でも日本が昭和二十年八月一五日に降伏せず、東日本がソ連に、西日本がアメリカとイギリスにそれぞれ占領されて冷戦ないしはゲリラ戦を行うというパラレル・ワールド的な設定が使われていましたが、本作では、日本は北日本(ソ連の傀儡の日本人民共和国)と南日本(アメリカの傀儡の日本国)という分断国家となっています。しかし、本作では焦点を某県の小松という二軒の家しかない小村落を舞台にして、その二軒が北日本と南日本に分断されたら、村人はどのような行動に出て、どのような思考を働かせるのかという興味深い実験を行っています。
近藤芳正、戸田恵子、寺十吾、高田聖子をはじめとする出演者たちの出色の演技で、緊張感はどんどん高まっていきますが、昔の映画『ロリ・マドンナ戦争』のようなラストを予想していた私には、最後のオチは少し甘いような気もしました。おそらく、もし北日本と南日本が本当に対峙していたとしたら、清野菜名演じたスターリニスト少女「村上花子」が党派の論理を冷酷に貫くはずで、両家は最後の一人まで殺し合っていたにちがいありません。
ところで、私が冒頭で述べたように今年は審査委員の資格なしとしたのは、劇団チョコレートケーキの『追憶のアリラン』を見逃しているからです。見なかった芝居のことは語れませんが、見ていたら候補作に推した可能性は十分にあります。
さて、以上で推薦作のことは終わりにして、他の審査委員の方々が推している作品で私が見たものについてコメントを加えておきたいと思います。
まず、井上ひさし作、鵜山仁演出、劇団こまつ座『マンザナ、わが町』(紀伊國屋ホール)は演劇として最高のレベルに達している作品で、初演を優先するという原則がなかったら受賞作となっても当然の傑作です。土居裕子、熊谷真実、伊勢佳世、笹本玲奈、吉沢梨絵の全員の演技が素晴らしいのですが、とくに謎の日本人「サチコ斎藤」を演じた伊勢さんは出色で、さすがは劇団「イキウメ」の看板女優と唸りました。
次に上田久美子作・演出、宝塚歌劇団雪組『星逢一夜』(宝塚大劇場)ですが、私はこれを宝塚大劇場で見てきました。そういうと、いかにも宝塚通のようですが、何を隠そう、私にとってこれが宝塚初体験だったのです。実は、いまある雑誌に宝塚を創った小林一三の伝記を連載しているので宝塚歌劇を大劇場で見なければ話にならないと考えて、遠路、宝塚まで足を運んだのですが、それはあくまで大劇場と宝塚なるものを体験すれば演目はなんでもいいという体のものだったのです。ところが、なんとしたことか、『星逢一夜』の素晴らしさに仰天してしまいました。とくに、早霧せいなのアウラには圧倒されました。彼女は間違いなく宝塚の新しいスターに育っていくことでしょう。私はそうと知らずに「スター誕生」に立ち会ったことになります。
メルヴィル作、高橋正徳演出、文学座アトリエの会『白鯨』(文学座アトリエ)は、メルヴィルのあの大小説をどのようにして二時間半の戯曲にまとめるのか大いに興味がありましたが、少し期待外れに終わりました。白鯨の幻影がいっこうに現れてこないからです。エイハブ船長役にカリスマ性が感じられなかったのが原因だと思います。
最後に、二〇一五年で気になったことを書き留めておこうと思います。それは、商業演劇ばかりではなく、実験的な小劇場でも平日のマチネ公演が増えてきたことです。消息筋の話では、熱心な観客というのが専業主婦のほかに定年退職した往年の芝居好きの男性しかいないため、どうしてもこうなるのだそうですが、この傾向は演劇界にとってはなはだ危険な兆候ではないかと思います。この調子でいったら、十数年後には観客はいなくなってしまうからです。
観客の再生産には、若い人を劇場に呼び込むことが不可欠ですが、平日がマチネだけというのでは初めから再生産を放棄してしまったに等しく、これでは先細りになるのも当然だという気がします。
ちなみに、パリでは、小劇場は平日でもソワレを二回転、三回転させて、勤めが七時以降にしか終わらない人も観にこられるようになっています。
バーチャル・リアリティ全盛の世になればなるほど、演劇が盛んになるのは確かなので、演劇人は平日のマチネという安易な道は取らずに、なんとか若い世代を育てていってほしいと思います。
いずれにしろ、観客がなければ演劇は成立しません。人口減少が避けられない御時世だからこそ、観客の再生産を第一に考えなければならないのです。
ハヤカワ『悲劇喜劇』賞選評
辻原登(作家)
芝居を愛好すること人後に落ちないつもりだが、いつまでも素人愛好家に過ぎない私が、おこがましくも選考委員を引き受け、今回も選考会の末席を汚してしまった。内心忸怩たるものがある。
しかし、二〇一五年はシェイクスピア劇を三本観る機会に恵まれた。
二月二十八日(土)に『ペリクリーズ』(加藤健一事務所、演出・鵜山仁)を本多劇場で。四月十六日(木)に『リチャード二世』を彩の国さいたま芸術劇場インサイド・シアターで。八月一日(土)に『トロイラスとクレシダ』(演出・鵜山仁)を世田谷パブリックシアターで。
三作とも堪能した。
鵜山仁という演出家は大活躍だが、随分昔、彼が多分、イタリアの演劇大学かどこかに留学していて、帰国して最初に手がけたピランデルロの『作者を捜す六人の登場人物』を文学座のアトリエで観て、こいつは凄い、と讃嘆した記憶がある。
シェイクスピア劇以外では、七月二十五日(土)に『かがみのかなたはたなかのなかに』(作・演出・長塚圭史)を新国立劇場で。九月三十日(水)に別役実の『あの子はだあれ、だれでしょね』(演出・藤原新平)を文学座アトリエで。十一月二十三日(月)に『ラスト・イン・ラプソディ』(作・美苗、演出・原田一樹)を俳優座劇場で。そして、十二月六日(日)に『痕跡』(作・演出・桑原裕子)をシアタートラムで。
二〇一五年はこれで終わり。何だ、それだけしか観てないのか、と言われるかもしれなが、僕にはこれが精一杯。ただ、今年二月二十三日(火)に『リチャード二世』(再演)を観ることができた。
去年は、選考会の席上でも、授賞式の会場でも来年は年間最低二十本は観る、と宣言(宣誓)し、約束したのに、これでは……。
しかし、しかし、とにかく僕はネクストシアターの『リチャード二世』とKAKUTAの『痕跡』にはいたく感激した。近年、観たものでは『マニラ瑞穂記』(秋元松代)と『鼬』(真船豊)が出色だったが、『リチャード二世』と『痕跡』の素晴しさはそれに匹敵する。
『リチャード二世』は蜷川幸雄の演出が冴え返っていたし、俳優たち(ネクスト・シアターの若手たち、そしてゴールド・シアターの面々)の技量と熱、─僕は特にリチャード二世を演じた内田健司に類い稀な才能と不思議な役者の魅力、オーラを感じた─、そして落してならないのは松岡和子の翻訳! 流麗かと思えば詰屈、シェイクスピアの魅力が日本語で増強された。
とにかく『リチャード二世』を一年も隔てずして、全く同じスタッフで観ることができたのは幸運だった。いい本を再読する喜びと似ている。それにまた、リチャードの台詞、「むだに時間を使うた報いで、今は時間めがおれを使ひをる」(坪内逍遙訳)を再演時には頭に入れておいて、「私は時を浪費した、そしていま、時が私を浪費している」(松岡和子訳)に重ねて聴く喜びも加わった。
内田健司にはいつか、できのいい翻案劇で『ドン・キホーテ』を演じてもらいたい。
『痕跡』は、これまで僕が観て来た新作劇の中でベスト・ワンかもしれない。劇曲の構造が、精緻な中国の鳥籠のように編まれている。俳優の動きと台詞が、ドラマ(籠)の中をジグソーパズルのピースが自在に動きながら、徐々に組み合わさっていくかのように動いて、謎を解き、テーマを浮かび上がらせる。ラストには静かな、胸にしみるカタルシスが待っている。桑原裕子という若い才能をこれから追いかけてみようと思う。
二〇一六年は十五本は観るぞ!
劇の力は、世界を変える
今村忠純(近代文学・近代劇文学)
『マンザナ、わが町』■
一九四一年十二月七日の日本軍による真珠湾奇襲攻撃は、当時のワシントン、オレゴン、カリフォルニアの西海岸三州に居住していたおよそ十二万の日系人の運命をがらりと変えてしまった。
「ジャップはジャップだ。アメリカ市民であろうとなかろうとジャップに変わりはない」「ジャップは卑劣なイエロー・モンキーだ。ジャップは人間じゃない」
ルーズベルト大統領は、行政命令第九〇六六号、および第九一〇二号に署名する。この日をさかいにして日系人の西海岸から内陸への強制立ち退きと転住は合法化され、WRA(War Relocation Authority/戦時転住局)の手によってただちに実行にうつされる。
日系人の仮収容所(Assembly Center)は、転住所(Relocation Center)へ、さらに強制収容所(Concentration Camp)にそのまま移行していったのだった。
カリフォルニア州オーウェン郡マンザナ、シエラネヴァダ山脈のつらなりにそびえたつホイットニー山の山裾に拡がる広大な砂漠地帯、そこにつくられたマンザナ強制収容所もその一つになったのだ。
井上ひさしの『マンザナ、わが町』の舞台は、日系人の強制収容が開始されたばかりの一九四二年三月下旬のそこでの五日間の物語になっている。
バラック住宅の松板材でつくられた粗末な部屋には、五人の女性が送り込まれる。劇は、その五人の女性たちのいわばリーダー格になるソフィア岡崎がオトメ天津をうながして朗読劇「マンザナ、わが町」上演にむけての稽古を始めているところから幕があがる。二人の読み合わせから、マンザナがどのような町であり、なぜこの劇を収容所内で上演することになるのかもすぐ私たちは理解することになる。
もっといえばこういうことである。『マンザナ、わが町』とは、この劇の題名であるとともに朗読劇の題名でもあった。朗読劇の稽古がいわば劇中劇になっており、この部屋に送り込まれた五人の女性、その一人一人の境遇を明らかにするものになっていく。というのも同じ日系人であっても、一世と二世とでは、対日、対米のありかた、その思想(感情)が屈折し、異なっている。だから、強制収容施設が日系人の自治によって運営されるものと説く朗読劇が、かれらのリトマス紙になっていくという、そのような劇の仕掛けがこの劇のポイントにもなっていたのだ。そこからゆきつく問題は、この朗読劇を書いたのは誰かというのにほかならない。
そして日系人を名のっていたサチコ斎藤こそが朗読劇の作者であって、じつは、彼女はアメリカ国務省から派遣された人類学を専攻する中国系アメリカ人、エミリア・メイ・チャオリンであり、彼女は中国人(アジア人)の視点からも日本人とはいったい何者なのかについて考えていたのだった。
人種差別というよりもさらにそのことから生じる排除と区別とたたかい続けてきた日系人一世と二世、その一人一人の半生が、そこからも浮かびあがるのだが、同時に日本人のアジアの人々への差別と蔑視も相対化される。この論点も重要なので、けっして忘れてはならない。「すてきなソフィア」「夢見るリリアン」「子を恋うオトメ」「ふしぎなサチコ」「花のジョイス」「この五人」と名づけていた全二幕六場のこの劇は、その一場一場のくもりない鏡に一人一人の来しかたがきれいに映し出されていくことになる。
朗読劇「マンザナ、わが町」に出演する演技者の一人でもあったソフィアは、この劇の稽古を繰り返していくなかで、演技者に演出家として何を伝えなければならないのかについて深く教えられることになる。同時にこの朗読劇に出演する一人一人の女性は、演技者としてばかりではない、いわば全人的な人間性に目覚めることにもなっていくのだ。
ソフィア岡崎のミゾラ強制収容所行に抗議し、マンザナ強制収容所所長にこれを断念させた四人の行動は、もう一つの新しい朗読劇「マンザナ、わが町」の誕生を約束する。エピローグにあたる「この五人」の第六場がそれである。蛇足かもしれないのだが、やはりここでソフィアの声を引用しておかなければならない。
所長に抗議するみなさんの声、勁くて美しい、とてもいい声だった。心の中にあるものを素直に声にして出す……、みなさんは見事に正気を保つやり方を見つけ出したんだわ。それなのにわたしの演出プランは、みなさんをただせわしなく動かしたり、生花をつくらせたり、どこか狂っていた。そこで新しいプランは、こうです。ここはたしかにひどいところ。でも、いまのわたしたちにはここしか住むところがない。だったらみんなして、できうるかぎりいい町をつくるほかはない……。
そこであらためてソフィアの合図で朗読劇の稽古を再開するのだが「日本人の血を引くすべての人びとのまほろば」というこのせりふの書き変えを提言したのが、作者のチャオリンその人だった。「人間の血を引くすべての人びとのひろば」と。劇の力は、人間を世界を変える、ということである。
「何人も正当な法の手続きによらなければ、その生命、自由、または財産を奪われない」。アメリカ合衆国憲法修正第五条に背かないものであることを、このあるべき朗読劇の誕生が担保していたのにほかならない。
『マンザナ、わが町』の鵜山仁演出の初演は、こまつ座第二十九回公演で一九九三年、それからじつに二十二年が経過しての同じ紀伊國屋ホールでの再演だった。鵜山演出は冴えわたっていた。五人の女性一人一人の半生の輪郭がはっきりとした。いってみればこの劇には五人の半生が詰まっていた。説明せりふのちからをいかに劇の言葉にするかが勝負になっていた。聴かせる劇にした。
カリフォルニアの農場の移動労働者として海を渡った亡き夫太郎吉の一生を語り続ける女流浪曲師オトメ天津の熊谷真実の熱度の高い切れのいい節まわしと演技、心あふれるものを抑えながら、しずかにやがて鋭く「ゴッド・ブレス・アメリカ」を歌い上げていくリリアン竹内の笹本玲奈、レストラン・シアターで歌うその声をじっと聞いている新聞記者ソフィア岡崎の、りりしくまっすぐなその土居裕子を観客は見ていたはずである。彼女の頬はぬれていたと思う。
サチコ斎藤というマジシャンに扮したチャオリンは、いちばんの難役だったと思われるのだが、伊勢佳世は、自分の生い立ちをものしずかにうち明けるチャオリンと、おもしろおかしく、しかも生真面目にサチコ斎藤を演じ分ける、その変身のギャップが見所だった。帰米二世の日系女優ジョイス立花の役どころは明瞭だった。ハリウッド映画の企画が真珠湾攻撃で「下田脱出」から「日本潜入」にさしかえられ、やはり日本人は「蝶々夫人」の類型としてしか扱われないことをジョイスの吉沢梨絵からあらためて私たちは知ることになった。
『白鯨』■
『白鯨』は、もちろんハーマン・メルヴィルの『白鯨』の劇化である。セバスチャン・アーメストというイギリスの俳優で、舞台や映画に出演しており、また演出家・脚本家としても知られている。「カリガリ博士」や「天井桟敷の人々」といった世界の映画史に残る名作などを、舞台のパフォーミング・アーツとして生まれ変わらせてきたという実績もある。
『ANJIN』(ホリプロ制作)で、小林勝也がセバスチャン・アーメストと共演したことが、今回の文学座アトリエの会での『白鯨』上演のきっかけになった。
?ジョン・ヒューストン監督の『白鯨』は、私の世代で知らない映画ファンはいないはずで、おそらく小林勝也もその一人ではないか。もちろん小林勝也がエイハブ船長である。グレゴリー・ペックのエイハブ、たしかレオ・ゲンがスターバック……、これもセバスチャン・アーメストの名作映画劇化シリーズの一連にある作品だったのではないかと思われる。
文学座アトリエ公演にむけてのスタッフ、キャストの連帯は、おそらくメルヴィルの『白鯨』上中下(八木敏雄訳、岩波文庫)にたちもどり、その再読、そしてセバスチャン・アーネスト台本(小田島恒志訳)の解体から始まっていたのではないかと思われる。もっといえばそこから文学座アトリエの会仕様の、もう一つの『白鯨』が生まれたとはいえないかということである。演出は高橋正徳。美術は乘峯雅寛。
映画からも連想されるのだが、一種のトランスフォーメーション・ドラマ、つまり次々とシーンが変わり、一人が劇中で何役にもいれ変わり、いってみれば出演者すべてが物語の語り手ということにもなっていく。
それがもっとも顕著にあらわれるのは、これから上演する『白鯨』に出演する役者たち一人一人が『白鯨』に旧くは『創世記』『ヨナ書』から『ハムレット』『ヘンリー四世』『失楽園』など、もちろんメルヴィルその人が引用している文献をあげていく。つまりこれは役者たちの連帯がつくりあげた劇であるということの表明であったのだ。
裸舞台である。ロープ、布や銛、板切れなどが、次々とマストや帆にともづなやボートになっていく。布が風をはらむ。たとえば、イシュメイル(釆澤靖起)が初めて対面することになる、そしてイシュメイルをエイハブ船長のピークォッド号に乗船させる運命にみちびくことになる銛撃ち、全身をタトゥーでおおったクィークエグ(藤側宏大)と同室になるばかりではなかった。ロープをはりめぐらすことによってつくられた一つのベッドに枕を並べて一夜を送り、大海原にむかう同行者になるのだ。
台風のさかまく波にのみこまれ二枚の帆が解ける、二本のロープを持ってふみとどまっていたクィークエグが、イシュメイルを残して暗い海に投げ出されてしまうのだ。クィークエグの棺が海上を流れ去る。同行者は命綱ともいえるロープから手を離した。
ピークォッド号は、海に沈み、残された船乗りたちが捕鯨ボートに乗り込んだ。エイハブは、近づいてくる白鯨に身体ごと銛を投げる。
この劇の語り手が、最後に生き残ったイシュメイルであった。文学座版からやはり私はたえずジョン・ヒューストンの『白鯨』のワンシーン・ワンシーンを思い出さないではいられなかったのだが、それでもなお映画版『白鯨』とはまったく異なる感覚で劇づくりの可能性を発見することができたのだ。アトリエの空間は、客席から船底をのぞきこむことのできるような空間であり、また帆柱を高く掲げ、帆走する船上から大海原を望むこともできる空間である。台風にぶつかった船は、大波にのみこまれ、波しぶきがあがり、波間に隠れてしまう。『白鯨』は、アトリエの空間の機構に、もっともふさわしい劇として選ばれていた。
文学座アトリエの会のこの劇に連なるような作品、と書いていけば『白鯨』のチームがつくりあげたようなアトリエの会の舞台を、私たちはすでに二、三の作品に想起することができるはずである。アトリエの会の明るいその可能性を二〇一五年末の、十二月公演の『白鯨』に発見できたのは幸せだった。
『リチャード二世』■
『リチャード二世』は、彩の国さいたま芸術劇場のインサイド・シアターで上演された。彩の国シェイクスピア・シリーズ第三十弾で、さいたまネクスト・シアターとさいたまゴールド・シアターと、あわせて六十名以上の競演が、見るものの目を奪った群像劇である。ネクストとゴールドの融合が、ふしぎな化学反応をおこし、まだ出会ったことのない『リチャード二世』という歴史劇の舞台を現出させた。
オープニングは、あかりの入った舞台奥から大勢の車椅子のゴールドの俳優たちが、ネクストの俳優たちに誘導されながらざわざわと大挙して正面にむかいまっすぐに進んできて、ぴたりととまる。やがて車椅子のゴールドの俳優たちの手をとったネクストの俳優たちとともに、タンゴのリズムに合わせて一斉に踊りだす。
まずこうして幕開きの黒留袖。紋付袴の貴族、従者たちがウィンザー城の玉座の間に一堂に会するところに、電動車椅子でリチャード二世が群衆を割るようにして舞台に現れる。このプロローグが圧巻だった。
蜷川マジックは、オープニングが、一気に観客を舞台にひきこんでしまう、いわばハレの光景から始まる。
十四世紀末、ちょうど一四〇〇年にリチャード二世は、三十三歳で息をひきとるのだが、撲殺された、窒息死させられた、餓死したなどの諸説がある。
松岡和子訳のちくま文庫版の巻末にある『リチャード二世』関連年表を参照しながら、あらためてそうした基礎情報を確認し、『リチャード二世』を読み返してみる。
リチャード二世は、歴代英国王きってのハンサムボーイで、これまた若いハンサムな寵臣を側にはべらせていたという。この英国王のとりまきのイエスマンがにこやかに見守るなかで、これもまた軽快なタンゴのリズムにのせて踊りだす。こうしたリチャード二世の享楽的で放縦、贅を尽くした生活を象徴するようなふるまいは、たちまちリチャード二世を転落させる。
ウェールズの海岸をのぞみ、荒波にもまれながらリチャード二世が、尾羽うちからしてアイルランドの遠征から帰国する場がある。いずこからともなくわきあがり、襲いかかるような高波に身をよこたえ、やがてさかまく波間に没してしまう。ボリングブルック(ヘンリー四世)へと譲りわたされる王冠の行方を暗示させるシーンにもなっている。これがいわば歴史の輪廻であるというように。
追放されていたボリングブルックが、大軍を率いて帰国する。派手好みのリチャード二世とは対照的に従兄弟でありながら冷徹なボリングブルックとの暗闘が繰り広げられ、ボリングブルックによる王位簒奪のなまなましい現場が公開される。王冠が空中に飛んで中空をさまよう、やがてこれがボリングブルックの頭上に静止する。また照明でつくられた十字架にリチャード二世が横たわる。ゴルゴタのキリストが準らえられているのだ。リチャード二世の現世のふるまいが浄化される。裸舞台なのだが、こうした蜷川幸雄の周到果敢な演出が目覚ましい。
ボンフレット城の牢獄につながれたリチャードのせりふを聞きながら、私たちはこの歴史劇が、蜷川幸雄の歴史劇スペクタクルにたちあがっていくプロセスを、あらためて理解することになる。聖書やシェイクスピアの韻文劇に疎遠であっても蜷川演出の意図も、シェイクスピアの言葉も十分堪能できると思われる。これはなにもこの『リチャード二世』の蜷川演出にかぎらないことなのだが。
エピローグは、ウィンザー城内、王位についたボリングブルックが、おおぜいの貴族、従者に祝福される。オープニングと同じようにタンゴの群衆が舞台いっぱいに拡がり、歴史の更新を知らされる、ヘンリー四世の治世の始まりが告げられる。見事だ。
魅惑的な蜷川シェイクスピア劇『リチャード二世』
高橋豊(演劇評論)
演出家・蜷川幸雄は八十歳を迎えた。車椅子に乗り、酸素吸入をしながらの稽古場入りだけれど、俳優やスタッフに投げかける言葉は痛烈で、かつ的確だ。「もっと面白く腑に落ちる舞台を作りたい」といつも前向きである。
傘寿の二〇一五年、蜷川は六本も演出している。うち四本が新演出である。公演順に挙げれば、『ハムレット』、『リチャード二世』、『青い種子は太陽のなかにある』、『ヴェローナの二紳士』と続く。再演は海外四都市も回った『海辺のカフカ』と十七年ぶりの『NINAGAWA・マクベス』だ。シェイクスピア作品が四本も並ぶのが蜷川らしい選択だ。
さて彩の国さいたま芸術劇場インサイド・シアターで上演された『リチャード二世』である。シェイクスピア作、翻訳が松岡和子、演出補が井上尊晶。出演が、さいたまネクスト・シアターと、さいたまゴールド・シアターの約六十人。この演劇集団について少し触れたい。
ゴールド・シアターは、彩の国さいたま芸術劇場の芸術監督である蜷川の「年齢を重ねた人々が、その個人史をベースに、身体表現という場を提供する」という発案で、〇六年にスタート、現在、平均年齢は七十七歳に達する。取材しながらつい微笑んでしまうのは、それぞれが独自の世界観を持ち、蜷川にもきっちり反論すること。「俺もゴールド・シアターの一員なんだよ」と蜷川は苦笑する。
ゴールド・シアターの舞台で最も感動したのは、清水邦夫作・蜷川演出の『鴉よ、おれたちは弾丸をこめる』だった。裁判所に老女たちが乗り込み、判事や検事を逆に裁いていってしまう。警察機動隊によって老女たちが粛清されていく極めて過激な「闘争劇」だ。一九七一年、蜷川が立ち上げた現代人劇場で初演された。若い俳優たちが老女役を務めていたのだけれど、ゴールド・シアター版は、高齢者が演じているため、生活感がきちんと出て、広がりがある。ラストに老女たちは若者に変身するのだが、かつて現代人劇場版を観ている私は思わず涙が出た。老女たちの切実な思いが最後にファンタジーを生んだのだ。本作の反響は良く、一三年にパリ、一四年に香港・パリと海外公演も行った。
ネクスト・シアターは、〇九年に「次代を担う若手俳優の育成」を目的に発足。ゴールド・シアターに比べると、蜷川の厳しい目も光り、メンバーの出入りも大きい。
だが、近年の蜷川の意欲的な試みは、ネクスト・シアターの舞台に多い。忘れられないのは一二年に上演した「2012年・蒼白の少年少女たちによる『ハムレット』」だ。稽古場に取材に行って驚いた。透明なアクリル板の板の床による二層の舞台で、俳優は上下二つの舞台を四つの切り穴から上下するしかない。透明な床だから大丈夫かなとも思ったが、取材中に俳優二人が穴から転落した。幸いケガはなかったけれど。本番になって、演歌デュオ「こまどり姉妹」が突然登場、歌い出したのにも驚いた。日本の「芸能人」「生活者」の彼女たちに対抗できる舞台をつくっているのか、と若い役者に覚悟を求めているのである。
本筋の『リチャード二世』の話に移ろう。
さいたま芸術劇場大ホール内の舞台に設置されたインサイド・シアターーで『リチャード二世』は始まる。車椅子に乗った高齢者が次々と登場し、そこで突然、タンゴが流れ車椅子から立ち上がった老若男女が踊り出す。圧倒的な迫力で、蜷川は「開幕三分間」で観客の心を掴んだ。
かつて蜷川からこう聞いたことがある。「財布からお金を取り出す生活者のまなざしに耐える演劇をつくりたい。『三分間で生活を忘れさせて、非日常の劇の時間と空間に連れ去ること』がプロの演出家の自己責任と規定しました。観客が払った金額に見合わないような演技の役者には遠慮なく灰皿を投げつける。『生活者に恥ずかしくないのかよ!』」
『リチャード二世』は、「開幕三分間」原則を守り、狭い劇場空間での華やかなタンゴの輪で観客の心を捉えてしまう。しかも、ほとんどが和服だから、さりげなく入り込める。若手のネクストと高齢のゴールドの団員が入り混じっているのもいい。実に魅惑的なオープニングである。
シェイクスピア作品で、『リチャード三世』は『ハムレット』と並んで男優たちが演じたがる役だが、『リチャード二世』は地味な歴史物とされ、日本での上演が少ない。
リチャード三世は醜悪な容姿だが、野心にあふれ、「口先で奇麗事を言う今の世の中、どうせ二枚目は無理だとなれば、思い切って悪党になる」と悪党宣言をする。殺した敵の妻を口説き落とし、実の兄を陥れ、幼い子を惨殺し、奸計を重ねて、念願の王となる。だが、その王座はあっけなく破滅した。戦場での最期の言葉「馬だ! 馬をよこせ! 代わりに俺の王国をくれてやる」と名台詞を吐く。彼は自分が演技していることをはっきり認識していて、爽快な「悪党」なのだ。現代人も笑いと共に引き込まれ、人気演目となった。
一方、リチャード二世は容姿にも恵まれ、既にイングランド王に就いている。宿敵である従兄弟ボリングブルック(後のヘンリー四世)を決闘直前に追放し、彼の父の全財産を没収してしまう。追放先でそのことを知った従弟は大軍を率いて反旗を翻す。戦果も人望もないリチャードは追い詰められ、王位を簒奪され、屈辱のうちに暗殺される。一言で言えば、脆弱で内省的な国王だった。
『リチャード二世』は全文韻文で綴られている。今回の松岡和子の新訳はよくその趣を伝えるもので、悲劇の王の心の嘆きを込めた叙情に満ちた台詞が続く。リチャードを演じる内田健司らがよく応えている。
前半は比較的、静かに進むが、後半はリチャードが戦に敗れ、ウェストミンスター大会堂で諸卿が見守る中でボリングブルックに王冠を渡す屈辱を受けるなど、かなり劇的な展開となる。この切り替えも快い。
いい台詞があることにも改めて気付かされた。王位と王冠の譲位を迫られた時のリチャードの言葉は痛切だ。「王冠は喜んで譲る、だが悲しみはまだ私のものだ。私の栄光や王位は奪い取れるだろう、だが私の悲しみは別だ。私は悲しみの王なのだ」。誌的イメージにあふれた「悲しみの王」リチャードである。
ビジュアルの視覚的イメージも優れていた。冒頭のタンゴのシーンだけでなく、浪布が効果的に使われていたし、特に臣下らに裏切られて孤立感を深めたリチャードが、床に落ちた十字架型の光で半裸の姿をさらけ出すのは、息を呑むほど美しい。まさしくキリストに通じる。一瞬、思い出したのは、蜷川が敬愛していた舞踏家の土方巽(一九八六年没)が七二年、新宿で行った『四季のための二十七晩』の連続公演である。かつて蜷川に思い出を聞いたとき、「『二十七晩』の踊りは凄かった。頭に花を飾り、大八車にくくり付けられて半裸の土方さんが現れたときは、『受難のキリスト』にも見えて、ヨーロッパの知性に裏打ちされながら、日本の原風景を探す姿勢に共感しました」と語っている。
今回のリチャードの半裸に、土方へのオマージュを感じたのは私だけだろうか。リチャードの内田に性別を超えるような魅力があり、ネクスト・シアターからスターが生まれる予感がある。
もともとはネクスト・シアターだけによる公演だったのが、緊急にゴールド・シアターの出演が決まったと聞いている。とてもいい選択で、冒頭のダンス・シーンだけでなく、彼ら彼女らが登場することで、世界の深みが違ってくる。
この狭い空間を活かしきった美術の中越司、技術監督・照明の岩品武顕も特筆したい。
ハヤカワ『悲劇喜劇』賞受賞が決定した後、彩の国さいたま芸術劇場で『リチャード二世』が上演されたのは嬉しかった。普通ならありえない再演である。予定していた蜷川と若い劇作・演出家の藤田貴大と組んだ新作『蜷の綿─Nina’s Cotton─』が、蜷川の体調がよくないため、公演延期となり演目が変更されたのだ。
一六年四月、「国際シェイクスピア・フェスティバル」の招聘を受け、ルーマニアのクライオーヴァでの上演が決定している。『リチャード二世』はヨーロッパできっと大きな反響を得るはすだ。
* *
選考会で私が推した二作品についても少しばかり触れる。
私の第一候補は、同じ蜷川演出ながら『青い種子は太陽のなかにある』だった。
その年を象徴するような作品にあげたいという気持ちが強く、一五年が蜷川八十歳と「永遠の前衛」だった劇作家・詩人の寺山修司(八三年に急逝)の生誕八十年だったため、本作を選んだ。
『青い種子は?』は、六三年に当時、二十八歳の寺山が執筆、未刊行のまま幻の音楽劇とされていた。五十年後の二〇一三年に発掘された。蜷川による初の舞台化だ。
六〇年代の高度成長期、スラム街に近代建築のアパートが建設され始める。建築現場で朝鮮人の作業員が転落して死亡。現場監督らは、その死体をアパートの土台のコンクリートに埋め込んでしまう。目撃した工員の賢治(亀梨和也)は、その場所にチョークで太陽のマークを描く。恋人の弓子(高畑充希)に真実を明らかにしたいと告げるが、彼女は結婚を夢見て同意しない。
やり場のない若者たちへの共感に満ちた作品だが、同時代を生きた蜷川は壮大なスケールの舞台とした。
上演劇場がオーチャードホール。客席が二千を越え、クラシックやバレエ、オペラが専門の縦長の劇場だ。蜷川にとって初めて挑むスペースである。
蜷川は傾斜舞台を作り、生々しく、かつ幻想的に物語を展開した。またも「開幕三分間」の魔力。ボッシュやブリューゲルらの絵を思わせる奇怪な人物やオブジェを登場させ、六〇年代の群像劇に移って行く。
劇中歌を松任谷正隆が担当、寺山の混沌とした劇世界に、透明な叙情性のある歌を提供した。出演者では高畑が光る。読売演劇大賞の杉村春子賞を受賞している。
大劇場での「目と耳の快感」などから、こちらを推したのだが。『リチャード二世』の方こそ、シェイクスピア劇の蜷川の本筋らしく、受賞は当然である。
もう一本は、ケラリーノ・サンドロヴィッチ脚本・演出の『グッドバイ』だ。
太宰治が入水自殺し、未完となった小説が原作だけれど、KERAが大胆に書き加えて上質なコメディーとなっている。
雑誌の編集長(仲村トオル)は、疎開した妻子を呼び寄せるため、美女(小池栄子)を伴って、多くの愛人と別れる旅に出た。
この美女が超個性派。大食いで、鴉のような悪声で、怪力の持ち主だ。男が愛人たちに「グッドバイ」を告げるはずの旅だったのが、逆に次々と彼女たちから別れを宣告される。
KERAの演出は多層的で、愛人同士が話し合うさまをはさみ、スピーディーに展開する。美女が実は純情だったことが判明するなど、ドンデン返しが続き、客席からは笑いが絶えなかった。
KERAのこれまでの作品は、根底にブラックな時代認識、未来予想があった。今回はそれとは違う突き抜けた笑いがある。
本作は読売演劇大賞の最優秀作品賞、小池が最優秀女優賞を受賞している。
- <<前の記事:第三回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考結果
- 第三回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞贈賞式を開催:次の記事>>