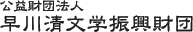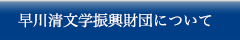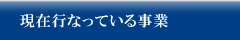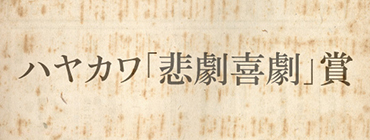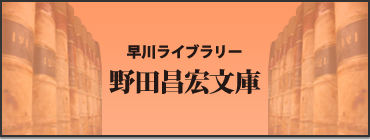第四回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考委員批評文
アレンジメントのオリジナリティ
鹿島茂(フランス文学)
二〇一六年は前年度に比べて豊作な一年だったような気がします。それぞれの劇作家、演出家が自分の得意な分野で全力を出し切ったからだと思います。
まず受賞作の『キネマと恋人』からいきましょう。
ケラリーノ・サンドロヴィッチさんは、一昨年末の『グッドバイ』が大変評判がよく、観逃してしまったことをおおいに後悔していましたが、万難を排してとまでは思わなかったのは、以前に観た『社長吸血記』の記憶が強く残っていたからです。『社長吸血記』は作者が一人でおもしろがっているだけで観客は全然楽しめないという、ケラリーノさんの悪い面ばかりが強く出た作品で、「才能の空回り」という印象を強く受けました。その前に観た岸田國士『パン屋文六の思案』には感心していましたので、失望は大きかったのです。
しかし、今回、『キネマと恋人』を観て傑作だと思うと同時に、ケラリーノさんの才能のありかがよくわかりました。そして、『キネマと恋人』が傑作なのに『社長吸血記』が失敗作である理由もはっきりしました。
それはケラリーノさんの本質がアレンジャーだからだと思います。アレンジャーは作曲家がつくったメロディーを「音楽」に仕上げていく人で、作曲家に比べてあまり偉い人とは思われていませんが、アレンジャーに言わせると、メロディーなんてどうでもよく、極端にいえば、子供がつくったプリミティブなメロディーでさえアレンジ一つでベートーヴェンのように重厚にも、モーツァルトのように軽快にもできるそうです。つまり音楽の本質はアレンジメントにあるのですが、ケラリーノさんの芝居(戯曲ではなくあえてこの言葉を使います)はまさにアレンジメントそのもので、元になる戯曲なんてものは「どうでもいい」のです。おそらくケラリーノさんは、こちらが任意の戯曲を渡して「これを芝居にしてくれ」と言ったら即座にかなりおもしろい芝居にしてみせる腕前をもった人なのです。
しかし、本当に元になる戯曲や映画あるいは小説(つまりメロディー)はどうでもいいのでしょうか?
おそらく、次のように言えるのではないでしょう
か?
アレンジに向いたものとそうでないものの違いはある。基本的になんでもアレンジはできるが、アレンジすることで、アレンジメントのオリジナリティが出せるものとそうでないものがある。前者でなければやっていておもしろくない、と。
そう、ケラリーノさんの芝居は、やはり原作を選ぶのです。
この意味で、ウディ・アレンの『カイロの紫のバラ』はケラリーノ・サンドロヴィッチにとって、アレンジのオリジナリティが出せる格好の「元メロディー」に思えたことでしょう。つまり、これをベースにすればいくらでもオリジナルなアレンジメントを楽しむことができる、いや、たんなる元メロディーにすぎない『カイロの紫のバラ』などよりもはるかにおもしろい作品をつくる自信があると確信したはずなのです。
こうした「元メロあり」の芝居の場合、観客や批評家の目は、『カイロの紫のバラ』とどこが同じでどこが違うかという点にしか向かわないものですが、まさにそれこそがケラリーノさんの狙いそのもので、手品師さながらに、観客がそこばかりに目をやっているすきに、こっそりとトリックを仕掛けて、別の場所でオリジナリティを強く打ち出しているのです。
ひとことでいえば、ケラリーノ・サンドロヴィッチという人は、かなり構造のしっかりとした原作があったほうがかえって良い作品を作り出すことのできるアレンジャー的劇作家だということになります。
しかし、それはオリジナル戯曲の場合には大きな欠点ともなりえます。アレンジメントの方にオリジナリティがあるために、オリジナル戯曲だと「核がない」ということになりかねないからです。
とはいえ、現在の演劇シーンを見ればわかるように、芝居においてはオリジナル戯曲はむしろ少数派で、シェイクスピアにしろ、ラシーヌにしろ、歌舞伎にしろ、演出、つまりアレンジをどうするかにすべてがかかっているわけで、アレンジこそが芝居の本質なのです。こうした意味では、ケラリーノさんはまさに芝居の王道を行っていることになります。というわけで、今回の「ハヤカワ『悲劇喜劇』賞」が『キネマと恋人』に与えられたということは、もっとも芝居らしい芝居が高く評価されたといっていいでしょう。
次には推薦作としてあげた『ビニールの城』を取りあげたいと思います。
唐十郎の戯曲というのは「読んでもおもしろい戯曲」の典型で、唐芝居の上演に同時代的に立ち合えなかった人でも戯曲を読むことで十分に雰囲気を味わうことができます。そのため、唐戯曲を読んだ演出家はみな一度は唐芝居に挑戦してみたくなるようです。
ところがこれがなかなかうまくいきません。理由は唐さんの戯曲にはアレンジを働かせるべき「あそび」が少ないからだと思います。言いかえると自由気ままに想像を働かせることができないような「剛構造」になっているのです。
そのため、唐芝居では売り物だった前近代的なおどろおどろしさが、他の演出家の芝居では、さながらファションに取り入れられたSMのボンデージのように毒気を欠いた空疎な記号になってしまうのです。
蜷川幸雄さん演出の唐戯曲でさえこの弊を免れることはできませんでした。
ですから、蜷川幸雄追悼公演と銘打った『ビニールの城』もあまり期待せずに観にいったのですが、期待は良い意味で裏切られました。
なぜかといえば、『ビニールの城』の「仮想現実性」がグラビア・アイドル出身の宮沢りえにぴったりとフィットして不思議なリアリティをつくりだしていたからです。すなわち、一方向的に無数の視線の矢を浴びるが、自分からは決して視線を返すことが出来ないという状況、つまり「ビニールの城」の内側に留まることを永遠に運命づけられた美少女モモという設定が、ヴァーチャル・リアリティのほうが現実よりもはるかにリアルになってしまった二十一世紀において大きな意味を持つようになってきたのです。この意味では、唐の戯曲の中では、『ビニールの城』はダントツに現代的なのかもしれません。モモに宮沢りえを得たことで二重にリアリティを持つ結果となったのです。
しかし、『ビニールの城』が成功していたのは、やはり、なんといっても「大人計画」所属の荒川良々でしょう。手入れをせずに放っておいたら伸び過ぎてしまったとでも言えるような「無意味に大きい」体格。おしゃれでもいきがりでもない、これしか似合うヘア・スタイルがないからという理由でそうしている坊主頭。お人よしのように見えながら、まがまがしい犯罪者の凶暴さを内に抱えているようなその顔付き。いずれをとっても、全盛期の状況劇場にジャスト・フィットする怪優です。
思えば、状況劇場があの圧倒的な迫力をつくりだしていたのは、それぞれの劇団員の「身体性」にありました。個性あふれる劇団員が舞台に立って「そこにいる」というだけで観客は熱狂したのです。あの「身体性」の迫力はその場に居合わせて目撃した人でなければ理解不可能です。
その「身体性」が荒川良々にはある、と彼が舞台に現れた瞬間に感じました。荒川良々を『ビニールの城』に抜擢したのは蜷川幸雄さんだそうですが、まさに蜷川幸雄さんも私と同じ「身体性」を彼の中に感じたにちがいありません。この意味では、蜷川さんこそ、もっともよく唐十郎を理解していた一人なのではないでしょうか?
最後に、他の審査員の方々が推薦作に挙げながら受賞には至らなかった作品について言及しておきたいと思います。
まず劇団イキウメの『太陽』ですが、純粋に芝居の完成度からいったら、あきらかにこれが二〇一六年のベストプレイです。劇団イキウメのオリジナル・メンバーを用いた前川知大さんの演出は一部のスキもないという言葉がピッタリなほど研ぎ澄まされていて、完璧な仕上がりになっています。セリフとセリフのぶつかり合いからドラマツルギーが生まれるという芝居本来の醍醐味を心の底から味わうことができました。この作品ひとつをとっても劇団イキウメが日本のトップクラスにいることは明らかです。
ただ、残念なことに初演を優先するという本賞の方針を顧慮し推薦するのは断念せざるをえませんでした。
そこで秋公演『遠野物語・奇ッ怪 其ノ参』には期待をもって足を運んだのですが、ウーン、柳田國男と前川知大は空中で接近遭遇しながら、そのまますれ違ったとでもいうほかありませんでした。イキウメの特徴はSF的ないしはファンタジー的枠組みを設定することで現代の問題を凝縮して露呈させるという点にあるのですが、『遠野物語・奇ッ怪 其ノ参』では現代が浮かび上がってきませんでした。残念。
『エノケソ一代記』については選考会で発言した通りです。ニセモノを主人公にするなら、ロッパのニセモノとの対決によってニセモノがニセモノではなくなってしまう瞬間を扱うなど工夫が必要だったのではないかと感じました。
最後に、二〇一六年に印象に残った芝居について簡単に触れておきたいと思います。
世田谷パブリックシアター、シアタートラム公演の『同じ夢』は私好みのストレート・プレイで、壁を叩く音しか登場しない寝たきり老人を巡る家族とヘルパー、それに近所の人々の心理劇ですが、主演の麻生久美子さんの演技が光りました。表面的に交わされるセリフとそのセリフの下で動いている心理の乖離を巧みに演じていて、作・演出の赤堀雅秋さんの意図を見事に汲みとった素晴らしい解釈だと感じ入りました。
文学座公演・紀伊國屋ホール『春疾風(はやて)』(作・川﨑照代、演出・藤原新平)は『野分立つ』の川﨑照代さんの新作ということで期待していたのですが、いま一つ切れ味に欠けた感じがしました。敢えて欠点を指摘するなら、不在の中心となる夢追い人であった夫のキャラクターが善人すぎたような気がしました。ここはもっと謎を残しておくべきところだったのではないでしょうか?
同じ文学座のアトリエ公演『野鴨』(作・イプセン、演出・稲葉賀恵)は短期間の上演ながら今年一番の拾い物だったと思います。稲葉賀恵さんの単純で力強い演出は、情念のぶつかり合いをクライッマクスへと運んでいくイプセン劇とソリが合うのか、演出家の力量をまさまざと見せてくれた舞台でした。稲葉演出でラシーヌ劇を観てみたいものだと思いました。いま伸びしろの一番大きな演出家ではないでしょうか?
『悲劇喜劇』賞選評
辻原登(作家)
オマージュとパスティーシュこそ創造の源泉だと考えると、それが芸術作品だけに限らないことに気付く。精微な職人仕事も、より良く生きようとする我々の生もまた先人や古典に依拠しつつ営まれる。
もしその作品が、あるいは人間がオマージュとパスティーシュの対象を超えるようなことがあるなら──稀にしか起こらないが──、我々はそれを傑作と呼び、高潔な人と称えるだろう。
ケラリーノ・サンドロヴィッチ台本演出の『キネマと恋人』は傑作である。
『キネマと恋人』は『カイロの紫のバラ』を凌いでいる。それについていくつかの点を挙げてみたい。
先ず、舞台設定だが、『カイロの紫のバラ』はニューヨークの隣州ニュージャージーのどこかの街の映画館、『キネマと恋人』は東京を遠く遠く離れた島の、一軒しかない映画館(梟島キネマ)。ニューヨークからの移動は飛行機だが、島へは連絡船。つまり、かたや地続き、かたや海に隔てられている。トム役の俳優ギルは飛行機でやって来て、飛行機で去る。寅蔵役の高木高助は船でやって来て、船で去る。島にやって来る映画は一、二年遅れ。
空間と時間における、東京からの大きな距離がこのファンタジーのリアリティーを『カイロの紫のバラ』より保証する。
さらにハルコが観る映画の豊富さ多彩さ──マルクス兄弟『吾輩はカモである』『オペラは踊る』、バスター・キートン『キートンの蒸気船』、他にローレル&ハーディ、ハロルド・ロイド、ハリー・ラングドンetc──、そして映画『カイロの紫のバラ』にあたるのが、オール・トーキー映画と銘打った『月之輪半次郎捕物帖』。これがまた出色の出来映えなのである。
人物の多彩さ、豊富さにおいても、人情喜劇の組立てにおいても──、ハルコ、電二郎夫婦の絡みは、セシリアと夫のそれを、テンポ、ユーモア、ペーソスのいずれにおいても上回る。同じことは、ハルコと妹ミチルの関係にも言える(『カイロの紫のバラ』とは姉妹が逆転している)。
ミチル 人間がら、みぃんな見捨てられた魂んような存在だり。
ハルコ なに?
ミチル ええお姉ちゃん? 魂の観察者は魂ん中ん入ってくことはできんがっさ。だけんが魂ん淵んとこがら歩いて、魂と接触することはできるんだり。
ハルコ (実はよくわからないのだが)ああそう。良かったね。
ミチル お姉ちゃんわかっとる?
ハルコ わかっとらん。ちんぷらかんぷらだり。
ミチル 見捨てられた魂と見捨てられた魂が、せめてがら来世にでも出会えればええだりが……。(溜息)
ハルコ どうしたんだり。ミチル。
ミチル どうもせんよ。
ハルコ 見捨てられた魂?
ミチル そう。キミコにも今朝そう言って聞かせたんよ。
ハルコ キミちゃんに?
ミチル 「早く起きて芋がゆ作ってくれ」て駄々がこねるから。
ハルコ (ギョッとして)キミちゃんまだ三つよ。見捨てられた魂はまだ無理だり。
ミチル うなずいてただり。
ハルコ そりゃこわいからじゃないの?
ミチコ 違う違う。結局がら人生は無だって言うたら、考え込んでただり。
ハルコ 芋がゆ作ってやりんね。どうしたんミチル。妙ちくりんな本読んどらんで映画行こ。ね!
ミチル 映画なんて何千年か経てば誰も覚えてないがっさ。
ナンセンスと情理の入りまじった台詞のやりとりは、どの人物同士との間にも弛緩することなく続き、展開してみごとなアンサンブルをなす。
見逃してはならないのは、ハルコがセシリアより映画通であり(『キネマ旬報』の愛読者)、見巧者、すぐれた批評眼の持主であることだ。彼女が熱狂的な喜劇映画ファンであることがその証拠だ。ハルコはケラリーノ・サンドロヴィッチの分身に違いない。
ハルコのまなざしに込められた熱狂と批評によって、寅蔵はスクリーンから誘(おび)き出される。あるいは拉致されるのである。セシリアにはそのようなまなざしはない。強い現実(批評)の吸引力はない。
寅蔵 (嬉しそうに)現実の世界は不可思議でいっぱいだ……。
ハルコ 映画ん世界の方がずっと不思議よ。ワクワクするだり。ミイラ怪人もドロドロ妖怪も現実にはおらんし。
***
高助 惚れるわけがないだろう。架空の人物なんだから。架空の人物とつきあってどうなる?
ハルコ 寅蔵さんがら最高が人がっさ。
高助 それは僕が最高が人に演じてやったからだよ。だけど最高だろうが完璧だろうが、いないんだから実際には。実在しないんだよこいつは。
ハルコ だけんが。
寅蔵 実在できるよう精進する。
架空の人間が自己意識を持った瞬間だ。
梟島には、この物語が始まる前にすでに『月之輪半次郎捕物帖』の作者・脚本家が乗り込んでいたことが第一幕前半で明らかになるが、そのあと、寅蔵がスクリーンから抜け出したと聞いて役者やスタッフが島に押しかけて来る。ここで演じられるスラップスティックの面白さは、時代劇中の侍言葉と島の言葉(ケラリーノ語)と東京言葉とが三つ巴となって入り乱れ、絡み合い、展開することで倍増する。
畢竟、『カイロの紫のバラ』は映画の中の映画の話。スクリーン(フィルム)からスクリーン(フィルム)への出入りに過ぎない。『キネマと恋人』は舞台の中の映画の話だ。寅蔵が抜け出して来ると、そこは生身の役者がいる舞台であり、目の前には生身の観客がいて、寅蔵はそのまなざしも意識せざるを得ない。当り前のことだとはいえ、ドラマの深味と広がり、強度と輝きが違ってくるのである。
この舞台が傑出している点は他にもある。映画館の雇われ支配人小松さんと売り子の存在だ。妻子持ちの小松さんがハルコに恋をしている、という事実は貴重な補助線で、ドラマの強度を上げている。だが、何よりも素晴らしいのは売り子だ。
脚本家根本は『月之輪半次郎捕物帖』シリーズの筋書とセリフを支配しているが、売り子は常に梟島キネマの中にいて、スクリーンとスクリーン外のすべてを観ているのである。だからこそ、寅蔵がスクリーンを抜け出して起きるスクリーンの中のてんやわんやを「こん映画、傑作だり……」と賞賛し、やがてスクリーンの奥へ悄然と消えて行く寅蔵の後ろ姿に拍手し、「最高! 最高がっさ!」と喝采を送ることができる。胸のすく場面である。
しかも、舞台では、脚本家根本と売り子は一人二役(村岡希美)。絶妙の演出というほかない。
島の外から来た人間、映画の中から来た人間は全員去っていく。島はまさに陸から離れた島そのものとして、映画館もハルコも島の住人たちも海にというより宙に置き去りにされ、ハルコはまたスクリーンに夢中になる。掛かっているフィルムはハリー・ラングドンだ。
構造はアレン作品より複雑、深化されているうえに、物語はテンポよく、笑いと涙を誘いつつ、我々のノスタルジーを掻き立てて幕となる。我々の内奥は島となり、一人の女性(ハルコ)の残像が焼き付けられる。
しかし、我々は一つの傑出した舞台を観たはずなのに、一篇の映画を観たような思いに引き込まれるのはなぜか? ウディ・アレンの術中にはまったのだろうか。
再演だが、前川知大作・演出の『太陽』にも喝采を送りたい。SF・寓話の世界を借りて、家族と共同体、愛憎のテーマを鮮やかに織り上げた。
他に次の舞台が強く印象に残った。
『母と惑星について、および自転する女たちの記録』(パルコ・プロデュース)
『パーマ屋スミレ』(新国立劇場)
『ビニールの城』(Bunkamura)
『まちがいの喜劇』(Kawai Project)
『尺には尺を』(公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団/ホリプロ)
演劇の夢と映画の夢
今村忠純(近代文学・近代劇文学)
『反応工程』■
戦争と戦後情況に立ち入り、そこから出てくる諸問題と真摯に対峙し、自己の負うべきものとしての責任を問う──それらすべてを含みこんで、演劇的、舞台的実際(表現)をどのように追求し、とらえ得るのか。それらの導入的プロセスのようなものとして宮本研の『反応工程』を考え上演し、一九五八年五月に発足したばかりの劇団自由劇場を軌道に乗せることができたのは、程島武夫だった(『情況と演劇』社会新報、一九七〇)。
後年、一九六八年の程島武夫は、若き日の太田省吾の改編したW・ボルヒェルト(小松太郎訳)の『戸口の外で』をもって転形劇場をスタートさせることになるのだから、十年前の『反応工程』上演とこれとは一筋道にあったと思う。
米山実演出の文化座アトリエ公演の『反応工程』は、空襲警戒警報の臨時放送のたえない敗戦を至近にした軍需工場のあわただしい日々を、ひたむきに生きた人々の、新旧それぞれの生活と思想の衝突をいきいきと描き出してみせていた。それは何よりも演技者たちの新旧キャリアをこえたアンサンブルの勝利だったと思われる。
時は一九四五年八月と四六年三月、つまり広島・長崎に原爆を落とされた前後の三日間と、そのあくる年三月のある日。三池炭坑から出る石炭を原料にしてロケット砲の発射薬、爆薬をつくっている九州中部の、ある軍需化学工場、これが『反応工程』の舞台になっている。
コークス炉に放りこまれた石炭が、ガスとコークスとコールタールに分離される、その工程で、いわば石炭のガス化、液化によって水素やメタン、ベンゼン、トルエン、アセチレン、ホルムアルデヒトなどに化けて、さまざまなモノをつくり出す。『反応工程』というタイトルは、そのような蒸留工程から精留工程をへて、または乾留によって化学変化をおこす「装置」をさすのだが、同時に民間工場が時局の風向きしだいでいつでも軍需工場に「変化」し、またそこの労働者たちの「反応工程」そのものを含意するだろう。
劇は、(旧制)中学、高校、工専からこの工場に動員され、反応工程班に配属された勤労学徒たちと、かれらの監督教官、くわえて反応工程班長から責任工、見習工、現場担当係長、などとの関わりを中心に展開する。
召集令状がとどき、動員解除の手続きがあって明日にも入隊しなければならない勤労学徒が出てくる、工場に持ち込んだ本に難くせをつけられたり、召集をまぬかれようと姿をかくした学徒がいる、というようなことが起こるのだ。
会社は、そろそろ工程を止めようとしている、戦争も終りに近づいている、その気配を感じているのはここでずっと働いてきたベテラン。かれらは軍需生産で支えられているこの国の資本主義のカラクリを現場で見てきている。しかし工程を止めるわけにいかない。ほかに行き場はないからだ。これに対して戦争が終われば勤労学徒に用はない、そんな学徒たちを軍需工場に差配し、赤紙の運び屋として現れる監督教官がいる。国家の手先としての役まわりを演じている。憲兵に連れていかれた学徒は、飛び降り自殺をする、また防空壕から飛び出したところを機銃掃射で射たれた学徒もいる──。
敗戦のあくる年三月は、短いエピローグである。GHQの指令で組合をつくることになっている。会社は民主化をはからなければならない。これがスローガンである。
「八時間労働制即時実施」「賃金値上げ即時実施」のビラや「戦争は、もう、するな、人が死ぬ」と大書したプラカードは、いわば看板のかけかえにすぎないのだ。
石炭を乾留してコールタールをつくり、コールタールからベンゼンを工業的に生産するようになるのは東京ガスがいちばん早かった。ついで三池炭鉱や八幡製鐵所が、石炭ガスからベンゼン生産を始めることになる。第二次大戦中には、爆薬の原料としてベンゼン需要が拡大する。
『反応工程』は、こうして石炭化学工業の歴史をあらためて思い出させてくれたばかりではない。
二〇〇八年になって豊洲の東京ガスの跡地から環境基準の四万三千倍のベンゼンが検出されていたことや、豊洲市場移転を間近にしての最終モニタリングで、やはり環境基準を大きくうわまわるベンゼンが検出されていたことまでもが『反応工程』問題としてなまなましく浮上してくるのだ。
『フリック』■
舞台は、映画館内で、そこからは場内全体がみわたせる、また正面奥が映写室になっていることも分かる。だから私たちは映画館のスクリーンの側から、この劇を見ていることになる。『フリック』という劇のこういう舞台の仕掛けがまずおもしろい。
『フリック』には、おびただしい数の映画を公開してきた古い映画館の歴史がつまっている。まさにこの劇は題名が表象する舞台にふさわしい。そればかりではない、ここで公開されてきた数多くの映画の記憶とこの場所とが、分かちがたく結びついている。
映画が終わったようだ。観客はもういない、空(から)になった館内の掃除が始まる。
サムとエイヴリーは、この映画館の掃除やもぎりをしている。エイヴリーは、ありとあらゆる映画を見つくしているかと思うほどの映画オタクで、大学を休学してここにやってきたばかり。サムは、観客席の列を移動しながらモップでごみを掃き出し、それをゴミ箱に放りこむなどして、エイヴリーに仕事の手順を教えていく。エイヴリーはサムの手際を見ながら掃除のコツを少しずつのみこんでいくのだ。もう一人、映写室にいるのはローズ。白人女性で、男性を誘う性的魅力は十分。
このローズをまじえての、とりとめもない対話をつづけながらひととおりのノルマをこなしていく日々がくり返される。これが暗転によって強調されている。
しかし、いささかとりとめもなくみえる対話の呼吸、その息づかいや沈黙、そこから少しずつ三人のそれぞれの物語がみえてくる。これがとてもスリリングなのだ。
社会、家族、恋愛など、現代の若者たちの徒労感がにじみ、かれらの生き難さが伝わってくる。暗転がこれを加速する。
この劇を翻訳した平川大作が、作者のアニー・ベイカーの言葉を引用している(プログラム参照)。「私にとって(黙劇は)沈黙じゃない」「自分の書いてきた戯曲でいつもいちばん気に入っているのは、誰も話していない瞬間」と、これがアニー・ベイカーの言葉である。
それは、ただの沈黙や間ばかりではない、長い(短い)沈黙か、長い(短い)間か、さらにそれが一分、一秒と、厳格に指定されていることもある。六秒くらい後……、(間が)十秒ほど続いて、変な間、まったく信じられないという間、しばしの沈黙、いやな感じの沈黙、という指定もある。マキノノゾミ演出は、『フリック』がマキノその人の原作と思わせるほどに緻密に、しかも自在にこの沈黙と間を実行してみせたのだった。
沈黙や間とは、「もの言わぬ術」のことである。もっといえば、沈黙や間とは言葉の裏にある言葉のことであり、さらにその裏にある言葉が事件の裏にある事件をさえ隠しているのだ。劇は、これを味解し、深く洞察することを強く求めている。劇の「もの言う術」は、この「もの言わぬ術」に担保されている。
映画オタクのエイヴリーと、そこそこに映画情報に通じているサムとが掃除の手も休めずに一息入れながら、ある映画スターの出演作品をあげてそこに登場するもう一人のスターの出演した別の映画を連想ゲームのように次々とあげていく。こうして五十本以上の映画リストがならぶのだが、そこにはフィルムからデジタルへと移行することによって、映画産業(生産)そのものの転換と需要の変質のあることを知らされる。
エイヴリーはデジタル化をきらっているのだが、サムはデジタル化は進化だというのだ。
古い映画館の歴史は、同時に映画史を語る。
フランソワ・トリュフォー監督の『突然炎のごとく』でジャンヌ・モローの歌う「つむじ風」が流れるのだが、これが、フィルム時代のノスタルジックなメロディにも聞えてくる。『突然炎のごとく』と『フリック』の物語は別なのだが、『フリック』のローズとサム、エイヴリーは、『突然炎のごとく』のカトリーヌとジュール、ジムを想起させるのは容易だと思われる。
『フリック』は、そのような六〇年代のヌーヴェル・ヴァーグへのオマージュのようにも見えてくる。
エイヴリーの父は大学の学部長で言語学を教えている。社会的にも経済的にも安定し自由な生き方を選ぶことのできるアフリカ系アメリカ人のエイヴリーに対して、映画館のゴミを集め運び出す労働に明け暮れるサムのやり場のない気分は、アメリカのプアホワイトの、いわば今日的な焦躁にもみえる。
境遇のちがうこの二人が対照されるのだが、そこによこたわる社会の経済的格差と思考のズレが氷解するエピローグがとてもいい。そこに一瞬間であれ、かすかな光が射す。
フィルムの映写機がとりはずされ、デジタルにきりかわる。映写室にとり残されていたフィルムのロールとともに、解体された映写機がサムからエイヴリーに手渡される。
そしてエイヴリーは、大学に復学するだろう、いつか映画館をつくるという言葉をサムに残している。
平川大作の翻訳は、サム、エイヴリー、ローズ……一人一人のいわば言葉の性格をちゃんと書き分けていく。
サムの言葉は粗雑でとがっているのだが、心根のやさしさがのぞく。潔癖すぎるかもしれないエイヴリーを気づかい、また知恵のおくれた兄の結婚をよろこぶサムに拍手を送りたい。
菅原永二(サム)、木村了(エイヴリー)は、ともに役の居所(いど ころ)をみきわめて見事。女性の性をもてあますローズ(ソニン)は、そんな自分に戸惑っている。ローズをさりげなくかばうエイヴリーと二人、サム・ペキンパーの『ワイルドバンチ』のフィルムを見つづけるシーンが永く記憶される。
ウディ・アレン監督主演作品『マンハッタン』のラストシーンには、エイヴリーの思いが重ねられていた。映画館から去っていくエイヴリーのサムとの別れが重なる。
またこの映画『マンハッタン』からは、ブロードウェイミュージカルの楽曲を発明したあのジョージ・ガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」も聞こえてくる。
『フリック』は、この劇を見るものに、じつにさまざまな記憶をよみがえらせるのだ。
『キネマと恋人』■
ウディ・アレンは、名だたる映画作家である。映像と言語の機知縦横の実験は、ちょっと類を見ない。映画のための映画をつくりつづけている世界の映画作家である。
『キネマと恋人』には粉本があった。ウディ・アレンの『カイロの紫のバラ』をモチーフにしている。そのことは、ケラリーノ・サンドロヴィッチのロングインタヴュー「ぼくのキネマ体験、そして、この舞台を作った理由。」を読めば十分に足りる。KERAの映画に寄せる熱意は、ひととおりではない、なみなみならぬものが伝わる。『カイロの紫のバラ』についてならば、大森さわこの的確このうえない解説を、KERAのロングインタヴューとともにプログラムで読むことができる。
そこで今度はあらためて『カイロの紫のバラ』を観て、戯曲『キネマと恋人』も読むことになった。
大森さわこの解説を大きく省略しながら、一九三〇年代のニュージャージーが舞台になっている『カイロの紫のバラ』のプロットを確認しておく。
ヒロインのセシリアは映画に夢中、姉のジェーンとともに簡易食堂で働きながら、映画になぐさめられている。夫のモンクは、ギャンブルや女遊びにうつつをぬかしている。映画館にいるときだけは、つらい生活も忘れることができる。『カイロの紫のバラ』というモノクロ映画のスクリーンから抜けだした探検家のトムがセシリアに恋をした。トム役の俳優ギルまでもセシリアに一目惚れ。しかしセシリアは映画の中のロマンティックなあこがれの世界をあきらめ苦(にが)い現実の世界にもどっていく──。
『キネマと恋人』は全二幕、さらに場(シーン)を数えると第一幕が全二十場、第二幕は全十六場である。この全三十六場の多場物(多幕物ではない)の出現が、劇の仕掛けに新技法をもたらしたことは疑いえない。多場物の劇が見る者の息をつかせないスリルをもたらす。演劇革命は、トーキーの発明とも呼応するだろうし、サイレントからトーキーへの移行が映画産業に一大変革をもたらしたことは、説明するまでもないだろう。
『キネマと恋人』が、一九三〇年代なかばに時が指定されていることもとても重要である。全三十六場とは、その多彩な小話(コント)の集積であり、その小話から小話への大胆で、アクロバティックな転換が、劇の推進力になっていく。
これは、KERA構成演出による岸田國士劇の『犬は鎖につなぐべからず』と『パン屋文六の思案』ですでに実験ずみである。
くわえてこの劇『キネマと恋人』の絶対の魅力は、KERA新発明、新開発の新方言による劇言葉をおいて外にない。
永いこと私たちは「普遍的方言」という特権化された劇言葉、偽方言に悩まされてきた歴史をもっていた。どこの地方(くに)とも分からない土地の言葉は、「普遍的方言」でもなにものでもないのだ。
『キネマと恋人』におけるKERA発明の新方言は、劇言葉のリズムを創造する。新たな劇言葉の可能性を示唆している。ヒロインのハルコ(緒川たまき)の劇言葉を任意に引用しその資料に供しておく。『月之輪半次郎捕物帖』というモノクロ映画のスクリーンから抜けだしたヒーロー間坂寅蔵(妻夫木聡)に語りかける言葉である。
「ごめんちゃい。そんがらつもりじゃないだり」「こっちん世界のことがらよう知らんからそんがら思うんよ。あいにくこっちは今ばりんこ暮らしにくい世の中だりよ」「こっちはそんがら簡単な世の中と違うんよ。悪いこと言わんから戻った方がええだり。映画ん中ん人達困っとるだりよ。ごめんちゃい、あたしもう帰らんと」
「だり」言葉、言葉のユートピアに戯れ、劇言葉の夢を語る劇として推賞しておかなければならない。
『キネマと恋人』――ウディ・アレン映画の日本的な演劇化
小藤田千栄子(映画・演劇評論)
まずは『エノケソ一代記』を推薦した■
今年のハヤカワ『悲劇喜劇賞』は、『エノケソ一代記』の圧勝だと思っていた。二〇一六年十一月公演。企画・製作=シス・カンパニー/上演=世田谷パブリックシアター。
作・演出=三谷幸喜の、傑作喜劇の誕生であり、演劇を見ることの幸福感にあふれた作品だった。
この作品の、いちばんの魅力は『笑の大学』との関連だ。言うまでもなくこれは三谷幸喜の傑作喜劇。よく知られているように『笑の大学』のタイトルは、古川ロッパの〈笑の王国〉から来ている。
『笑の大学』は、戦時中の劇作家と、検閲官との闘いがメインだが、この劇作家のモデルは、菊谷栄と言われている。この人は、エノケンの座付き作者でもあり、戦時中に大陸で、若くして戦死した人だ。ここから三谷幸喜と、エノケンとの繋がりが見えてくる。
だがこの『エノケソ一代記』のポイントは、エノケンその人が主役ではないということだ。人気絶頂のころのエノケンには、なんとソックリさんがいて、その人も、全国を巡演していたというのだ。しかも複数いたらしい。
私は、エノケンさん出演の東宝ミュージカルを見たことがあるし、それ以前の、ラジオ、あるいは映画時代も、情報としては知っている。だがエノケンの、いわばニセモノが、全国を巡演していたなんて、全く知らなかった。ここにポイントをあてて、劇化したのが、さすが三谷幸喜の才覚である。
しかも最初にチラシを見たときは、私も〈エノケン〉と読んでしまった。でも、よく見ると〈エノケン〉ではなく〈エノケソ〉が正しいらしいと気づく。〈ン〉と〈ソ〉。実によく似た字画だ。〈エノケン〉と〈エノケソ〉。多くの人が、読み間違えたとしても、不思議ではない。ここにポイントを当てた作劇であり、このことを思いついた三谷さんは、思わずヒザを打ったのではあるまいか。
エノケンの晩年は、かなり悲劇性が高いように見えたが、悲劇性を持ちながらも、快活な喜劇で統一されているところが素晴らしい。
時代設定を、昭和三十年代にしたのも成功している。つまりエノケン最後の華を咲かせた時代と、最晩年に絞った作劇だ。
第一場は、昭和三十二年の、香川県のとある公民館の控室。田所(市川猿之助)率いる〈エノケソ一座〉は巡業中。どこも満席で、誰も〈エノケソ〉とは気づかない。コトがバレそうになると、妻・希代子(吉田羊)と、座付き作家・顧問弁護士と称する蟇田(ひきた)一夫(浅野和之)が丸め込む。あるいは、開き直りで逃げ出す。座員は熊吉(春海四方)ただひとり。
ついで第二場は、昭和三十五年十一月の青森県。ここで地元の女の子(水上京香)が、からんでくる。第三場は、昭和三十六年一月、福岡県博多のクラブの控室。たしかこのシーンだったと思うが、古川口(くち)ッパ(三谷幸喜)が訪ねてくる。もちろんこちらもニセモノである。でも、このニセモノがソックリで、もう笑うしかない。
私は、ホンモノのロッパさんは見たことがないが、映画で見たことがあるし、写真は、いくつも見たことがある。そんなイメージの中のロッパさんと、三谷幸喜が演じる古川口(くち)ッパが、なんともソックリなのである。多分、見た目から入ったのだと思うが、こんなに似せることが出来るオドロキがある。基本的な体型が、似ているのだろうか。
三谷幸喜が出演したこと。さらに、あの有名な〈エノケン&ロッパ〉を、舞台上で並ばせてしまったこと。このふたつは、演劇史上の快挙と言っていいだろう。
そして第四場は、昭和三十七年の兵庫県のストリップ小屋の楽屋。ここでエノケンの病気が語られ、エノケンを尊敬してやまない〈エノケソ〉も、同じ手術を受ける覚悟を語るのである。
エピローグは、昭和三十八年五月の新宿コマ劇場の楽屋。病後のエノケン登場である。同じ年の七月=東京宝塚劇場でのオリジナル・ミュージカル『ブロードウェイから来た13人の踊り子』に、エノケンさんは出演していた。
この時代に、ブロードウェイから来た人たちが、東宝ミュージカルに出演するなんて、もう夢のような話で、私など舞い上がってしまったほどである。この十三人の踊り子さんたちは、同年九月=日本初演の海外ミュージカル『マイ・フェア・レディ』に、ダンサーとして出演もしていた。
まあ、いろいろと思いはあるのだが、『エノケソ一代記』のいちばんの功績は、市川猿之助の好演につきると思う。軽快で、笑えるし、ひとつのことに集中する男の作り方。とにかくエノケンになりたい。エノケンその人になりたい。その感じが素晴らしかった。
さらに圧倒的だったのは、カーテン前で見せるエノケンの有名曲の披露だ。開幕早々に歌ったのは『洒落男』だったか。「♪俺は村中で一番モボだといわれた男~」という歌。猿之助って、やっぱりスゴイ。もう、ほとんどミュージカル・スターだった。
ほかに『金色夜叉』や『不如帰』をテーマにしたパロディ・ソングや、『月光価千金』があり、さらには『東京節』というのか「♪ラメチャンタラ ギッチョンチョンデ パイノパイノパイ~」という歌。意味、全く分からないけど、とにかく猿之助は達者そのもので、もう圧倒的だった。
というようなわけで『エノケソ一代記』は、私にとっては、二〇一六年のベスト舞台だった。
平幹二朗、最後の作品『クレシダ』■
平幹二朗が亡くなったのは、二〇一六年十月二十二日。そのおよそ六週間前の九月七日に、シアタートラムで見たのが『クレシダ』だった。イギリスの芝居で、作=ニコラス・ライト。実は、こういう作品の存在を知らなかったのだが、一六三〇年代の、ロンドン演劇界の話。ヒロイン役を演じる少年俳優を、ベテラン俳優が指導する話である。タイトルは、シェイクスピアの『トロイラスとクレシダ』から来ている。主催・製作=シーエイティプロデュース、演出=森新太郎。
よく知られていることだが、この時代のロンドンには、女優はいなかった。だから女性の役は、ほとんど若い男優が演じていたのだが、その若い男優を見つけ、演技指導をして、舞台に立たせるベテラン俳優の話なのである。この時代には、若い男優を見つけてきて、いささかの指導をし、劇団に売りつける。そんな立場の人もいたようなのである。
そういう組織があったのか。私など、まったく知らなかったのだが、この舞台を見ていると、そういう組織があっても不思議はないと思えてくるのだった。
その指導者を、平幹二朗が演じていた。必ずしも常に正しい演劇人というわけではなく、いささか、うさん臭いところもあるのだが、こういう人って、いたでしょうねえと思わせる、存在の正当性があった。
この人のところに、養成所から送られてきた少年俳優(浅利陽介)を指導し、『トロイラスとクレシダ』の主役として舞台に立たせようとするのである。もちろん、その裏には、他の劇団主も招いて競売にかけようという企みがある。少しでも高値がつくようにと指導を始めるのだが、それは次第に熱をおびてくる。
この熱をおびてくるプロセスが、まさに平幹二朗だったのである。競売にかけて、高値をつけるなんてことは、どこかに飛んでしまい、ただひたすらに演劇の指導をするのだ。ここがいちばんの魅力だった。まさに演劇人=平幹二朗であり、若い浅利陽介も、よくついてきて、魅惑の舞台を作り上げた。
演劇というものの魅惑、演じることへの執着、少年俳優たちが、やがては立派な俳優になっていくだろうことが想像できて、奥の深い芝居だった。演劇人=平幹二朗の遺作としても、記憶しておきたい。
ウディ・アレンが時代劇になるなんて■
ウディ・アレンの映画『カイロの紫のバラ』(一九八五年/日本公開=一九八六年)は、とても好きな作品だ。ウディ・アレン作品の中では、その昔の『アニー・ホール』(一九七七年/日本公開=一九七八年)や、わりと最近の作品で『ミッドナイト・イン・パリ』(二〇一一年/日本公開=二〇一二年)と並ぶくらい好きだ。
『カイロの紫のバラ』は、映画好きの女性が、映画館に通いつめて、常に憧れの思いでスクリーンを見つめているのが始まり。何回も見ているうちに、なんと映画の中のヒーローが、スクリーンから出てきてしまう話なのである。
「何回も見ていますね」と言ったかどうかは記憶にないが、これって、映画ファンの、おそらくは最高の夢に違いない。多分、その昔、ウディ・アレンも夢見たことではないだろうか。そして、おそらくは、『キネマと恋人』の作・演出=ケラリーノ・サンドロヴィッチも。
『キネマと恋人』のいちばんの特徴は、日本を背景にしただけではなく、劇中の映画を、時代劇にしてしまったことだ。こういう方法があったのかと、思わずヒザを打つ作劇であった。演じる妻夫木聡が、端正な二枚目サンなので、ヒロインが夢みてしまうのは当然でもあるのだが、スクリーンから出てきて、普通の青年になってもステキなので、かなり忙しくはあったものの、見とれてしまったものである。
しかもウディ・アレン映画がそうであったように、映画好きのヒロイン(緒川たまき)は、家庭的には、あまり幸せではない。あの夫は、どうしてあんなに威張っているのだろう、たいしたことないのにと、こちらは思ってしまうのだ。ウディ・アレン映画の夫も、なんだか偉そうにしていて「アンタねえ」と、こちらも、スクリーンに声をかけてしまいそうになるのだった。
ウディ・アレン映画との、いちばんの違いは〈上演時間〉であったと思う。原作映画は一時間三十分足らず。ウディ・アレン映画というのは、ほとんどの場合そうなのだが、一時間三十分足らずで、あっさりとエンド・マークを出す。もう少し見たいときもあるが、あまり長くはないのが特徴でもある。
ところがこの演劇版は、三時間超えなのである。これは私には意外であった。もちろんそこには、原作映画にはないエピソード、あるいは物語の広がりがあるのだが、ちょっと長いなあと思ったのも確かである。
『カイロの紫のバラ』と、ほぼ同時代の日本の港町に置きかえ、物語は複雑化。さらに言葉が、どこの方言なのかは分からなかったが、かなり凝っていて、手の込んだ作劇であることが分かる。このように思ってしまうのは、多分、こちらが最後まで、原作はウディ・アレンの『カイロの紫のバラ』なのだという思い込みの深さがあったからであろう。
物語の見せ方で、いちばん感心したのは、日本の時代劇の感覚を、丁寧に見せたことだ。演出のこだわりが第一だが、映像の見せ方がうまく(映像監修=上田大樹)、昭和の初めころの、時代劇映画の感じが、とてもよく出ていることに感心した。
どの映画と指摘することは出来ないが、その昔、フィルムセンターでの〈時代劇特集〉などで見た総合的な印象と、ピタリと一致するのであった。しかもその物語進行が、映像とうまく重なり、これはかなり稽古を重ねたのではと、感じさせたのであった。
最近の舞台は、映像の使い方がうまく、あまりにうまいと、私など〈映画〉を見にきたのではないのに、などとも思ってしまうことがある。だが、とてもうまくなっていることは確かで、このうまさが、今後は、どのように演劇と繋がっていくのか。このことに注目したいと思っている。
さらに、時代色を出したタイトルも良かったと思う。最近は誰も、映画のことを〈キネマ〉などとは言わないが、このひと言もまた時代色を、うまく表わしていた。
それにしても、繰り返しになるが、ほぼ一時間半のウディ・アレン映画が、なんと三時間超えの、日本の演劇になったことは大きな驚きであった。ウディ・アレンは知っているのだろうか?
ケラリーノ・サンドロヴィッチも、かなり多作の方だが、ウディ・アレンのほうも、なんだかとてもお元気で、早くも新作の試写が始まっている。一九三〇年代のハリウッドの話だそうで、まさかこれは日本の話には、ならないでしょうねえ。
『キネマと恋人』は、「幸福を約束された作品」
高橋豊(演劇評論)
ハヤカワ『悲劇喜劇』賞に推した『キネマと恋人』に触れる前に、台本・演出のケラリーノ・サンドロヴィッチ(KERAと略す)について少し記す。
肩書きは劇作家・演出家・音楽家・映画監督と多才にして多彩。KERAは、一九六三年一月三日、東京生まれ。本名が小林一三(かずみ)。ジャズミュージシャンだった父の命名だが、阪急電鉄・宝塚歌劇・東宝映画を創立の大物・小林一三(いちぞう)を意識した遊び心もあったのかもしれない。
KERAは子供のころから喜劇映画にのめりこんだ。父の麻雀仲間に由利徹や南利明ら喜劇人がいたほか、小学四年でチャールズ・チャップリン、五年でバスター・キートンの無声映画のリバイバル上映に夢中となり、作家・小林信彦の名著『世界の喜劇人』や『日本の喜劇人』まで読破している。小学校の卒業文集の「自分の希望する将来」の寄せ書きに「喜劇映画の監督」と明確に記した。
中学二年のときに「喜劇映画研究会」を設立、会長となり、小ホールでマルクス兄弟の『マルクス一番乗り』など、戦後国内初上映を果たす。恐ろしいほどの行動力だ。
高校では演劇部、軽音楽部、映画研究会の三つに掛け持ちで所属。いつしかライブハウスに通い詰めるようになり、初めてのバンド「伝染病」(何という命名か!)を組んだ。
高校卒業後、横浜放送映画専門学院(現・日本映画大学)に進んだが、長い助監督を経て監督に上りつめる日本独特のシステムに絶望、コメディ映画専門の監督になる夢は不可能と感じて、音楽の方に軸足を移したのだ。
十九歳のときに、ニューウェーブバンド「有頂天」を結成。メンバーの半分がまだ高校生だった。有頂天のレコードを自主製作しようと思い、自主レーベル「ナゴムレコード」を立ち上げた。すぐ実行してしまうのがすごい。
一九八五年、二十二歳のとき、「劇団健康」を旗揚げ。「映画をやるよりも劇団の方が現実的だと思い、バンド活動の傍ら、年二回の公演を打つようになった」。九二年に「劇団健康」は解散。而立の三十歳となった九三年、「ナイロン100℃」を結成している。
KERAはナイロン100℃の劇団公演のほか、「KERA・MAP」、「オリガト・プラスティコ」などのユニットも主宰、外部プロデュース公演への参加も多く、これまで百五十本近い数の戯曲を書いたという。多才、多彩にして多作でもあるのだ。半端でない公演数は、劇団員たちを鍛え、個性ある俳優を育てたとも言える。
KERAの作・演出作品で忘れ難いものを挙げていくときりがない。「劇団健康」時代の代表作『カラフルメリィでオハヨ』(八八年初演)。病院を舞台に馬鹿馬鹿しい冒険を繰り広げる少年が、実は死の床に伏す老人の分身だった。実父の病死が背景にあるけれど、しっかりとした「喜劇の風」が吹き通り、涙を乾かし、再演が重ねられたのも当然だ。
KERAはナンセンスなギャグに、人間の不条理をにじませる。渇いた笑いのナンセンス・コメディーは、日本で難しいが、二〇一一年夏の『奥様お尻をどうぞ』はその極北か。その年、3・11の東日本大震災でお笑い〝自粛”ムードが広がる中で、敢然と笑いに徹しながら、原子力発電所を「実は、そんなもの意味がない」と糾弾する鋭い批評精神が隠されていた。
その一方、KERAは好きな作家・劇作家・映画監督に触発され、コラージュとも呼ぶべき作品を発表している。深く影響を受けたカフカに関しては『カフカズ・ディック』(〇一年)を経て、彼の代表作を編集しつつ、東京都世田谷区に登場させる『世田谷カフカ』(〇九年)として結実させた。また、岸田國士については、一幕劇を集めて構成する『犬は鎖につなぐべからず』(〇七年)、『パン屋文六の思案』(一四年)と二本も上演している。この岸田体験で、KERAの劇世界が大きく開いた感じがする。一五年、各種の演劇賞に輝いた『グッドバイ』は、太宰治の遺作となった未完の小説をもとに、一人の男の何人もの愛人との別れを描いたもので、KERAの構想力の豊かさにうなってしまった。
さて、『キネマと恋人』である。KERAも言う通り、ウディ・アレンが一九八五年に監督した映画『カイロの紫のバラ』に触発された舞台作品だ。
映画は一九三〇年代のアメリカ・ニュージャージーを舞台に、結婚生活に失望したヒロイン(ミア・ファロー)がスクリーンから抜け出した探検家から恋を告白される。出演者がいなくなったことで映画館は大騒ぎとなり、探検家役を演じた男優も町にやってきたが、彼もヒロインに心を奪われる。
KERAは、一九三六年(昭和十一年)の日本の架空の港町・梟島に移し替え、もっと複雑な物語とした。食堂で働くハルコ(緒川たまき)は、失業して暴力的な夫に悩まされながら、島の映画館で映画を見ることを唯一の楽しみとしている。喜劇のマルクス兄弟の映画が好きで、日本映画では時代劇の『月之輪半次郎捕物帖』が贔屓。しかも主役でない間坂寅蔵(妻夫木聡)のファン。その寅蔵がスクリーンから出てきたのだ。二人でダンスホールに行くなど楽しい時を過ごすが、演じる役者の高木高助(妻夫木の二役)も島を訪れ、ハルコに愛を告白、東京に駆け落ちしようと誘う。失恋した寅蔵は、映画のスクリーンの世界に戻った。ハルコの妹で実りない恋を繰り返すミチル(ともさかりえ)の挿話も加わって、三時間近い舞台になっている。
この舞台の良さは、いつもはプロジェクション・マッピングなど大胆に使うKERAが、アナログ感たっぷりに展開したことだ。寅蔵がスクリーンから飛び出すシーンも、あえてシンプルに展開。スクリーンに残された登場人物のあわてぶりも丁寧に描き出す。小野寺修二の振付が実に細かく、映像(上田大樹)の範囲と、役者の身体との境界線を探って、ギリギリまで映像が効果的になるよう人力で表現している。場面転換に快いリズムがある。客席が二百余のシアタートラムという小空間を選んだことも奏功し、手作りの温かさが舞台から伝わってきた。
梟島語というのだろうか、KERA創作の架空の方言で語られていることも効果的だ。お互いに思いやる姉妹のピュアな会話が、方言のせいか、違和感がない。
現実と幻想を自由自在に往還する想像力を織り込んだウディ・アレンをはじめ、喜劇作家たちへのKERAのオマージュとも言える。
『カイロの紫のバラ』と同じように、『キネマと恋人』も、現実の前でちょっとビターな終わり方をするけれど、後味はとてもいい。ロマンチックでファンタジーに満ち、ブラックな要素がまったくない。KERA自身が本作について、「広範囲のお客さんに受け入れられるという確信があり」「幸福を約束された作品」と言っているが、予測は違っていないようだ。
KERAは〇九年に『東京月光魔曲』、一〇年に『黴菌』、そして今年『陥没』と、「昭和三部作」を発表、昭和の裏側を描いているが、『キネマと恋人』はそれらに連なる変奏曲とも言える。舞台となる昭和十一年は「二・二六事件」が起き、軍の発言力は強化され、やがてアメリカ映画などの上映が禁止されていく。ハルコらにとって束の間の「幸福」は消え、息苦しい時代に変わって行くことまで、舞台を観ながら感じられる。
俳優では、妻夫木が時代劇の寅蔵と俳優・高助の二役をうまく演じ分けている。映画の中だけでの存在なので純粋無垢な寅蔵に対し、高助はミュージカル・コメディーに主演したいなど、それなりの野心を持っている。緒川は、切なさがよく出て、人を魅了する。女性脚本家と時代劇でお局役の村岡希美など、脇にも個性派がそろい、何役も演じ分ける。場面転換をになう黒衣のダンサーたちも、さまざまな役を演じている。
それにしても、一六年、KERAの演劇活動の充実ぶりにはおどろかされる。トレイシー・レッツ作・目黒条訳『8月の家族たち』の演出で読売演劇大賞の最優秀演出家賞を受賞、『ヒトラー、最後の20000年~ほとんど、何もない~』の作・演出などで紀伊國屋演劇賞個人賞を受け、『キネマと恋人』はハヤカワ『悲劇喜劇』賞のほか、読売文学賞の戯曲・シナリオ賞も獲得した。ともすれば、KERAは演出のうまさの方が評価されがちだが、劇作家としても実力は飛びぬけている。そのことが証明された感じだ。
『キネマと恋人』は、キャストがインフルエンザ感染のため、四日間五ステージを休演した。映像と実演が一体になった精緻な舞台だから、代演はたてられず、見逃した人も多いはずだ。ぜひいつか再演してほしい。
もう一つ、ハヤカワ『悲劇喜劇』賞に推した維新派の『アマハラ』について書きたい。
昨年は現代演劇を率先、リードしていたアーティストが次々と去った年になった。
演出家・蜷川幸雄の逝去は大きく、蜷川作品によく主演していた平幹二朗も後を追うように急逝した。平の最後の舞台となった『クレシダ』(ニコラス・ライト作、芦沢みどり訳、森新太郎演出)は、元シェイクスピア役者を演じ、平の軌跡と重なって忘れられない作品となった。
もう一人、維新派を率いた演出家・松本雄吉も亡くなった。維新派は一九七〇年、松本を中心に大阪で活動を開始。劇団員総勢五十人ほどが巨大な野外劇場を自らの手で作り、公演が終われば釘一本残さず解体して撤収、再びもとの更地に戻すという徹底ぶりで知られた。野外でしかなしえない「一回性の劇場」にこだわり、国内外のさまざまな場所で公演してきた。琵琶湖畔や瀬戸内海の島などでの上演は忘れられない。
今回の『アマハラ』は、松本が数十年来、望んでいた奈良の平城宮跡の公演がようやく実現したもので、本作品準備中の六月に松本は帰らぬ人となった。松本は平城宮跡について「その場所の一点に立つだけで、その四方に展開する地理が歴史を呼び起こしてくれるところ、まさに身体に空間の広がりと時間の深遠を強く認識させる場所」と語っていたという。
約千三百年前に都が置かれ、今は広漠とした遺跡の野原の真ん中に、巨大な廃船をイメージした野外劇場が作られた。十月に維新派の最終公演として『アマハラ』は上演された。西の生駒山が正面で、夕日が沈んでいくのが見え感動的だった。
七年前に瀬戸内海の岡山・犬島で上演した『台湾の、灰色の牛が背のびをしたとき』をベースに再構築されたものだ。海を越えて島から島へとアジアに希望を抱いて飛び出していった日本人たちの夢と絶望が、壮大に描かれた。
二十世紀はじめにフィリピンに渡った日本人がかかわった「ベンゲット道路」建設は難航を極めたもので、工事の様子を木組みの巨大なセットで見せた。「海の道」を通って、南洋の島々を目指した、知られざる日本人たちの姿が描かれていく。
しかし、太平洋戦争がこれらの人々の運命を大きく変える。「海の生命線」とされた南洋諸島は戦場となり、多くの移民が命を失った。
脚本・構成が松本、音楽・演奏が内橋和久。ヂャンヂャン☆オペラと呼ぶ独特のリズムに身体性。『台湾の~』と曲順が違うなど、いくつか大きな変更点があった。初演で四番目だった「おかえり」が、今回はラストを飾った。少年の世界というイメージの強い維新派には珍しく、大人の女性のみが出演する曲で、作品全体として明るさが出てきたように感じられた。
維新派は公演時に、通称「屋台村」と呼ばれる食事や雑貨の売店、ライブステージ空間などを併設する。野外劇場を囲んで祝祭的な雰囲気に満ちた「架空都市」となることも魅力である。十月の平城宮跡は、日が落ちると震えるように寒かったが、最終公演を観たい人たちが押しかけ、いつまでも賑わっていた。
『アマハラ』は平城宮跡の野外で公演されたこともあり、時間軸が古代へ遡り、さまざまな異人たちが登場し、交流するような幻想まで与えてくれた。維新派という稀有な演劇集団を私たちに観させてくれた永遠なる前衛派、松本を心から追悼する。
- <<前の記事:第四回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考結果
- 第四回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞贈賞式を開催:次の記事>>