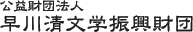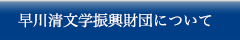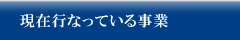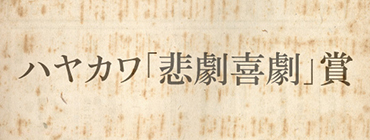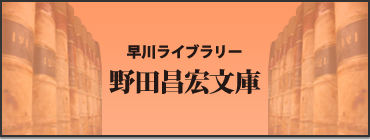第五回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考委員批評文
『荒れ野』が「女性の劇作家の年」の棹尾を飾る
高橋 豊(演劇評論)
二〇一七年の日本の演劇界は、女性の劇作家たちの活躍が一際、目立った。ともすれば「自分とその周辺」に限って描こうとする男性劇作家に対し、彼女らは社会に、時代に異議申し立てをすることを恐れない、硬派の志を持つ。年初の『ザ・空気』から師走の『荒れ野』まで、印象に残った作品をまず振り返ってみよう。
一月に開幕した永井愛の作・演出『ザ・空気』(二兎社)。大手テレビ局の人気ニュース番組が「日本の報道の自由は今」という特集を組もうとしたが、放送当日、政府や与党の意向を気にする局の上層部から番組の編集長やキャスターに内容変更の打診があった。編集長らは抵抗するものの、特集は形骸だけしか残らなかった。権力者の思惑を「忖度」し、「空気」を作り、「政治的な公平性」の名のもと、報道は「自己規制」しすぎていないか、という問い掛けを、永井は人間喜劇の笑いを交えながら突きつけている。「忖度」は昨年、政界を駆け巡り、流行語大賞になった。
同じく、テレビ局に対する政治の圧力、責任転嫁をテーマにした作品に、石原燃の新作『白い花を隠す』(小笠原響演出、Pカンパニー)がある。〇一年、NHKで放送された旧日本軍による従軍慰安婦制度を裁く女性国際戦犯法廷の番組に関わったドキュメンタリー制作会社の人たちの物語だ。彼らはこの法廷の意義に共感し、精力的に取材を進めるが、放送直前になって、NHK側から手直し・改変を求められた。当時、官房副長官だった現・安倍首相が「矢部議員」として言及されるけれど、政府幹部からNHKへの強い申し入れがあり、NHKは制作会社に異例の手直し指示を出した。会社存続のため指示を受け入れた社長、最後まで抵抗するディレクター、降板する新人ディレクターなど、さまざまな人間模様が展開する。石原は、制作会社が会議室代わりに使っていた喫茶店の姉と妹の相克を編み込み、ドラマに深みを与えた。女性からの視線が貫かれていることがとてもいい。
八〇年代の小劇場ブーム時代から女性の演劇人をリードしてきた渡辺えりは、オフィス3○○で『鯨よ!私の手に乗れ』を作・演出した。東北の介護施設に入居している母を女優が訪ねてきた。郷里に残った弟夫婦に母を任せきりのまま東京で芝居をしている彼女は渡辺自身の分身と言えるだろう。演じているのが、渡辺と同じく劇作家・演出家で女優の桑原裕子だ。介護の厳しい現実が描かれる一方で、施設の老女たちが若い頃に上演できずじまいだった芝居を公演しようとする夢の彼方への動きも活写された。渡辺の演劇による再生の願いがよく伝わった。
気鋭の女性劇作家は、自分の劇団以外の依頼も多かった。詩森ろばもその一人。最も印象深かったのは、主宰する風琴工房による『アンネの日』の作・演出である。大手企業で生理用ナプキンの新製品開発に関わる理系の女性たちの日々を描いているが、自身の肉体の歴史にきちんと向き合い語らせているのがいい。初潮がいつだったか、大人になっても生理との付き合い方の難しさ、精神のイライラなど月経前症候群とどう折り合うかなど、プライベートなことも明かされる。身長が低いことをハンディとしないため、何倍も努力して女子力を高めた女性や、性別の違和感から性転換手術を受けてどう見ても女性だが生理はなく、それでも生理ナプキンの開発に夢を掛けるメンバーなど、多彩な人間模様も描かれる。男性にこそ観てほしい舞台だった。なお、風琴工房は一七年でクローズ、一八年から「serial number」と名前が変わる。
一九七七年生まれの三人の女性劇作家の活躍が目覚ましかった。てがみ座の長田育恵、劇団ミナモザの瀬戸山美咲、ユニット「パラドックス定数」の野木萌葱(も えぎ)である。
長田は劇作に専念し、演出は専門の演出家に委ねる。一七年、劇団民藝に『「仕事クラブ」の女優たち』の脚本を提供しているが、感銘の深さでは、てがみ座の『風紋~青のはて2017~』(田中圭介演出)の方が勝っていたと思う。タイトルから一二年初演の『青のはて~銀河鉄道前奏曲~』の再演と判断していたら、まるで違っていた。前作が妹トシを喪くした宮澤賢治の樺太への旅がテーマだったのに対し、『風紋』は死の二カ月前の賢治を描く。ほぼ新作と言っていい。一九三三年夏、岩手県の遠野と釜石の間にある難所、仙人峠に近い岩手軽便鉄道の終点の駅舎兼旅籠が舞台だ。高熱で寝込んだ乗客、賢治が運び込まれる。この年の春、岩手県沿岸部を三陸大津波が襲い、悲劇が生まれた。長田が本作を単なる再演としたくなかった理由はよく分かる。二〇一一年の東日本大震災の惨状とその後を知るにつれ、賢治の物語を書き改め、晩年を見据えようとしたのだろう。死の床に横たわっても理想を捨てない賢治の強さを美化も神格化もせず、描き出そうとした長田の強靱さが見事。駅舎兼旅籠の主人役の佐藤誓の食えないふてぶてしさが鮮烈だ。
瀬戸山の新作としては、椿組に書き下ろし、演出した『始まりのアンティゴネ』を挙げる。ある食品会社の前社長の息子が自殺した。現社長は「自殺でなく病死ということにしよう」と体裁を繕おうとするのだが、息子の妹は「なぜ隠す必要があるのか」と強く反発し、親族の間で論争が起きる。ギリシャ悲劇の『アンティゴネ』をモチーフに現代日本で展開させたのだけれど、舞台上では死者が一言も発しないまま、残されたもののやりとりを見ている。ギリシャ悲劇に比べると、前へ進む家族たちの姿勢が見えるのが救いである。
野木の戯曲では、ウォーキングスタッフがプロデュースし、和田憲明が演出した『怪人21面相』。未解決事件「グリコ・森永事件」を基に、大胆に四人の犯人像を特定し、人間社会の闇を炙り出す。彼女の作品は、実際の事件や史実を枠組みにしながら、硬派の会話劇を繰り広げるのが魅力である。
「女性劇作家の年」の掉尾を飾ったのが、桑原裕子作・演出の『荒れ野』である。愛知県豊橋市の穂の国とよはし芸術劇場PLATのプロデュースで、共同企画にアル☆カンパニーが参画している。
十一月末、豊橋公演がスタートし、師走、北九州公演を経て、ようやく東京で観ることができたのだけれど、パンフレットに記載されている「いつの間に私たち こんなところまで来てしまったの」の言葉通り、中高年の男女ほど、心に沁み込んでくる舞台だった。
登場人物は六人だけ。集合住宅の団地に住む薬剤師の路子(井上加奈子)宅の2DKが舞台だ。この団地を出てマイホームを構えた哲央(平田満)と藍子(増子倭文江)夫婦が、近くの元ショッピングセンターで起きた火災から避難して路子の部屋を訪れた。勤め先をリストラされた娘・有季(多田香織)も駆けつけてくる。一方の路子宅。かつてキャリアウーマンとして華々しく恋愛に生きたのはもう昔で、介護していた父が亡くなった後は、家財道具もそのまま古びるに任せ、服装にも気を使わない。上の階に住む元高校教師の広満(小林勝也)と彼の教え子のケン一(中尾諭介)が自宅のようによく出入りしていた。
大火災という非日常が起きているのに、コタツや布団など生活感の強い部屋で彼方の火炎を遠く見ながら、いつか六人は鍋をつつきあい、アルコールを飲む。
路子と藍子は、かつて同じ団地に住んでいたものの、ライフスタイルが全く合わず、特に夫の哲央が学生時代から、路子に恋心を抱いていたことを藍子は知っていて、これまで胸にたまっていた疑問を遠まわしで尋ねる。戯曲を読んでも面白いが、舞台では二人の女優が、互いに呼び合う声音で、言葉にならないニュアンスまで伝えるのが見事だ。
なぜ団地の上の階に住む広満とケン一の元師弟が路子宅に自由に出入りしているのか。寝るときは時に三人で川の字だから、男女の性的な関係まで疑ってしまうが、ケン一は否定し、広満とはホモセクシュアルな愛だとさらりと言う。ごく普通の会話の中に「爆弾」のような事実が混じっている。ケン一が語る。
「世界中を(広満)先生と一緒に旅して、最初は愉しくても、そのうち限界が来る。お互いに飽き飽きするような『氷点』が来ると思って、その時は突然、消えてやろうと思っていた」
ところが、「捨てるため旅に行ったはずが、逆にしがみついていた」と気付いてしまったと言う。性愛の深遠さ。人は心の中にそれぞれの「荒れ野」を抱えているのだ。
有季は高校時代のバイト先でケン一と知り合い、初めての体験をしていたのだけれど、ケン一は彼女のことをほとんど忘れていた。それでも二人は大火の日の夜、再び、関係を持つ。それほど深い意味はないままに。
いしだあゆみのヒット曲『あなたならどうする』が、登場人物によって口ずさまれる。それまで封印されていたものが掘り起こされ、弁解ともつかない言葉が繰り返される。ごくさりげない会話なのに、いろいろ考えさせる罠が仕掛けられている。例えば、路子の父は長患いだったのに、なぜアッという間に亡くなったのか。薬剤師の彼女が「薬が合わなかった」と言っていたのだが……。冠動脈のバイパス手術をした哲央は本当に身体が回復しているのか。何より、夫婦の家は類焼したのか、免れたのか。たった一晩なのに、濃密な人間関係が明らかになる語り口が鮮やかだ。
桑原裕子は一九七六年生まれで東京都出身。高校三年の時に平田オリザ作・演出の『転校生』の出演者オーディションに合格して出演。二十歳の九六年に劇団KAKUTAを結成し、作・演出を手掛ける。渡辺えりの項で紹介したように女優としても活躍している。
忘れられないKAKUTAの作品は、一四年に上演され、鶴屋南北戯曲賞を受賞した『痕跡(あとあと)』だ。ある川沿いの通りを、借金まみれで自殺しようという男が少年と行き違う。少年はそれきり行方不明となり、母親がずっと探し続けている。実は少年は車にはねられ、川に落ち、自殺志願の男が救い出して、逆に再び生きる気持ちが生まれ、懸命に育てたのだ。けれど、男は借金で追われる身だから、少年は戸籍なしのまま成人を迎えることになってしまう。初演は、今はなき東京・青山円形劇場。客席がぐるりと囲む円形の劇場の特性を生かした演出で、劇中の「時間」や「空間」の処理の鮮やかに感心させられた。
『荒れ野』をプロデュースし、皮切りで上演した穂の国とよはし芸術劇場PLATは、愛知県豊橋市のJR豊橋駅の南側に隣接する。コンサートなどの主ホールに、自在に舞台と客席を設定できるアートスペース(小劇場)などを持つ。東京一極集中の演劇状況に、地方から風穴を開け、日本各地に創造発信していこうと、一三年に開館し、豊橋出身の俳優、平田満が芸術文化アドバイザーを務めてきた。
平田は、一九七〇年代から八〇年代、若者たちに熱狂的に支持された、つかこうへいの舞台で忘れられない俳優の一人である。つかの代表作『蒲田行進曲』で、しがない大部屋俳優ヤスを演じ、時代劇の大スター銀ちゃんに斬られて、命がけの階段落ちをする。舞台だけでなく映画化もされ大ヒットした。
つかこうへい事務所の看板女優が井上加奈子である。平田と井上は結婚。〇六年に夫妻で旗揚げしたのが、アル☆カンパニーである。劇団という形をとらず、毎回、気鋭の劇作家、演出家、俳優を招き、共同作業の中で人間主体の演劇を目指してきた。東京・新宿三丁目の小空間「SPACE雑遊」を拠点に、シンプルで想像力あふれる舞台を創り続けてきた。
今回の『荒れ野』もそうだが、夫妻はさまざまな形で、中年男女の愛憎の様相を演じてきた。最も鮮烈だったのは、一四年、ポツドールの三浦大輔の作・演出による『失望のむこうがわ』だった。子供のいない五十代の夫婦で、夫(平田)は妻(井上)の携帯電話のメールをのぞき、異変に気付く。妻はパチンコ店で知り合った三十代の男性と浮気していたことを告白する。結婚して三十年、「空気感」のように安心していた夫婦関係がまやかしと分かったときから、夫はひたすら「言葉」を紡ぎ続ける。妻は詫びながらも「あなたじゃない、別の人にちやほやされたのが気持ちよかった」と時に切り返す。暴力シーンは一切なく、息詰まるような会話の応酬が続き、アル☆カンパニーの代表作の一つとなった。
平田が穂の国とよはし芸術劇場PLATの芸術文化アドバイザーとなった一三年、小劇場アートスペースのこけら落としとして上演したのが、ONEOR8(ワン・オア・エイト?一か八か)の田村孝裕の作・演出による『父よ!』だった。八十歳を過ぎた一人暮らしの父の面倒をだれがみるべきか、長男(花王おさむ)、次男(ベンガル)、三男(平田)、四男(徳井優)の四兄弟が実家に集まって話し合う。お互いに世話を押し付け合い、兄弟それぞれの事情が明らかになってくる。そんな時に、民生委員の女性(井上)が家を訪れ、兄弟が知らない「現在の父」の姿を語り出した……。観劇した後、観客が思わず語り出したくなるような作品で、こけら落としにふさわしい舞台だった。好評で二年後に再演も果たしている。
PLAT開館五周年を迎え、記念事業として、今回の『荒れ野』が立ち上がった。平田は「『父よ!』を含め、男性中心の芝居ではなく、今度は女性にフォーカスを当てた舞台を創りたい」と提案、妻の井上と一緒に観て感銘を受けたKAKUTAの桑原裕子の名前を挙げたという。
私は『荒れ野』を超満員の東京の「SPACE雑遊」で観た。平田、井上はもちろん、文学座の小林勝也、青年座の増子倭文江とベテラン俳優が男女の心の動きの細かいニュアンスまでよく造形しており、心動かされた。会話劇の魅力を存分に楽しめた。若い中尾諭介はライブバンドやボーカルとして活躍していて、初めて彼の舞台を観たのだが、存在感ある若者像に触れた感じがした。娘を演じたKAKUTAの多田香織は、どこかコケティッシュで、素直で、女優としてのこれからの可能性を大いに期待させる。
カーテンコールで、平田は「アル☆カンパニーの拠点としてきた、この劇場が、私たちの公演の後、クローズします」と挨拶、観客から熱い拍手が起きた。
SPACE雑遊は〇六年、新宿三丁目のビルの地下に誕生し、文字通りの小空間ながら、舞台をどう作るかは劇団・カンパニーへ自在に任せられていて、どんな芝居に出会えるか、わくわくしながらいつも階段を下りていた。
聞けば、観客の通報で関係官庁が査察、避難路などの改築が指導され、一七年師走、『荒れ野』などを最後の舞台としてクローズした。改築・改装しての再開は「官庁と交渉中で、今のところ未定」と言う。
穂の国とよはし芸術劇場PLATの芸術文化アドバイザーは、今春の五周年を機に平田満が退き、新たに桑原裕子が就任する。『荒れ野』がいい橋渡しになった感じだ。
不条理と不穏
今村忠純(近代文学・近代劇文学)
荒れ野■
『荒れ野』(全四場)の第一場(オープニング)の時と場所は、次のとおり。「十二月半ばの日曜日、夜二十三時半。/S市西町にある集合住宅「西の森団地」のD棟四階に位置する、加胡(か ご)路子(みち こ)の家」。
時計の針がまわって、あくる朝月曜日の九時過ぎまでに、この「家」(八畳間)でどのようなことがおきたのかというのが『荒れ野』の輪廓。
足の踏み場もないほどにとりちらからした室(へや)には蒲団が敷かれているのか、雑魚寝の三人の影がぼんやりとうかびあがる。老朽化した団地の吹きだまりのような室で一人暮らしの加胡路子(井上加奈子)。上の階に住む元教師石川広満(小林勝也)と教え子だったケン一(中尾諭介)がここに居つき、共同生活をつづけている。
横たわったままの路子とケン一は「あなたならどうする」という歌を口ずさんでいる。この室におきざりにされどこにも行き場のない気分だ。作詞はなかにし礼、歌うのは、いしだあゆみ。一九七〇年初頭のヒットソング。この歌に誘われるように窪居哲央(平田満)、藍子(増田倭文江)夫婦とその娘有季(多田香織)が転がりこんできた。近所で火の手があがった。風に乗って救急車、消防車の走る音、サイレンが聞こえてくる。飛び火をおそれて一家で避難してきた。あらかじめ路子に連絡をいれたのは藍子、なぜ路子を頼ったのか。
以下プロットというよりも『荒れ野』に登場する人物の関係図を味解しておくことが重要である。
哲央は路子と幼なじみでこの団地にいたことがあり、いまは保険会社につとめる。路子の父の保険の相談に乗っていたので、この団地をたずねていた。路子の父は三年前に死んでいる。父の死といれかわるように路子の室に居つくようになったのが、広満とケン一。
路子の両親は離婚、母にかわってずっと父の世話を続けてきたのだが、路子は酬われなかったという思いにとらわれていた。父からは、母の影がいつまでも離れなかった。父は、亡くなる時はアッという間だった、新しい薬に替えたばかり、薬が合わなかったとか、と路子は広満にいっていた。父の保険は受け取ったか。路子は薬剤師。一体何があったのか。
藍子は、哲央と路子との関係を疑っていた。
広満とケン一は同性愛者、そして有季は十年以上も前にケン一とアルバイト先で出会っていた。
イベント広場の仮設テントに引火し、そこから火事は一気に住宅街にも拡がり焼きつくして鎮火したようだ。窪居家も、火勢にのみこまれてしまった。「火宅」とは、うるさくいえば本来の意味から逸脱するのだが、文字どおり「三界に安きことなし、なお火宅の如し」という、その安きことのない「三界」に放り出されるのだ。「三界」に放り出されているのは、窪居家の一家族ばかりではなかった。
愛されたことのない記憶を託(かこ)ち、それでも愛されることを切望することは益体(やく たい)もないことなのか。
「人はみんな捨てられるよ。どこにいても一緒よ」「だから会社も家も、気にすんなよ」とケン一は有季にいっていた。これがほんとうの希望かもしれない。「どこにいても一緒よ」「気にすんなよ」。
「三界」は「火宅」であり、「荒れ野」であり、不条理と不穏が渦まいている。
「あなたならどうする」を口ずさむ声、ぶつぶつとつぶやく。つぶやくように歌う声が、あちこちから聞こえてくるというのがエピローグである。日が昇りまた一日が始まっている。
「あなたならどうする」は、自問なのだが、この劇を見ている観客への「あなた」への問いかけでもある。
ザ・空気■
二兎社公演の『ザ・空気』のプログラムに掲載された永井愛とマーティン・ファクラーの対話は、「接近(アク セス)ジャーナリズム」と「調査報道」のちがいに言及している。
この対話は『ザ・空気』を深く理解するうえでいちばんの指針になっている。そればかりではない。永井愛その人の演劇の方法と理念が語られている。
あらかじめこの対話の大要をまとめておくと──。
権力者に接近(アク セス)し、取材対象との距離を縮めて記事をつくる。「記者クラブ制度」は、権力の側に都合のいい情報だけが流される装置であり、別にいえば不都合な情報は隠蔽される。これを「接近(アク セス)ジャーナリズム」「発表ジャーナリズム」という。この対極に「調査報道」がある。
権力者から一歩身を引いて、権力者とはちがうファクト(事実)を探り出し、別の角度から新たなストーリーをつくる。「調査報道」で重要なのは「物語」であり、「ファクト(事実)」を正しく組み合わせ「ナラティヴ(語り)」を完成させることである。「調査報道」は「オピニオン(意見)」や「モラル(倫理)」の指示であってはならない。
こうしてファクラーの『「本当のこと」を伝えない日本の新聞』『安倍政権にひれ伏す日本のメディア』の二著の提起する問題を二人は語り合い、「日本のメディア(ジャーナリズム)の今」のファクト(事実)をリポートしていくのだが、永井愛はこの「調査報道」の方法で、日本の報道ジャーナリズムの現場の「ファクト(事実)」を深く正しく『ザ・空気』で伝えていく。
『ザ・空気』は、あるテレビ局の報道番組「ニュース・ライブ」の制作現場が舞台である。
「ニュース・ライブ」の編集長今森俊一(田中哲司)の携帯電話から、キャスターの来宮楠子(若村麻由美)の声が聞こえる。「ねえ、どこにいるの? 私、感じる。デスク回りの空気がヘン」。今夜放送するばかりになっていた目玉の報道特集に「直し」が出た、それで呼び出されたというのだ。
「報道の自由は今」、日本の報道ジャーナリズムのありかたを問うというのがコンセプトだった。これに保守系アンカーの大雲要人(木場勝己)からクレームが入った。政府官邸サイドや与党の顔色をうかがうテレビ局の上層部の意向を代弁してのことだった。勝負ネクタイをしめなおし、「ここは戦略的に行きませんか?」というのがミスタ・バランスの提言である。
「報道の自由は今」という特集は、ここにきて総務大臣の電波停止発言をいたずらに刺激しかねない、結果として日本には報道の自由がないとまっこうからケンカを売ることになりかねないというのだ。
「ニュース・ライブ」の二十二時スタートが刻一刻と迫っている。制作現場がにわかにあわただしくなる。
それならばいっそ先回りをするのがいちばんいい。そこで「戦略的に行きませんか?」と。
大雲要人は、新聞記者、論説委員として四十年以上も報道の世界に生きてきたキャリアをもつ。ジャーナリストとしての長年の姿勢を買われ、大物政治家の番記者をつとめたこともある「記者クラブ」あがりのアンカー。いってみれば、彼は「接近(アク セス)ジャーナリスト」の権化としてテレビ局会長のトップダウン人事で、つい三カ月前にこのポストに着任したばかり。
劇は、大雲の「戦略」に抗して報道特集の編集長、キャスター、ディレクター、編集マンの「報道の自由」をめぐる論議が白熱し展開していくのだが──。
それにしても大雲の「戦略的に行きませんか?」とは、一体どういうところにあったのか。気配と慮り、すなわち「忖度」が肝要、それは自己規制とはいわない。「空気」を読み、政治的公平、「中立」を説くのが大雲なのだから。しかしそのむこうに待ち受けているものは──。
『ザ・空気』の「物語」は、こうである。
かつてはこのテレビ局の人気「女子アナ」で、転じていまは花形キャスターの来宮楠子。彼女はディレクターの丹下百代(江口のりこ)を同行、ケルンに飛んだ。報道の自由を担保するドイツのジャーナリズムを取材し、これを参照しながら日本の報道の自由を問う特集を制作するためだった。
来宮楠子が、この特集にこだわったのは死んだ桜井アンカーの遺志に酬いたかったからだ。
調査報道に筋を通し、「権力を監視するウォッチドッグ」であり続けた桜井アンカーは、気骨あるジャーナリストだった。しかし上層部と衝突したあげく、九階の会議室で縊れた。この桜井の後釜に座ったのが大雲だった。
来宮の老いた母は、自分の娘の今森との結婚を疑わなかった。いまも二人の連帯は変わらない。そのような二人を鼓舞し、ジャーナリストとしての本分を説き続けていた桜井。このような「物語」が「接近ジャーナリズム」と「調査報道」の狭間で起きていた。
来宮は、憤死した桜井とのかかわりを「監視」されていた。テレビ局の会長室というブラックホールから追い出された今森は、非常階段から身を投げる。
短いエピローグは、その二年後。
テレビ局から放り出された今森は、長い入院生活を送り、リハビリから復帰する。日本国は、改憲がすすみ、超法規的権力を行使する国家に生まれ変わっていた。テレビ局をやめて、バイク便の配達をしているのは丹下、今森を支えた編集マン花田路也(大窪人衛)はいまも現場を走り回る。来宮は、テレビ局の経営側のポストに就いていた。今森は「調査報道」の道にすすむ決意をするのだが、日本国に希望の未来図はない。
美術は大田創。シアターイーストの場内に巨大なテレビ局のビルが建設される。ありありと見えてくる。九階の会議室の窓から非常階段がのぞいている。エレベーターと階段、階上と階下の往き来がせわしない。携帯から聞こえる声が瞬時にその場の「空気」を変える。各シーンの組み合わせと転換が劇に緊迫感をつくる。
きらめく星座■
『きらめく星座』は、こまつ座の旗揚げ公演のあくる年、一九八五年九月の初演で、井上ひさしの初演出だった。
昭和庶民伝三部作の第一部にあたり、『闇に咲く花』『雪やこんこん』がこれに続く。タイトルに、星、花、雪がならび、別に「星・花・雪」三部作とも。『闇に咲く花』は、当初『花よりタンゴ』が三部作のうちに数えられていた。
井上戯曲の上演回数は、群を抜いている。そのうちでも『きらめく星座』は格別で、いちばん上演を重ねていると思われる。観客が更新され、新しい目がこれを「新作」として深く受けとめている証拠である。初演から三十年以上たっても新作である。『きらめく星座』のように上演回数を重ねる例は、まったく類を見ない。『きらめく星座』の初演から今日までの数多くの公演回数と座組は、数多くの俳優たちの技量を成長させ、名舞台をつくり続けている。井上ひさしから木村光一へ、そして栗山民也に継承された演出家としての達成も評価しなければならない。
昭和十五年の秋の深まる頃から翌十六年(十二月七日)の冬のはじめまで。開戦前夜銃後の東京・西浅草(田島町)のレコード店オデオン堂が舞台。
防空訓練、空襲解除の半鐘の音、それを合図に幕があがる。防空訓練の六人は防空面をかぶっていた。「人間の髑髏(され かうべ)」とよく似た防毒面である。これがオープニング。
エピローグは、オデオン堂がまるごと強制収用となり、こんどは空襲警報解除の半鐘ではない、空襲警報の半鐘がなり、かれらはいっせいに防毒面をかぶる。防毒面たちは、浅草を追われる。次第にはなればなれに遠くへ去って行く。「そこへ巨大な運命のやうに幕が降りてくる」というのだ。
防毒面をかぶるとは「髑髏」にもどったことを意味する。かれら一人一人は、ちりぢりになっていく運命の災厄をひき受け、それを予見する。つまりかれらは生きている死者たちだった。流れ星が流れ、一拍遅れて「青空(マイ・ブルー・ヘブン)」のメロディ(ウォルター・ドナルドソン作曲)が、うねるようにゆるやかに場内を包むラストシーンは、オープニングの序曲(オーバーチュア)(劇中で用いられる流行歌のメドレー)に重ねられる。
『きらめく星座』は、井上ひさしの発明した音楽劇である。劇中で「月光値千金」「燦めく星座」「愛国の花」「一杯のコーヒーから」「愛馬進軍歌」「小さい喫茶店(キッ チャ テン)」「チャイナタンゴ」「星めぐりの歌」「煙草屋の娘」「青空」の十曲の流行歌が、この順番で歌われるのだが、戦時下の出版統制は、もちろん音楽統制もふくみ、それは流行歌やレコード検閲を意味していた。ただしここで岩手花巻の詩人の「星めぐりの歌」を引用する機知も忘れてはならない。
この『きらめく星座』が、こまつ座の第一二〇回記念公演になったthe座特別号は、写真週報二五七号(内閣情報部刊)の「米英レコードをたゝき出さう」の見開き二頁を割いていた。「耳の底に、まだ米英のジャズ音楽が響き/網膜にまだ米英的風景を映し/身体中から、まだ米英の匂ひをぷん??させて/それで米英に勝たうといふのか/敵への媚態をやめよ/耳を洗ひ、目を洗ひ、心を洗って/まぎれもない日本人として出直すことがまず先決問題だ」。またこの頁には、「敵性一掃! 米英レコード供出致しませう/当店で御取扱ひ致します」と大書した店頭風景が写し出されていた。
オデオン堂主人小笠原信吉(久保酎吉)が、クリスタルレコードの専属歌手だったふじ(秋山菜津子)を後妻に迎えるきっかけをつくった「月光値千金」(エノケン訳詞)がプロローグで歌われており、エピローグでは、歌手廃業を決意させたふじに「青空」(藤原山彦訳詞)を歌わせていたのは重要である。「月光値千金」も「青空」もともに敵性音楽リストにあげられていたのだ。
強制収用での一家離散は、オデオン堂というレコード店の廃業を意味していたばかりではない、銃後の日本の市民生活の破産が、この劇のありとあらゆるシーンに描写されていく。配給品になったビールの小瓶を少量ずつコップに注ぎそのひと口を「最後の晩餐」と飲んでしまう、そのビールの銘柄は、正真正銘のサクラビールだった。
オデオン堂主人の後妻は元流行歌手、一家あげてジャズッ気のある音楽好きで非国民の家、ところが傷痍軍人(山西惇)を娘婿に迎える。娘の名前はみさを(深谷美歩)という。一転軍国美談の家となる。息子(田代万里生)は市川国府台砲兵隊を脱走し、やはり非国民の家、これの逮捕に乗り込んでくるのは憲兵伍長(木村靖司)。
さらに広告文案家(コピーライター)とオデオン堂の客のためにピアノを弾く大学夜間部の学生、この二人の下宿人が登場する。
『きらめく星座』の劇中歌は、その下宿人の一人、この学生の森本忠夫(後藤浩明)の弾くピアノの前奏が歌詞を誘い出していた。劇中歌のすべてが「昭和庶民」の流行歌であって、曲想も歌詞も「昭和庶民」の生活と意見そして希望を代表していたことを憶えておきたいのだ。舞台がはずむのはそのためである。
もう一人の下宿人、広告文案家の名前は竹田慶介(木場勝己)。竹田のつくった広告文案、その一言一言の言葉(せりふ)が、一人一人の命を織りあげていく。広告文案家という職業は、「きらめく星座」と名づけられたこの劇の題名にも関連する。言葉を扱う発信者側の責任、発信されたその言葉をどう受けとめるのかを自らに問う、つまり受信者側の責任、この二つの責任をどう考えるかということだった。その「言葉」におどりおどらされた帝国臣民が、戦争が始まっていた時代をかえりみての「聞かせる芝居」、せりふ劇の意味を、広告文案家の職業を通じて考えていたのが『きらめく星座』だったのにほかならない。
広告文「心臓と空襲に待ったなし 救心」、この広告文を読んだ小笠原信吉に「思はずドキッとしちやった」といわせている。こうした救心の広告文は、一体ギャグなのだろうか。井上ひさしは、こうした広告文の対極で、竹田慶介に「・・・・・・人間は奇蹟そのもの。人間の一挙手一投足も奇蹟そのもの。だから人間は生きなければなりません」という、ちょっと長すぎる「人間」という商品の広告文を書いていたのだった。
鹿島 茂(フランス文学)
二〇一七年は選考会で高橋さんが指摘していた通り、女性演出家と女性劇作家の進出が決定的となった一年でした。
これは日本社会の構造的な変化を暗示しているような気がします。
従来、女性が多数を占めていたのは客席の方でした。この現象は女性の方が可処分所得と可処分時間を多く有している(つまり、金があり暇がある)からだと説明されてきました。そして、それは観客の大半が専業主婦であるという意味において、日本社会の後進性・保守性の反映でもありました。
ところが、女性演出家と女性劇作家の大量進出という現象は右のような「専業主婦がスペクタクル業界を支えている」という認識からは明かにズレるものだといえます。なぜなら、女性演出家と女性劇作家は観客席から「育ってきた」わけではないからです。つまり「昨日の観客」が「今日の演出家・劇作家」というものではないのです。
統計をとったわけではないので絶対に正しいとは言えませんが、女性演出家、女性劇作家の大量進出は、いってみれば、自己表現が許される場(トポス)はここ(演劇空間)しかないという女性たちの切羽詰まった思いに後押しされている様に思えます。
では、なぜ、女性たちは演劇空間に自己表現の場を見いだしたのでしょうか? たとえば、小説やエッセーなどの活字分野ではだめだったのでしょうか?
もちろん、自己表現は可能だったかもしれませんが、活字分野は孤独を運命づけられていますから、協同性や対話性、それにライブ性というものが欠けています。この欠落は案外、決定的なものです。活字を自己表現の場としている人間が達成感や幸福感を味わえないのはそのためです。
対するに、演劇にはなによりもライブ性、そしてそれに伴う協同性と対話性が存在します。これが他においては置き換え不可能な充足感を「演劇女子」に与えるのではないでしょうか?
さて、前置きが長くなりました。女性演出家、女性劇作家の進出元年となった二〇一七年について記憶に強く残った作品について語ることにしましょう。
まずは、永井愛・作・演出の『ザ・空気』(二兎社)からいきます。女性・演出家・劇作家の中で突出した存在だった永井の渾身の一作です。その作者の熱い思いをキャスター役の若村麻由美さんが見事に演じていました。これは報道の自主規制の問題という以上に、日本のような社会統合性(ホーリズム)の強い社会で最後まで統合に抵抗できるのは女性であることを示しています。
対するに男性はというと、編集長(田中哲司)に典型的に現れているように、ホーリズムと自由の板挟みにあって自己抹殺というかたちで「解決」を図るか、さもなければ、アンカー(木場勝己)のように「これでも精一杯抵抗したのだ」として自己合理化するか、いずれかの選択になる場合が多いようです。それは、終戦後の東京裁判の被告の態度を見ればよくわかります。とりわけ後者が問題で、こうしたかたちの「日本的抵抗」は、ホーリズムが全体主義から民主主義に替わると、全体主義者から民主主義者へと、いとも簡単に転向が行われる原因となっています。そして、現代のように再びホーリズムが強くなると、例によって自己合理化を行いながら、またまた全体主義へと傾斜していくのです。ただ、戯曲ではこの部分の描き込みがいま一つ足りないと感じました。ここが描けていたら素晴らしい作品となっていたはずです。
しかし、エピローグはなかなか皮肉が効いていると思いました。抵抗を貫けなかったことを忸怩とした思いで反芻しているのは編集長のような男性であり、若村さんが演じる女性キャスターに典型的に示されているように、女性は、現場を離れたとたん完全にふっきれて、抵抗者から権力者側に一気に転身してしまうというケースなきにしもあらずということのようです。女性の社会進出が成功した後の日本社会の硬直的未来が暗示されているのかもしれません。
女性進出著しい演劇界で、男性の作・演出家としてひとり気を吐いているのが劇団イキウメの前川知大さんです。イキウメの作品はほとんど毎年、候補に挙げているのですが、毎年、新作よりも旧作のほうがよく出来ているので、残念ながら受賞には至りませんでした。しかし、今年の『天の敵』は二〇一〇年上演の短篇を長篇化したもので新作と呼んでいいものなので強く推したいと思いました。これまで、イキウメの舞台はSF的な設定を用いることで寓意性を高め、それによって現代の諸問題をより鮮明に描き出すということを得意としてきましたが、『天の敵』で扱われているのは超長寿化した日本社会ですから、アクチュアリティは非常に高く、寓意性も抜群だと感じました。
内容は、戦前、偶然、他人の血を飲んだことで永遠の生命を保証されてしまった医師が死ぬことができずに、二十一世紀の現代に健康志向の料理人として生き延びざるを得なかった悲喜劇ですが、もちろん、その下敷きにあるのはブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』です。いま、日本では、体力、気力、知力とも衰えた老人がそれでも長生きするということが危惧されているようですが、では体力、気力、知力とも充実した青年のような老人であればいいのかといえば、そうではない、というのがこの戯曲の提起する問題です。つまり、死を運命づけられた人間が死ななくなってしまったら、あるいは限りなく死を後ろに引き伸ばすことができるようになったら、いまとは別の問題が生まれてくるのではないかということなのです。
この意味で、主演の浜田信也さんははまり役でした。色白で、唇の赤さが目立ち、まさに人間の生き血を飲んで永遠に死ねなくなってしまったメトセラの悲劇を演ずるにふさわしい俳優で、こんな役ができるのは浜田さんしかいないのではないかと感じました。
イキウメのレギューラー陣に加えて、ナイロン100℃の村岡希美さんが客演しているのも満足度を高めました。
しかし、アクチュアルな問題意識という点では、さすがのイキウメも年末に観た二つの女性演出家の作品には及ばないかもしれません。
一つは、シアター風姿花伝の『THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE』です。介護の必要な母親と介護しているために婚期を逃してしまったアラフォーの娘との心理的葛藤劇で、原作はアイルランドのマーティン・マクドナー、演出は二〇一八年から新国立劇場の芸術監督に就任予定の小川絵梨子さんです。
劇場主であり、プロデュースも引き受けている那須佐代子さんが自ら主演してアラフォーの娘役を演じ、共同プロデューサーになるはずだった故・中嶋しゅうさんの奥さんの鷲尾真知子さんがその母親を演じています。
この戯曲は二〇〇七年に大竹しのぶさんと白石加代子さんという凄い顔合わせで上演されたことがありますが、今回の舞台は、この「怪物対決」とはまったく違った意味で、とても面白いと思いました。
それは、エキセントリックなところのない普通の女性が、たまたま母と娘という関係にあり、しかも母親が要介護という状態に置かれたとすると、そのごく普通の二人の女性が、とんでもないモンスターに変わりうるという「普遍的構造」を見事にあぶり出しているからです。この「普遍的構造」があるために、那須佐代子さんと鷲尾真知子さんという、特にエッジが立っているようには見えない女優さんが母娘を演じることにより、逆に、モンスター的状況が前面に出てくる結果になるのです。
なぜでしょうか?
それは演劇というものが「関係性の芸術」だからです。昔、吉本隆明は、『マチウ書試論』で「関係の絶対性」という言葉を用いましたが、演劇こそはこの「関係の絶対性」を描くのに最も適している芸術なのです。
さて、この場合、関係の絶対性をつくりだすのは、母と娘という関係です。これは、父と息子というもう一つの「関係の絶対性」に比べると、あまり取り上げられなかったテーマですが、いまや日本の文芸においては、父と息子よりも母と娘のほうがはるかに重要なテーマになってきているのです。それは昨今の文芸雑誌を開いてみれば一目瞭然です。
しからば、なにゆえに、いまことさら母と娘という「関係の絶対性」が問題になっているのでしょうか? 女性の社会進出に伴って、労働と介護が相いれなくなったから?
そういうこともあるでしょうが、私は別の見方をしたいと思います。
それは日本が世界の辺境であるがゆえに、最もアルカイックな末子(特に末娘)相続の伝統が残っているからです。そのために、母娘という「関係の絶対性」が現代に蘇って多くの女性を苦しめているのです。
あまりに牽強付会的な推論でしょうか? そうは思いません。その根拠がまさにこの『THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE』です。というのも、これはアイルランドという、日本と同じような辺境の島国が舞台の作品で、辺境であるがゆえに末子(末娘)相続の伝統が強く残っているという点で両国は同じなのです。たぶん、家族類型の異なるイングランドやアメリカではこうした末子(末娘)相続というのは極端に少なく、あまりテーマ系としては浮上してこないと思われます。『THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE』はアイルランドと日本という辺境の国同士であるがゆえに共振した戯曲なのです。
穂の国とよはし芸術劇場PLAT、アル☆カンパニー、作・演出桑原裕子『荒れ野』もまた、「関係の絶対性」をテーマにした作品ですが、この場合の「関係の絶対性」というのは核家族です。つまり、本来、親・子・孫の三代が同居する直系家族が主流であった日本が、核家族の国アメリカの占領によって核家族化せざるをえなかったことに、戦後の住宅難が加わって、「団地」という核家族単位の住宅が昭和の時代に次々に誕生したことが問題なのです。いまになって思うと、この「団地」こそは、戦後の日本人がアメリカから与えられた「核家族という幻想」を育んでいった繭(コクーン)のような空間だったのではないかと思われます。
舞台として設定されているのは、まさにこの団地の一室ですが、そこにはすでに「核家族」は解体されてしまって存在していません。核家族と見えたのは、じつは、介護していた父親が死んだ後に残された娘(井上加奈子)、上の階の住人である元高校美術教師(小林勝也)、その教え子でホモセクシュアルなパートナーである青年(中尾諭介)という、疑似核家族です。この設定が素晴らしい。
彼らが寝ていると、近くのショッピング・モールが火事になったといって、昔、団地から一戸建に引っ越していった平田満の一家が避難してきます。この一家は、いちおう核家族の体裁を保ってはいますが、しかし、こちらも解体寸前で、夫婦関係、親子関係ともにうまくいってはいません。
その原因は、どうやら平田満自身にあるようです。平均的日本人の男性を演じると抜群にうまい平田満は、そうした平均的日本人男性のフラストレーションを巧みに演じています。平田満は、まじめ一方の勤め人で、浮気もDVも一切なしという典型的な日本のお父さんなのですが、まさにそれゆえにアメリカ型の核家族の父親としては不適格なのです。いいかえると、直系家族の父親としては最適であったはずの平田満的なキャラクターがアメリカンな核家族の父親とはマッチしていなかったことに、現代日本の悲劇が懐胎されているというわけです。
アメリカンな解釈では、核家族の父親は、まず第一に妻を愛し、常に優しい言葉をかけ、子供たちに対してはよき相談相手となるような肉親でなければならないという「規範」があります。しかし、このアメリカンな核家族規範に照らすと、日本的直系家族の典型的父親である平田満は不合格となるのです。
しかし、にもかかわらず、平田満は彼なりの核家族の幻影を追いつづけています。そのため、妻(増子倭文江)ではなく、団地で妻が憧れていた井上加奈子に好意を持ち、この人となら自分の夢見ていたような「幸せな核家族」が築けたのではないかと思いつづけているのですが、それがショッピングセンターの大火で思いがけず実現したためにかえって戸惑いを感じているという設定です。
いっぽう、平田満の妻の増子倭文江はまったく核家族的な夫というものに幻影を抱いていなかったがために、むしろ、同性である井上加奈子に、レズビアン的とは言わぬまでもそれに近い感情をもって接していたようです。これもまた日本の女性同士によくある、夫より女友達という関係で、それが団地という状況により加速されているのです。
では平田満と増子倭文江の娘である多田香織はというと、これは核家族を構成するのにふさわしくない直系家族的な父と母がつくりあげた核家族に育ったため、核家族的な人間関係の構築の仕方も知らず、かといって直系家族的規範もないアノミーな精神構造にあります。ところが、それは例外どころか日本の子供の典型となっているのです。ですから、当然、父と母に対してどう振る舞ったらいいかもわかっていない状態にあります。
これに対し、井上加奈子・小林勝也・中尾諭介という、相互に無関係なパートからなる「疑似核家族」の方は妙に安定しています。なぜなら、それはそれぞれの核家族から漂流してきたシングルの連合体であり、はじめから核家族規範とも直系家族規範とも無縁でいられたからなのです。
そして、現在の日本の家庭は、誠に残念ながら、この二つのタイプの「核家族」のいずれかに分類されてしまうのです。
こうした重要な問題提起を行い得たという、その事実一つだけでも、『荒れ野』は「悲劇喜劇」賞に十分値するといえるのではないでしょうか?
『お勢登場』と『荒れ野』
辻原 登(作 家)
二〇一七年は多くの優れた舞台を観る機会に恵れた。私が劇場に足を運ぶのは〝享楽〟のため、ただ魅了されたいという想いが充たされればそれでOK。芝居がはねて、闇から解放され、帰路につく。しかし、外に出ても、やはり舞台の幻影(フア ントム)は追いかけてくる。舞台そのものがファントムなのに、そのまたファントムに掴まってたまるかと振り払おうとする時、初めて批評の目とでも呼ぶべき胡散臭い思考が兆して、今日のこの享楽の核にあるものはいったい何だったのだろうと疑い始める。
俳優の存在、その演技、演出術、台詞の受け渡しの妙と綾、美術、照明、音響、衣装のアンサンブル、それが時空の中に描いてみせた美しいシステム(ドラマ)をたどり直して、その核にあったもの、エッセンスは何だったのかという問いかけ。だが、それに答えることなど到底できない。無理にも名付けてみようとすれば、するりと指の間から逃れて行くもの、それをしかし強引に、〝真実味〟とでも名付けるか。ファントムの中心に〝真実味〟を据えるとはアイロニーそのものだ。劇的アイロニー。
そこで、チェーホフの舞台を思い起こす。
チェーホフの舞台をみる時、あるいは彼の戯曲を読む時、最初は訳が分からない。
蝋燭を持ったドゥニャーシャと一冊の本を手にしたロパーヒン登場。
ロパーヒン やっと汽車が着いたようだ。何時だい?
ドゥニャーシャ もうすぐ二時です。(蝋燭を消す)もう、明るい。
(※『さくらんぼ畑』第一幕)
人物たちとその関係、彼らが抱えている問題(関心・心配)、それらの関係がおいおい分かってきて、やがて観客は惹き付けられていく。誰がどういう位置で、どういう顔つきで立っているか、それをみている観客の〈私〉はどこらへんにいるか。──その時、〈私〉はチェーホフ劇の〝真実味〟というものを実感する。あるいは会得する。人生の、と付け加えていいかもしれない。
こういう体験は、初見、初読の時だけに限るのではなく、同じ舞台、戯曲で繰り返し起きる。シェイクスピアまた然り。
二〇一七年の舞台で、そのような体験を持つことができたのは、二月の『お勢登場』(世田谷パブリックシアター)と十二月の『荒れ野』(穂の国とよはし芸術劇場PLAT)だった。
『お勢登場』は江戸川乱歩の短篇八篇を、その中の一篇『お勢登場』のヒロイン、ファムファタル、お勢をいわば八個の物語団子を刺し貫く一本の串として、切れのいいエンターテインメントに仕上がった。時空間の自由な移動、フィクションの階型(入れ子構造)の巧みな構築と変換。動き出す挿絵、変装、謎解き、倒錯、殺人……。
我々が舞台に求める願望の一切をパズルのように配置して、見手を当惑させながら、遂にパズルが鮮やかに繋がり、嵌まって統一に至る。
兄 そいつって?
お勢 何をやってみたところで退屈よ……このまま一生退屈なんだわ。
という終盤の台詞に結実する、負の人生の〝真実味〟が浮かび上がる!
二月十九日のシアタートラムの舞台にも魅了されたが、日をおいて戯曲を読み、倉持裕という才能に目を瞠った。この戯曲は一個の歴とした文学作品である。
もう一度、是非この舞台がみたい。もちろん同じ配役で。
最もチェーホフの作劇術と舞台作りに近く、人生の〝真実味〟なるものを実現してみせてくれたのは、『荒れ野』だった。
作・演出の桑原裕子には一昨年『痕跡(あとあと)』で出会って以来、新作を待ち望んでいた。その期待は充分叶えられた。
舞台は、古い団地の2DKの居間。上手手前にダイニングキッチンや洗面所、風呂、玄関の鉄扉に続く入口があるはずだが、これは舞台袖、つまり観客からは見えない。さらに上手奥にこの部屋の住人、加胡路子(か ご みち こ)(井上加奈子)の父親の位牌が飾られている隣室があるのだが、これも見えない。
下手前に窓と出入りのできるベランダ。これは見える。
夜十一時半、明りの消えた部屋。端に置かれた円形型の石油ストーブが鈍い光を放っている。ひと組の布団に三人の男女が寝ている。まん中に路子、両側に上の階の住人である男二人。
ベランダ窓の外は妙に明るい。暗闇に聞こえる消防車、救急車のサイレン、風の唸る音、炎がはぜる音。遠くの新興住宅地ウエストランドが炎上中なのだ。
寝ている若い男が歌う。
私のどこがいけないの それともあの人が変わったの
遠くで火事の爆発音。年取った方の男が起き上がり、ベランダの方へ向かう。
残されてしまったの 雨降る町に
哀しみの眼の中を あの人が逃げる
路子 開けたら煙いよ。
あなたならどうする あなたならどうする
ベランダに出て行く年取った男。コタツ台の上の携帯電話がバイブする。
路子 はい……ああ、もしもし、藍子ちゃん?
不思議な三人の部屋に、火事で焼け出された夫婦と娘の三人が避難してくる。
最初は訳が分からなかった六人の登場人物が徐々に顔を持ち始め、やがてヒリヒリするような関係性の中に投げ込まれてゆくのがくっきり見えてくる。
なぜくっきり見えてくるかというと、この舞台は、我々観客に見えないところで発せられる、つまりキッチンや洗面所、風呂、玄関、隣室といった舞台袖で発せられる様々な音──シャワー、トイレ、鉄扉の開(あ)け閉(た)て、救急車、消防車のサイレン、ベランダの向こうで燃えている町の爆発音などの効果的な挿入によって、我々の舞台に向けられた頼りない視覚を排除して、聴覚のみで強化されるリアルが、劇空間が、実現されるからである。
さらに、その効果が強まるのは、姿の見えない登場人物たちの舞台袖からの声だ。
避難してきた夫婦、窪居哲央(くぼ い てつ お)(平田満)と、藍子(あい こ)(増子倭文江)の関係は壊れかけている。避難先は、哲央の幼なじみで初恋の路子の部屋。藍子は哲央と路子の関係を疑っている。
舞台上で、酔払って嘔吐した藍子が偶然、一人になるシーン。(*は舞台袖で発する台詞)
藍子 ふう……。
*路子 てっちゃん脱いで、それ洗うから。
*哲央 ああいいよ、流し貸して。
*路子 いいからいいから。ああ、結構ススかぶってるね。
*哲央 ほんとだ気づかなかった。たぶん家出るときに……アッ、(舌打ち)ゲロに触っちゃったよ……何で俺に引っかけるかな。
藍子 (寝そべったまま笑い)フフ、
*路子 シャワー浴びたら?
*哲央 ええ、いいの?
*路子 うん、暖まるし。そのあいだに着替え用意しとくよ。
*哲央 そう?
藍子 ウフフフフ、
上手奥の隣室には、路子の父親の幽霊が出る。反対側の下手前のベランダの向こうには火炎。
遠くで救急車のサイレンが聞こえる。哲央は窓を開ける。屋外の音が飛び込んでくる。
藍子 待ってあなた、
哲央 や、どこにも行かないよ。ベランダだから。
藍子 (やや拍子抜け)ああ……。
哲央 ……どこも行けないだろ。
藍子 ……。
路子 あっ。
(路子はハッとしたように隣室の方を見る)
ラストは静穏である。カタストロフィとカタルシスが巧みにまざり合う。
怒り、苛立ち、ふがいなさ、けなげさ、悲しみ、愛憎を、六人の俳優はキャラクターに応じて存分に、巧みに演じ分けて、出色のアンサンブルだった。
授賞は、『お勢登場』と『荒れ野』、この二作のいずれかと考えながら選考会に臨んだが、最後は『荒れ野』に投じた。
※『桜の園』で定着しているが、敢えて原題に忠実な堀江新二、ニーナ・アナーリナ訳(群像社 二〇一一年)を択った。訳文もまた同書。
- <<前の記事:第五回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考結果
- 第五回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞贈賞式を開催:次の記事>>