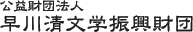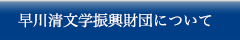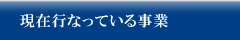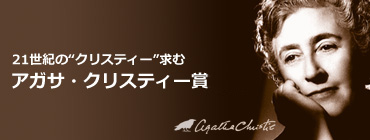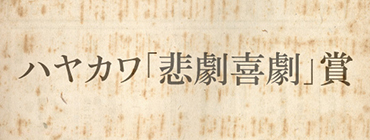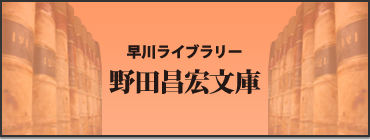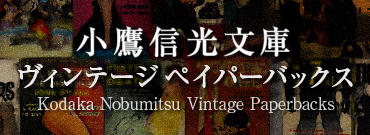第十二回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考委員批評文
生の舞台にできること
有吉玉青 (作家・大阪芸術大学教授)
もともと劇場にはよく足を運んでいたのですが、長いコロナ禍ですっかり足が遠のいていました。昨年は委員就任を機に久しぶりに劇場に通い、生の舞台を観ることのできる幸福をかみしめる、そんな一年となりました。
久しぶりに観劇をすると、いろいろなことが新鮮で、これまで特に疑問を持たなかったことが不思議に思えることがありました。
そのひとつが、演劇のチラシです。コロナ禍を経て、情報はすっかりインターネットで取得するようになりましたが、劇場に行くと、公演のチラシを束で配布されたり、ラックやカウンターに多くのチラシが置いてあります。実にアナログ、でも一枚一枚繰りながら、これから上演される作品の情報を収集するのは楽しいことです。
もちろん、そこですべての公演を把握できるわけではありません。情報はネットに比べて格段に少なくなりますが、そこは縁というものでしょう。
そんな中で、人は数多ある作品の中で、どうしてその作品を観に行くのだろうということも、あらためて考えました。劇団のファンであったり、劇場の会員であったり、作家や演出家のファンであったり、贔屓の役者さんが出ていたり、原作がどんなふうに脚色されているか興味を持ったり、劇評を読んで……等々、いろいろな理由がありましょうが、たまたま目にしたチラシのビジュアルやコピーに惹かれて、ということもあるに違いありません。
青年劇場による『マクベスの妻と呼ばれた女』(作=篠原久美子 演出=五戸真理枝)は、まさにチラシに惹かれて観に行きました。劇場で配布されたチラシの束の中の一枚で、裏に「マクベス夫人、あなたのお名前は?」とあり、言われてみれば確かにマクベス夫人には名前がないと思ったのです。
舞台はアイボリー色を基調とした美術がきれいで、同じくアイボリー色の衣装をつけたデズデモーナ、オフィーリア、ヘカティ、ケイト、クイックリー、ポーシャ、ロザライン、シーリア、ジュリエットといった、シェイクスピア作品の「名前のある」九人の女性たちが、マクベス夫人にお仕えしていました。彼女たちがそれぞれの作品の中のキャラクターそのものであるのに対し、マクベス夫人は同じくアイボリー色のドレスに身を包み、上品なレディとして登場します。
悪女として名高いあのマクベス夫人が! 意外でしたが、よく考えれば上品な悪女というのがいてもおかしくはなく、これまでに観たマクベス夫人にイメージを作り上げられていたことを思います。とはいえ、原作通りに夫人が夫をたきつけ、国王殺しの事件が起きればやはり──けれども、夫人はあくまでも夫のためを思ってしたのでした。
貞淑な夫人は夫のためだけに生き、そのことにまったく疑問を持っていません。名前がないことにも──女性の権利を主張し、自分であろうとする周囲の女性たちに問いただされても、「名をなすのは殿方のお役目」と、夫人の信念は揺らぎません。
ジェンダーの視点はもちろんありますが、当のマクベス夫人にその意識がまったくないために、彼女が気の毒に思え、非常なるシンパシーを抱きました。再演ということですが、この感情移入の大きさから、第十二回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞の候補作二作のうちの一作に推しました。
選考会を終え、本稿を書きながら、あまりにも抑圧の歴史が長いために、それが疑問をはさむ余地のない常態となり、自分が差別や抑圧を受けていることに気がつかない人々もいることに、今更ながら思い当たりました。マクベス夫人はその代表だったのでしょう。
こうしてみると、差別されてきたと切々と訴える女性たちよりもマクベス夫人の存在のほうが、ジェンダーに関する問題提起は大きいものです。可哀想に! と思ったことで啓蒙されている。作者のねらいはここにもあったでしょうか、演劇というものの力も、あらためて知った思いです。
◆
選考会で候補に挙がったオフィスコットーネプロデュース『兵卒タナカ』(作=ゲオルク・カイザー 翻訳=岩淵達治 演出=これも! 五戸真理枝 企画=綿貫凜)のチラシは黒色です。縦長にデザインされたTANAKAの白い文字が主演の平埜生成さんの顔に重なり、牢獄のような印象を受けました。
裏の地色が薄いピンク色なのが救いでしょうか。(あるいは、観劇後に思ったことですが、これは潔く散る桜色?)そこに書かれた内容紹介によると、貧しい農家出身の兵卒タナカが休暇に実家を訪れ、軍人という自身の身分が身近な存在の犠牲で成り立っている現実を突き付けられる、「タナカが信じて疑わなかった世界が音を立てて崩れていく──。」
客席でパンフレットをぱらぱらと読み、作者はドイツ人で、一九四〇年にチューリヒで初演されたが、日本公使館の抗議を受けて上演が中止となったという厳めしい情報を得たところで場内は暗くなりました。
なんとなく話は想像できるような気はしましたが、やがて闇の中に照らし出された、舞台に吊り下がる、鈍色の大きな球体の圧迫感、その下で繰り広げられた舞踏に引きつけられ、物語を追うことになりました。
タナカは帰省の折に、家族と村人の歓待を受けますが、実は村は大飢饉に喘ぎ、妹は妓楼に売られていました。饗宴がほかならぬ身内の犠牲によるものであったことに気づき、タナカの信じていた価値観が崩れます。
帰省の折に知った現実とはこういうことでしたかと、チラシの情報にあけられた括弧が閉じた思い。それでも休憩をはさんでの全三幕、長い上演時間に緊張感が途切れなかった大きな理由のひとつは、タナカの平埜さんが変化の前と後で、まったく別人になっていたからです。明るく自信に充ちた表情が陰鬱に、あるいは狂気を漂わせるものに変わる、そんなレベルを遙かに超えて、同じ人間とは思えない顔になっていました。
自分の信じていたものが間違いだとわかったら、世界観が崩壊したら、こんなことになるのだろうかと恐怖さえおぼえました。ほんとうに上手い役者さんです。
はじめに、観劇の動機のひとつとして、好きな役者さんが出ているというものを挙げましたが、平埜さんが出ているということもあり、「銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件」(原作=アンドリュー・カウフマン 脚本・演出=G2)を観劇しました。銀行強盗に今持っているもので最も思い入れのあるものを差しだせと言われて渡すと、それで魂の五一%が失われる。そして被害者たちに、夫が雪だるまになったり、自分が九八人に分裂したり、足首に彫ったタトゥーのライオンが出てきて追いまわされるといった不思議な事件が起きるという奇妙な話。事件が舞台上でどう表現されるのか興味を持っていましたが、平埜さんが出るとなれば興味も増すというもの。しかも役どころは銀行強盗というのですから。
事件は、人形を使ったり映像を駆使したり、いろいろな仕掛けや工夫で、舞台上に表現ならぬ「実現」され、楽しませてくれました。
タイトルの妻が差し出したものは、これまで家計など、家族のためにさまざまな計算をしてきた電卓でした。それを失ったことで身体が縮んでいく様子は、まわりのものが巨大になって舞台上に現れるといった縮尺の変化で実現されます。
彼女は自分の身長の変化を壁に記していきます。日に日に縮む身長は、とうとう六一ミリに。やがて消滅してしまう妻を、夫はなんとか救おうと懸命になり、夫婦の関係も変わっていきます。
目の前でまさに〝事件〟が起きること、これも舞台の醍醐味のひとつでしょう。最近、昭和の歌謡曲が人気で、当時の歌番組の映像を見る機会が多くありますが、セットの豪華なこと、仕掛けの面白いこと。そこに加えて本作は、自分にとって一番大事なものは何か考えさせてくれました。妻が電卓を差し出したように、大事なものは何よりも思い出でしょう。そして、それが自分の魂の五一%を占めるという一見根拠のない数字も、おそらくは舞台に波打つファンタジー世界のリズムの中で納得させられました。
さてお目当ての平埜さんは──銀行強盗は怪傑ゾロの風貌で、顔は覆面で見えず残念──必ずしもそうではなく、顔を覆うことで逆に演技力が試されます。じっさい仮面劇のオーディションは仮面をつけずになされ、役者の表現力そのものを審査します。ふだんは気がつきませんが、顔の表情は身体表現の一部にすぎません。平埜さんは妖しくも凜々しい強盗となってマントを翻し、摩訶不思議な世界を颯爽と駆け抜けていきました。
◆
第十二回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞の候補作、もう一作は、イキウメによる『奇ッ怪小泉八雲から聞いた話』(脚本・演出=前川知大)を強く推しました。こちらも再演だそうですが、観るのは初めてです。
劇場に一歩足を踏み入れると、そこには異空間が現出していました。舞台はシンプルで、黒い木の柱が立ち、坪庭のまわりに回廊がしつらえられています。上から一筋の砂が静かな音を立てて降り、奥には祠も見えます。凜とした緊張感の中で、自分の五感が開かれていくのがわかります。
そこに着物姿の女性たちが、すり足で登場してきました。衣擦れの音も聞こえます。お能のようでもあります。そしてじっさい夢幻能よろしく、虚実皮膜のあわいにつれていってくれました。
田舎の旅館に二人の男がやってきます。そこには長く滞在している小説家がいました。この三人が怪談話をはじめ、小泉八雲の「常識」「茶碗の中」といった作品が、聴覚視覚にうったえてくる演出で繰り広げられます。
八雲作品のオムニバスかと思いきや、そのうちに二人の男が警察官と検視官で、二人は遺体安置所から消えた女性の死体を捜していることがわかります。そして、どうやらこの小説家に疑いがかけられているようなのです。二人は、この小説家の事情聴取をするためにやってきたのでした。
小説家に話を聞くうちに、彼の過去の話になります。かつての恋人は生まれ変わって戻ってくるという言葉を遺し、自らこの世を去っていました。そして小説家はつい最近、その恋人にそっくりな女性に、この旅館で出会います。まるで八雲の「宿世の恋」のように……。
小説家の過去と現在、そして八雲の怪談が、旅館の女将をはじめ登場人物たちがさまざまな役になりかわり、展開されていきます。現実と怪談は行きつ戻りつして、あるいは平行して、あるいは──。
大緊張でのぞんだ、はじめての選考会、選考理由を述べるために、簡単にでもあらすじを説明しようと思いました。それで記憶とメモをたよりに準備しようとしたのですが、あらすじを説明できるのは、このあたりまで。この先は、舞台上で進行している現実、それも過去と現在を行き来する現実と、怪談という虚構がとけあって、どこからどこまでが現実でどこから先は虚構なのかわからず、どうにも説明ができません。
そもそも言葉で観ていませんでした。劇場では、感じて観ていたのです。そして感性のレベルでは、現実と虚構の往還も融解も、「わかって」観ていたようでもあります。それを言葉で説明できようはずもなく、舞台には、まさに言葉を超えた時空が現出していたのでした。
最後に二人は小説家の遺体と消えた遺体を発見しますが、では、今まで小説家と話をしていたのは幻だったのか? 二人の混乱は必定ですが、観ている側は、もう攪乱されています。といっても心地よく、すずやかに。
ふと気がつくと、目の端に、小説家の姿がありました。舞台の端で、小説家とその過去の恋人の死体を見つけた二人を、小説家が見ていたのです。
自分は今、どこにいるのだろう? 最後は客席に座って舞台を観ているはずの自分の居場所さえあやうくなって暗転。最初から最後まで、ここではないどこかにつれていかれるという至福の劇場体験、まさに〝体験〟をさせてもらいました。
昨年は小泉八雲没後一二〇年でした。イキウメによる本作の上演が、この周年を意識したものかどうかはわかりませんが、私には周年のこの年に、小泉八雲がイキウメを借りて(小説家のかつての恋人が現世に現れたように)ふたたび現れたように思えてなりません。
CGやAI、映像は何でもできるようではありますが、観る者を現実ではない世界に、劇場にいる現実さえ忘れて、別の次元につれていってくれる、これは舞台の力、生の舞台ならではの力です。舞台の力の無限をも、あらためて感じました。
今年も佳い作品にたくさん巡りあえることを願いつつ──。
『奇ッ怪小泉八雲から聞いた話』
『阿呆ノ記』
辻原登 (作家)
劇評は難しい。記憶はどこまで正確か。批評は記憶の中から生まれる。あるいは記憶そのものだ。しかし、引き込まれるような舞台は記憶を許さない。一級の舞台は批評の無用を強要する。劇評の困難さは音楽に対しても言えるだろう。
しかし、私は、その困難を乗り超えて物される劇評や音楽評を読むのを楽しみにしている。当の舞台を観ていなくても、劇評だけでも満足することが多い。そこには書評などにはない緊迫感がある。劇評家たちはどんな工夫で言葉を紡ぐのだろう。その工夫を知りたい。
例えば、今回の受賞作『奇ッ怪小泉八雲から聞いた話』(イキウメ)の評は、主だった新聞にこぞって掲載され、いずれも読み応えがあった。
私はこの舞台を二度観ることが出来たが、とても各紙の評のようなものは書けないと改めて思った。
──舞台は、廃墟の上に再現された山奥の温泉旅館という設定。そこへ麓からやって来た二人の旅行者はいわば現実(現世)からの来訪者なのだが、我々観客もまた来訪者で、旅館が廃墟だと明かされるのは、幾多・幾重の劇中劇を串刺しにして辿り着く衝撃的なラストにおいてである。
ストーリーは、小泉八雲の五つの「怪談」を基に、「百物語」ふうに展開していく。語りから劇中劇へ、現実から虚構、虚構からさらなる虚構、虚構から現実へと軽やかに行きつ戻りつして行くうちに、主人公(死者)の痛切な恋物語が迫り出して来て、ラストの惨劇へと至るのだが、舞台は初端からコミカルなステップで進行、展開してのちのことだから、逆に衝撃度は大きい。
しかし、二人の来訪者が立ち尽くす廃墟からはカタストロフとカタルシスが渾然一体となって、しみじみとした気が立ち籠めるから後味は非常に良い。
幽霊が幽霊話を語る時、あるいは幽霊が幽霊を演じる時、当の話者、演者は現身となる。幽界と現世が交錯し、言わば入れ子構造のまま螺旋を描いて進行する奇ッ怪な展開なのだが、その展開をスムーズにし、美的に支えるのが、能舞台に似た設えと、橋掛りを渡る旅館の女将や使用人の姿勢と歩きにある。
私はこの舞台を十日ほど間を置いて二度観た。更にもう一度と思った程で、それならと台本を読んで、再々体験することにした。「悲劇喜劇」編集部のお蔭で台本コピーを入手することが出来た。
台本を読むことで、確かに『奇ッ怪』の隙のない精緻な戯曲構造、先に述べた「入れ子構造のまま螺旋を描いて進行する」を確認することが出来た。同時に、当たり前のことだが、読むことと観ることの違いに改めて気付くことになった。
読むとは線的時間、文章という一筋の線上の移動でしかないから、台本もまた小説を読むような展開になってしまう。舞台の時空間で味わう魅力、醍醐味がすっぽり抜け落ちてしまう。胡乱な言葉の藪を、どこに行き着くかも分からず潜り抜けて行かなければならない。
例えば、7「劇中劇 茶碗の中」冒頭に置かれた長めのト書きを読んで、次に登場人物たちのセリフのやりとりに入る。分かりにくい。しかし、ト書きに書かれたこの場面を、劇場で私たちが了解するのは一目、一瞬のうちである。ドラマはすかさず進展する。入れ子と螺旋が合体したアインシュタイン的時空の中に放り込まれているのに、私たちは苦もなくドラマを理解し、魅力を享受する。
俳優たちの演技について云々する資格は、私にはない。しかし、この奇ッ怪な構造物を見事な流れのドラマに仕上げたのは、無論出演者たちの並はずれた力量の賜物だろう。
◆
すみだパークシアター倉での「桟敷童子」の舞台は、いつもたまらない魅力だ。理屈抜き、贅言を弄する必要は全くない。
『阿呆ノ記』(24年6月)。戯曲、役者、演出、そして装置! 四拍子揃って、芝居小屋の醍醐味が私の背筋を駆け抜けた。芝居は背筋で見よ、と教えた先人がいる。
阿呆村の女頭目伊織(音無美紀子)の孫甚太郎(加村啓)が初めて鉄砲を構えて熊を撃つ場面で、私は舞台上どこにも見えない熊になったような気がして、こちらに銃口が向けられているわけでもないのに戦慄を覚えた。
青年座『ケエツブロウよ─伊藤野枝ただいま帰省中』では、ラストに巨きな伊藤野枝の墓石が置かれた時は肝をつぶし、思わず瞑目、合掌した。
はえぎわ×彩の国さいたま芸術劇場 ワークショップ『マクベス』。約百分のノゾエ版『マクベス』だったが、やはり内田健司のセリフ回しと身体演技にただならぬオーラがあった。
新国立劇場の『テーバイ』は、私には見逃せない舞台だった。ソポクレスの『オイディプス王』『コロノスのオイディプス』『アンティゴネ』の三部作が『テーバイ』のタイトルのもと、一つの悲劇として上演されたからで、その試みだけでも画期的だと思われたし、期待に違わぬ充実した舞台だった。特に『オイディプス』の流れの中で、私が愛好する『アンティゴネ』を鑑賞することが出来たのは幸運だった。
シス・カンパニー『カラカラ天気と五人の紳士』。やはり別役実の不条理劇、いや「喜劇」は面白い。
オフィスコットーネ『兵卒タナカ』、パラドックス定数『諜報員』が強く印象に残る。
東京芸術劇場『インヘリタンス─継承─』について。作者マシュー・ロペスは、E・M・フォースターの『ハワーズ・エンド』に着想を得たと言うが、本当? と首を傾げざるを得ない。『ハワーズ・エンド』はまるで違う小説である。ヴァージニア・ウルフのブルームズベリー・グループの中心的存在だったフォースターの文学と権威を悪用した底の浅い戯曲で、何かというと、フォースターの名を口にする登場人物たちが文学を本当に志しているとはとても思えないし、後篇は特に安易なストーリー展開で、大富豪が大団円の主力になるなんて!?
ロンドン、ニューヨークで権威ある演劇賞を受賞したというが、あちらの劇評を読んでみたい。
唯一無二の「宇宙」の強度
濱田元子 (毎日新聞論説委員 学芸部編集委員)
「怪談ばなしと申すのは近来大きに廃りまして、余り寄席で致す者もございません、と申すものは、幽霊と云ふものは無い、全く神経病だと云ふことになりましたから、怪談は開化先生方はお嫌ひなさる事でございます」
ちょっと引用が長めになってしまったが、落語中興の祖とされる三遊亭円朝(一八三九~一九〇〇年)作の怪談『真景累ケ淵』の速記は、こんな言葉で始まっている。タイトルの「真景」は「神経」に掛かっている。
江戸末期から明治にかけた激動の時代に活躍した円朝。『真景累ケ淵』の速記録が新聞に掲載されたのは一八八七(明治二〇)年からだ。鎖国が解け、一気に西洋の文化や技術、思想が流れ込んできた。そんな時流に乗っかるような「開化先生方」の西洋的合理主義を受け止めつつ、でも、それだけでは説明のつかない世の因果の不思議、人の心の闇を「怪談」という仕立てでえぐってみせたのが円朝なのだろう。
時代はぐんぐん下り、技術革新が進み、デジタル化の世になって、でもやっぱり科学では説明のつかない不可思議なことはある。それどころか、科学的に、合理的に説明のつかない領域のものは、効率優先の流れの中でますます切り捨てられていってはしまいか。
そんな時代へのアンチテーゼのように、SFやオカルト、ホラーといった現代の「怪談」を切り口に、現代人や社会の「闇」と「病み」を照射してきたのが、前川知大率いる劇団「イキウメ」だ。劇団公演として上演された『奇ッ怪小泉八雲から聞いた話』は、構成・脚本・演出の前川の深遠で哲学的な世界観が、俳優の言葉や身体、装置、照明、音響などのスタッフワークと一体となってエンタテインメント性も豊かに創り上げられ、パズルのピースがぴたりとはまったラストに震えがきた。劇評意欲がかき立てられる舞台は、この賞にふさわしく、一番に推した。
観客揺さぶる「劇中劇」の仕掛け■
物語は、「小泉八雲から聞いた」とあるように、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン、一八五〇~一九〇四年)の再話文学、すなわち日本に伝わる昔話や伝承を八雲自身が書き直した作品のうち五篇を取り上げている。八雲と円朝が、同時代人というのも興味深い。
象に乗った普賢菩薩が現れる『常識』、後妻が亡き先妻に取り殺されるという猟奇的な『破られた約束』、かと思えば湯呑の中に顔が浮かぶ奇天烈な『茶碗の中』、転生や運命の不思議な力を感じる『お貞の話』、生死を超えた愛の宿命を描く『宿世の恋』(中国の『牡丹燈記』に取材したとされる円朝作の『怪談 牡丹燈籠』と同工異曲)が、劇中劇となって展開されていく。
「騙る」にもつながる「語る」ことに重きをおいてきた前川。本作も「語り」が物語を推進していくカギとなる。舞台は人里離れた山中の古い旅館だ。小説家の黒澤(浜田信也)は逗留しながら執筆しているが、そこに旅行者の田神(安井順平)と宮地(盛隆二)がやって来るところから始まる。かつてはお寺だったという旅館にまつわる不思議な話を、まずは黒澤が「語り部」となって語り出すと、八雲の『常識』が劇中劇となって立ち現れてくるという仕掛けである。
女将(松岡依都美)をはじめ、旅館の仲居(生越千晴、平井珠生、大窪人衛、森下創)も交えて、外の人物が、スーッと劇の中に入って劇中劇を演じる登場人物となり、そして、場面もシームレスに転換していく。観客側も知らず知らずに中と外の境界が溶けていくのを感じながら、妖しい世界に引きずりこまれていく。
実は、田神と宮地は遺体安置所から若い女性の死体がなくなった事件を捜査している警察関係者だと明かされ、「語り部」を変えながら語られる八雲の「再話」と死体行方不明事件が次第に絡まりあってくる。劇中劇が、単なる劇中劇ではなく、事件を解くカギになっているという構造にゾクゾクさせられる。
劇と劇の境界を溶かしていきながら、でも、観客の意識を揺さぶるように、ツッコミによる笑いや破調を作ったりしているところも、凝ったたくらみを感じる。たとえば『茶碗の中』という、怪談というより不条理寄りの再話の再現では、宮地が語り部となり、田神が登場人物として演じていたが、宮地が「この前僕に起こった」と言って、今度は田神に代わり宮地が登場人物を演じ始めるといった具合だ。
また、『破られた約束』では、後妻に恨みを持つ亡き先妻の狂気のさまを演じた女将が、女将に戻った時に、髪の乱れが指摘されるといったように、意識的に境界をゆがませ、観客を揺さぶる。いま自分が目の前で見ているものは、自分がいま存在しているレイヤー(層)はどこなのか、一筋縄ではいかない作劇が、人間存在についての根源を突いてくる、といったらうがちすぎだろうか。
オペラ『アイーダ』を思わせるような悲恋の成就の大団円。その段になってようやく、最初に『常識』、すなわち象に乗った普賢菩薩というのは狐のいたずらだったという再話が語られた意味が氷解する。
この五篇を選び、それらを有機的に構成し、円環構造のように一つの大きな「愛」の物語を紡ぎ出す前川の作家としてのセンス、演出のうまさを改めて感じさせた。同時にそれが効果的に機能するのは、体現する俳優の身体があってこそのものである。戯曲を読み解き、輻輳するレイヤーを自在に行き来しながら、その場その場の人物たちに、リアルな息を吹き込んでいく。物語と溶け合うナチュラルな立ち居振る舞いに目を奪われた。
浜田はクールなたたずまいに深い愛を秘める黒澤を奥深く造形。安井は持ち味の飄逸さが重い筋立てに軽みをうまく生む。客演の松岡は着物のたたずまいに貫録があり、凜とした女将から狂気の先妻まで見事に演じ分け、盛、大窪、森下も要所、要所を押さえた確かな演技で支えた。
目を見張った「劇団力」■
もともとは二〇〇九年に公共劇場である世田谷パブリックシアターのプロデュース公演として上演された。今回は満を持しての劇団公演で、座組としてのまとまり感が、前川の仕掛けと相まって唯一無二の宇宙を作り上げていったことは間違いない。劇団として力をつけてきたことを実感させられる。
これまでの前川の作品も、夢幻能そのものだったり、夢幻能を強く意識させるものは多かったが、今作もやはり、人物たちの存在する位相が、生だったり、死だったり、幻想だったりと、能的なものを強く感じさせた。その意味で、装置の果たした役割も大きい。
時折砂が上から流れ落ちてくる祠のある中庭を配し、能舞台のように生と死の世界をフラットに交錯させる回廊形式の土岐研一の装置も奏功する。砂の流れは、時間のようにも、生命がこぼれ落ちていくようにも見えてくる。無常観が通底しながらも、でもその中で愛を貫こうとする人間のけなげさが胸を打つ。濃く陰影を刻む佐藤啓の照明、心にさざ波を立てていくようなかみむら周平の音楽も特筆したい。
円朝が「怪談」を通して描いたように、科学や自然の摂理を超えたものの中に、世の真理や人間の真実がひそんでいるのではないか。社会や人間の根源を探ろうとする姿勢が、時代を超える作品の強度を生み出すことにつながっている。五年後、十年後、百年後でも、時代時代の人間の胸に迫ってくる普遍性を持ち続ける。そんな作品に出合えたことを喜びたい。
百年の時超える『兵卒タナカ』■
二つ目に推したのは、オフィスコットーネが上演したゲオルク・カイザーの『兵卒タナカ』(岩淵達治訳、五戸真理枝演出)だ。こちらも百年の時間を超えて、なおアクチュアリティーのある作品ということに驚く。二〇二二年に急逝したプロデューサーの綿貫凜が生前に公演を企画し、制作を進めていた。ちょうど二四年は築地小劇場創立百年であったが、劇団としての築地が分裂するまでの足かけ五年半の間に、百十七本中七本(うち二本は再演)を上演している作家である。
ドイツ表現主義を代表し、第一次大戦の経験を基に社会批評性の強い作品を書いているカイザーが日本を舞台に、北国の貧農出身のタナカ(平埜生成)を主人公にして、いびつな支配構造や国家の体制を痛烈に批判する。三幕構成の堅牢な組み立ての作品を、キッチュな仕掛けで演出した五戸のセンス、俳優らの芸の幅広さで、「いま」に通じる作品として提示されたのは見事だった。
大飢饉に見舞われた故郷に休暇で帰ったタナカは、戦友ワダ(渡邊りょう)を妹ヨシコ(瀬戸さおり)と結婚させようとするが、妹は妓楼に売られていた。妓楼で上官を殺したタナカが軍法会議にかけられる三幕は、理路整然と民の窮状と軍のまやかしを批判するタナカを演じる平埜の、説得力あるセリフが際立った。戦争が過去ではなく、格差や分断が深刻化する中で、この作品が上演される意義を強く感じた。
◆
二四年を振り返ってみると、世界でやまない戦争と失われる多くの命、高騰する物価、不祥事や事件が浮かび上がらせる社会の格差と劣化の進行などに、演劇界も深く影響を受けていると感じた一年だった。SNSでいとも簡単にデマや不確かな情報を拡散し、憎悪や分断をあおることが可能な時代になってきたというのも深刻だ。その中で、歴史と現在性を意識した作品が、新劇の劇団を中心に上演されたのは収穫だった。
今年は戦後八十年である。いつまで「戦後」と言っていられるのだろうかとも考えさせられる。そんな時代の中で演劇は、劇場は、立ち止まって思考することができる場として、ますます重要になってきている。築地百年でさまざまなシンポジウムが開かれ、劇場を取り巻く危機感も共有された。演劇の「場」を守り、文化の多様性、持続可能性を探るために演劇界は知恵を絞る必要がある。 (了)
二〇二四年の収穫
矢野誠一 (藝能評論家)
「能率手帳A5」なるノートにその年に観た芝居の演目と劇場名を記しているのだが、昨年つまり二〇二四年は歌舞伎や文楽のような見取り狂言の昼夜興行も一本と算えて、観劇数は一一一本だった。コロナ禍以前は年に二〇〇本を下ることのなかったのを想えば多少減り加減だが、三日に一度の割で観劇の椅子に座る暮しのできるのはやはり冥利につきる。その一一一本からハヤカワ「悲劇喜劇」賞を選出するにあたっての私のベスト3をあげるなら、
ケエツブロウよ─伊藤野枝ただいま帰省中
白衛軍 The White Guard
奇ッ怪小泉八雲から聞いた話
となるか。
この国の現代史で一九一二年七月三〇日から二六年一二月二五日までの、後の世の人が「大正デモクラシー」と呼んだ十五年間は、まるでエアポケットよろしくそこだけ独立して存在し、風俗、世態、人情のどれもが、何か別の国のそれであるかのように際立って特徴的な色彩を発揮してのける。時代そのものがドラマであるかの如き、いやドラマ自体としての展開を見せるのだ。
劇団青年座公演、マキノノゾミ作、宮田慶子演出『ケエツブロウよ─伊藤野枝ただいま帰省中』は全篇大正の時代色に横溢した舞台だった。展開されるドラマの小さなピースのひとつひとつに、金太郎飴よろしく大正固有の貌が塗りこめられている。なかでも圧巻は那須凜の演じたと言うより扮した伊藤野枝で、これまで何人かの女優が演じた伊藤野枝を吹きとばしてしまった。那須凜イコール伊藤野枝、そしてもうひとつのイコール大正として、作品を象徴してみせた。
ミハイル・ブルガーコフ作、アンドリュー・アプトン英語台本、小田島創志訳、上村聡史演出、新国立劇場『白衛軍 The White Guard』はチェーホフの芝居を思わせるような家庭の場面と、組織の持つ非情な現実をかかえた軍隊の場面が交互に出てくることで、日常と戦争を通してロシアの二面性がうまく表出されている。家庭にあっては酒の言わせる大言壮語でまるで世界を手中にしているように振舞いながら、軍隊という組織の中では歯車のひとつに変貌し、保身に徹して立ちまわる人間の持つ本質的な狡さを露呈するのだ。
さて、小泉八雲原作、前川知大脚本・演出になるイキウメ『奇ッ怪小泉八雲から聞いた話』である。
数々の怪談の作者として小泉八雲という名には、子供の頃から馴染んでいた。ラフカディオ・ハーンという日本に帰化する以前の名前も知っていた。ギリシャで生まれ、アメリカはニューオリンズで新聞記者になり、一八九〇年(明治23)に来日し、島根県松江市尋常中学校の英語教師になったことは、いま調べて知った。そのいま調べたところによると、松江のある出雲地方に八雲の生まれたギリシャに通じる古い多神教の世界を見出していたようだ。
子供の頃から知っていた小泉八雲だが、その作品を読んだことはなかった。「耳無し芳一」も「雪女」も活字で知ったはなしではなく、お伽噺の「桃太郎」や「浦島太郎」のように耳から得た物語である。小泉八雲について論じた文章を読んだ記憶もないのだが、加納孝代の言う、「人間の魂の世界だけでなく、鳥や木や草や極小の虫の魂にも向かい」あっている視点が、八雲の怪談を支えていることはなんとなく理解していた。
大方の国語辞典では怪談を「化け物・幽霊などの出てくる気味の悪い話」としているが、三遊亭圓朝がこの世に存在していない幽霊と訣別した怪談を創作していらい、幽霊は怪談にとって必須の存在ではなくなった。
前川知大の『奇ッ怪小泉八雲から聞いた話』という命題はまことに秀逸である。死者は出るが幽霊ではないこの作品を怪談と名乗らず、『新明解国語辞典』に言う「どうして起こったか、人間の知恵や常識では考えられない様子。不思議」の強調表現である「奇ッ怪」とすることで荒唐無稽な化け物ばなしであるのを否定している。
『奇ッ怪小泉八雲から聞いた話』は、小泉八雲の怪談「お貞の話」など五本に三遊亭圓朝の『怪談牡丹燈籠』を重ねあわせたもので、初演は二〇〇九年に世田谷パブリックシアター。現実性に乏しいSF的異界を舞台にしながら、現代社会のかかえる不条理を的確に抽出してみせる。「聞いた話」と設定することで小泉八雲との距離感を生じさせ、前川知大独自の視点で怪談の持つ「気味の悪さ」を消し去り、人間の真実をあぶり出しているのだ。
- <<前の記事:第十二回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞贈賞式を開催
- 第十三回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞 選考結果:次の記事>>