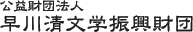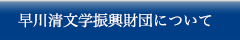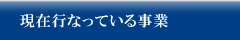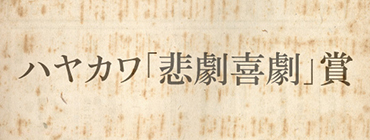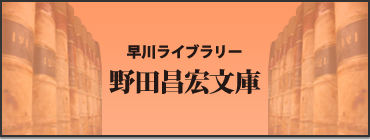第九回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考委員批評文
「疑いの時代」の傑作
鹿島茂 (フランス文学者)
二〇二一年は前年に引き続き、コロナ禍の影響で演劇界はさまざまな影響を被りましたが、観劇する方も、ある意味、命賭けでした。私はコロナに罹患したら最も危険といわれる血液型A型の七〇歳以上の男性で、おまけに生まれつき肺が弱いときているのですから、臆病になるのも当然です。
いかにも換気が悪そうな小劇場の満員の席で前後左右の観客の咳やくしゃみに神経を尖らせる一方、もし自分がコロナ・ウィルスに罹患していたとしたらこれも大変なことになるなあと思いながら舞台に目をやっていましたので、作品や演技・演出に対して正しい評価が下せるか否か自信がもてなくなるときもありました。
しかし、たいていは観ているうちにコロナのことなど忘れ、いつしか劇に熱中している自分を見いだすことの繰り返しでした。演劇の力はコロナよりも強いようです。
とはいえ、絶対的な上演本数の少なさに加えて私個人が劇場に足を運ぶ機会も例年よりもかなり減っていましたから、「ハヤカワ『悲劇喜劇』賞」に値いする作品に遭遇できるか不安を感じつづけていた一年でした。
そんなとき、年末のギリギリになってようやくこれはという作品に出会えたのがジョン・パトリック・シャンリィ作、小川絵梨子翻訳・演出『ダウト〜疑いについての寓話』(劇場・プロデュース゠シアター風姿花伝)です。
プロデューサー、劇場支配人、主演の三役を兼ねる那須佐代子さんは二〇一七年にも『THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE』で演出家の小川絵梨子と組んで素晴らしい演技を披露され、私も本賞の候補作として強く推しましたが、受賞には至りませんでした。
それが今回、同じコンビで、ピューリッツァー賞、トニー賞同時受賞のシャンリィの作品(二〇〇四年)の上演ですから、これには期待せざるをえませんでした。
舞台は一九六四年のニューヨーク・ブロンクスのカトリック寄宿学校。まず、私はこの時代設定と舞台設定だけで、おおいに唸りました。なぜでしょう?
現代ならまだしも、ケネディが大統領に就任した一九六四年のブロンクスとはどのような地域だったか、これが重要です。ブロンクス地区は、戦前には、アイルランド系移民とイタリア系移民(どちらもカトリック)、それにユダヤ系移民が混在するかなり物騒な地域で、プロボクシングの世界ヘビー級チャンピオンを輩出したことからもわかるようにWASPの白人は住まないローワーな界隈として知られていました。戦後は、蓄財して中産階級に成り上がったアイルランド系やイタリア系、ユダヤ系移民が脱出し、かわって黒人やプエルトリコ人が流入してきたため、治安はさらに悪化していました。
さて、このような時代背景と住民事情の中に『ダウト〜疑いについての寓話』を置いてみると、どのようなことが浮かび上がってくるでしょうか?
まず重要なのは、舞台となっている学校がカトリックの女子修道会が経営する男女共学の寄宿学校とされていることです。ブロンクス地区におけるカトリック校はどんな親も、荒れた公立のハイスクールを避けて子供を入学させたがる地区エリート校ですが、ニューヨーク全体のエリート校ではありません。一九六四年の時点では、ジョン・F・ケネディが大統領に当選したとはいえ、カトリックはまだマイノリティだったからです。このあたりが微妙なところです。
ドラマの導入部では、この学校始まって以来初の黒人生徒が入学を許可されたことが語られていますが、これもブロンクス地区における私立のカトリック校という微妙なポジションと関係しています。地区転入者である黒人の間でも成功者で教育熱心な親は公立校を避け、私立のカトリック校に子供を入学させたがる風潮がありました。「カトリック」の意味は「普遍的」ですから、人種、民族、肌の色は問わないのが原則です。またケネディが大統領選挙の際にキング牧師の支持を取り付けて黒人層の票を集めたこともあって、カトリック校のほうが黒人に対して融和的とも言われていたのです。
もう一つ重要なのは、カトリック校である以上、宗教の授業を担当する司祭が配属されていることです。司祭は教員ではありますが、カトリックのヒエラルキーにおける上司は学校長ではなく地区の司教です。ただし、司教はカトリック校の監督権をもってはいますが、女子修道会が完全にその管轄下にあるわけではありません。このあたりの捩れた権力構造もドラマに間接的な影響を与えています。
しかし、ドラマツルギーの観点から見て最も重要と思われるのは、人間というものに対するカトリックとプロテスタントの考え方の違いです。
カトリックは基本的に人間を過ちを犯しやすい弱い存在と捉えます。弱い存在ですから、肉の欲求に負けないよう制度的にガチガチに縛り、外側から監視を怠りなくしなければならないと考えます。神は各人の心の中ではなく教会にいますから、弱さに負けて罪を犯した場合には教会の司祭の前で懺悔しなければなりません。聖職者は妻帯を許されず、生涯独身を貫くことになっています。
いっぽう、プロテスタントは人間は努力によって弱さを克服できる強い存在と認識しています。神は教会ではなく信徒各人の心の中にいるとされます。信徒は常に心の神と対話し、おのれを鍛練するよう期待されます。そのため、男女の婚前交際には寛容ですし、聖職者にも妻帯は認められています。
こうした前提を頭に入れたうえで『ダウト〜疑いについての寓話』を観ると、いろいろと腑に落ちるところが出てくるはずです。
まず、修道女の校長先生(那須佐代子さん、好演! 最高演技賞もの)に対して観客が抱く「なんで、こんなに居丈高で、頭から人を信じようとしないの?」という疑問も、カトリックは人間を弱い存在と見なすという原則に照らせば納得がいくでしょう。女性修練士の教員(元劇団「イキウメ」の伊勢佳世さん)に向かって、生徒を信用せずに監視を怠りなくしろと説く冒頭の場面からして、私は「いかにもカトリックだなあ」と思いました。校長先生の個性もさることながら、カトリックの特徴がよく出ている場面です。
しかし、タイトルとなっている「ダウト(疑い)」はカトリックの専売特許ではありません。もう一つ、冷戦たけなわだったこの時代の風潮という要素も無視することはできません。というよりも、こちらのほうが作者が訴えたかったことかもしれません。なんのことかというと、共和党右派のマッカーシー上院議員(ちなみにマッカーシーもアイルランド系のカトリックでした)が弁護士のロイ・コーンと組んで一九五三年頃から展開したいわゆる「赤狩り」で、共産主義者ないしはその同調者として疑われた人々が次々と公的に追放された事件です。なんらかのきっかけで(あるいは何も疑念の余地がなくとも)共産主義者ではないかという疑いを掛けられたら最後、その人がいくら身の潔白を主張しようと、疑いを晴らすことができないという事実が多くの心あるアメリカ人に衝撃を与えたのです。
ところで、この「赤狩り」が進行する過程で明らかになったのは、共産主義者と並んで同性愛者も「疑い」の対象となったことです。これも「疑い」の構造は同じで、疑いに根拠があるか否かは問われることなく、疑った者のほうが疑われた者よりも優位に立つという構図がいつしか出来上がってしまったのです。
しかも、同性愛者糾弾の急先鋒であったロイ・コーン自身が同性愛者であったことが暴露されるに及んで、同性愛の広がりが逆に社会に認識され、「赤狩り」ならぬ「同性愛者狩り」が始まるという始末でした。この時代に創られた戯曲や映画には、リリアン・ヘルマンの原作をウィリアム・ワイラーが監督し、オードリー・ヘップバーンが主演した『噂の二人』、テネシー・ウィリアムズの戯曲など、同性愛者という「疑い」が作品の中核となっている作品が少なくありません。
オットー・プレミンジャー監督の『野望の系列』という政治映画は、共産主義者と同性愛者という二つの「疑い」をドラマツルギーの柱としていたほどです。
このように、一九五〇年代と一九六〇年代は、共産主義者という「疑い」の構造が「同性愛者」のそれへと転移して、まさに「疑い」の時代となっていたわけですが、こうしたコンテクストの中に『ダウト〜疑いについての寓話』を置いてみると、また新しい発見があるようです。
一つは校長先生と対峙する司祭のキャラクターです。舞台は生徒たちに向かって愛と希望を訴える司祭の説教から始まりますが、この愛と希望の呼びかけというのは明らかに、一九六〇年の大統領選挙で、共和党候補のリチャード・ニクソン(「赤狩り」の主役の一人)を僅差で破って当選した民主党候補のジョン・F・ケネディを連想させます。ケネディはじつは弟のロバートとともにマッカーシーに同調する議員の一人でしたが、ニクソンを相手とすると決まるや否や、「疑いの時代」と決別し、ニュー・フロンティアに向かって一致団結して「愛と希望の時代」に入ろうと説く戦略を打ち出したのです。
つまり、思い切って図式化してしまえば、『ダウト〜疑いについての寓話』は、疑いの時代を象徴するマッカーシーと愛と希望の時代のシンボルであるケネディの対決の寓意とも読めるわけで、事実、一九六〇年代の文学作品や映画は、「ケネディ」的なものの最終的勝利を匂わせながら終わるというかたちを取っていました。しかし、『ダウト〜疑いについての寓話』は時代設定こそ一九六〇年代前半ですが、戯曲が初演されたのは二〇〇四年というブッシュ・ジュニア政権下ですから、ストーリーと戯曲構造はもっと複雑になっています。愛と希望を訴える熱血先生たる司祭はおのれの内なる弱さを克服できず、少年愛という誘惑に負けてしまうのですから、ケネディではなくマッカーシーが勝利したことになるのです。イラクの生物化学兵器への「疑い」だけでイラク戦争を起こすことに成功してしまったブッシュ政権下ならではの皮肉な結末でしょうか?
しかも、司祭は司祭で、校長から黒人の少年との不適切な関係を指摘されると、直接の上司たる司教の力を借りれば、校長をクビにできるぞと恫喝して反撃に出るなど、生臭い面も持つ政治的人間であることが示されています。このあたりの弱さと狡さを兼ね備えた理想主義者の司祭のキャラクターを亀田佳明さんは見事に引き出していました。
しかし、この戯曲を本当に面白いものにしているのは、校長先生に呼び出されて面会にやってくる黒人少年の母親(津田真澄さん、うまい!)でしょう。というのも、少年が司祭との不適切な関係にあったことを指摘された母親は、少年自らにそのような傾向があり、誘ったのは少年のほうかもしれないとあっさり認め、家庭でも同性愛を嫌う父親の暴力に少年がさらされていると訴えて、不適切な関係など些細な問題にすぎないのだから少年を卒業するまで学校に置いてくれと校長先生に懇願しますが、これは黒人の置かれた格差社会の実態を絶妙な方法で浮き彫りにしています。
この種明かしは、一方的で絶対的な悪などというものは存在せず、すべては人と人との関係が生み出す相対的な葛藤に過ぎないというLGBT時代のダイヴァシティの到来を暗示したものなのでしょうか? にわかには即断できませんが、とにかく観劇中にいろいろなことを連想してしまう作品でした。
最後に、演出とプロデュースに触れておきましょう。
演出の小川絵梨子さんはやはり小劇場のストレート・プレイでこそ真価を発揮するタイプの演出家であると改めて認識しました。校長先生と司祭のあいだのピンと張り詰めたセリフのバトルも小川さんの演出があってこそと感じました。小川さんは中規模以上の劇場を若干、苦手とする傾向があるようですので、今後は、ストレート・プレイをホームグラウンドとしつつ、大箱というアウェイにも挑戦しつづけていただきたいと思います。
そして、主演と同時にプロデュースも担当された那須佐代子さん。世界的に優れたストレート・プレイでありながら、日本での知名度がいまひとつの作品を選んで上演するために、手作りでプライベート・シアターを完成された功績はなにものにも替えがたいものだと思います。
「良い芝居小屋がないなら自分でつくればいいじゃないか」、この意気込みがこれからの日本の演劇を支えてゆくことになるでしょう。
明日への希望を灯す
杉山弘 (演劇ジャーナリスト)
ハヤカワ「悲劇喜劇」賞は、劇評意欲を最も奮い立たせる優秀な演劇作品を顕彰する。華麗で優美な舞台、思わずもらい泣きしてしまう人情話、破天荒な冒険譚、現代的なテーマに鋭く切り込んだ社会派劇、時代のうねりの中で翻弄される人間ドラマ、運命に抗う人物を克明に追った感動作など、多種多様な芝居が日々上演されている。その中にあって、個人的には、新しい視点や切り口で演劇が本来持っている力を感じさせてくれる作品、言葉を変えれば、想像力を刺激し、新しい発見があり、明日への希望を灯してくれる作品に強い関心があり、これを軸に候補作を絞り込んだ。
二〇一九年を振り返ると、翻訳劇の上演で優れた舞台が多かった。東京芸術劇場/兵庫県立芸術文化センター『Le Pe re 父』、世田谷パブリックシアター×パソナグループ『 CHI MERICA チャイメリカ』、 unrato(アン・ラト)『LU LU』、劇団青年座『SWEAT』、ホリプロ『ドライビング・ミス・デイジー』、パルコ『人形の家 PART2』、シス・カンパニー『死と乙女』、風姿花伝『終夜』、名取事務所『屠殺人ブッチャー』、新国立劇場『あの出来事』、KAAT・KUNIO共同製作『グリークス』、劇団昴ザ・サード・ステージ『8月のオーセージ』などが、舞台成果とともに演劇の多様性を感じさせてくれた。その中にあって、文学座アトリエの会九月公演『スリーウインターズ』は、骨太の戯曲、劇団公演の強み、上演への熱意の三点で抜きんでた演劇の力を示してくれた。
(一)骨太の戯曲
クロアチア・ザグレブ生まれの劇作家テーナ・シュティヴィチッチが二〇一四年に発表した戯曲(翻訳=常田景子)で、四世代にわたるコス一家の物語を、第二次世界大戦が終結した一九四五年、ユーゴスラビア分断が決まった一九九〇年、クロアチアがEU加盟条約に署名した二〇一一年と、三度の冬のシーンを交錯させながら全十四場で綴っている。一九七七年生まれのシュティヴィチッチは、「七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家」からなる理想の国家建設を目指したユーゴスラビア時代に育ち、独裁政権の腐敗やベルリンの壁崩壊に象徴される東西冷戦の終わりでユーゴスラビアが分断され、ナショナリズムの急激な高まりによる内戦の激化した時代に思春期を送っている。目を覆いたくなるような殺人や暴行を見聞きしたことも想像に難くない。このような混乱を招いたのはなぜなのか、という疑問を出発点に、作者は、母、祖母、曾祖母たちの世代が時代とどう向き合い、どのように生きてきたのかに思いを馳せ、女性を軸にした視点から「時代と人 間」を見つめ直している。
オーストリア=ハンガリー帝国下の貴族階級に支配された曾祖母のモニカは、本を読むことや学校に通うことが女には許されない環境の中、メイドとして貴族に仕えながら苦労して子育てをした。ナチスと闘った祖母のロ ーズは、パルチザンに加わっての勇姿とともに理想の国家建設の夢を追いかける。その娘であるマーシャとドゥーニャは理想と現実の狭間に苦しみながら懸命に生きてきたものの、ユーゴスラビア分断に怒り、失望し、後悔する一方で、ある種の空しさに包まれている。そして、独立国家としての新しい道を模索することを迫られたマーシャの娘アリサとルツィアは作者の世代に重なる。イギリスで教鞭をとり、キャリアウーマンとして自立しているアリサ、生き残るために手段を選ばないルツィア。全編を貫いているのは愛する家族を守り、より良い暮らしや社会の実現のため誠実に生きてきた女性たちの姿。悩みながらたくましく生きてきた姿を映し出し、メッセージ色を前面に押し出さない静かな会話から熱い想いを溢れ出させる。構成力確かな骨太の筆致で、クロアチアの悲劇と希望を遠い異国の日本の観客に手渡してくれた。
(二)劇団公演の強み
有志が集まっての劇団という存在は、時として組織の論理を優先させてしまい、所属する俳優やスタッフの自由を奪い、束縛する側面がない訳ではない。少し厄介な存在でもあるが、同じ空間で芝居を練り上げる中で互いの間合いを知り尽くした劇団員による芝居は、長年積み重ねてきた阿吽の呼吸が芝居のアンサンブルを醸し出すことがある。その点で今回の上演は、劇団という存在が大きくプラスに働いた。ベテランから若手までがそろう劇団だけに四世代にわたる配役にも無理がなく、各世代の主役級がこの芝居に集結した。さらにアトリエという小さな空間での競演となり、芝居の緊密度が一層増した。
没落した貴婦人のカロリーナ役に気品を添えた寺田路恵、正しいことをしようとして家族を傷つけてしまい、「呼吸が出来なくなるほど」苦しむヴラドとマーシャの夫婦を演じた石田圭祐、倉野章子のベテラン陣。時代の目撃者として静かな怒りを劇場に解き放つドゥーニャ役の山本郁子や、敗軍の兵士の悲哀を淡々と語るアレクサンダー役の上川路啓志の中堅世代、そして、闘う女性ローズ役の永宝千晶、新しい時代の到来に戸惑うアリサと希望や不安の入り混じった感情を爆発させるルツィアを演じた前東美菜子と増岡裕子の若手と、文学座の俳優の層の厚さと力量を実感することが出来た。同時に、彼らを見続け、その個性を知った上でプロの仕事に徹した美術(石井強司)、照明(賀澤礼子)、舞台監督(加瀬幸恵)などのスタッフワークが芝居を支えた。劇団ならではの強みがこの芝居に注ぎ込まれ、総合芸術としての演劇の力を感じさせる仕上がりでもあった。
(三)上演への熱意
公演実現までの経過もドラマティックだった。発案者で演出の松本祐子は、公演企画を提案したものの、「時代を表現する美術や衣装に経費が掛かり過ぎる」「クロアチアの歴史が日本の観客には分かりにくい」などの理由から本公演とアトリエ公演を二度、見送られている。しかし、松本はそれでも諦めず、家族、とりわけ女性たちを軸にした物語に絞り込み、馬蹄形に客席が取り囲む演技スペースに、テーブルと数脚の椅子、二つのベッド、食器戸棚を置いただけのシンプルな作りに発想を変えた。観客の想像力に委ねることが許されるアトリエという小空間を逆手に取り、ある種「開き直り」にも近い大胆さで企画を再々提出し、ようやく公演実現をつかみ取った。さらに松本はザグレブへ出向いて物語の舞台を肌で感じ、よく知らなかった国のドラマに戸惑いを隠さない俳優たちと劇団内でクロアチアについての勉強会を開き、公演中に作者を招いてトークショーに出演するなど、芝居への理解を深めるための努力も惜しまなかった。俳優たちの演技も稽古中に様々なアイデアが出されたばかりでなく、公演中も日々深化し、ドラマに膨らみが生まれていったという。精神論に聞こえてしまいそうだが、やはり上演にかける熱意こそが、芝居の原動力であり、推進力であることを改めて思い知る機会ともなった。
推薦理由は三点だったが、中でも、上演への熱意を高く評価したい。クロアチアという遠い国から届いた戯曲には、痛みを伴った生々しい肉声があり、その苦しみに耐えながら希望を願って生きる人間の姿が克明に描かれている。人への関心が強い演劇人ならば、誰もが上演を望む作品だったと思う。その反面、実現させるには大きな壁が何層にもわたって立ちはだかる作品でもあった。そこを突破出来た要因として劇団という幸運があり、アトリエ という使い勝手のいい空間があったことは間違いない。しかし、しかし、である。松本の粘り腰と実行力の源泉は「私が感動した作品を舞台で見て欲しい」という情熱に尽きるのではないだろうか。これがなければ日本の観客が『スリーウインターズ』と出合うことは叶わなかったと言っても過言ではない。選考会でも委員三人の推薦があり、最後は全員一致で授賞が決まった。国や環境が異なっても、生きることに苦しみ悩む人へエネルギーを与える舞台になったこと、そして「演劇の力」を存分に示した舞台の受賞を喜びたい。最後にお願い事がひとつ。アトリエでの十六ステージだったことから見逃した方も少なくないと思う。是非、再演を果たして欲しい。
受賞作に次いで推したのがDULL-COLORED POPの『福島三部作』だった。福島・石川町生まれの谷賢一が作・演出し、福島原発事故に正面から向き合った。二〇一八年に発表した第一部「1961年:夜に昇る太陽」に加え、新作となる第二部「1986年:メビウスの輪」、第三部「2011年:語られたがる言葉たち」の三作を休憩時間含め八時間で通し上演した。福島原発事故を語るに際して、その起点となった一九六一年、チェルノブイリ事故に揺れた一九八六年、そして東日本大震災の起きた二〇一一年と、二十五年刻みで物語を描き、半世紀にわたる大河ドラマとして三部作を書き上げた着眼が優れている。さらに、現在も避難生活を強いられている双葉町に暮らしていた農家の穂積家に視点を定め、第一部は長男で原子力研究所の学者となった孝、第二部は次男で双葉町長となった忠、第三部は三男で地元テレビ局の報道局長となった真をそれぞれ主人公に据えた点も秀逸だった。
第一部では双葉町議会が原子力発電所の誘致を議決し、建設候補地の大地主でもある穂積家には町長や東電社員らが訪れ、原子力発電の明るい未来を語って用地買収に応じるよう説得する場面が軸となる。東京五輪を前に、所得倍増計画の恩恵にもあずかれないまま貧しさから抜け出せなかった双葉町にあって、原子力発電に夢を描き、その平和利用に未来を託した思いを物理学者の卵の目を通じて浮かび上がらせる。人形劇にミュージカル仕立て、つかこうへい風のせりふ回しなど手法に工夫を凝らし、祭りのような賑やかさとその後に訪れる寂しさを対照的に描き分けた。続く第二部はウクライナ(事故当時はソビエト連邦)でチェルノブイリ原発事故が起きた際に、対応に追われる双葉町長の姿をクローズアップ した。前年に原発反対派から転向して町長となった忠は、違和感を覚えながら基幹産業として原発を推進し始めていた。 その矢先に事故の報を受け、立ち戻るのではなく、信じてもいない原発について「安全です」と記者 会見で断言してしまう憐れな男を丹念に追いかけた。中でも忠が原発反対の旗をおろして町長選に立候補するまでの討論劇に見応えがあり、ソーントン・ワイルダーの『わが町』を模して、愛犬に人間の営みを俯瞰させ「死者のささやくような声が聴こえますか」と語りかける見立ても効果的だった。第三部ではテレビ局を舞台に報道番組 で指揮をとる真の苦悩が描かれる。「福島県は全滅です」とネットで発信した女子高校生、避難所で放射線被ばくに怯える元教師夫妻、育てていた牛をすべて失った酪農家に加え、原発が建設されて潤った町と事故で避難を余儀なくされただけの町の住民同士のいがみ合いも登場させ、ドキュメンタリー調に被災者の声をすくい上げた。報道の使命と現実とが乖離したために真がある決断をする場面を通じて、警鐘を鳴らす。
故郷の大惨事を数年かけて取材して戯曲を練り上げ、八時間の通し上演が平板にならないよう演出に変化をつけるなど、力作と呼ぶにふさわしい三部作に仕上げた。三作を通して登場する、まばゆいばかりの強烈な光を発する美術(土岐研一)の存在も威圧的で不気味。東日本大震災から九年。復興への道はまだまだ険しい。「第四部」「第五部」と書き続けていって欲しいとエールを送りたい。
選考会で候補作として討論された舞台についても手短に触れておきたい。オフィス・コットーネの『さなぎの教室』は、劇作家・大竹野正典の没後十年を記念した企画。四人の女性看護師による福岡・久留米の保険金連続殺人事件をモチーフにした大竹野の戯曲『夜、ナク、鳥』へのオマージュとして、松本哲也が舞台を宮崎に移して作・演出した新作だ。一人の看護師が夫を殺害する日を起点にして、四人の過去と未来を行き来し、特に中心的人物だったヨシダが看護学校時代から徐々にその怪物性を剥き出しにし、同僚の三人を巻き込み、洗脳し、支配していく過程に主眼を置いて筆を進めている。生命を預かる看護師がなぜ親族の生命を奪っての保険金殺人に手を染めたのか。その経緯を追うことで動機を手繰り寄せようとした。また、公演直前にヨシダ役の女優が降板したため松本が代演し、「瓢箪から駒」の怪演をみせた。選考会でもこの演技を巡って意見が闘わされた。
劇団俳優座『インコグニート』は英国の劇作家ニック・ペインによる脳と記憶とアイデンティティにまつわる物語(翻訳=田中壮太郎、演出=眞鍋卓嗣)。アインシュタインを検死解剖し、その脳を持ち出した病理学者トーマス・ハーヴェイ、てんかん治療のため脳外科手術を受けた患者のヘンリー ・メゾン、そして臨床神経心理学者のマーサ・マーフィーの三人のエピソードを、記憶のプロセス(記銘、保持、想起)に従ってドラマを再構築している。初めて知るエピソードが断片的に進行することに加え、外国人名の二十一役を四人の俳優で演じ分けているため、シーンごとの関係性を整理するだけで手いっぱい。観客への挑戦状のような異色作ではあるが、事前の勉強不足もあって芝居を楽しむまでには至らなか った。
世田谷パブリックシアター+エッチビイ『終わりのない』は、前川知大が作・演出した新作。ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』を原典に、日常と宇宙をつなげる意識の旅が描 かれる。「自分はなぜここにいるのか」「自分は何者なのか」と人生の目的を失った青年の心の放浪を、時空を超えた未来人との遭遇から見つめた作品。背景には地球温暖化での異常気象による未来の地球の姿があり、量子論の多世界解釈を説き明かしながら、地球を離れた人類との意識の交感で「自分探し」をしたところに前川の新境地が示されていた。
『フタマツヅキ』と 『ダウト〜疑いについての寓話』
辻原登 (作家)
『フタマツヅキ』(iaku 東京公演)■
二荒亭山茶花こと鹿野克は十年近くぶりに慰問落語に出演して、いつもの自虐風長口舌の枕のあと、「初天神」に入って早々、肝心の息子の名前が出て来ない、ネタが止まって、 「俺、今どこにいるんだ?」。スグルは頭が真っ白になって高座を下りる。
噺の息子の名前は「金坊」だが、スグルの息子の名前は「花楽」である。息子は落語家みたいな自分の名前を嫌っている。介護施設への就職が決まった彼は、母の雅子に苦労ばかりかけている甲斐性なしの父親に猛反発し、家を飛び出そうとしている。だが、父スグルもまた家を出ようとしている。外に愛人がいるわけではないが。
家といっても襖一つで仕切っただけの狭い二間続き。花楽は小学一年の時、一度は落語家になりたい気を起こし、襖ごしに父親の稽古を聞いていて、「初天神」を覚えたこともある。今は、父も落語も大嫌いだ。舞台は快調に滑り出した。スグルと雅子のなれそめは、ドラマチックでもあり笑劇風でもある。雅子が男に欺されて、死のうとして、飛び降りるのに適当なビルの屋上を物色して、とある屋上に立っていた時、三階の笑劇場に出演中の漫談師スグルがタバコを吸いに上がって来て、彼の漫談を聴く破目になった。 「私、応援します。スグルさんのこと」
これが雅子の口癖で、やがて結婚し、花楽が生まれる。 「スグルさん、落語やって下さい。わたし、応援します」
四十になって、落語家への転身を図るのだが、うだつが上がらず、一門は解散する。スグルには、雅子の応援が鬱陶しくてならなくなる。尾羽打ち枯らしたスグルにとって、慰問落語とはいえ、久し振りの高座は起死回生のチャンスだったが、「息子」の名前が出て来なかった。ここがミソだ。
対する息子花楽の父親攻撃は苛烈だ。家族の紛糾が最高潮に達する。 悲しみの余り、雅子は隣の部屋に襖を閉めて閉じこもり、慟哭する。
雅子「みんな出て行ってよ。終わらせるから、こんな人生」
克「何言ってんだよ」
雅子「入って来ないでよ。入って来たら、舌噛み切ってやるから」
スグル、出て行こうとする。すると、襖の向こうから、行かないでよ、と雅子。「落語やってよ」沈黙の長い時間。舞台の時間が劇場全体を支配した。
突然、スグルが座布団をテーブルの上に乗せ、そこに上がって襖の方を向く。「初天神」を演り出す。最初は雅子に呼び掛けるように。 「おっかあ、おっかあ、ちょっと羽織出してくれ」
ここから父と子の、──花楽は最初はいやいやながらだが、「初天神」の協演が始まる。花楽は、父親が忘れた名前の「金坊」となって……。やがてサゲが来る。雅子がそっと襖を開ける。ウェルメイドの極み、人情噺の真骨頂。古臭いなどと言わせぬ“人生の真味”“人生の快味”がある。襖を挟んだ二間のあいだで起きる、ささやかな劇的アウフヘーベン。
『ダウト~疑いについての寓話』(シアター風姿花伝)■
私は、演技陣の〝巧演〟に魅了されつつ、『ダウト』という戯曲に対する疑いに掴まって、分裂した鑑賞状態から最後まで脱け出せなかった。ラストの、シスター・アロイシスの「嘘です。そんな電話はかけていません」「疑いが! 私の中に疑いがあるのです!」にも、カタルシスは訪れなかった。白々とした疑いだけが残った。そういう意味では、私は、悲劇における「劇的アイロニー」を、あるいはブレヒトの「異化効果」なるものを変則的な形で味わったとも言える。 先ず、冒頭のフリン神父の疑いについての譬話、「星の位置による針路」への疑いは、星が見えなくなった後、筏は風や波や海流によって常に方角を変えているはずだから、説教として成立しない。 フリン神父はシスター・アロイシスの疑いによって学校から追放されることになる。アロイシスの自他に向ける疑いは、フリンが提起した疑いとは全くレベルを異にしたもので、精神科医に相談した方がよい類のオブセッションに過ぎない。 修道院付設の学校を舞台とした物語で、常に神が話題になりながら、肝心の疑いが作者から抜け落ちているのが最後まで気になった。演技陣の〝好演〟にもかかわらず、戯曲に対する疑い、つまり不信が僅かに残ったが、授賞にはためらいなく賛成した。
『帰還不能点』(劇団チョコレートケーキ)■
残念ながら公演を観ることを逸したが、戯曲を読むことが出来た。 昭和十六年夏、総力戦研究所の開戦をめぐる模擬内閣会議に参加した各界の若いエリートたちが、敗戦後、昭和二十五年、当時のメンバーの一人だった、亡くなった男の妻が営む一杯飲み屋に集まって、酒を飲みながら、再度、模擬内閣を戯れに演じる。昭和十五年夏の模擬内閣も模擬なら、当然昭和二十五年のそれは、パロディーのパロディーである。その上、彼ら自身のパロディーにもなる。読んでいて、そこが面白かった。 舞台に奥行きを与えているのは、未亡人道子が、ト書によれば、「照明が変わる。舞台上、ごく狭い部分だけが明るくなる」、その部分を使って演じる劇中劇だろう。 パロディーにパロディーを重ねれば、思いがけない真実が顕れる。それがラストだ。昭和二十五年の秋、一杯飲み屋「とうげ」で行われた模擬内閣は、激論の末、開戦回避の決定を下して、空しく、溜飲を下げて散会する。
『雨花のけもの』(さいたまネクスト・シアター最終公演)■
飽きず奇想を繰り出してくれる「ほろびて」の細川洋平だが、今回のアイデアもまた奇抜で、鬼面人を驚かす展開だったが、回収に失敗したように思う。 社会になじめない若者をペットとして、富豪に売り捌く。格差社会の様態を利用してドラマに仕立てようとしているが、ペットたちが「パドック」で演じる疑似ドラマ(寸劇)と、飼主、店主、ユーザーたちの歯車がうまく噛合わない。何かが欠けている。空回りしている。ペットのさすけすとるしあの恋愛劇もつくりものめいて、文楽の人形劇ほどのリアルさも獲得しない。どこかに齟齬がある。例えば、観客からは見えない邸の庭にある小屋、ホールの二階、赤い橋で、ペットたちに何か悲惨なことが起きているらしい、そのことと、舞台の前面を占めるホールで展開する出来事との間に、もっと強く有機的、構造的関係が配慮されていたら……、という感想を抱く。戯曲上の齟齬、演出上の齟齬……。だが、この齟齬にこそ、この舞台の生々しい、面白さもあったという気がする。しかし、『雨花のけもの』というタイトルは何なのだろう? 蜷川幸雄創設のネクスト・シアターの掉尾を飾る作品だったが、おそらくさらに練り込み、練り上げた上で再演された時、その真価が発揮されるだろう。再結集が望まれる。
不確かで迷い多き現代に
濱田元子 (毎日新聞論説委員 学芸部編集委員)
バスに乗るか、それとも歩くか──。JR目白駅からシアター風姿花伝へ向かう時に、いつも迷ってしまう。目白通りを歩いて十五分あまりというのは、なんとも微妙な距離感なのだ。
決して至便な場所にあるわけではない小空間に、なぜ引き付けられるのか。その答えは間違いなく、俳優で支配人の那須佐代子を軸に、濃密な会話劇にこだわっている風姿花伝プロデュース作品の魅力にある。
そして、観劇後には迷うことなく駅まで歩く。見たばかりの舞台の余韻をじっくり反芻するのには、ちょうどいい距離感なのだ。
今回、受賞作に選んだ『ダウト~疑いについての寓話』(原題:Doubt, A Parable)は、風姿花伝プロデュースの八作目となる。このジョン・パトリック・シャンリィの戯曲は、二〇〇四年にアメリカで初演された。
日本でも文学座やプロデュース公演などで上演されている。例えて言うと、レジナルド・ローズの『十二人の怒れる男』やアーサー・ミラーの『るつぼ』のように、筋も展開も結末も分かっているはずなのに、それでも息を詰めてハラハラしながら、心理戦の行方に見入ってしまう。
コロナをめぐる情報にしても、何が本当で嘘かが不確かになった現代と共鳴する戯曲の普遍性、言葉で緻密に関係性を構築していく小川絵梨子の演出(翻訳も)、そして卓越したセリフで緊迫した空気を醸成する那須、亀田佳明、津田真澄、伊勢佳世という四人の俳優の演技力、スタッフワーク。どれ一つ欠けても成立しなかっただろう舞台の余韻が、まだ残っている。迷わず推した。
新旧価値観のぶつかり合い■
さて、「寓話、たとえ話(Parable)」である。シャンリィは舞台を一九六四年、ニューヨーク・ブロンクスにあるカトリック系のミッションスクールに置く。作者自身、ブロンクスのカトリック系の学校で学んだという。厳格な校長のシスター・アロイシス(那須)は、バスケットボールも上手く、進歩的で親しみやすいフリン神父(亀田)に対し、ある「疑い」を抱く。学校で唯一の黒人生徒であるドナルドと不適切な関係にあるのではないかというのだ。
「疑う・信じない」という意味の「ダウト(doubt)」は、ラテン語のdubitāre、「二つ(duo)のうちから一つを選ばなければならない」のが原義という。物語はその「二つに一つ」、シスター・アロイシスの抱いた「疑い」が真実か、真実でないかを巡って展開していく。
六四年とはどういう年なのか。戯曲でもフリン神父の冒頭の説教で言及されるように、前年に米国史上初のカトリックの大統領であったジョン・F・ケネディが暗殺された。新時代の到来を予感させた若々しい大統領を襲った悲劇に、「人々は一体となって先の見えない不安を感じました」とのフリン神父のせりふは、戯曲を読み解く一つの鍵だ。
さらに戯曲では明確には語られていないが、カトリック教会を巡っては六二年に始まった第二バチカン公会議が、それまでの教会の伝統を揺るがしつつあった。それもまた教会関係者には、先行きの不安を抱かせるものであっただろう。公民権運動が高まるなか、米国における人種差別を禁止する公民権法が制定されたのも六四年だ。
既存の権威がよりどころとしてきた古い価値観と、時代に即した新しい価値観。その二つがぶつかる中で、自身の立場や信念が脅かされたと感じる時に生じる「不安」や「疑い」。その時、人はどう振る舞うのか。シスター・アロイシスを通して浮かび上がってくる人間への普遍的な問いが、作品に通底する。
シャンリィはあちこちに両義的なピースをちりばめる。フリン神父がメモを取る時に使う(万年筆ではなく)ボールペン、フリン神父の伸ばした爪、「雪だるまのフロスティ」のような非宗教的なクリスマスソング……。シスター・アロイシスが、それらへの敵愾心をあらわにするさまは、ある意味、滑稽に映る。フリン神父が示唆する「不寛容」や「分断」のタネになりかねない。だが、信仰や信じてきたものを守り、生徒を守ろうとする者にとっては、譲れないところというのも理解できる。
「フェイクニュース」時代に■
戯曲の書かれた〇四年という年も鍵となるだろう。米同時多発テロの二年後の〇三年、イラクが大量破壊兵器を保有しているという「疑い」や、イラク指導者とテロ組織アルカーイダが協力関係にある可能性があるといった理由で、英米を中心とした有志連合は国連安保理決議のないままイラク戦争に突入した。しかし、その「疑い」が招いた結果は、どうだっただろう。
一方で、米紙「ボストン・グローブ」がカトリック教会の数十人の神父による児童への性的虐待を報道したのは〇二年のことだ。それを教会が組織ぐるみで隠蔽してきたというスキャンダルだった。米映画『スポットライト 世紀のスクープ』(一五年公開)でも描かれ、米アカデミー賞作品賞・脚本賞を受けた。好ましい人物に見えるフリン神父にも実は裏の顔があるのかもしれない。舞台を見ながら、さまざまな考えが頭をよぎっていく。それこそが、シャンリィが仕掛けた「寓話」の狙いなのだろう。
今回の上演は、初演から二十年近くたっているが、「寓話」はその意味合いをより強くし、まさにタイムリーな上演だと感じた。
「フェイクニュース」である。
ネット社会が進み、タブレットやスマホの中は真偽不明の情報であふれかえる。国民の情緒的支持を基盤にするポピュリズム政治の台頭とも深くつながる。シャンリィは、二〇一六年のトランプ大統領の誕生をまるで予見していたかのようだ。それとも、その十年以上前に萌芽を社会に見てとっていたのだろうか。いずれにしても、真実と嘘の見分けがつけにくくなっている今の世界の危うさを、この戯曲は痛打してくる。
「ポスト・トゥルース(脱真実)」という言葉まで生まれた。「火のないところに煙はたたない」と言うが、フェイクニュースはたとえ火がなくても真実を燃やしかねない。
緊迫感あるせりふの応酬■
さて、シスター・アロイシスの「疑い」の根拠となる「火」はあるのか。軸となる腹を探り合うようサスペンスフルな心理戦を、那須と亀田が緊迫感あふれるやりとりで聴かせてくれる。
両者の立ち位置は対照的なのだが、共に見えたままではないかもしれない。小川は注意深く、予断を排するようニュートラルに、そして、言葉の裏で動いていく感情を丁寧に、スリリングに見せていく。ある状況下で人間はどのように振る舞うのか。それこそが芝居の醍醐味だ。
二人の最初の対決は校長室だ。フリン神父を頭っから疑ってかかっているシスター・アロイシスの険しい表情や口調に、厳格な校長としての強固な意志、自身の信じる正義感を映す。すべての毛穴からフリン神父への生理的な嫌悪がにじみ出る。昔なら異端審問、今で言うなら「テロとの闘い」といった感じさえする。
対するフリン神父は、冒頭の説教のモノローグから、亀田が粒だったセリフで引き付ける。ここで語られることが、この先展開していく話の補助線となるだけに、言葉の意味を会衆でもある観客にきちんと届けてくるのはさすがだ。会衆に寄り添い、悩みや不安を共有しようというフリンの好感度の高さは、亀田のニンによるところも大きい。ジャージー姿になり、生徒にバスケットボールの指導をするモノローグも、親しみやすい好人物像をあますところなく伝える。
それだけに、シスター・アロイシスによって示唆される疑惑の主としての落差が、観客を動揺させる。そんな観客と同じ目線に立つのが、若く教育熱心なシスター・ジェームス(伊勢)だ。フリン神父に感じの良さを抱きながら、シスター・アロイシスには「自分の安らぎを求めるだけでは、簡単に、惑わされる人間になってしまう」と事なかれ主義を批判され、猜疑心を植え付けられていく。伊勢は屈託がなく、教育に情熱を持つ若いシスター・ジェームスがぴたりとはまる。そのまま観客の不安や不信と見事に共振させていく。
白か黒か──。二項対立の緊迫した空気が、サッと変わる。挟み込まれる第三の視点が、またまた劇的に観客を揺さぶっていくという作劇が巧みだ。シスター・アロイシスと、ドナルドの母であるミラー夫人(津田)との会話は、短い場面だが、論議に一石を投じてパンチがある。那須と津田のせりふの応酬に聴き応えがある。
フリン神父にいかなる疑惑があろうと、「グレー」のままのほうがいいと、黒人であり、同性愛者かもしれない息子を思う母の心情を、津田の知的な語り口が説得力を持たせる。力のある俳優が演じることで、グッと場面がクローズアップされた。
戯曲は、結論を示さず観客を不確かさで宙づりにしたままで終わる。それはある意味、何もかもが不確かな現実世界を映しているかのようだ。多くを観客にゆだねたままの芝居は、シスター・アロイシスが強調する「簡単に、惑わされる人間」にならないために、考え続けなければいけないという、作者からのメッセージとも受け止めたい。
「疑い」は、それ自体は決して毒ではなく、思考の出発点でもある。「信じる方が楽」という言葉にもハッとさせられる。情報の洪水の中で、しらずしらずに受け身になってしまいがちな現代人への警鐘でもあろうか。この点ではシスター・アロイシスに軍配を上げたい。
微細な表情の変化や、言葉の小さなニュアンスがビビッドに伝わってくるのは、シアター風姿花伝という小空間でなればこそであろう。津田をのぞいて小川とこれまでタッグを組んできた顔ぶれというのも奏功した。演出家と俳優が培ってきた信頼関係が、質の高い上演成果につながった。
演劇の多様性の砦に■
コロナ禍による公演の中止や延期、客席数制限などで演劇界が大きな打撃を受けた。そのせいもあるのだろうが、チケットが売れる著名なタレントを起用した商業的な演劇が以前にもまして増えてきた感がある。劇場に多くの観客が訪れ、裾野が広がるのは歓迎すべきことだ。ただ、それだけでは演劇の未来が先細りしてしまう懸念がぬぐえない。
風姿花伝プロデュースのような、作品至上主義でキャスト、スタッフにこだわったモノづくりは経済的にも決して容易ではないだろう。商業主義とは一線を画した、日本のアート系映画館の草分けであった「岩波ホール」の閉館発表が、文化芸術界に影を落としている。だからこそ、シアター風姿花伝には演劇の多様性を守る砦の一つとして、灯をともし続けていってほしい。僭越かもしれないが、今回の授賞にはそんな思いもこめたつもりである。
時代えぐる創作戯曲も■
個人的には、次点としてKAAT神奈川芸術劇場プロデュース『未練の幽霊と怪物─「挫波」「敦賀」─』(岡田利規作・演出、内橋和久音楽監督)を推した。原子力政策と五輪という、戦後の日本社会が連綿と抱えてきた夢とひずみを、岡田が夢幻能の様式を用いてアイロニーたっぷりにあぶり出した。特に新国立競技場のデザイン案が白紙撤回された建築家ザハ・ハディドをシテ(森山未來)にした「挫波」は、能の囃子のようなダクソフォンの響きに乗せ、森山の身体がザハの競技場を見事に出現させた。まさに鎮魂である。賛否が渦巻いたコロナ下のオリンピックの一つの断章を記憶する、象徴的な作品といえよう。
候補に上がったiaku『フタマツヅキ』(横山拓也作・演出)も忘れがたい。若者が生きづらさを抱える時代、古典落語「初天神」をモチーフに使いながら、どうしようもない人間を優しく包み込むのは横山の真骨頂。まさに立川談志の言う「人間の業の肯定」のようなドラマであった。
選考の対象にはならなかったが、さいたまゴールド・シアター『水の駅』(太田省吾作、杉原邦生演出)を二一年の成果として特筆しておきたい。亡くなった蜷川幸雄が〇六年に創設した高齢者演劇集団の、十五年にわたる活動の集大成だ。蛇口の壊れた水道に、何らかの渇きを抱えた人々が訪れては去っていく。テンポのきわめて遅い動き、セリフの一切ない沈黙劇だが、年齢を重ねた身体が豊穣な時を紡ぎ、人生の年輪を雄弁に語りかけてきて圧倒された。
そして渇いているのは、私たち自身でもあるのだ。干からびてしまいそうなこの世界で、演劇は、劇場は、潤いをもたらす存在であり続けられるだろうか。
- <<前の記事:第九回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考結果
- 第十回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考結果:次の記事>>