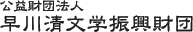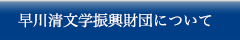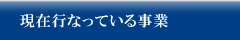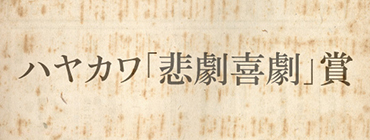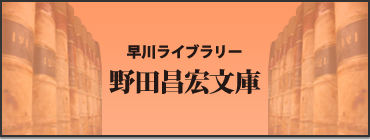第六回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考委員批評文
演劇は仕事である
今村忠純(近代文学・近代劇文学)
『消えていくなら朝』■
宮田慶子が新国立劇場の芸術監督に就任したのは、2010/2011シーズンからである。それから2017/2018シーズンまでの八年間の全仕事を経ての決算となった最後の作品、それが蓬莱竜太の書き下ろした『消えていくなら朝』(の演出)だった。
新国立劇場の開場記念公演のために書き下ろした井上ひさしの『紙屋町さくらホテル』の演出は、当時芸術監督であった渡辺浩子である。「当時」渡辺は、二代目の芸術監督だった。一九九七年だったのだが、さまざまな紆余曲折を経ての開場であり、あまりにも永い助走あってのことだった。
蓬莱新作の宮田演出は、そこから数えてすでに二十一年目に入ってからのものなのだが、いやがうえにもこうした新国立劇場物語を通じてこの劇の輪郭を考えてみることになったのだった。
すると平成という元号は、天災、人災を問わず大災害の時代の徴であったばかりではない、世界をおおいつくした(民族)テロ、それは同時に平成が、宗教の時代であったことを意味していた。それはいまも続いているのだが、宗教の動向を注視すること、そこに平成が鏡のように映し出されるかもしれないと。
それは世紀末から新世紀にまたがる世界の終末論に通じてもいたと思われる。
国会が宗教法人法の改正をめぐっての本格的な論議を開始し、宗教活動の監視態勢と法律とがつよく結びついていく、それは元号が平成にあらたまってからのことである。
あるいは政教分離基本法を制定するなど、法的整備の急務がいわれる一方で、あきらかに「宗教」活動の集票能力を利してのものであっても、けっして政治活動ではないと主張する例もきっとあるだろう。また宗教活動の法的規制の限界の説かれる事例は、この劇にもあった。教育現場における柔道や剣道などの武道、の未履修者の論理が容認されるなどがそれである。
プログラムには蓬莱竜太と宮田慶子との対話があった。「家族を通して世界の普遍を描く」というのが題名である。「世界の普遍」は「家族」にある。そしてそこに「宗教」があった。
『消えていくなら朝』にならえば、この家族をおおっているのは、母の君江がもたらした「神の子」という宗教(活動)だった。その「神の子」の信者にとっては「ヤーウェ」だけが「真理」と母はいまも訴えている。
羽田家の老いた家長たる父の庄次郎ばかりではない、庄吾と定男(僕)の二兄弟と妹の加奈が、これにひきこまれ、ひきまわされてきた。
定男 伝道に行った家が同級生の家でさ、次の日クラスで笑われてたりさ、してるんだよ。そうやって学校にいるしんどさとか、わかってた?
君江 何よそれくらい(笑)もっとひどい迫害を受けてる「神の子」はいっぱいいるから
定男 だから「神の子」じゃないから(笑)! こっちは
君江 何?
定男 七夕集会参加しません、誕生会参加しません、クリスマスやりません、盆踊り行きません、お祭り行きません、正月やりません、校歌歌いません、国家歌いません、大会があるから学校休みます、柔道、剣道の授業はやりません、給食のクジラ肉は食べません、ねぇ、どんな目で見られながら学校生活を送ったか、わかってる? 自分は大人になってからやってるけどさ、子供の世界は大変だよ、(庄吾に)そうだよねぇ?
庄吾 うーん(笑)
定男 そういうの学校で俺たちにどういう影響を与えるか、考えてた?
君江 そんな小さなこと(笑)
定男 小さなことじゃないから(笑)子供にとったら
君江 アンタがわかってない。正しい行いをしてるの。アンタらのためを思ってそうしてるの
緊迫した「対話」と、その緩急がスリリングだ。「対話」の横合いから口を挟み、よどみなく別の新しい「対話」が始まる。「対話」のすれちがいとタイミングからこの家族の問題、家族の歴史の息づかいが浮かびあがる。
宗教活動に傾倒する母親君江(梅沢昌代)の独善性は、無気味なおだやかさと発作的な狂気をはらむ。妹可奈(高野志穂)の狂乱、とり乱しかたは尋常ではなく、兄庄吾(山中崇)の理屈とやり場のない気持ちに困惑、同情もする。父庄次郎(高橋長英)には、もうここに居場所はない。定男(鈴木浩介)の劇作家としての矜持と自負。劇作家と新しい「家族」をつくろうとしている売れない女優レイ(吉野実紗)は、日本人の父とフィリピン人の母とのあいだに生まれていた。羽田家という家族の形を静かに批評する。
この役者たちの入魂の演技に拍手を送りたい。
羽田家の次男定男(僕)は劇作家。定男は海辺の町に住む家族に久しぶりに会うことになった。劇の幕はそこから上がる。
父の庄次郎は、母との離婚を考えている。「そのつもりだ」と定男に言っていた。しかし「まぁ、あの人の宗教は離婚禁止だからな」とも。定男の兄庄吾はまだそのことを知らない。しかしまず父の口から定男の耳にいれておく、妹の可奈がそのようにとりはからった。まったく短いオープニングで、こうして家族の一人一人の関係、その全情報を注意深くしかもすばやく庄次郎と定男の「対話」で伝えていく。いまは年金暮らしで暇にまかせて家の増築に一人手間をかける庄次郎の老いた余生が見えてくる。海の音が風にのって聞えてくる。日が西に傾きはじめた。
日が落ちて、十八年ぶりに羽田家の親子全員が会しているリビング。
そこで定男がいちばんに切りだしたことが「国立の劇場で。まあ演出はしないんだけど、本だけで」、そこでこの家の、家族のことを題材にして「本」を書くことにした、つまり定男が、家族一人一人をモデルにして戯曲を書くということだった。
別にいえばこういうことになるだろう。これから定男が書こうとしている劇のプロットの先まわりをして、舞台では羽田家の家族総出の劇はすでに始まっている。だからこれは、もはや羽田家の家族一人一人をモデルとして定男が書いた劇なのではない。
「演劇とは何だろう」という問いもおそらくここから生まれてくるはずである。あるいは「演劇は仕事か」と定男に問うのは会社員の庄吾なのだが、この問いはおそらく演劇人一人一人が自らに問いなおさなければならない言葉なのである。いかなる「仕事」(「職業」)であれ、それに謙虚であり、つつましいものでありたいと願うばかりである。
「演劇は仕事か」と演劇人が自らに問うように、庄吾もまた自らに問わなければならない。「会社員とは何か」と。いずれ「仕事」であることにおいて同列であるなどと私は言うのではない。演出家宮田慶子は、「演劇の社会的地位」と捉えなおしていることもこれと無関係ではないだろう。
そこでこの劇の登場人物についてあらためて考えてみなければならない。この劇が私戯曲であるという蓬莱の言葉に誘導されていたことにもっと早く私は気づくべきだったのかもしれない。この劇は、ありきたりの家族劇ではなかった。寓話仕立てのすこぶるアイロニカルな劇だったのだから。見てきたとおりの家族一人一人の役まわりがどのように記号化されていたかに注意しなければならないということである。
「神の子」の信者である母の君江(宗教)、劇を「六十本以上作ってきた」定男(表現者、劇作家)、生真面目な会社員の兄庄吾は営業マン、ドラえもんのフィギュアなどを蒐集するマニアックな趣味が生きる支えの妹可奈、そして身を粉にして一家を養い老いた父庄次郎、というこの三人は普通の生活者である。定男に同行したレイは、定男とこの海辺の家とのいわば蝶番になろうとしている。しかしレイとまた宗教家、芸術家(劇作家)、生活者の蝶番にはなりえない──。
現代演劇を上演するために、はじめてわが国につくられた国立の公共劇場、その新国立劇場のあるべきかたちを、これからも、われひとともに全力で問いつづけていくこと、そのことも深く重要な課題となってくる。
『ウィルを待ちながら』■
「シェイクスピアは、なんでもないものはない『没思想』(と逍遥が云った)の海である」、と井上ひさしが書いたのは一九七一年(『パロディ志願』)。「没理想」と「没思想」、井上ひさしの説くところは留保しておくのだが、とにかくシェイクスピアは「没思想」の海、とそのように井上ひさしが書いたのと同じころにシェイクスピア劇の全訳に着手したのが小田島雄志である。この画期の訳業こそが、わが国のシェイクスピア上演史にルネッサンスの気運をうながしたことは疑いえないと私は思っている。
その刺戟は一九七四年の年明け早々に現れた。井上ひさしが西武劇場(現パルコ)開場記念公演のために書き下ろしたのは七三年の『藪原検校』、この上演についで同年十二月のうちに「書き下ろし新潮劇場」として刊行されていた『天保十二年のシェイクスピア』の同劇場上演がそれである。井上はこの劇で、シェイクスピア劇全三十七作品のプロット、せりふをないまぜにして新たな物語をつくっていた。演出は出口典雄。
蜷川幸雄演出のシェイクスピア劇の幕が上がるのは、日生劇場。同じ七四年五月、小田島訳の『ロミオとジュリエット』だった。
小田島全訳による出口典雄演出は、そのあくる年、一九七五年から始まっていた。『ウィルを待ちながら』に出演した役者一(田代隆秀)は言っていた。「小田島雄志先生の全作品上演達成が一九八一年。七年がかりだった」。田代は、このシェイクスピア・シアター創立メンバーの一人。
シェイクスピア劇全訳は、次いで松岡和子が試みており、蜷川演出がこの松岡訳を継承し、テクストとする。
新世紀をむかえて蜷川幸雄演出は、さらに次世代の河合祥一郎訳のシェイクスピア劇上演にも及んだ。そしてここにきて河合は、シェイクスピア劇全訳の決意をかためたと私には思われる。河合祥一郎の新作『ウィルを待ちながら』を読み、あらためてそのように理解しているところだ。こまばアゴラ劇場での公演は、演出ももちろん河合である。
チラシはこの劇について「シェイクスピア全40作品から名台詞を集めて1本の芝居に!/ウィルを待ち続けるふたりの役者が口にする名台詞の数々!/シェイクスピア演劇の真髄に、ややベケット風に迫る新作芝居!!」とうたっていた。
このチラシのコピイにならって『ウィルを待ちながら』の内容に解説を試みれば次のようになる。「シェイクスピア演劇の真髄」は、劇の名せりふにこそあるという見立てに従い、ゴドーを待ちつづけるウラジミールとエストラゴンのように、ウィルを待ちつづける二人の役者が、例えばその名せりふがどの作品にどのようにつかわれているかを当て合うゲームをするなど、名せりふを口にしつづける、つまり「ややベケット風に迫る」。
「見立て」とは「シェイクスピア演劇の真髄」は名せりふにありと見きわめた劇作家にして研究者、翻訳家、演劇評論家である河合祥一郎の「世界」をさす。そして「仕掛け」とは、いかにその「世界」を観客に、つまり御見物衆にとどけるか、そこに「趣向」をこらすところにある。河合にはすでに『ゴドーを待ちながら』の新訳とそれによる新演出もあった。
そこであらためてシェイクスピア演劇の名せりふを次々と口にする役者一と役者二の二人は、同世代で同時代を生きて来た七〇歳凸凹の年恰好の田代隆秀と高山春夫だったことを思い出しておかなければならない。先述の小田島雄志全訳の開始とともに演劇現場にたずさわり、ともにシェイクスピア役者として俳優の道を歩きつづけてきた、かけがえのないそれぞれの一代記と名せりふによってよみがえらせてくれていたのだった。
さらにいいかえれば、二人の一代記を通じて一九七〇年代以降のわが国のシェイクスピア演劇翻訳上演史のはるかなる発展と進化・深化を測定することになっていたのである。
「古典」となる資格を有した傑作
鹿島茂(フランス文学者)
『消えていくなら朝』──内的規範なき核家族の行方■
候補作七作のうち、観ている四作について語っていきたいと思います。
蓬莱竜太作、宮田慶子演出、新国立劇場『消えていくなら朝』。
ここのところ、人類史というものに熱中しているのですが、一つ驚いたのは、最新の研究では、地球中に拡散した初期人類は、はじめから一夫一妻で、しかも核家族だったということです。そのわけは、人は、子供が自立するまで時間がかかりすぎるので母親一人では育てることができず、父親の手助けを必要としたこと。もう一つは、狩猟採集が中心だったので移動せざるを得ず、そのためには核家族でいる以外にはなかったからです。
この発見は、人類は原始時代は乱婚状態で大家族だったが文明が進歩するにつれて核家族となったとするモーガンの古代社会観とはまったく逆で、元から核家族だったものが、大家族という中間段階を経て核家族に戻ったというのが正しい見方のようです。
このことを頭に入れて、近年、内外で非常に増えてきた家族ドラマを見てみると、どうなるでしょう?
少し前までは家族ドラマの模範だったイプセンやストリンドベリーは日本でも新劇のレパートリーとして広く受け入れられ、日本の劇作も多くはこのモデルに従ってきましたが、それはノルウェイやスウェーデンが日本と同じ直系家族という、父母・息子夫妻・子供という三代が同居する家族類型の国だったため、日本人はとても理解しやすかったからです。つまり、直系家族の抑圧的な精神風土から逃れようとして、自我に目覚めた主人公がタテ型の家の構造とぶつかるというのがドラマを構成していたのです。
ところが、戦後も七十年以上たつと、こうした直系家族も崩壊し、日本でも父母子供という核家族が当たり前になりました。つまり、アメリカの占領を経て英米型の核家族に変容したのですが、しかし、何百年も前から核家族でやってきた英米とは異なり、日本には核家族が核家族として成立する内的規範というようなものが存在しません。すなわち、親はできるだけ早く子供の独立を促し、親は親、子供は子供というかたちで、それぞれに自立した個人として家族を構成するというような風土がいまだ生まれてはいないのです。
たとえば、各人が考えていることをできる限り言葉にして伝えるという規範は日本の家族の中にはありません。換言すると、失われた直系家族の「無言のコミュニケーション・システム」が核家族になってもそのまま続いているために、言葉によるコミュニケーションという核家族の文法が成立しないまま核家族が営まれているのです。
問題はもう一つあります。それは寿命が二十年伸びたことで、精神的成熟もまた二十年後ろ倒しになっていることです。親は二十代か三十代で親となってもまだ精神的には子供のままで、子供が子供を育てることになります。また子供は子供で四十歳近くになるまで成熟しません。
さて、以上の前提を踏まえて『消えていくなら朝』について考えてみると、どのようなことがわかってくるでしょうか?
羽田家という核家族の核を成している羽田庄次郎と君江の夫婦ですが、これは核家族第一世代ともいえる団塊の世代に当たります。彼らの親の世代は多くが職住近接の第一次産業従事者で直系家族を成していました。庄次郎・君江の世代はこの親の代の直系家族を主要敵と見なして、その大半が都市近郊に住んで夫はサラリーマン(第二次および第三次産業従事者)、妻は専業主婦という、いわゆる近代的家族を形成しましたが、職住近接ではなかったため、専業主婦の妻は現代でいうところのワン・オペ・マザー(家事・育児などを一人で行っている母親)とならざるをえませんでした。その結果、父親は家族のために収入を増やそうとすれば長時間労働・遠距離通勤をせざるを得ず、理の当然として家庭不在となり、妻とも子供たちともほとんどコミュニケーションを取ることのできない寡黙な父親となるほかありませんでした。
一方、母親はというと、まだ子供を保育園に預けるという世代ではありませんから、専業主婦として、子供の幼いときには過度の密着、子供が学童期となると暇を持て余すということになりました。君江はそのため、ある意味、「気晴らし」として新興宗教にのめりこみ、子供を巻き添えにします。
このように、羽田家の場合、母親が新興宗教にはまったという点が特殊ですが、しかし、構造的にみれば、この新興宗教は「暇の代償行為」という意味で他と置き換え可能なものと見なすことができます。
また、羽田夫妻は、その親の世代がしたような第一次産業と共同の子育てに夫婦二人でかかわることによって自動的に精神的成熟を遂げるという機会には恵まれてはいませんでした。つまり、夫は第二次・第三次産業従事→都市近郊生活→長時間労働・遠距離通勤・家庭への無関心、妻はワン・オペ育児→単独家事労働→余暇消費という時代がつくる制約から日本的核家族を成したがために、未熟なままの大人でいるほかはなかったのです。
では、そうした成熟の機会をもてなかった親に育てられた子供たちはどうしたのでしょう。
一般に直系家族というものは、権威は名目的には祖父→父親に、実質的には祖母→母親にあるものですが、本当のところは、さながらツー・バイ・フォー工法の家のように家族という構造体それ自体が権威を支えていたのです。ところが、産業構造の変化と占領軍の政策で直系家族が否定の対象となり、核家族が主流となると、構造体が支えていた権威を一人の人間である父ないしは母が支えなければならなくなりますが、右に指摘したように、この父と母も未成熟のままですから、権威を支えるなどということは土台不可能であり、その結果、子供たちは権威のない父と母の発するアト・ランダムな命令に振り回されることになります。しかし、相手は父と母ですので、権威がなくても権威があると思いこまなければなりませんから、かなり無理することになります。
すなわち長男は父に代わって母を支え、「権威の代行」をつとめようとしますが、やがて無理が祟って破綻に追い込まれます。長女は母に代わって父を支えるために「スカートを履いた女の子」として振るまいますが、同じように破綻せざるを得ません。
では、次男はというと、「権威のない権威」ないしは「権威を装おうとする権威」が四人もいる家庭に戸惑って、一刻も早く家を出て「見えざる権威」から逃れようとしますが、それはじつのところ、世間的名声という「外側からの権威」を獲得して、「権威の不在」を埋めようとする心理が働いていたようなのです。
さて、作品とも演出ともあまり関係のないところで家族論を展開してしまいましたが、それは、選考会でも指摘したように、優れた家族ドラマは個々の家庭の個別的なドラマを扱いながら、普遍性を志向するものだからです。つまり、『消えていくなら朝』は作者の私演劇でありながら、そのうちに普遍性へと通じる骨太の構造を有していて、すでに「古典」となる資格を有する傑作となっているのです。この作品は作者の代表作となると同時に、日本演劇の古典として何度も上演されることになるでしょう。
『豊饒の海』──冒険精神にあふれる舞台■
三島由紀夫原作、長田育恵脚本、マックス・ウェブスター演出、パルコプロデュース『豊饒の海』。
ここ数年、私演劇的な家族ドラマが増えてきましたが、その一方では、現代オペラや現代バレエのような大胆な演出技法を駆使する作品もまた増えてきて、両極端化しているようですが、後者の傾向の作品から一つ選んだのが『豊饒の海』です。
『豊饒の海』を貫く思想はいうまでもなく輪廻転生です。では、それまで仏教思想などになんのかかわりもなかった三島由紀夫がなにゆえに輪廻転生などに興味をもつようになったのでしょうか?
思うに、強烈な自己愛の人である三島由紀夫が死を射程に入れた晩年において、自分の名声と作品を死後にも生き続させるには、その影響力を輪廻転生的に何度も蘇生させるほかないと考えたからではないでしょうか? つまり、作品が読まれたり上演されたりするたびに、三島由紀夫は輪廻転生するのです。
この意味で輪廻転生の小説である『豊饒の海』を戯曲化した今回の試みは、永遠の輪廻転生を願った三島由紀夫にとっては願ったりかなったりのことだったに違いありません。
三島由紀夫は自分には無意識というものがなく、すべてを意識のコントロール下に置いているというのが自慢でした。なにしろ出生時に浸かっていたタライの縁が光っているのが記憶にあったという人ですから、もし、三島由紀夫の脳が保存されていたら自刃した瞬間にもこれを意識していたことが証明できるかもしれません。
ではそうした自意識の人である三島由紀夫は自分というものをどのようにイメージしていたのでしょうか?
行動したり思考したりする自分を脇で眺めているもう一人の自分がいるというイメージに違いありません。
ここまでいえば、松枝清顕とその輪廻転生した人物を横から眺めている本多繁邦こそアナザー三島由紀夫であり、その本多繁邦を眺めているわれわれは、三島由紀夫によって輪廻転生の環にはめ込まれたアナザー・アナザー三島由紀夫であることがわかるでしょう。
長田育恵の脚本とマックス・ウェブスターの演出はこうした空間化された輪廻転生の構造をうまく生かしているといえます。
賛否両論の作品ですが、私はその冒険精神を高く買いたいと思います。
『遺産』『チルドレン』──大状況を題材にしたドラマ■
古川健作、日澤雄介演出、劇団チョコレートケーキ『遺産』。
家庭のような小状況を扱う作品が多い中、劇団チョコレートケーキは歴史の中の大状況を選んでそこにドラマツルギーを見いだすという方法を採用していますが、七三一部隊の人体実験を舞台設定として選んだ『遺産』は緊迫感溢れた芝居となっていました。
七三一部隊やナチズムがテーマとして選ばれる場合、極端化された功利主義が最終的に行き着くニヒリズムが問題となるわけですが、『遺産』を観たかぎりでいえば、七三一部隊の本当の問題はこのニヒリズムがあまり意識化されていなかったことにあるのではないかと思いました。ならば、ドラマツルギーを見いだすべきは、意識化されたニヒリズムと意識化されていないニヒリズムの対立ではないでしょうか? 日本人には意識化されたニヒリズムを体現するような人物はなかなか現れませんが、劇作ですから、こうした人物造形は許されるはずです。次回作に期待したいと思います。
ルーシー・カークウッド作、小田島恒志訳、栗山民也演出、パルコプロデュース『チルドレン』。
ルーシー・カークウッドも歴史の大状況を題材にするという点では劇団チョコレートケーキと同じですが、この劇作家の特徴は、家庭の三角関係などの小状況をこの大状況の中に埋め込み、その埋め込みから生まれるドラマツルギーで芝居を成り立たせるという方法を取っていることです。この方法の場合、うまくいくか否かはひとえにはめ込まれた小状況がそれ自体で自立しえるほどの緊張感があるかどうかにかかっています。この条件を満たしていないと、それは一昔前に逸った社会主義リアリズムの「主題の積極性」というものになってしまいます。また小状況をはめ込まれた大状況もまたそれに対する歴史的な理解が深いものでなければなりません。そうでないと、たんに舞台を借りたということになるからです。
『チルドレン』は、はたして、この二つの条件を満たしているといえるでしょうか?
以上、総括すると、小状況と大状況への両極化という傾向はここしばらく避けられないものと思いますが、なんとかそれを止揚するような作品が出てきてほしいものだと思います。
演劇の力を感じる新しい視点
杉山弘(演劇ジャーナリスト)
受賞作は新国立劇場公演『消えていくなら朝』に決まった。モダンスイマーズの座付き作家・蓬莱竜太が書き下ろし、宮田慶子が演出した家族劇。二期八年にわたり芸術監督を務めた宮田の任期最後の作品でもあった。
東京で劇作家として活動する中年の男(鈴木浩介)が、波の音の聞こえる故郷、おそらく蓬莱が思春期を過ごした北陸の海辺の町へ帰って来る。突然、離婚を切り出す父(高橋長英)、宗教の教えに従い不倫はしていないと反論する母(梅沢昌代)、要領良くチャランポランに生きてきた、と弟を責める兄(山中崇)、男の子のように育ち不惑を超えても独り身の妹(高野志穂)。十八年ぶりに家族五人がそろった羽田家で、仕事や人生、結婚、親子関係、幸福感などを巡り、家族一人ひとりが積年の思いをぶつけ合う。
蓬莱本人を思わせる劇作家の設定を含め、赤裸々なドキュメンタリーを見ているような錯覚に陥る。「結婚生活を耐えてきた」と互いに言い出して口論する父と母、母の願いを受け止めて宗教の世界に生きようとして失敗した兄、父の思いをくんで「理想の息子」を演じてきたことに疲れを感じている妹の人生がリアルに迫ってくる。非常時や貧困に追われる時ならば結束出来たはずの家族も、豊かで平和な暮らしの前には弱く、旧来の家族像では共同幻想が抱けない現実も丁寧に描かれる。「家族を思うことを強要するのは暴力」と叫ぶ劇作家のせりふは蓬莱の本音でもあるのだろう。家族が混乱していく過程を笑いに転化させる一方、この家族を外から眺める存在として劇作家の恋人(吉野実紗)を登場させて自問自答する姿を映し出した手法もうまい。
また『LOVE30~女と男の物語~』の一話『兄への伝言』(二〇〇六年)以来、蓬莱との信頼関係を築いてきた宮田が、跳ね馬のように暴れる戯曲を懐深く受け止めた。たとえてみれば、渾身で投げ込まれる投手の剛速球を荒れ球も含めて楽しむ捕手のように。言葉のバトルを繰り広げる登場人物を生身の肉体に落とし込んだ俳優たちの好演も手伝って、受賞にふさわしい舞台に仕上がった。一点だけ気になったのは、家族崩壊とも映る嵐の一夜が過ぎ去った後、主人公に「考える」とだけ語らせて幕を降ろした点。蓬莱が『まほろば』(二〇〇八年)や『嗚呼いま、だから愛。』(二〇一六年)で登場人物に注いだ愛や寛容のスパイスが薄い。率直で正直な思いを、ギリギリの境目に立って生々しいドラマとして成立させ、現在地を表現したとも言えなくもないが、人間の弱さや醜さを受容した先のドラマを見たい衝動に駆られた。個人的にはこの作品以上に劇評意欲を駆り立てられた舞台があったことや、最高傑作を待ちたいという思いが強く働き、推薦までには至らなかった。しかし、この作品に賞を贈るという選考結果は心から素直に喜びたい。
未来へ目を向けさせた『チルドレン』■
推薦作として候補に挙げたのは、パルコ『チルドレン』とiaku『逢いにいくの、雨だけど』の二本だった。社会派劇と風俗劇。まったく異なる作風の芝居だが、新しい視点によって演劇の力を確認することが出来た舞台だったことが推薦の大きな理由だった。
『チルドレン』は、一九八四年生まれの英国人劇作家、ルーシー・カークウッドが二〇一六年に発表した戯曲で、巨大地震による大津波で原発事故が起きた、という設定は、東日本大震災での悲劇が元になっている。波の音が聞こえる英国の東海岸。原発事故でロビン(鶴見辰吾)とヘイゼル(高畑淳子)夫婦は、避難区域から少し離れた知人のコテージを借りて暮らしていた。水道の水は飲めず、計画停電で不便な生活をかこっている。六〇歳を過ぎた二人の下へ、女友達のローズ(若村麻由美)が三十年ぶりに訪ねてきた。原発で科学者として勤務していた三人は、子供や健康のことなどを語らい、冗談を言い合う。しかし、ロビンとローズがかつて恋仲だったこともあり、堅実な生活者で良き母でもあったヘイゼルは、感情の赴くまま男性遍歴を重ねてきた独身のローズが夫を奪いに来たのかと訝る。ローズの来訪の真意を測りかねる夫婦が疑心暗鬼にかられる様がサスペンスタッチで進む中、ローズの提案で物語が急展開する。
ローズは原発の復旧作業について、「放射能汚染のリスクを若い世代に委ねるのはフェアじゃない。建てたわたしたちに責任がある。仕事を引き継いで、若い人たちを解放するために」と、かつて働いていた原発の職場に戻る決心を告げ、二人に協力を求めてきた。強く拒否したヘイゼルは、女として母として未来を見つめ直していく。言葉数が少なくなったロビンは、余命に限りがあることを自覚する。夏の夕陽がリビングに長い影を差し、教会の鐘の音が聞こえてくる中、ヨガを始めるヘイゼル、浸水してきたトイレの汚水を掃き出すロビン。普段と変わらない作業をする二人は、未来の子供たちのためへの決意を固めていく。
明るかった表情に徐々に暗さを増すことで陰翳に富んだ人物を作り込んだ高畑。欲を言えばもう少し色気と抱えている問題の大きさを分かりやすく表現してほしかったものの、落ち着いた口調と的確な仕草で演技に知性を感じさせた鶴見。冷やかしのような軽薄な言動とは裏腹に心の奥から湧き出てくる真摯な思いを巧みに噴出させた若村。栗山民也の周到な演出の下、三人の俳優が期待に応えた。三人は事故後の人生をどう刻んできたのか。なぜヘイゼルとロビンは家を借りてまで被災地近くに住み続けているのか。ローズの登場と告白によってそれぞれの心の中にどんな感情が沸き起こり変化していったのか。自然体で濃密な会話を観客と共有することで、テーマをじっくりと考えさせる舞台とした。
福島で起きた原発事故を世界全体の問題と位置付け、ともに悲しむ思いを寄せた内容だったこと。そして、科学の進歩による明るい社会を信奉してきた人類へ突き付けるような問いかけをしたこと。この二点については既視感がない訳ではないが、表題にある「子供たち」、つまり未来のために現代を生きる人間は何をすることが出来るのか。母なる地球から託された警鐘を、どう未来の子どもたちのために繋いで行ったらいいのか。「叡智」の結集を問いただす作品へと戯曲を昇華させている。福島原発事故を題材にしたこれまでの芝居になかった新しい視点だった。
東日本大震災から八年が過ぎた。引き起こされた事態の大きさ、悲しみの深さが故に、過去と向き合い、現状をどう打開していくのかを考えることで精一杯ということも十分に理解出来る。それだけに、三十代の若い英国人から一歩を踏み出して未来を見つめる視点を投げかけられたのは虚を突かれる思いだった。カークウッドは福島で働く科学者たちの自己犠牲と勇気あふれる行動に感銘を受けて執筆したとも語っている。この問題とどう向き合い行動していったらいいのかを示した戯曲が日本で上演されることによって、その祈りは日本人の観客を勇気づけることになったのではないか。演劇には魔法の力が宿っている。そんな風に形容したくなるような一夜でもあった。
研ぎ澄まされた『逢いにいくの、雨だけど』の会話■
もうひとつの推薦作『逢いにいくの、雨だけど』は、大阪出身の演劇ユニット「iaku(いあく)」の横山拓也が書き下ろし、演出した舞台だ。小学生の時の絵画教室のキャンプ中に、女の子と男の子がガラスペンを取り合いして事故になり、男の子が左目を失明してしまう。親同士も仲の良かった二組の家族は、この小さな事故を境に険悪になる。そして、それぞれの家族が壊れてしまう。事故から二十七年後、加害者の少女は絵本作家(異儀田夏葉)として新人賞を受賞する。一方の被害者の少年は飲料水メーカーの営業マン(尾方宣久)となり自販機の売り込みに飛び回っている。新人賞受賞作のキャラクターが、少年時代に営業マンが描いたイラストに酷似していたことから、連絡を受けた絵本作家は営業マンと再会することになる。事故が起きた一九九一年夏と、当事者が大人になった二〇一八年冬を小刻みに行き来させながら、二十七年という時の流れの中で、加害者と被害者との間にある割り切れない思いは変わったのか変わらなかったのか。当人同士とその家族の姿を見つめることから「許すこと」についての新しい視点を模索している。
理解することが出来ない人は不満を抱え続けるしかなく、承認することが出来ない人は憎しみ続けるしかない。許すことが出来ない人は差別を続けるしかない。戦争をはじめ、紛争地の衝突やテロなど世界を震撼させている暗いニュースの根源には、無理解や誤解、そして差別意識や憎しみが横たわっている。この負の連鎖を断ち切る方法はないのか。現代人が抱える大きな課題に対して、横山は明言こそしないが、「許す」「許さない」の最小単位となる身近な事故を見つめることで、負の連鎖への解決策を探ろうとしたのではないか。通常なら裁判や社会福祉などの社会システムを介在させ、目に見える形で解決を図るのが一般的だろうが、それでも心から許すまでにはなかなか至らない。横山がその一歩先、心の領域に踏み込んでドラマを組み立てたのは、大きなテーマに普遍化させる狙いがあったに違いない。
再会した二人を前に、盗用を指摘する知人(松本亮)は、「視界も奪って、好きだった絵も奪って、将来の夢も奪った」と強く非難する。一方、絵本作家は事故後に二人の父親(近藤フク、猪俣三四郎)がともに家を出てしまった結果、それぞれの家族が無茶苦茶になったことを悔い、「自分で自分が許せない」と声を振り絞る。ところが、被害者の営業マンは、「不慮の事故だった」から「許すとか許さないとか、そういうのはない」と静かにこたえる。そして、誤解を与えないように、相手を傷つけないように、慎重に言葉を選びながら事件当時と今の思いを語り出す。横山は感情に訴える安易な手法は取らず、平易で豊かな言葉を積み重ねることによって洗練された会話を醸し出し、登場人物の奥に広がる心象風景を観客の心の中に映し出した。「許す」ことはそんなに難しいことではないかもしれない、と人間の想像力に希望を託す。リアリティを感じさせる俳優たちの細やかな演技も相まって、この舞台からも演劇の大きな、そして豊かな力を感じることが出来た。歴史が動いたり時代がうねったりする大きなドラマではなく、日常生活の中で起きた小さな物語ではあるが、『チルドレン』と共通する新しさを感じた。
二〇一八年の横山は、俳優座に『首のないカマキリ』を書き下ろしたほか、「iaku演劇作品集」と題して、過去に発表した『人の気も知らないで』(二〇一二)、『梨の礫の梨』(同)、『あたしら葉桜』(二〇一五)、『粛々と運針』(二〇一七)の四作品を東京で上演した。小松台東との共同制作による『目頭を押さえた』(二〇一二)のほか、他劇団が横山の戯曲を上演したことも手伝い、俄かに脚光を浴びる存在になっている。戯曲の大きな特徴は関西弁口語がポンポン飛び交う生きのいいせりふで、リズミカルな会話のやり取りの中から鮮明になってくる人物像でドラマをうねらせる。この作品でもその特徴を生かしつつ、「うん」「え。」「はい?」などの間投詞を多用したり、無言の間を作り出したりすることで、会話のキャッチボールに厚みと凄みを増している。作劇術が研ぎ澄まされ、ますます目が離せない作家になってきた。
充実度を増す劇団チョコレートケーキ■
推薦作には届かなかったが、注目し刺激を受けた芝居についても触れておきたい。「作=古川健、演出=日澤雄介」のコンビで劇団チョコレートケーキが上演した『ドキュメンタリー』『遺産』の二作は、医の倫理をテーマに戦時中から現代へと連なる負の歴史に光を当てた連作だった。『ドキュメンタリー』は、薬害エイズ事件の真相を追う中で、戦時中の七三一部隊の悪夢が亡霊のように蘇る瞬間を切り取った三人芝居で、ジャーナリスト、製薬会社員、医師を演じた劇団員への当て書きもぴたりとはまった好舞台だった。一方の『遺産』は、七三一部隊が犯した罪そのものに切り込んだ。戦争に勝つためには何をしてもいいという狂気の時代にあって、非道な人体実験に手を染めてしまう医師にスポットを当てている。研究者としての業の深さをあぶり出すと同時に人間はどこまで残酷なのかを突き詰めた問題作として強い印象を残した。
演劇集団円『藍ノ色、沁ミル指ニ』は、東京で藍染めを仕事として受け継いできた一家に沸き立った、さざなみの様な出来事を見つめた作品。新月の朝から満月前日の夜更けまでの五場構成で、作・演出の内藤裕子は、上手前に甕場、奥に板場、下手に居間を設け、藍を染める作業工程を見せながら芝居を進行させた。仕事の未来、家族の暮らし、結婚、親と子など、慎ましく懸命な日々の暮らしの中で心をざわつかせながら、互いの気持ちを思いやり、現実を受け止めていく三世代の人々の姿を丁寧に写し取った。チェーホフ劇の面白さは「生活がそのまま正直に、人間の姿がそのまま正確に、誇張されずに示される」点にある。チェーホフ劇を思わせる生活劇の誕生を喜びたい。
もう一作は、翻訳劇の再演となるシーエイティプロデュース『Take Me Out 2018』。二〇〇一年の「9・11」事件を契機にした異民族排斥、社会的弱者への嫌がらせなどに対して、アメリカを象徴するスポーツである野球を介して、人種問題やLGBTなど社会的な弱者をテーマに据えた作品。再演では演出の藤田俊太郎が楽園を追われた二十一世紀のアダムとイブの物語に重心を置き、「愛を知ることで自分が分かる」というメッセージが痛いように伝わってきた。口幅ったく気恥ずかしくもあるが、やはり世界を救うのは愛。これは、『チルドレン』『逢いにいくの、雨だけど』とも共通するメッセージのように思えてならない。
間が闇となり、深渕となる
辻原 登(作家)
世田谷パブリックシアターで仲代達矢の『肝っ玉おっ母と子供たち』(無名塾)を観た。隆巴演出・仲代の肝っ玉おっ母(アンナ)は一九八八年の初演から二十九年振りの再演だという。
私はこの舞台に、演技?リアルの関係を超えた〝何かが立ち現われた〟という感慨に打たれた。
ブレヒトの〝異化効果〟なるものを文学的さかしらとしてずっと敬遠気味だったが、今回のブレヒトの舞台に関しては、その効用を改めて認識した。全ては仲代達矢の「アンナ」像にある。八十五歳の老男優が、壮年から初老にかけての一人物を演じる(物語では十三~四年の時間を生きる)、しかもそれが「女」だということ。歌舞伎ならありうるだろうが、型も約束ごともない自由演劇の新劇(敢えてそう呼ぶ)の舞台で、しかも仲代はじつは「女」を演じているわけでも壮年を演じているわけでもないのに、ある〝状況〟が〝肝っ玉おっ母〟の状況としか言いようのない、戦場の中に戦場を超える場面が我々の中に立ち現れる。劇的アイロニー、異化効果とはこのことだったのか。聖なるものが降りて来る。顕現。
舞台上で、死者に肉体と声を与え、死者は死者のまま生者と交流しつつ、異和を抱えながら〝カタルシス〟が成立する夢幻能の世界。『遺産』(劇団チョコレートケーキ)は、戦時下の「満州」における日本軍の七三一部隊をめぐる物語だが、歴史上の出来事、犯罪については超越的な「審級」など存在しないのだから、我々に出来るのは、過去を、死者を如何に甦えらせるかだけだ。死者は、公平な未来からのまなざしを待っている。
私がこの舞台から受け取ったのは、七三一部隊における人体実験に従事していた軍医、軍人たち、四十五年後のその記憶と記録にまつわる騒動ではなく、「マルタ」として人体実験に付される中国人女性「王静花」の悲しみだった、李丹演じる「王静花」が残して来た子供のもとに帰るため、必死で覚えようとする日本語とその声は、死んでいる筈の彼女が、中盤で中国語で観客に語りかけ、終幕ではしなやかにダンスを踊る。中国の庶民の女性が着る衣装(日本だとモンペ服のようなもの)、布靴、音楽としての中国語、身体音楽としてのダンス、その背後に聞こえるたどたどしい日本語の声。これら非言語的時空=シーンが、むごたらしくも殺された王の内面を鮮やかに形象して、我々に悲哀の感覚(カタルシス)を掻き立てるのだ。
現実にはありえない魂の浄化は、ただドラマにおいてのみ起こり得る。死者が、「私たちを見捨てないで」「私たちを数えないで」と声を上げるのだ。深渕が我々の足下にあることを知らせる死者たち。
倫理の問題を悲哀の感覚に解消するものだと批判することもできるだろうが、アンティゴネーの悲哀を味わうだけでも、生には意味がある。
「家族劇(ファミリー・ロマンス)」。一昨年は、何と言っても『荒れ野』(穂の国とよはし芸術劇場PLAT、アル☆カンパニー)だった。そして、昨年は『て』(ハイバイ)と『消えていくなら朝』(新国立劇場)に瞠目した。二作品とも、親子の関係と兄弟姉妹の関係を舞台の縦軸と横軸に据え、それを時に転倒させたり、捩れさせたりしながら、独特の葛藤(螺旋構造)を描出して、見事だった。
殊に『消えていくなら朝』は、批評の視点を持ち込んで、従来の「家族劇」にない深さと広がりを見せた。
題材の尽きた劇作家の男(鈴木浩介)が、自分の実家のことを書く、と決めて十八年振りに帰省する。「放蕩息子の帰還」を描く舞台。
人はたれでも、故郷とか家とかでは、ひとつの生理的、心理的な単位にすぎない。そこでは、いつも己れを、血のつながる生物のひとりとしてしか視ることのできない肉親や血族がいる。己れの卓越性を過信してやまなかったマチウ書の主人公は、むらむらと、近親憎悪がよみがえるのを感ずる。
吉本隆明『マチウ書試論』
劇作家(定男)の郷里には両親、兄、妹がいる。皆、心はバラバラだ。帰郷息子は恋人レイを伴っている。
定男は、小さい頃、宗教に凝った母親に神の子として連れ回されたうらみや、両親に心理的に捨てられたというトラウマを抱えている。
書く人間が登場して、それまで思ってもみなかった事態が生じる。両親、兄妹は書かれる人間として意識し始める。家族という動物が己れを意識し始めるのだ。
定男が登場して導入されるのは、絶えざる間(沈黙)と、セリフの最後に尻尾のように常にくっついて、低く発せられる笑い(くぐもった笑い、バツの悪い笑い、自嘲的な笑い)である。やがてそれが家族全員に感染していく。彼らは間そのもの、笑いそのものを相手にし始める。
可 奈(妹) あぁ(笑)
間。
定 男 いや、この間何よ(笑)
一同笑う。
庄 吾(兄) あったな間、あったな(笑)
庄次郎(父) みんな困ったんだよ
可 奈 困る困る(笑)
関係の糸は幾重にも吐き出され、架け渡され、彼らは自らの網に搦め捕られ、抜け出せなくなっていく。間は闇ともなり、深渕ともなる。笑いは凍り付く。
救いは、不意打ちように外部から来る。放たれるレイの批判の矢。
定男に向かって、
レ イ 自分の見せたくないもの、それだって調整して書けるじゃない。でも書かれる人はそれが出来ないから……本当に辛いことになるかもって……
定 男 ……
間。
第二の矢は、やはりレイ。
レ イ 私はフィリピンのハーフです!
全 員 ……?
レイの最後のセリフ。
「……ほんとに、朝が全部を帳消しにしてくれたらいいんだけど……そんなの無理だしね」は、前の場面での、小学校五年の頃、定男が夜、離婚話をする両親の会話から受けた衝撃を、朝が全部帳消しにしているみたいに……だが帳消しになることのほうに恐怖する、という定男の告白をリフレインして、余韻の深いラストとなった。ここで、我々は改めて、この芝居のタイトルを呼び起こすことになるのだ。
『消えていくなら朝』への授賞を喜びたい。
- <<前の記事:第六回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考結果
- 第六回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞贈賞式を開催:次の記事>>