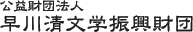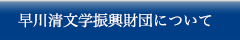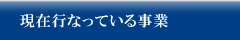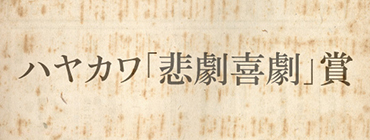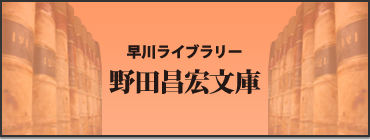第十一回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考委員批評文
「本当の幸い」を探すジョバンニたち
杉山弘 (演劇ジャーナリスト)
新型コロナウイルスの感染拡大から三年が経った、二〇二三年五月には感染症法上の分類が二類から五類へ引き下げられた。医療体制や社会経済活動が平時に移行し、学校の授業もオンラインから対面に、飲食店での外食や旅行・レジャーを楽しむ人も増え、マスクの着用も個人の判断に委ねられるようになった。ライブ芸術の演劇もスポーツ観戦やコンサート鑑賞などとともに観客が戻りつつある。
二〇二三年はパンデミック前の日常を緩やかに取り戻した一年だった。しかし、この三年間は感染症の流行を止めるため、人と人の間に一定の距離を置く「ソーシャルディスタンス」が叫ばれ、そのことによる分断と孤立で心に傷を受けた人も少なくない。一方、多くの演劇人は「エンターテインメントは不要不急のもの」とみなされたことに少なからずショックを受けた。この状況にあって演劇は何が出来るか。個人的には劇場空間の暗闇の中で、そのことを考え続けた一年でもあった。
現代の幸福論を描いた『人魂を届けに』■
宮沢賢治『銀河鉄道の夜』では、孤独を抱えた少年ジョバンニがカムパネルラとの心の旅で「ほんたうのさいはひ(本当の幸い)」を探す。この旅でジョバンニが持つ切符は、宗教や科学では答えの出せない希望を探し続けるための切符である。前川知大が二年ぶりに書き下ろし演出したイキウメ公演『人魂を届けに』は、日本社会に巣くう病理を解きほぐしながら現代人にとっての「本当の幸い」の切符を手渡してくれる作品だった。
表題は象徴や比喩ではなく、絞首刑の直後に死刑囚から飛び出した人魂から「寒い」「さみしい」「お母さん」の囁きを聞いた刑務官の八雲(安井順平)が、深い森に住む死刑囚の母・山鳥(篠井英介)に人魂そのものを届けに来る話。この人魂は大気中にフワフワ漂う物体という既成のイメージとは少し異なり、重量感のある黒いゲル状の物体に設定された。人里離れた森の一軒家で八雲が出会うのは、山鳥ばかりでなく、恋人を失った葵(浜田信也)、親の期待に応えられそうもなく逃げ出してきた棗(藤原季節)、会社を潰して夜逃げした鹿子(森下創)、勤め先の工場を放火した清武(大窪人衛)の四人。
社会に居場所を見つけられず、森で死のうとして山鳥に助けられた四人は、開幕直後は床にうずくまり、毛布にくるまっていたが、八雲の訪問で物語が進むにつれてゆっくりと動き出し、終盤には身体の自由を取り戻していく。まるで、度が過ぎる忖度や協調性という名の同調圧力、何もなかったことにする厚顔さなど、現代社会にはびこる病理に傷つけられ、生きにくさを感じてきた魂が恢復するかのように。四人はまさに「現代のジョバンニ」たち。そして、公務員のパートナーを死なせてしまった過去から逃れるようにして、この一軒家に暮らす山鳥を、J・D・サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』の主人公が願った生き方、つまり「誰でも崖から転がり落ちそうになったら、その子をつかまえること」を実践する人物として描いていく。
なぜ五人は身を寄せ合うようにして一軒家に暮らしているのか。八雲が抱いた疑問を解きほぐすようにドラマを進める筆法は前川の得意とするところ。この家に暮らす人々が抱える心の痛みを自然体の会話に落とし込み、八雲が自らの物語を語り始めるあたりから舞台が熱を帯びてくる。大学受験に合格したものの家族旅行先で行方不明となった息子のこと。その失踪を悲しむ妻に寄り添えず、離婚届を突き付けられたこと。そして、息子が好きだったミュージシャンのライブ会場へ出掛けて、右ひざを撃たれたこと……。前川はここに公安警察の陣(盛隆二)を絡ませる。陣は山鳥が社会へ凶悪犯を送り出していると疑い、そのアジトとにらんだ一軒家に潜入していた。生真面目なあまり仕事に忠実であろうとして家族を省みなかったことを後悔し、やり直そうとする八雲。上司の命令を疑わず、硬直した固定観念にがんじがらめの陣。二人を対照的に描いてはいるが、その差は現状に疑問を持ち、自らの考えで行動を改めるか否か、のわずかな違いでしかないことも明らかになっていく。八雲がこの一軒家の住人に寄り添い、支えていこうと決意する幸福論に祈りが込められた。
芝居の完成度の高さでもこの年を代表する一作となった。八雲役の安井が語りのうまさで物語の世界に引き込み、山鳥役の篠井は受けの演技で芝居全体をコントロールする。特に、陣と向き合う場面での、怒りや哀しみ、憐みが綯い交ぜとなった視線が忘れられない。回想劇で藤原が少年のような純粋な目で息苦しさを体現し、浜田は悲しみを劇場空間に解き放つ。社会の病理を一手に引き受ける盛、独特な口調で本質を射抜く大窪、せりふ回しが小気味よい森下と、七人のアンサンブルで少し不思議な物語に現実味を与えた。
スタッフワークも見逃せない。登場人物の立ち位置を回転するように微妙に変え続けることで心理状態をあぶり出した下司尚実のステージング、柔らかな光と鋭い光の強弱で激しく変わる森の風景を映し出した佐藤啓の照明、鳥の鳴き声や木々の葉擦れの音、雷鳴などの自然な音で異世界へ誘い込む青木タクヘイの音響……。山鳥をトランスジェンダー的な存在に位置付けるという篠井の提案を採用する柔軟性や、初日直前までせりふを書き直した粘り腰など、前川が本番ギリギリまで悩み続け、良質な芝居を届けようとした姿勢も高く評価したい。
前川は二〇二三年に二本の新作を書き下ろしている。一本はこの『人魂を届けに』で、もう一本は世田谷パブリックシアターから委嘱された『無駄な抵抗』。いずれも「山鳥」と名乗る人物を軸に物語を展開させ、日本社会に巣くう病理を暴き出しながら、苦しみ、抗い、恢復しようとする現代人に焦点を当てている。これまで前川は不思議な現象や都市伝説、宇宙人などを題材にして数多くの戯曲を発表してきた。願ったことを叶える「ドミノ」探しのミステリー『関数ドミノ』(二〇〇五)、地球を侵略する宇宙人が登場する『散歩する侵略者』(同)、ドッペルゲンガーをテーマにした『プランクトンの踊り場』(一〇)、進化した人類の悲劇を描いた『太陽』(一一)など、ラフカディオ・ハーンの「怪談」や一九五〇年代の米テレビドラマ「トワイライト・ゾーン」の世界観を劇場に持ち込み、エンターテインメント性豊かな作品群で観客に愛されてきた。その作風を一変させ、新しいドラマ作りに取り掛かったのは三年前の『外の道』(二一)からだろう。この『外の道』のヒロインの名前も山鳥で、コロナ禍で心を痛めた現代人に寄り添う「山鳥シリーズ」を、これからも書き続けていくという。今後の創作への期待も込めて、幸福論ともいうべき現代人への寓話を提示した『人魂を届けに』を第一候補に挙げた。
関西口語劇の快作『モモンバのくくり罠』■
もう一作はiakuの『モモンバのくくり罠』を推した。作・演出の横山拓也が得意とする関西弁を使った口語劇で、親の生き方や価値観を植え付けられて育った娘が、大人になっていく過程で親に反発し、闘い、納得して自分の道を選択する経緯を爽やかに描いた快作だった。設定はやや特殊。山間部に家を建て罠猟と畑作での自給自足生活を実践する母(枝元萌)と、その思いを理解してサラリーマンをしながら都市部で別居して経済的に支える父(永滝元太郎)。高校卒業まで母のもとで育った娘(祷キララ)は、同級生との違いに疑問を感じ、「普通に育ててもらえなかった」ことから社会になじめない疎外感を覚えたため、父のもとで新生活を始めている。一人暮らしの母の家へ父と娘が久しぶりに帰り、家族三人そろって互いに近況を伝えるところから物語が動き出す。
「親ガチャ」「宗教二世」の言葉がジャーナリズムを賑わせている。展開次第では深刻なドラマになりかねないところを、横山は相手を傷つけずに柔らかく包み込む関西弁を武器に、リズミカルな会話を笑いに転化させて物語を弾ませる。枝元は『あつい胸さわぎ』(二〇一九)同様に、テンポの良いせりふと自然体の仕草で生活感あふれる母親を好演し、罠猟を手伝ってもらっている近隣の猟師仲間(緒方晋)を相手にした軽妙な掛け合いで観客を芝居に引き込んだ。さらに市議会議員の家に生まれたことに反発して動物園に勤める青年(八頭司悠友)、父が好意を抱く妙齢の女性(橋爪未萠里)を登場させて、親子三人の会話を掻きまわす。大いに笑わせた上で、母が娘の自立を促し、娘が次の一歩を踏み出そうと決意するハッピーエンドまで、母娘の心の動きを丁寧に浮かび上がらせる手際も見事だった。いつの時代、どこの世界でも起こる家族の問題。そして特効薬となる処方箋もない難しいテーマを扱って普遍的なドラマに仕上げた姿勢を高く買った。
受賞作『閻魔の王宮』について■
受賞作の俳優座公演『閻魔の王宮』は、一九九〇年代に中国・河南省で起きたエイズ集団感染事件に想を得て、資本主義的経済の闇を暴いた告発劇で、農村部の貧困に苦しむ人々が豊かな生活を夢見て売血に走った経緯と血液ビジネスに問題が生じたときの国家衛生部の研究員の苦悩を描いている。日本のB型肝炎感染拡大と同様に、ずさんな管理でエイズ感染者が拡大し、そのために地域社会が崩壊する経緯が分かりやすく描かれたほか、非を認めて謝罪するどころか隠ぺいして事業継続へと暴走する官僚機構が、いかにもありそうな展開だった。しかし、科学者の闘いのドラマがもう一つ腑に落ちなかった。倫理観から血漿採血センターの閉鎖を求め、告発へと走ろうとしたセンター所長(清水直子)が当局に軟禁されるまでは理解出来たが、彼女を説得しようとする夫(志村史人)の描き方が乱暴で、家族が平和で裕福な暮らしを続けるために見て見ぬ振りをしようと語るだけに単純化させたところが問題。この夫が幼少期に文化大革命で家族が酷い目にあった体験をしていることや心が荒廃しているエリートの弱さは示唆されてはいる。しかし、国家的な事件で「家族」と「正義」を天秤にかけるのなら、夫婦の会話はもっと書き込んで欲しかったし、日本での上演でも中国人の家族観を分かりやすく提示しなければ、夫の存在は妻であるセンター所長の正義感を引き立てるだけの道具となってしまう。夫婦が対立するシーンでの人間ドラマが観たかった。
また、二〇一九年にロンドンで初演されたキャスト表にならって日本でも一人二役で演じられた。ところが、場面が切り替わる度に同じ俳優が別の衣裳で登場し、農村部と研究所の物語が交互に進んでいくことに困惑した。滝佑里が上昇志向の強い若い衛生部職員と死者の国へ旅立つ家族を見送る農村の純朴な娘の二役を演じるなど、対照的な人物を演じ分ける負荷を俳優にかけて人間の諸相を描いてみようとする演劇的な試みだったのかもしれないが、多才な俳優を数多く抱える俳優座の公演で、出演者全員に一人二役を担わせた狙いが今一つ伝わってこなかった。加えて、表題の「閻魔」にも違和感を覚えた。日本では冥界の王として死者の生前の罪を裁く裁判官というイメージだが、ドラマで展開されるのは「現代の地獄絵」そのもの。観客がそれぞれの登場人物を六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)に振り分けて裁く趣向のドラマでもなく、表題にも工夫が欲しいところだった。
選考会はこの作品を第一候補に挙げる矢野誠一さん、濱田元子さんと、『人魂を届けに』を推した私とに分かれたが、討論の中から『閻魔の王宮』の受賞に賛同した。理由の一つ目は眞鍋卓嗣の演出。俳優座劇場の舞台を上下二層に分け、農村部のシーンを上層、研究所のシーンを下層と、アクティング・エリアを明確に分けて、場割の多い戯曲をスムーズに転換させたアイデアが優れていた。二つ目は河内浩、塩山誠司、清水直子、安藤みどり、志村史人、千賀功嗣、八柳豪、野々山貴之、滝佑里、松本征樹の十人の俳優たちの活躍。眞鍋演出で劇作家の横山拓也が書き下ろした『首のないカマキリ』(二〇一八)、『雉はじめて鳴く』(二〇)、『猫、獅子になる』(二二)や、ジェイムズ・グレアム『インク』(二一)やアルベール・カミュの『戒厳令』(同)などの翻訳劇でも息の合った演技を見せていたほか、「修復的司法」を題材にしたオーストラリア演劇を俳優の森一が演出した『面と向かって』(二一)と『対話』(二三)などに出演してきた十人は、老舗劇団の新生面を切り開く原動力となっている。
三つ目は、米国に生まれ育った作者フランシス・ヤーチュー・カウィグの問題作をロンドン初演に続いて東京で上演した進取の精神。近年、俳優座が意欲的な芝居の上演で活気を取り戻していることからも窺える。そして最後に、矢野さんの「分からないものがあったほうが芝居って面白い」の言葉。以上の四点を総合的に見渡したとき、「劇評意欲を奮い立たせる優秀な演劇作品」を顕彰するハヤカワ「悲劇喜劇」賞にふさわしいという結論に達した。併せて俳優座創立八十周年の節目の年での受賞を素直に喜びたい。
「血」の物語に血を通わせた
濱田元子 (毎日新聞論説委員 学芸部編集委員)
「汝は人間である。つねにそのことを自覚して忘れるな」
東京・六本木の「俳優座劇場」。ロビーから客席へ向かう階段を上がると、正面のレリーフが自然と目に入ってくる。表情豊かな人間たちの姿。そして、この古代ギリシャの作家、ピレーモンの言葉が刻まれている。
一九五四年、俳優座創立十年の年に建設された俳優座劇場の入り口に掲げられていたもので、八〇年に改築された現在の劇場にも受け継がれた。
「人間である」とはどういうことか。演劇がつねに追求してきた根源的な問いが、大胆に切れ味鋭く、この劇場で投げかけられた。劇団俳優座が眞鍋卓嗣の演出で上演したフランシス・ヤーチュー・カウィグの『閻魔の王宮』(小田島恒志訳)である。
二〇二〇年からの新型コロナウイルスの世界的パンデミックに加え、三年目に入ったロシアのウクライナ侵攻、そして昨年十月七日のイスラム組織ハマスの急襲に端を発したイスラエルのガザへの大規模侵攻、異常気象による世界的な大規模災害の発生と、「人間の安全保障」が根底から揺さぶられている。その意味において、二三年という「時代」を象徴するさまざまな寓意をはらんだ骨太な戯曲の面白さ、それを深く読み解く演出家の力量、八〇年を迎えた新劇の老舗劇団の地力が感じられる舞台成果に、劇評意欲をかきたてられた。
◆
何に心をつかまれたのか。一九九〇年代のセンセーショナルな事件を題材にしながら、作者の仕掛けた深遠なたくらみが、〝いま〟を射抜いたことが一つに挙げられる。
舞台は、中国政府が民主化運動を弾圧した一九八九年の天安門事件を経て、改革開放政策を加速させた九〇年代。河南省で起こったHIV集団感染事件に想を得たという。化粧品などにも使われる血液中の血漿を採取し、米国の製薬会社に売却してもうけようという「売血ビジネス」に翻弄される農村の家族の姿が軸となる。
河南省衛生部が立ち上げた血漿採血センター局長に就任したワン・ウェイ(千賀功嗣)と同僚のシェン(志村史人)兄弟は米国にわたった親戚と手を結び、ビジネスに乗り出す。 かたや、大飢饉と文化大革命の嵐を乗り越えたものの、貧困にあえぐジャガイモ農家のクァン(塩山誠司)とウェン(八柳豪)の兄弟は、環境の悪い鉱山に出稼ぎ労働することを余儀なくされている。それでもクァンの娘ペイペイ(滝佑里)の進学費用さえままならない。そこに、売血してリッチな生活を送る親戚のルオ・ナー(清水直子)と息子のシャオ・カン(野々山貴之)が現れたことで、物質的な欲望が〝感染〟したように蔓延していく。
フィクションではあるが政治的なバイアスがかかりやすい、センシティブな問題をはらんでいるのも確かだ。初演は二〇一九年のロンドンのハムステッド劇場。だが、それは人類がコロナ禍に対峙する前である。今回の上演は世界がコロナ禍を経験した後だったということで、作品がより普遍的、アクチュアルに見えたのではないか。というより、戯曲がそもそもはらんでいた寓意が、コロナによってはっきり見えるようになったといったほうが、正しいかもしれない。
コロナ禍がなければこの戯曲は、単に中国の隠蔽体質を告発するだけにしか見えなかったかもしれないが、コロナ禍はこれまで見過ごしてきた社会構造のゆがみ、何かあればすぐにしわ寄せがくる弱者の存在を浮き彫りにした。
原発事故やコロナ禍が暴いた「政治と科学」という切実な問題も突き付けてくる。科学的見地を軽視し、もしくは隠蔽し、人命よりも経済を回すことを優先しようとする政治の姿は遍在している。さらに言えば、「安全神話」が強調されてきた、原発事故の問題へもつながってくるだろう。売血ビジネスは貧しい農村がターゲットにされた。そこには、原発の立地が過疎問題を抱える自治体に集中していることと同じ構造が透けて見える。けしてひとごとの話ではない。
◆
搾取する側と、搾取される側──。そんな戯曲のはらむ社会のゆがみを、丹念に読み解き、ダイナミックな世界を立ち上げた眞鍋の演出も戯曲に新たな光を当てた。近年、ミュージカルやオペラも手がけるなど劇団内外で幅広く活躍し、劇団のけん引力になっている。何といっても目を引いたのは、舞台上に出現させた巨大なダイニングテーブルの装置(杉山至美術)だ。
「搾取される側」すなわち売血で金を稼ごうとする農村の人たちをテーブルの上に、一方、その血でもうけようとする「搾取する側」をテーブルの下という配置にすることで、分断と格差を見事に視覚化した。また、中華テーブルのように大胆に装置を回すことで、心の揺れ、立場や関係性の変化をビジュアルとして大胆に見せた。
新劇の劇団ならでは、層が厚く、力ある俳優がそろったのも見逃せない。物語の芯を担うのが、清水が二役で演じるシェンの妻で感染症専門医のインインだ。それこそ「血」のつながりもあって、血漿採血センターの所長に任命されるが、ウェンの息子シャオ・イー(松本征樹)がセンターで突然倒れたことをきっかけに、血液汚染の可能性に気付き、危険性を科学的検証でもって告発しようとする。
そのインインと、安全より経済を重視し、隠蔽しようとする当局側との対立は、まさに水質汚染を告発しようとした科学者が孤立するイプセンの『人民の敵』と相似形をなす。さらに、インインが多くの人命を救うために、採血センター側の人間である夫と子どもを捨てて出ていくところは、同じイプセンの『人形の家』のノーラの姿をほうふつとさせる。そんなインインの科学者としての矜持を、清水がきっぱりと演じ、説得力を持った。
たんなる二項対立の物語に終わらせていないところも、時代にフィットする。それを演劇的に見せるのが、清水が売血の危険性に警鐘を鳴らすインインと、売血による物質的豊かさに感染したルオ・ナーを演じるといった、裏表の一人二役の妙だ。
滝佑里は、父のクァンが売った血で大学に進学するペイペイと、野心的な看護師(省衛生部職員)ジャスミンを演じる。人間はどっちの側に転んでもおかしくないという危うさがあるということだろう。インインの正義感、行動力の裏に、血液汚染の犠牲となり死んでいくルオ・ナーの無念があるとみることもできるだろう。死んだルオ・ナーの抜け殻から、インインになるところをあえて見せるという演劇的な仕掛けで、観客に配役の意味を強く印象づけるなど、眞鍋の感性が細部まで行き届いた。それはラストシーンにも言える。一族で生き残ったペイペイがこの先どんな道をいくのか。ペイペイとジャスミンをダブらせて見せたのも意味深長だ。観客の心に波紋を広げ、思考へつながる回路を開いた。 「血」というものについても、いろいろ思いを巡らすことになった。一つは欲望をかなえるための、ある意味元手がかからない商品としての「血」が核として存在する。日本でも、血液製剤による薬害エイズ問題が大きな禍根を残したことは記憶に新しい。
一方で作品に通底しているのが「血のつながり」である。親は子を思い、子は親を思う。危険な売血もいとわない。命を金に替えようとする兄弟の、互いをかばい合うやりとりは胸に迫る。「血」でつながった家族の絆という、普遍的な物語でもあるのだ。塩山、八柳に土に生きる者の朴訥としたおおらかさ、人の体温が感じられ、ウェンの妻リーリー演じる安藤みどりに農村の女性のたくましさと情が濃くにじむ。
興行資本によるスターシステムの舞台とはまた違う、新劇の劇団ならではのアンサンブルが芝居に厚みを生み、人間関係にリアリティーを持たせ、物語に「血」を通わせた。
戦後新劇の黄金期を支えてきた俳優座劇場も、来年四月末で閉館する。眞鍋にとってはここでの演出が最後と聞くと、惜しまれてならない。新劇の原点といわれる築地小劇場創設から今年で百年になるが、「芸術」と「経済」をどう両立させるかの問題は、いまだに積み残しになったままだ。節目に、社会における演劇の役割を、『閻魔の王宮』を通して改めて考えさせられることにもなった。
◆
その築地小劇場で思い浮かぶのが、スタート時、小山内薫が「向こう二年間は西洋のものばかりをやる」と宣言し、山本有三や菊池寛ら既存の作家の猛反発を生んだことだ。小山内は日本の創作劇に演出意欲がそそられないとして、「未来の日本の劇術のために」と、実際、二年間は翻訳劇ばかりを上演した。
はたして百年を経た、いまの日本の創作劇はどうなのか。
今回の「悲劇喜劇」賞は翻訳劇の上演を選ぶことになったわけだが、もちろん創作劇上演に面白いものがなかったわけではない。「生きづらさ」「閉塞感」を強く感じさせる、特に若い作家による作品に多く出合ったのは、時代の表れであろう。だが総じてみると、時代や社会の普遍的な問題に斬り込んだ骨太な作品が少ないのが残念だった。
その中で、候補のもう一本に選んだイキウメの『人魂を届けに』は、前川知大の社会の不条理、時代の閉塞感への深い洞察と作劇の巧みさ、劇団のアンサンブルのよさが、一歩抜きんでた成果を上げた。それまでのSFやオカルト的な設定から社会を照射するという作劇を離れ、とはいえ、刑務官(安井順平)が死刑囚の身体から落ちた魂を、親の山鳥(篠井英介)の元に届けるところから始まる不可思議な物語だ。
そんな魂を巡る物語は、魂を売った者、気付かぬうちに魂をなくしてしまった者らを通して、社会の闇が浮かび上がり、鋭い文明批評となって刺さってきた。浜田信也、安井順平、大窪人衛といった劇団員のアンサンブルに安定感。客演した現代劇の女形である篠井のジェンダーレスなあやしいたたずまいが異界を創り出したことも、作品にシャープな陰影を与えた。
iakuの横山拓也作品も、着実に演劇界に爪痕を残し、高い信頼を得ている。毎回、新作が楽しみな作家の一人だ。『モモンバのくくり罠』も、作家の真骨頂である関西弁のボケとツッコミのノリをフル回転させた会話のセンス、テンポ感の良さで、横山ワールドを出現させた。同じ横山の『あつい胸さわぎ』で母親役を好演した枝元萌が、今回もワイルドな母親をコミカルかつ情濃く演じて芝居を引っ張った。ただ、何気ない日常会話から繊細な心模様を緻密に織り上げてきた横山のこれまでの秀作群に比べると、やや物足りない感じが否めなかった。
風姿花伝プロデュース『おやすみ、お母さん』は、劇場支配人でプロデューサーでもある那須佐代子が、実の娘である那須凜と、母娘の壮絶なドラマを緊迫感あるセリフの応酬で見せた。二二年の悲劇喜劇賞を受賞した『ダウト』しかり、小空間における濃密で上質な舞台を生み出してきた、このプロデュース公演だからこそできる舞台だ。娘が自殺を宣言するという衝撃から始まるが、実の母娘という関係を超えた俳優同士の対峙のすさまじさが、観客を最後までみじろぎさせない。那須凜の著しい成長も強く印象づけた。
◆
二三年は、舞台芸術界も深く傷ついたコロナ禍がひとまず波を一つ越えた感があった一方、歌舞伎界やジャニーズ事務所、宝塚歌劇団などで長年のシステムのひずみが大きな悲劇を伴って露わになった。所帯の大小にかかわらず、どの創造の現場にも無関係な問題ではない。
長引く戦争も影を落とす。電気代高騰や物価上昇の影響が、制作費、そしてチケット代にも及んでいる。劇場不足の問題も指摘される。高度成長期に建てられた公共ホールの改修時期が重なり、国立劇場の建て替えもめどが立たず、閉場が長期に及ぶとみられる。「劇場」という場の重要性は、それこそ築地小劇場が目指した一つであり、芸術性の追求、表現の自由を確保することにもつながる。困難な時代に、演劇が、劇場が、社会にオルタナティブな視点を投げかける場でありつづけることを願いたい。
『おやすみ、お母さん』と『閻魔の王宮』
矢野誠一 (藝能評論家)
国鉄大宮工場長を父に、三人姉妹の末娘として明治の終わりに生まれた私の母は、お嬢さん育ちが抜けきれず、身勝手につきる振舞いに終始して、世間のふつうの母親とはいささか違った存在だった。一九六五年に三〇歳で所帯を持ち実家を出ている私は、五五歳過ぎの母の行状について知るところは少ないが、どうやら一世紀を生き抜いたらしい。父親同様母親にもあまり良い思い出が私にはない。
物ごころのついてきた幼い頃は別として、六・三新学制の第一期生として一九四七年に私立の中高一貫の男子校、麻布学園に入学してからの私と母親の関係は険悪そのものだった。成績はもとより素行のほうもけっして良くなかった私は、停学こそ喰らわなかったがじつにしばしば保護者の呼び出しを受けていた。呼び出しを受けるたびに母は私に、
「まさか月謝を使いこんでいないだろうね」
と問いただす。実際は使いこんで何カ月か滞納になっているのに、
「使いこむわけないだろう」
と言いかえしていたから、呼び出しから帰宅した母との親子喧嘩は壮絶をきわめた。母に対して暴力をふるうことはさすがになかったが、私の悪口雑言に対する母の口癖が、
「ああ、こんな息子をもって世間様に申し訳ない。死んでお詫びするほかない」
だった。それに対して、
「ああ死にな。自分で死ぬ死ぬと言う奴に死んだためしがない」
と悪態を返すのがいつものことだった。
本当に死ぬ気などないくせに自死をほのめかす発言をするのは、生きることに対して真摯に向き合っていないことの証左だろう。だったらその発言に同意してそれをすすめるのも、多分にからかいの気分からのものと言えるだろう。
この年齢になると、身のまわりで自死した人を何人か見ているが、知る限り遺書をしたためたことはあっても、生前その気持ちを他人に告白したケースはない。
IT弱者の私は、いまやほとんどすべての人が利用している「ネット」なるものと縁がない。そのネットを通じて自死願望の人に、自死を幇助する犯罪が出来しているのを新聞やテレビの報道で知るにつけ、自死願望の人と、それを阻止しよう、あるいは幇助しようとする人との間に「対話」というものが存在していないケースがすこぶる多いのを痛感せざるを得ないのだ。苦しんでいる人たちになんらかの助言を与えるための電話番号が告示されているのも、対話による説得で自死を防ぐ効用を期待しているからだ。
母の「死んでお詫びを」に対する私の「死にな死にな」は、対話どころか単なる遊戯にすぎなかったので、遊びと現実の格差をふまえて、自死に関する対話の問題が頭の片隅に残るようになった。
そんな折も折りに出会ったのが、風姿花伝プロデュース、マーシャ・ノーマン脚本、翻訳・演出小川絵梨子による『おやすみ、お母さん』だった。母セルマ、娘ジェシーによる二人芝居で、母を那須佐代子、娘を那須凜と実際の親子が演じている。
舞台には時計が設置されていて、娘が二時間後に自死すると宣言するのを母親がその決心を覆そうと説得にあたる。言ってみればシンプルな対話劇で、「言葉」によって成立する演劇の王道を行くものだ。結果は二時間後に舞台裏から銃声がきこえて終わるのだが、本当に自死したか否かは不明だ。
マーシャ・ノーマンの脚本の優れているのは、母と娘の台詞のすべてが論理的で説得力を持っていることだ。こうした台詞で相手役ばかりか観客をも納得させるのは役者の演技力のほかにない。
銃を手に二時間後に自死するという娘の、自死しなければならない理由のひとつである夫の浮気と離婚。うまくいっていない息子との関係などは、世間によくあることで大抵の人が克服している性質のものだ。そんな娘の自死の決意をひるがえすべき母親の説得が難行しているのは、娘の宣言が論理的で隙がないためである。
娘の論理的で隙のない発言を覆すためには娘以上に論理的で隙のない主張が母親に要求されるわけで、それにつとめる母親と宣言した娘それぞれの孤独がひしひしと伝わって、なんともせつない観劇感が残された。
もう何度も書いてきたことをここでまた繰り返す愚をお許し願いたいのだが、一九五三年になんとか高校は卒業させてもらったものの受けた大学は全部落ちてしまった。予備校に通って来年を期すような殊勝な心がけはまるでなく、ころがりこんだ暇な時間を映画館・劇場・寄席通いに費す思い出しても至福な時代を過ごしたことがいまの私の貴重な財産になっている。
そんな時期・新宿の安酒場あたりで知りあった新しい友人のほとんどが地方出身のひとり暮らしだった。なかに鹿児島の高校を出て上京し、キャバレーのボーイ、パチンコ屋の裏方、サンドイッチマンなどでアルバイトしながら若い劇団に首をつっこんでいる演劇青年がいた。その彼から、自分たちが目指しているような演劇とはまったく異なった大衆演劇で、旅まわりしている劇団の芝居を上演している山谷の寿座なる芝居小屋のあるのを教えられ、一緒に観に行ったことがある。
薄汚い畳敷きの寄席で蚤の襲撃と闘いながら観た寿座の芝居の内容などまるで覚えていないが、浅草から明治通りに通じる吉野通りを渡り、ドヤ街山谷に足踏入れた第一印象はいまも鮮やかに思い出すことができる。この広い東京にこんな一郭が存在している事実に驚くと同時に、得体の知れない恐ろしさに胸の鼓動が早まった。
簡易宿泊所の軒をつらねた街なみには、仕事にあぶれたのか真昼間からアルコールを摂取している筋肉労働者たちがたむろして、場ちがいなところにまぎれこんだ私たちに不審な目をそそぐのだ。そんな視線を避けて歩をすすめる先に立てられた電信柱のどれにも墨で書かれた下手糞な文字で「血を買います」と記されたポスターが貼られていた。
血を売ることも、それを買い入れることも社会的に認知された行為ではなく、言うところの闇商売だがそれに頼らねばならない生活困窮者の少なくなかった時代が、ついこの間まで存在したのだ。デビューしたばかりの岩下志麻とその父親の野々村潔や北村和夫の出演していた血の売買を扱ったNHKのテレビドラマを観た記憶がある。
その時分地方から出てきて、文学、演劇、音楽などを志す若者のほとんどがアルバイトに身をやつしていたのだが、暮しに困ったあげくの果てに血を売ってしのいだ者もいて、売りに行く先はほとんどが山谷だった。山谷の血を買ってくれる業者にも買入れ値の高低があるらしく、売血の常習者は値段のほうもたたかれたらしい。寿座の芝居を一緒に観た友人にも一度売血の経験があるとかで、採血後に出されるオレンジジュースが美味かったと言っていた。
そんな売血という闇取り引きを撤廃してこんにち見られる献血制度を確立するのに大なる功績は、読売新聞記者時代の本田靖春による「黄色い血」と題した売血禁止のキャンペーンだろう。しばしば競馬場で顔を合わせた氏は、この件に関して多くを語ることはなかったが、自身取材のために売血し、死因となった肝硬変を患っている。
フランシス・ヤーチュー・カウィグ脚本、小田島恒志翻訳、飯塚容ドラマトゥルク、眞鍋卓嗣演出による俳優座公演『閻魔の王宮』は、一九九〇年代の中国河南省における売血ビジネスとそれに翻弄される家族を描いたドラマだ。
まず社会主義国家であるはずの中国で、売血ビジネスが成立している事実に、文化大革命以後のあの国が変革していく実態が見えてくる。
河南省衛生部という組織に所属する兄弟が、米国にある親戚の製薬会社と組んで、貧困にあえぐ農村の人びとから血漿を採血して利益をあげようとする。人間が生きていく限り必要不可欠な血が商品化されていく過程のなかで露出する国家と個人、都市と農村の問題が抽象化されることなく、具体性に富んだ人間関係に象徴され視覚化される好舞台に仕上った。
共産主義国家中国が、資本主義の矛盾を追及しながら結局は資本主義に包容されてしまう現実が描かれているのだが、昨今伝えられる中国経済の問題点が既に一九九〇年代に露呈していたことを教えられる。
それにしても人間が生きていく限り必要不可欠な、体内をめぐる赤色の体液「血」そのものがきわめてドラマティックな存在であることを、「血の通った」「血のにじむような」「血で血を洗う」「血と汗の結晶」「血沸き肉躍る」などなど、血という文字のつく表現から、いまさらのようだが気づかせてくれるのだ。
- <<前の記事:第十一回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考結果
- 第十三回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考委員について:次の記事>>