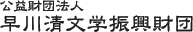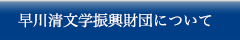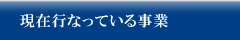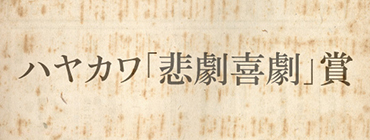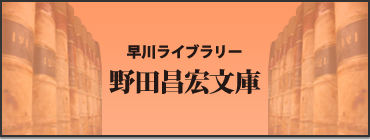第十回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考委員批評文
構造的なドラマの問題
鹿島茂 (フランス文学者)
二〇二二年は「打率」の良い一年だったのではないかと思います。
まず候補作に挙げたフリードリヒ・デュレンマット作、増本浩子訳、稲葉賀恵演出・オフィスコットーネ『加担者』からいきます。
デュレンマットの作品に触れたのは、高校生のときに見た映画『訪れ』が最初でした。『橋』で有名なベルンハルト・ヴィッキが監督し、イングリッド・バーグマンが主演した異色作で、故郷の村を不道徳を理由に追放された娘が億万長者の未亡人となって戻ってきて、自分を辱めた村人たちを次々に裁判にかけて復讐するという心理劇に強い印象を受けました。金の力で村の全権力を掌握した未亡人が気まぐれで繰り出す無茶苦茶な命令に、村人たちが理不尽さを承知しながら保身のために従い、自分以外の者たちの処刑に積極的に賛成してゆくという、スターリン体制への強烈な風刺をこめたグロテスクな風刺劇でした。
以後、めったに翻訳されない作品を追いかけて読むように心掛けていましたが、今回、『加担者』が稲葉賀恵さんの演出で、しかも、御贔屓のオフィスコットーネによって上演されると聞き、期待に胸を膨らませて下北沢に駆けつけました。
一般に、デュレンマットの作品は戯曲、小説とも次のような特徴をもっています。
①現実ではあり得ないような極端にデフォルメされたシチュエーションの設定。
②にもかかわらず、その異常なシチュエーションに置かれた登場人物はシチュエーションを異常だとも感じずに、ごく凡庸な人間として日常的に行動し、思考する。
③明らかな体制批判であるが、その体制批判は①と②の著しいギャップからくるように仕組まれている。つまり異常なことを正常に行っているというそのこと自体が鋭い批判になる。
④登場人物は、異常なシチュエーションをまったく意識に入れないでいることはできない。なぜなら、あまりに異常な状況が意識に上らないのはありえないからだ。だが、はっきりと意識化することもできない。なぜなら、はっきりと意識化したら、普通に行動・思考することは不可能になってしまうからだ。よって、意識していながら意識していないという、オーウェルのいう「二重思考」を生きることを余儀なくされる。
⑤戯曲の場合、演出のポイントは、この二重思考を生きざるをえない登場人物たち(つまり、イコール私たち)が感じている「居心地の悪さ」をどのようにして引き出すかにある。①を強調しすぎても、また②にこだわりすぎても、④の本質、つまり、そうした二重思考的な居心地の悪さが現代にも遍在しているという事実を表出することはできない。
さて、稲葉演出とオフィスコットーネの演技はどうだったのでしょうか?
①~④をクリアーして見事に⑤に成功しているといえます。
とりわけ、冴えていたのは、主要な登場人物が客席に向かって独演する場面です。というのも、この部分では、登場人物が自分は二重思考を生きているのを自覚しているのを独白することになりますが、もし、この独白部分の演出を①に寄りすぎたり、あるいは逆に②に寄りすぎたりすると、醍醐味である「居心地」が浮かび上がってこないからです。
その点、稲葉演出はこのクリティカル・ポイントを巧みに乗り切りました。ひとことでいえば、⑤の「遍在性」がはっきりとしたかたちで舞台空間に現出したのです。
次に推薦したのは、横山拓也作、真鍋卓嗣演出、俳優座『猫、獅子になる』です。
横山さんは劇中劇を得意とする劇作家で、昨年も『フタマツヅキ』が候補作になりましたが、これも劇中劇の構造の作品でした。
ところで、劇中劇というのは、芸術家小説と同じような構造的な問題を抱えています。それは以下のように要約できます。
①劇中劇の真のドラマは、外側のドラマにある。すなわち、内側のドラマを作ったり演出したりする過程それ自体がドラマとならなければならない。
②しかし、内側のドラマが凡庸であってはならない。なぜなら、内側のドラマが凡庸であっては、それを作ったり演出したりする外側のドラマも凡庸にならざるを得ないからである。
③しかし、内側のドラマがあまりに素晴らしいものであってはならない。なぜなら、それでは外側のドラマを作る必要がなくなるからである。
④想定される唯一の解決策は、内側のドラマが外側のドラマの結末として生まれてくるという円環構造にすることである。ジョイスの『若い芸術家の肖像』、プルーストの『失われた時を求めて』然りである。
⑤だが、劇中劇では、この構造を取るのは難しい。そこで内側のドラマで提起された問題が外側のドラマの問題を発動させ、外側のドラマの解決が内側のドラマの解決を呼び込むというような往還構造にして、内側と外側のドラマが連動するようにしなければならない。
『フタマツヅキ』が受賞に至らなかったのは②に原因があり、外側のドラマが「下手な落語家」として設定されていたため、内側のドラマ(つまり落語)が面白くなかったことが躓きの石となりました。
では、『猫、獅子になる』はどうだったのでしょうか?
完璧とはいえませんが、⑤に近づいていると思いました。内側のドラマに宮沢賢治の戯曲『猫の事務所』を用いたことが、外側の引きこもりや異分子排斥といった問題との連動を容易にしているからです。
ただ、内側と外側の連動をいささか図式的にしてしまった感がなきにしもあらずで、その点がマイナスとなっているかもしれません。
劇中劇というのはあまりに完璧に仕組むと、かえって効果が損なわれるという内在的問題があるからです。しかし、横山さんはこの難関に敢えて挑んでいるわけで、その勇気を私はおおいに買いたいと思います。
最後に、受賞作となった、エーシーオー沖縄・名取事務所、内藤裕子作・演出『カタブイ、1972』について。
選考会でも話しましたが、『カタブイ、1972』を観ながら思い浮かべていたのは、折口信夫の神様(マレビト)の定義です。
マレビトというのは、稀なる人という意味と稀にしか訪れてこない人という二重の意味があるのですが、肝心なのは、マレビトが果たして神であるか否か判断つきかねる中で、とにもかくにも、もてなしておこうとなることです。そのさい、やってはいけないのは、いきなり訪れてきたマレビトが神であるのかそれとも迷惑なただの人なのかを考えたりしないことです。いいかえると、理性による価値判断を働かせてはいけないのです。理性的価値判断を働かせるよりも前に、マレビトであればとにかくもてなす。もてなして喜んでもらい、そして機嫌よく帰ってもらう。帰ってもらったあとはまた平和な日常を生きる。
これが折口信夫が『万葉集』に見た万葉人たちの「神」でしたが、おそらく、そこには、妻問い婚よりももっと昔に溯る純粋母方居住の母系集団の価値観が働いていたものと思われます。
純粋母系集団というのは、結婚した姉妹が実家を継ぐという形式を取りますが、妻問い婚とは違い、その実家で実務的な采配を奮っているのは姉妹の父ではなく、母の兄弟です。姉妹の世代になると、姉妹の夫ではなく兄弟が同じ役割を果たします。家では、父、および夫の影は薄く、ときどき訪れてくるような存在、つまりマレビトに近いのです。逆にいうと、マレビトから姉妹が子供を授かって次世代に繋げる家族類型であるともいえるのです。
折口信夫は、島尾敏雄がヤポネシアと名づけた沖縄群島にこうしたアルカイックな家族類型とそこから生まれるマレビト信仰を探りましたが、現代の沖縄には、家族類型に父系への傾きが加わるという変化はあったものの、マレビトを迎え、丁重ななおもてなしをする伝統は強く残っています。
さて、『カタブイ、1972』ですが、この戯曲のポイントは、沖縄戦で生き残ったのが家族のうち父(誠治)と娘(和子)だけだったというところです。母系集団において父というのはマレビト系の影の薄い存在ですが、その父が娘とともに生き残ったため、戦後のこの家族では、必然的に中心が娘になります。娘は戦前のヤマト的な父系価値観とアメリカ的価値観をミックスした戦後の沖縄に育ち、インテリ左翼の教員となりますが、しかし、基層部では母系集団的な心性を残していますから、夫にはやはりマレビト系の影の薄い信夫を選んだものと思われます。
そして、そうした母系集団的なムコ選びが無意識に繰り返されようとしているのが、舞台における現在たる一九七二年の本土復帰直前の状況なのです。つまり、ヤマト化した母親の上昇志向により東京の大学に「留学」(本土復帰以前はこうした形式になっていた)させられた娘は、そこで「自由意志」により、東京都議会議員の息子の大学生杉浦を選んで、その後で「自由意志」で別れたはずだったが、ほとんど必然と呼べるような偶然から、本土復帰直前の状況を見ようと沖縄を訪れたその元カレを自宅でマレビトとして迎えてしまうということになります。
じつに巧みなシチュエーション設定と言わざるをえません。
しかし、さらに巧みなのは、これに、沖縄戦争で家族をすべて失い、戦災孤児となって母系集団から切れ離されてしまった女性ユミを配したことです。ユミは本来、母系集団の中でも大地母神のような中心的な存在としてマレビトを受け入れる側にいるはずの女性だったのでしょうが、運命のいたずらか、いまや女マレビトとして誠治のもとを訪れ、おもてなしを受けて居座ってしまいます。
その結果、本土的(父系的)価値観を体現する娘の和子とは対立することになり……、というように、家族的な観点から見ると、『カタブイ、1972』は表面的なドラマよりもはるかに深い、常民的なところにまで届く層を有する芝居なのです。
以上が、受賞に賛成した理由です。
ハヤカワ「悲劇喜劇」賞の選考委員となってちょうど十年、良い区切りだと思うので、いわゆる「卒業」をすることにしました。自分の専門と関係のない分野からのオファーは積極的に引き受けるをモットーにしてきましたが、この原則に誤りはなかったと確信できる十年間でした。
悲劇喜劇賞 講評
辻原登 (作家)
「すみだパークシアター倉」へ通うのを楽しみにしている。自宅のある東戸塚から横須賀線・総武線快速に乗って錦糸町で降り、北口改札から東西に走る駅前通りを西へ、すみだトリフォニーホールを過ぎ、長崎橋のたもとを右折して北へ進む。太平一丁目の角に「エアリアル・アート・ダンス・プロジェクト」の本拠地がある。たいていいつも大きな両開きの扉が半分開いていて、私はそっと忍び込んで、空中サーカスの巨大な天井空間を見上げる。無人である。不思議な建物だ。シェイクスピア劇がいいのではないか。
法恩寺橋のたもとから大横川親水公園遊歩道に降りて水ぞいに北上して、紅葉橋の下をくぐると、やがて「桟敷童子」の幟が見えてくる。
木の階段をトントンと駆け上がって、受付から劇場(小屋)の中へ。
錦糸町駅から始まる、これほど心躍る劇場へのアプローチを私は他に知らない。近くにあるはずの東京スカイツリーは徹底無視である。あれに気を取られると、この素晴らしいアプローチの良さが殺がれてしまう。
サジキドウジ作の芝居を毎年、観ている。
彼が何者か私は知らない。二〇二二年は『夏至の侍』と『老いた蛙は海を目指す』を観た。何もかもが良かった。芝居からの帰り道も、来た時と同じように良かった。「エアリアル・アート・ダンス・プロジェクト」では、若い男女が竹馬の練習をしていた。
『夏至の侍』は、音無美紀子演じる金魚養殖池の女経営者の奮闘物語だが、私は昔、金魚が主人公の短篇を幾つか書いたことがある。
墨田区の東隣が江戸川区で、私は東小松川二丁目の友人宅に居候していたことがあり、近くに金魚養殖場の大きな池があった。この池に盲目の噺家が落ちて死ぬのだが、金魚たちに助けられて甦って、立派に高座を務めるという話(『遊動亭円木』)。
以前、江戸川区にはたくさんの金魚養殖場があった。船堀、春江、堀口、一之江、瑞江などの地名・町名はその名残りである。
わたしはもう一つ、金魚の話を書いた。
千葉の木更津港には東京湾に出入りする貨物船の積み下ろし貨物の倉庫が並んでいる。かつて、それらの大きな倉庫の一つに、中国から輸入されたザーサイを漬け込んだ甕が大量に保管されていた。ザーサイは根菜で一つが拳ほどの大きさで、甕は高さ約六十センチ、口径四十センチある。空になった甕は、金魚を飼う甕となって安く販売された。
日本では金魚は大体横から鑑賞するが、本場中国では上から見て楽しむ。そのため、日本と中国の金魚の姿体はかなり違っている。もともとフナである。三世紀頃、上海近くの池か川で突然変異で赤いフナが生まれた。中国から輸入された金魚は、改良に改良が重ねられ、江戸時代に全盛期を迎える。当時の女性はおしゃれとして、小さなガラス球(金魚玉)に金魚を入れ、腰に吊して歩いた。
さて、もう一つの私の金魚小説だが、タイトルは『ザーサイの甕』という、「昭和な」時代の(もちろん戦後)。ある時、東京に大地震が来て、木更津の倉庫に保管してあった甕が割れ、中に漬け込んであったザーサイがいっせいに金魚に変身して、東京湾に流された。すると、対岸の江戸川区内にあった金魚池の金魚も、子が親を慕うように、子孫が先祖を敬うように、いっせいに跳ね上がって、東京湾に飛び込み、東京湾を日中双方の金魚で赤く染める、という話である。
私はかつてのそういった金魚妄想の時代を思い出しながら、これは九州の話だが、桟敷童子の“夏芝居”の快味に酔い痴れたのである。
桟敷童子のもう一本『老いた蛙は海を目指す』は、金魚でなく蛙だが、「蛙」の方に凄味があって、どちらかといえば「蛙」に軍配を挙げたい。
中国には、蛙そっくりの金魚がいる。蛤蟆頭といって、門外不出の品種である。ハマはカエル、トウはもちろん頭。私はこれを杭州の動物園で見た。サジキワラシの幻術か。
別の日、私は“沖縄”をテーマにしためざましい成果の二つの舞台を観た。『カタブイ、1972』と『ガマ』。これらについては、私は既に選考会の席で発言しているが、少し補足すると……。
『カタブイ、1972』の良さは、三組の男女の恋が重層するダイナミズムだろうか。若い男女、中年の男女、そして老人の……。
中年の男女といってもこれは既に夫婦だから、そのなれそめの恋(戦争の悲惨を最も色濃く反映している)。
三つの濃淡の違う恋が、“三線”のように奏でられる。
危険な匂いを放つのは、波平誠治(七三)と当山ユミ(三四)のカップルだ。なぜ危険かというと、恋ではないからだ。恋の手前、あるいは恋の向こう側にいる二人。恋ではないものを、それでも恋というより他ない関係性。
恋とは、好意のギフトなのだと考えれば、年齢の問題はクリア出来そうだ。最後にユミから誠治に届く手紙がその証拠となる。素晴らしいギフトだ。素晴らしいラブレターだ。それも声に出して、孫娘や娘夫婦の前で読み上げることの出来るラブレター。危険な匂いを最も強く嗅ぐことが出来るのは、観客席にいる我々のほうかもしれない。
その手紙のあとに、ユミが元夫に殺害されたことを知る。ここに至って、すべての登場人物たちより誠治とユミの別れの場面を目撃している我々が、最も衝撃を受け、悲しみを覚えることになる。そういう風にこの舞台は作られている。
『ガマ』は沖縄戦そのものを取り上げている。私は観劇のあと、ギリシャ悲劇、例えば『オイディプス王』と比較して考えた。
オイディプスは、先王(父親)殺しの犯人の捜索に乗り出し、最後に真犯人が誰で、自分が何者であったかを知って、両眼を剣で突いて自らを罰する。観客である我々は初めから彼が真犯人であることを知っているし、結末も知っている。我々はオイディプスがどのように真実に到達するか、その過程を固唾をのんで見つめる。劇的アイロニー。
オイディプスが遂に真実を知るとき、舞台にはカタストロフ(破局)が、我々にはカタルシス(浄化)がもたらされる。
『ガマ』を簡単に「悲劇」の図式に当てはめることはできないが、女学生の安里文の一途な姿を“劇的アイロニー”の目をもって見つめる。彼女が信じた日本が、そして白旗を手に「行きます!」と叫んで米軍の戦車の前に飛び出して行った彼女に、アメリカは何をもたらしたか。
そのことを我々は知っている。結末には、カタストロフとカタルシスが同時にある。
生まれるべくして生まれた物語
濱田元子 (毎日新聞論説委員 学芸部編集委員)
市場の中の劇場─。こんな素敵な立地はそうないだろう。「ひめゆりピースホール」は沖縄のゆいレール安里駅を降りてすぐ、栄町市場の一角にある。迷路のように狭い路地が入り組み、昼は市場、夜は隠れ家的な飲み屋が灯をともすディープな地帯だ。
なぜ「ひめゆり」なのか。答えは歴史にある。一帯は、太平洋戦争前まで沖縄師範学校女子部と県立第一高等女学校があった。戦争末期の沖縄戦で学徒看護隊として動員され、多くの教師や生徒が犠牲になった「ひめゆり学徒隊」の母校である。
戦後は米軍の資材集積所となり、その後は市場となった場所に、同窓生たちが平和を発信する拠点として建設したのが「ひめゆり同窓会館」。ホールはその二階にある、こじんまりしたブラックボックスだ。
敗戦後、米軍の施政権下に二十七年間置かれた沖縄は、一九七二年五月十五日に返還された。その復帰五十年記念としてエーシーオー沖縄と東京の名取事務所が共同制作した『カタブイ、1972』(内藤裕子作・演出)は、ひめゆりピースホール公演から幕を開けた。ここほど、この作品を上演するのにふさわしい場所はない。劇場の持つ強烈な磁場に引かれるように、那覇に飛んだ。
内藤が丹念に描いた家族の物語、田代隆秀をはじめとする東京と沖縄のキャストの見ごたえあるアンサンブル、装置や照明のスタッフワーク。何ごとにも時があり、作品が生まれるにも時がある。沖縄の節目というだけでなく、なにやらきな臭さが漂い始めた二〇二二年に生まれるべくして生まれた作品として劇評意欲をかきたてられ、迷わず第一候補に推して、選考会に臨んだ。
『カタブイ、1972』■
二二年はとにかく、復帰五十年を捉えて東京でも沖縄でも、新旧問わず沖縄を題材にした多くの舞台が制作された。もちろん、それまでにも県民の四人に一人が亡くなったと言われる苛烈な沖縄戦や、ひめゆり学徒隊の悲劇、島ぐるみ闘争、人類館事件、辺野古など基地問題をテーマにした作品は上演されてきた。
ただ、現地取材や文献調査を重ねたとはいえ、東京からの視点で制作される作品がどこまで沖縄のリアルな思いや空気を伝えられているのかという思いもあった。基地問題一つとっても、「反対」という言葉だけではくくれない、十人いれば十の意見や考えがあるといわれる。そんな中、複眼で見つめ、多様な論点を提示する作品として『カタブイ、1972』は一つの転換点ともなるのではないだろうか。
どうしても歴史の講義や思想的になりがちな題材だが、これまで藍染や林業など、仕事を通して秀逸な家族のドラマを描いてきた内藤裕子(演劇集団円)に託し、家族という切り口から「返還」をえぐろうとした試みが高い上演成果につながった。
物語は、沖縄中部にあるサトウキビ農家、波平家が舞台となる。時は復帰の半年前の一九七一年十二月、サトウキビの収穫時期にさかのぼる。タクシー運転手を兼業するおじいの誠治(田代隆秀)は、人手が足りないところを、たまたま知り合った訳ありのユミ(古謝渚)に収穫を手伝ってもらっている。ユミは故郷の島でも収穫を手伝っていたから、手際もいい。父娘以上に年は離れているが、二人の間のやりとりがほほ笑ましいのは、田代の温かみのある包容力と、古謝に辛苦を感じさせない明るさと健気さがあるからだろう。
そこに誠治の娘・和子(馬渡亜樹)の夫・信夫(当銘由亮)が、旅行中の東京の大学生・杉浦(山田定世)を連れて来た。東京からは孫の恵(増田あかね)も帰郷。ユミと杉浦の存在を巡る波平家の波風が、復帰を巡り入り乱れるさまざまな思いと共振し、物語がうねっていく。
一人一人が背負ってきたものと、沖縄が背負ってきたもの。時に絡まり合い、メタファーとなり、物語が波平家から大きな同心円を描いていく。個人と国家、沖縄と本土、日本と米国の関係がビビッドに浮かび上がってくる作劇が巧みだ。
歴史と現実、悲憤とあきらめ。交錯する複雑な思いを刻む印象的なシーンがいくつもちりばめられている。
基地近くに住む家族の会話に、ベトナムの戦場へと飛び立つ米軍の爆撃機B52の轟音が異物のように侵入してくる。しかし、それが沖縄にとっても「日常」であることが、波平家の人々と、東京から来た杉浦のリアクションの違いで端的にあらわされる。轟音にことさら反応しない波平家の人々の一方で、杉浦がある時、「うるせー!!」と叫ぶシーンが劇的だ。
だが、そんな基地や米軍に経済を依存している面があるのもまた事実だ。大工である信夫が杉浦に、そして自身がかみしめるように、基地の建設に携わってきた思いを切々と吐露する場面は胸を打ち、秀逸だ。
米国は「銃剣とブルドーザー」で畑も家も潰して基地にしてきたが、「平気な人間より、辛い人間がやった方がいいと思った」「申し訳ない気持ちでやった」と言う。基地から爆撃機が飛んでいくことを「望んでる人間なんているわけない」。沖縄で生きる、基地とともに生きるということはどういうことか、観客の胸をえぐるように突き付けてくる。当銘の柔らかな存在感、そして沖縄を拠点に活動するアーティストだからこその言葉の持つ説得力が加わった。
当銘の歌三線、琉球舞踊家でもある古謝の踊りによる「加那ヨー」は、思わず息を止めて見入ってしまう。この「加那ヨー」が、いない相手を思う歌というのも、また示唆的ではないか。
山之口貘の詩『生活の柄』や『自衛隊に入ろう』、『会話』を巡る元恋人同士の杉浦と恵の会話も、夜ふけの甘酸っぱい空気の中で、それぞれの考える家族や国のかたちがにじみ出る。下北沢公演の初日舞台にも接したが、特にサトウキビの収穫手伝い、波平家とのふれあいを通した杉浦の成長というこの物語の芯が、沖縄公演よりもくっきりと見えてきた。沖縄での稽古、本番を経たことが、役への理解に大きく作用したことは間違いない。俳優も演出家も、沖縄でサトウキビ収穫を体験したという。沖縄と東京で上演できたことに加え、これも共同制作公演の意義であろう。
丁寧に一人一人のキャラクターが描きこまれたことも、作品の深さにつながった。基地を抱えたままの復帰に抗議し、水商売のユミが父と暮らすことに抵抗する和子。やや憎まれ役のようなところはあるが、馬渡が教師らしい几帳面さ、生真面目さを見せ、戦争で母と兄三人を亡くしたと語る場面に人間味が染み出た。
もう一つの沖縄の経済、「サトウキビ」も重要なファクターだ。基地同様、サトウキビ畑も舞台では目に見えないが、それぞれの会話から、畑の光景が浮かび上がり、そして「ゆいまーる(助け合い)」の精神がコミュニティーを支えていることに気付かされる。復帰では、ドルが円に変わり、パスポートも不要になり、車も左側通行になった反面、基地の現状は「変えられなかった」。けれど、「ゆいまーる」の精神は、「変えてはならない」ものだろう。
土砂降りの「5・15」ではさむ構成は、エピローグでその狙いがくっきりする。プロローグで誠治が聞くラジオから流れてくるのは、東京の式典での佐藤栄作首相(当時)と昭和天皇の演説。そしてエピローグは、沖縄の式典での琉球政府行政首席から知事となった屋良朝苗の演説だ。
沖縄の願いだった「核抜き本土並み」とはほど遠い復帰を象徴する、二つの間の距離感、温度差。ここまで波平家と時間を共にしてきたことで、屋良の「復帰の内容をみますと、必ずしも私どもの切なる願望がいれられたとはいえないことも事実であります」「これからもなお厳しさは続き……」という言葉がリアルに響いてくる。日の丸をつかみ、すっくと立ちあがる田代のおじいの表情に万感がこもった。
台湾有事を想定して、政府は与那国島にミサイルを配備するなど南西諸島の防衛体制強化に動いている。
繊細なドラマに揺さぶられながら、沖縄を考えることは日本のあり方も考えることなのだと、あらためて胸に刻みつけられた。
『夏至の侍』■
二番目の候補として、桟敷童子の『夏至の侍』(サジキドウジ作、東憲司演出)を推した。劇場は拠点とする、「すみだパークシアター倉」。東京・錦糸町駅から歩いて十五分ほど。夜に来ると何やら妖気を感じる大横川親水公園に面して建つ劇場は、「ひめゆりピースホール」同様、独特の磁場を持つ。
毎回、劇団員総掛かりで作る装置は土の匂い、人の匂いが強烈で、劇場に入った瞬間から、観客は物語の世界にすでにいざなわれる。北九州の金魚問屋が舞台となる今回は、舞台全面に本水を使った水路を通し、時代を感じる日本家屋に赤も鮮やかな金魚の絵看板が情緒を誘う。衰退していく地場産業、それに抗おうとする気丈なふみゑ(音無美紀子)、彼女を支える亡くなった息子の嫁菜緒(板垣桃子)。そこに、家出したまま十年以上音信不通だった娘二人、みちる(⻑嶺安奈)とわたる(⼤⼿忍)が突然帰ってくる。
東がドラマの芯にすえる伝承は、いつもノスタルジーとロマンにあふれる。自由を求めて養魚池を飛び出した「迷い金魚」が夏至に戻ってくるという言い伝えが、母と娘二人と重なっていくという仕掛けに詩情がこぼれる。希望の象徴でもある「夏至の侍」探し、水車堀の復活に躍起になる人々に、現代の閉塞感が重なる。音無に強さと情の濃さがあり、圧倒的な存在感。恒例のラストの屋体崩しも、ふみゑの慟哭を視覚化し、圧巻だった。
「生き残った子孫たちへ」■
二二年は、二月にロシアがウクライナに侵攻し、世界の秩序が大きく揺らいだことが、舞台公演にも、そして観客にも大きな影を落とした。
その中でも、劇団チョコレートケーキ「生き残った子孫たちへ 戦争六篇」(いずれも古川健作、日澤雄介演出)はタイムリーな上演だった。沖縄戦を題材にした新作『ガマ』を含む、新旧の六作品からなる企画ということもあり、「悲劇喜劇」賞の候補作は作品単位ということで断念したが、高い成果を上げた一連の上演として記憶されるべきだろう。
戦中戦後の朝鮮半島が舞台の『追憶のアリラン』、松井石根を軸に南京虐殺の実相に迫る『無畏』、対米戦をシミュレートした総力戦研究所を描いた『帰還不能点』は、初演と劇場も装置も変わっての上演で、より深みを増した。特に『無畏』『帰還不能点』が同時に上演されたことで、一九三一年の満州事変から続く十五年戦争の二つの「分岐点」、すなわち、対中戦争の泥沼化、対米開戦は避けることができたのではないか、という作者の視点が白熱した議論劇で浮かび上がった。
歴史に「たられば」はないが、原爆投下という惨事に至ったことは、忘れてはならない。核使用がちらつくウクライナでの戦争に鑑みると、これは「歴史」ではなく、「現実」に突き付けられている問題なのである。
『ガマ』■
新作『ガマ』は沖縄戦下、ガマ(洞窟)の中で行き会った学徒看護隊に動員された女学生、教師、日本兵による、生きるべきか死ぬべきか、ギリギリのせめぎ合いが繰り広げられる。抽象的な装置で、人間の身体と言葉にフォーカスした日澤のシャープな演出がさえたが、同様の題材を扱った先行作は多く、切り口も目新しさに欠けたのが残念だった。
とはいえ、やはり過去から学ぶべきことは多い。チョコレートケーキの「演劇的事件」とも言える試みを通して、演劇の果たすべき役割の一つを改めて確認させられた。
ここで挙げた三本(候補作と、候補作にしたかった作品)は、いずれも小さなプロダクションや劇団で、集客の期待できるスターを起用しているわけではないが、多くの関心と幅広い観客を集めた。
三年以上に及ぶコロナ禍で、高齢者の足が戻らないなど市場は縮んだかもしれないが、この三本以外でも、候補作として上がったオフィスコットーネ『加担者』、劇団俳優座『猫、獅子になる』、PARCO『セールスマンの死』を含めて、気骨のある多くの作品に出合え、演劇人の心意気を感じられた。観客冥利に尽きる。
声にならない声を響かせて
杉山弘 (演劇ジャーナリスト)
受賞作『カタブイ、1972』は、那覇市のエーシーオー沖縄(一九九二年設立)と東京の名取事務所(一九九六年設立)が制作し、二〇二二年末に那覇市のひめゆりピースホールと東京・下北沢の小劇場B1で上演された。米軍基地問題や歴史認識などで「温度差」のある二都市を拠点とする演劇制作カンパニーが、「沖縄の日本復帰五十年」をテーマに共同して企画するという演劇界では珍しい形での公演。その志の高さと公演実現までの労苦をまず評価したい。そして、家族劇で定評のある内藤裕子を作・演出に招き、東京在住の俳優四人と沖縄在住の俳優二人が出演した。芝居作りの過程で、思い違いや相手の痛みを想像し、互いの理解を深めることで見事な舞台成果へと結びつけた。「一+一=二」ではなく、「二」以上の感動があった舞台だったと言い換えてもいい。
雨の降る一九七二年五月十五日。自宅居間でラジオから流れてくる沖縄返還式典での佐藤栄作首相と昭和天皇のスピーチに耳を傾ける初老の男の姿から幕を開ける。暗転を挟み、舞台は式典の半年前に遡り、この家に暮らすサトウキビ農家の波平誠治(田代隆秀)の日常風景に切り替わる。太平洋戦争で妻や息子たちを失っていた誠治は、兼業とするタクシー運転手の勤務中に元夫からの暴力を受けていたユミ(古謝渚)を見かね、我が家に避難させてサトウキビの収穫を手伝ってもらっていた。ユミは戦争で孤児になり無学のまま世間へ放り出されたものの二人の子供を育て社会へ送り出している。教師をしながら米軍基地建設反対運動を続ける誠治の娘・和子(馬渡亜樹)、その夫・信夫(当銘由亮)は基地建設に従事し、裏切り者の非難を受けながらたくましく生き抜いてきた男だ。さらに東京の大学へ進学して帰省した孫娘・恵(増田あかね)は、沖縄返還の学生集会に参加して演説したことから、沖縄の存在を改めて見つめ直そうとしている。そして、都議会議員の親から後を継ぐように言われている大学生の杉浦孝史(山田定世)は、進路への迷いを抱えて東京から沖縄にやって来た。
表題の「カタブイ(片降り)」は、夏の沖縄によく見られる気象現象で、風が弱く晴れる日に局地的に積乱雲が発生し大雨となる不安定性降水で、ある地域で大雨が降っているのにすぐ近くが晴れている現象を指している。エピローグで初代沖縄県知事となる屋良朝苗のスピーチが登場する。「沖縄県民のこれまでの要望と心情に照らして復帰の内容をみますと、必ずしも私どもの切なる願望が入れられたとは言えないことも事実であります。そこには、米軍基地の態様の問題をはじめ、内蔵するいろいろな問題があり、これらを持ち込んで復帰したわけであります」の言葉は、式典から半世紀が経った今、何も変わっていないことに呆然とするばかりだ。
「加害者‐被害者」といった単純な図式から一方的な感情をぶつけ合うのでもなく、周年公演にありがちな通り一遍の物語を届けるのではなく、本土復帰を間近にした一九七一年の波平家で、三世代にわたる六人が、それぞれ単色ではない複雑な気持ちに揺れ、引き裂かれるような思いで「沖縄」と向き合っている姿を、内藤が丹念な取材に裏打ちされた繊細な会話劇から描き出していく。物語は一人暮らしの誠治がユミと同居する生活を不快に感じた和子が、世間体を理由に心無い一言を発してしまい、それを察したユミが無言で波平家を去ったことから起こる悲劇へと突き進んでいく。
演劇集団円に所属する内藤は、ここ数年、信頼をおく劇団仲間と豊かな作品世界を提供してきた。都市化が進む埼玉の農家での将来への決断が難しい悩みをすくい上げた『初萩ノ花』(二〇一四年)、東京・下町の藍染工房を舞台にした『藍ノ色、沁ミル指ニ』(一八年)、東京郊外で植林をする二つの林業一家の十年を見つめた『光射ス森』(二〇年)と、伝統的な産業に従事する家族の日常にさざ波のように沸き立った出来事を、産業の疲弊と跡継ぎ問題を絡めながら生活劇として展開させている。江戸末期の戯作者・曲亭馬琴とその息子の嫁・路による『南総里見八犬伝』完結までの道のりを描いた『ソハ、福ノ倚ルトコロ』(二二年、紀伊國屋演劇賞個人賞受賞)も、出版という産業に光を当てた家族劇でもあった。
内藤作品の最大の魅力は、それぞれの現場を丹念に取材し、実直に描いている点で、昔気質のまま懸命に産業を守ることに誇りを持つ親世代、伝統的な産業が利便性や経済性で時代から取り残されそうな厳しい現実に直面している子世代、そこに新しい価値観を見つけだそうとしている孫世代と、三世代を登場させ、取材で実際に見聞きした言動がリアルなことに加え、口には出さなかった思いや願い、ちょっとした仕草などで補助線を引いて、ドラマを立体化させている。ささやかで勤勉な日常の営みの中、時代の変化に気持ちが揺れ、一家に波風が立ちながらも懸命に生きようとする一人ひとりの佇まいが凜々しくも美しい。『初萩ノ花』での生活感あふれる居間、『藍ノ色、沁ミル指ニ』での本物と見まがう藍染工房、『光射ス森』での時空を超えた二つの家と、一杯道具の美術の使い方も作品ごとに工夫を凝らしている点も見逃せない。ベテランから新人まで、劇団の強みである俳優の層の厚さ、さらに長年をかけて積み上げてきた信頼関係を巧みに生かした演出が魅力的な芝居を届けてきた。
そんな内藤にとっても、『カタブイ、1972』を創作するにあたって、大きな壁が立ちはだかったことは想像に難くない。四十冊を超える関連書籍に目を通した上で、サトウキビ農家や激戦地だった南部の戦跡を見聞し、自爆しようとする祖父から手投げ弾を奪って生き延びた老人から話を聞くなど、沖縄での取材を重ねたという。その時に体験した驚きや戸惑い、怒り、哀しみをどう戯曲に落とし込むのか。歴史的な事実の重苦しさに押しつぶされて、作品が空中分解しかねない恐れもなかった訳ではないだろう。活路を開いたのは構成のうまさだった。敗戦から米国占領下での暮らし、返還までの四半世紀の道のりとその後、という歴史はプロローグとエピローグでの式典のスピーチに押し込み、得意とする生活劇に引き寄せて物語を展開させた。波平家での日常を積み重ね、声高で高圧的なメッセージを発せず、答えを求めることもしない。一見するとクールな印象を受けてしまうが、向ける眼差しの温かさがじんわりと伝わり、声にならない声が響いてくるまでにそう時間はかからなかった。「生活がそのまま正直に、人間の姿がそのまま正確に、誇張されずに示される」とチェーホフが願った生活劇が息づく。
内藤が渾身を込めた作品に俳優たちもこたえた。田代隆秀は、丸山ワクチンを題材に内藤が作・演出した名取事務所公演『灯に佇む』(二一年)で小さな町の老医師を演じ、柔らかな語りと温かみのある人物造形から、生死にかかわる重厚なテーマを穏やかな口調で丁寧に解きほぐした演技が強く印象に残っていた。今作でも、娘にはどこまでも優しく、不幸な女性に手を差し伸べる、実直で寛容な「おじい」を、明瞭なせりふ術と大地に根をおろした包容力から味わい深く演じた。さらに、戦争や国家に翻弄された男の哀しみを奥底に滲ませ、俳優としての新境地を開いてみせた。また踊りと歌三線で愛しい人に思いを馳せる琉球舞踊「加那ヨー」を劇中で披露した古謝渚と当銘由亮は、伝統芸能が生活に息づく沖縄の暮らしを沖縄言葉の柔らかな響きとともに情感豊かに彩った。内藤と同じ劇団に所属し、数多くの内藤作品に出演してきた馬渡亜樹も、観客から近寄り難い存在の和子役を甘えるでもなく突き放すでもなく、絶妙な距離感から辛抱役を演じ、そのきりりとした佇まいとともに忘れがたい瞬間を象ってくれた。若者らしいひたむきさを劇場空間に放った若手の山田定世と増田あかねも、元恋人同士という屈折した役柄をアクセントに、同じ俳優座の劇団員という息の合った演技で舞台を弾ませている。
この作品は三部作の第一作で、この後『カタブイ、1995』『カタブイ、2025』を計画しているという。杉浦と恵のその後、劇中に登場する山之口貘の詩集など、続く二作への伏線となりそうな素材もちりばめられていて、今後への期待を大きく膨らませた。また、沖縄で五日間八ステージ、東京で四日間五ステージとこの舞台を見逃している演劇ファンも少なくない。三部作がそろったところでも構わないが、是非、早い時期の再演を望みたい。
二〇二二年の演劇界を振り返ると、同じく「沖縄の日本復帰五十年」を題材にした佳作が相次いで発表された。コザ騒動の日に居合わせた当事者から沖縄の過去・現在・未来を群像劇として描いたホリプロ『hana‐1970、コザが燃えた日‐』(作=畑澤聖悟、演出=栗山民也)、食事風景という日常を戦争や基地という状況と対置させて私的な言葉を紡ぎ出したマームとジプシー『Light house』(作・演出=藤田貴大)、天地を逆転させた地図で沖縄と中国大陸の近さを実感させた青年劇場『豚と真珠湾‐幻の八重山共和国』(作=斎藤憐、演出=大谷賢治郎)、激戦地にあるガマ(洞窟)で負傷した兵士や教員、ひめゆり学徒隊員らが思いをぶつけ合う劇団チョコレートケーキ『ガマ』(作=古川健、演出=日澤雄介)、若い世代の新しい視点から本土と沖縄の間にある深い溝を突き付けたKAAT神奈川芸術劇場『ライカムで待っとく』(作=兼島拓也、演出=田中麻衣子)。それぞれのアプローチで演劇の持つ力を強く感じさせてくれた。その中にあって、『カタブイ、1972』は、企画の志、芝居の完成度、続く二作への期待と、文句なしに二〇二二年を代表する一作だった。
もう一つの候補作に挙げたPARCO『セールスマンの死』についても触れたい。既存の戯曲に現代的な意味を見いだしたり、新しい解釈を施したりした舞台が強く印象に残った一年でもあった。新国立劇場の招聘で九月に来日したフランス国立オデオン劇場の『ガラスの動物園』が美しくも哀しい「愛の協奏曲」を奏で、名取事務所『ペーター・ストックマン〜「人民の敵」より』では翻案・演出の瀬戸山美咲が大胆な読み換えから民主主義の劣化を社会問題として提示し、文学座の稲葉賀恵はオフィスコットーネ『加担者』でデュレンマットが六十年前に資本主義の行き着く先を予言した悪夢を呼び覚まし、PARCO『幽霊はここにいる』で安部公房が風刺した終戦直後の経済至上主義の歪みを痛快に暴いた。その中で、ひと際、印象に残ったのが『セールスマンの死』だった。
アーサー・ミラーがアメリカン・ドリームの光と影に切り込んだ戯曲(翻訳=広田敦郎)で、仕事と息子にかけた夢が非情な現実の前に破れ、資本主義社会にとり残されてしまった小市民ウィリー・ローマンの悲劇を見つめている。日本でも滝沢修や久米明、仲代達矢、たかお鷹、風間杜夫らの名優が演じてきたが、今回は英国人演出家のショーン・ホームズが、一九四〇年代ニューヨークの設定を三十年ほど後ろにずらし、さらに高度経済成長期にモーレツ社員として働いた日本のサラリーマンをイメージして読み直している。その上で、これをリアルな芝居ではなく、主人公の脳内風景に置き換え、バブル経済がはじけて時代や社会、家族から見放された男の心に走馬灯のように去来する想念として再構成した。この意表を突いた見立ては、グレイス・スマートの美術でも強調される。がらんとした空間の中央に大型冷蔵庫を置き、その上に二本の電信柱を浮かばせた。豊かさや成功の象徴である大型冷蔵庫と、コミュニケーションを取ろうとしても空回りする不安定な電信柱に、段田安則演じるウィリー・ローマンの心象風景を映し出しながら、可動式の舞台セットを入れ替わりで登場させて、ダイニングでの妻とのかみ合わない会話、子供部屋での息子二人の苦悩、庭先での友人からの助言、オフィスでの若い上司からの蔑みなど、これまでの人生をフラッシュバックさせ、亡霊に憑りつかれた男の落胆ぶりで消費社会の断末魔を浮かび上がらせた。原作に忠実な正攻法の演出もあるだろうが、現代的な視点から戯曲を解体して読み直す方法が許されるのも、演劇の自由で豊かな部分だろう。記憶の回路が寸断され、困惑し混乱する精神状態にあるウィリーを、段田はリアリズムの芝居を積み重ねて説得力を持たせつつ、脳内風景という飛躍のある表現を求められる演出家の意図をくみ取った人物造形で、見惚れるような場面を数多く生み出した。古典の再現ではなく、今の観客が実感出来る試みとして、この「変化球」の舞台を大いに愉しんだ一夜でもあった。
- <<前の記事:第十回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考結果
- 第十一回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞選考結果:次の記事>>